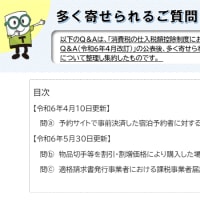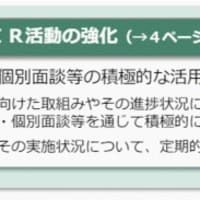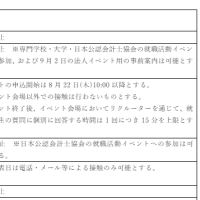企業会計基準委員会が昨年末に公表した「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」の一般向け解説記事。
現行基準については...
「...現行の実務指針では、2号から3号になると、計上できる期間が最大5年以内に限られるので、金額がガクッと減る。さらに3号から4号になると、最大1年以内に縮小するため、金額はさらに減る。また、4号のただし書きで「リストラ目的」ならば、1年でなく5年に拡がるが、2~3年に1回くらいリストラをしている場合はどうなのか、などの問題点が指摘されていた。
IFRS(国際財務報告基準)では、このような分類は存在しない。よって、分類をなくすべきだという意見もあったが、「15年間以上、日本に根づいているし、分類があったほうが(実務上の)ばらつきも少ないだろうから残した方がいい、ということになった」(ASBJの小賀坂敦副委員長)。」
新指針は...
「以上の回収可能性を簡略化すると、以下のように言い換えられる。
分類1=現行の1号と同じ。
分類2=現行の2号+企業が合理的な根拠を持って監査法人に説明できた、スケジューリング不能な部分。
分類3=現行の3号+企業が合理的な根拠を持って監査法人に説明できた、5年超の部分。
分類4=現行の4号+企業が合理的な根拠を持って監査法人に説明できた、1年超・5年超の部分。※リストラ目的によるただし書きはなし。
分類5=現行の5号と同じ。
以上を見る限り、繰延税金資産の回収可能性の基準は、緩くなると考えられるだろう。
しかし、小賀坂副委員長は、「緩めているつもりはない。企業が判断する局面は増えるが、監査が緩くなるわけではない。IFRSには分類がなく、すべてを企業の判断に委ねているが、だからといって緩いかというと、そうでもない。緩いか緩くないかは、今後出てくる決算で、判断されるべきものだ」と、そうした見方に反論した。」
現行基準でも、もっと柔軟にできるはずだったという見方からすると、新指針でゆるくなったわけではないのでしょう。
記事の最後のパラグラフが余計です。
「今後、新たな実務指針を”悪用”する会社が出てくるか、どうか。第2、第3の東芝、新日本監査法人が、現れはしないか。それはひとえに、企業自身の自律、監査法人の姿勢にかかっている。」
東芝の事件は、繰延税金資産のところで粉飾していたわけではないのですが...。
なお、新指針を実際に適用する場合には、指針本文をよく読まないと、まずいでしょう。
当サイトの関連記事
最近の「企業会計」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
2000年
人気記事