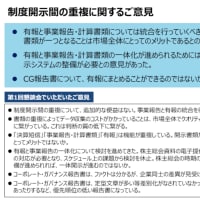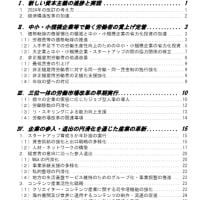国際会計士連盟の国際監査・保証基準審議会(IAASB)より、継続企業の前提に関する留意点をまとめたStaff Audit Practice Alertが、1月20日付で公表されました。
IAASB Practice Alert Helps Auditors and Management Assess Impact of Credit Crisis on Going Concern Assumptions(国際会計士連盟のプレスリリース)
参考のため概要部分のみ引用します。
Key Messages within This Alert
・The going concern assumption is a fundamental principle in the preparation of financial statements.
継続企業の前提は財務諸表の作成における基本的な原則である。
・The assessment of an entity’s ability to continue as a going concern is the responsibility of the entity’s management.
継続企業として存続する企業の能力を評価することは、企業の経営者の責任である。
・The appropriateness of the use of the going concern assumption is a matter for the auditor to consider on every audit engagement.
継続企業の前提を使用することが適切かどうかは、どの監査業務においても監査人が考慮すべき事項である。
・International Standard on Auditing (ISA) 570, “Going Concern,” establishes the relevant requirements and guidance with regard to the auditor’s consideration of the appropriateness of management’s use of the going concern assumption and auditor reporting.
国際監査基準570「継続企業」が、経営者による継続企業の前提の使用についての監査人の検討および監査報告に関連する規定および指針を定めている。
・The credit crisis and economic downturn have led to a lack of available credit to entities of all sizes,which may affect an entity’s ability to continue as a going concern; this and other factors may be relevant in the auditor’s evaluation of forecasts prepared by management to support its going concern assessment.
金融危機と経済状況の悪化は、あらゆる規模の企業にとって、信用の欠乏をもたらしており、そのことが継続企業として存続する企業の能力に影響を与えている場合がある。この点やその他の要因は、継続企業の評価の根拠となる経営者の予測を監査人が検討する際に、関連する場合がある。
・The extent of disclosures in the financial statements is driven by management’s assessment of an entity’s ability to continue as a going concern, coupled with the disclosure requirements of the applicable financial reporting framework.
財務諸表においてどこまで開示するかは、適用される会計基準の開示規定とともに、継続企業として存続する能力に関する経営者の評価によって決まる。
・Consideration of the need for an emphasis of matter paragraph in the auditor’s report will be a difficult matter of judgment to be made in the context of the entity’s circumstances; the mere existence of the credit crisis, though referred to in the financial statements, does not of itself create the need for an emphasis.
監査報告書における追記情報の必要性に関する検討は、その企業の状況に応じてなされる難しい判断である。金融危機が存在しているというだけでは、そのことが財務諸表において言及されていたとしても、追記情報が必要であるとはいえない。
継続企業の前提は、会計学では会計公準のひとつとして教わります。しかし、そこでは、企業はずっと存続するわけではない、何かあれば明日にも倒産するかもしれないというのが現実だが、企業会計では、そうした現実はひとまずおいておいて、存続し続けるものと仮定して、財務諸表を作成するのだということが強調されます。継続企業の前提を用いていいかどうかを経営者が評価しなければならないということは、監査人の拠り所である監査基準には書いてあるものの、会計基準上の扱いはあいまいであり、財務諸表作成者である企業側には浸透していないようにも思えます。継続企業を巡って監査人に責任転嫁するような例が見受けられるのは、そうしたところに一因があるのかもしれません。
今回の金融危機は実体経済にも大きな影響を及ぼすに至っており、有力企業が軒並み赤字決算の予想を発表しています。今後、継続企業の注記を行うかどうか、そして状況がさらに悪い場合には、継続企業の前提を使えるかどうかでもめる例が数多く出てくるでしょう。注記と鑑査報告書の追記情報だけであれば、(ほかに限定事項がなければ)無限定適正意見となりますが、継続企業の前提を使えるかどうかという点は、より深刻です。監査人が継続企業の問題で意見不表明を出すのは、継続企業の前提が使えない(言い換えるとすぐに破綻する)と決めつけているのではなく、不確定要素のために前提の使用が適切かどうかを確かめられないという意味なのですが、その点もあまり理解されていないようです。注記だけの場合と意見不表明の場合で制度上の扱いが違いすぎるのも問題を不必要に大きくしています。
最近の「会計監査・保証業務」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
2000年
人気記事