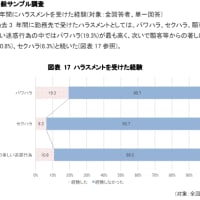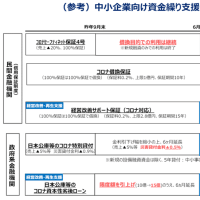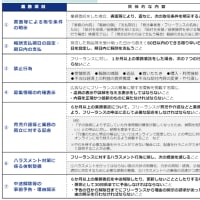日本公認会計士協会が、「包括利益の表示に関する会計基準(案)」に対する意見書の内容を公表したという記事。
「意見書では、「当面の間、個別財務諸表には適用しないこととしている本公開草案の取り扱いに関して反対するものではない」としながら、「包括利益の表示が実務に定着した段階において、再度、個別財務諸表への適用について議論することを要望する」という意見を述べている。その理由として、「連結財務諸表に適用される会計基準については、個別財務諸表にも適用することが原則と考えられる」ことを挙げている。」
協会の意見は、おそらく間違っていないとは思います。しかし、包括利益を個別に適用しないというのは、包括利益がIFRSの代表選手みたいになってしまい、個別財務諸表をIFRSの悪影響から守れという考え方と衝突してしまったからでしょう。原則とか理屈の話ではなさそうです。
会計士協会の意見書はこちら
↓
企業会計基準公開草案第47号「包括利益の表示に関する会計基準(案)」等に対する意見について
協会の意見には、以下のようなものも含まれています。
「簡便的な会計処理として位置付けられている、為替予約等に関して振当処理を採用している場合や金利スワップ等に関して特例処理を採用している場合において、組替調整額の注記を行う必要があるかどうかについて記載すべきである。」
振り当て処理などは、本式のヘッジ会計のような資本直入的処理はやらないので、組替調整の問題は出てこないような気もしますが・・・。しかし、協会がわざわざ意見を言うということは、いろいろな考え方があるのでしょう。
会計士協会といえば、会計士協会の機関誌である会計監査ジャーナルの2012年6月号に「包括利益表示基準の批判的検討」(明治大学・田中建二教授)という解説が掲載されており、参考になります。
結論の部分を抜粋します。
「「包括利益表示基準」を批判的に検討した結果、次のようなことが明らかとなった。1)「包括利益表示基準」は国際的な会計基準とのコンバージェンスを図ることを目指しているが、連結基礎概念に照らすと、異質なものをうまく融合しているとの解釈もあり得るかもしれないが、素直にみれば皮相的なコンバージェンスに止まっているといわざるを得ない、2)「包括利益表示基準」は、純資産と包括利益とのクリーンサープラス関係を明示することを通じて財務諸表の理解可能性と比較可能性を高めることを狙いとしているが、株主資本と純利益とのクリーン・サープラス関係と純資産と包括利益とのクリーン・サープラス関係をともに満たすことは困難である。」
ざっと読んでみて、包括利益表示基準だけでなく、日本版概念フレームワークもターゲットにしているようにも感じました。
最近の「企業会計」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
2000年
人気記事