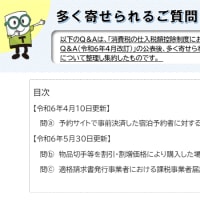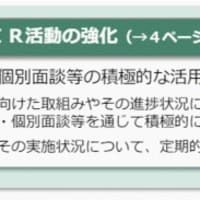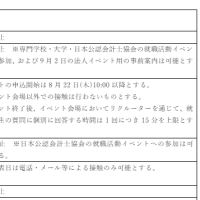東電原発事故の賠償スキームの記事。「政府内の試算」だそうです。
まず、スキームは以下のようなものです。
「賠償は、今年度から1兆円ずつ、4年で完了すると仮定している。賠償額の上限設定については、枝野幸男官房長官が否定しているが、めどとして賠償額を確定させないと東電の11年3月期決算をつくることができないため、上限を設けたとみられる。4兆円を超える場合には、言及していない。
試算によると、賠償は東電が担う。東電は自己資金で足りない分について、電力各社で新たにつくる「機構」から支援を受ける。機構には国も公的資金を拠出。公的資金は、東電を含む電力各社が毎年4千億円を10年間にわたって返済する。
内訳は、東電は毎年1千億円を特別負担金として拠出。残る3千億円は原発を保有する電力9社(東電を含む)が負担する。各社は電力量に応じて負担し、全国の電力量の約3分の1を占める東電は、約1千億円の負担となる。これらの賠償資金を確保するため、東電管内は電気料金の大幅な値上げを想定している。
東電以外の8社は、約2千億円を負担。これは、約2%の料金値上げ分に相当する。4兆円の賠償額の負担割合は、東電が約2兆円、東電以外の8社が計約2兆円になる見込みだ。
機構は東電が発行する優先株1.6兆円分を引き受ける。・・・」
気になるのは、まず、会計的にはどうなるのかという点です。
4兆円というのが根拠のある数字であれば、東電は、この数値で、2011年3月期に損失を計上しなければならないでしょう(「賠償は東電が担う」ので)。大部分は引当金となるのでしょう。実際には、このうち現時点で合理的な見積もりができる金額ということで、2011年3月期についてはもっと少ない金額になるかもしれませんが、今後の期も含めて4兆円の損失ということになります(このほかに廃炉費用なども発生する)。
よくわからないのが、「機構」からの支援の内容です。全く返済する必要がない資金であれば、もらうことが確定した金額を確定した期に利益(損失補てん目的であれば損失のマイナス)として計上することになります。2011年3月末現在では、「機構」自体存在せず、東電に支援を受ける権利は発生していないので、2011年3月期に利益計上はできません。
単なる資金的支援(貸付や増資)であれば、損益には直接は影響しません。また、この場合は、将来的にもどってくるわけですから、電気料金算定の際の原価には含まれず、電気料金から回収という話にはなりません。
公的資金の返済はどうなるのかというと、記事の図をみると、東電を含む各電力会社が、機構に拠出することになっています。これも、出資金のような戻ってくるカネでないのであれば、各社とも、支払うべき金額が確定した金額を確定した期に費用計上することになります。「電力量に応じて負担」とのことですから、各期の電力量から拠出すべき金額を計算して計上するのでしょう。他の電力会社からすると、機構を経由した、東電への贈与です。
問題は、東電が機構に拠出したり、支援を受けたりする金額の扱いです。支援を受ける金額のうちの4分の1(1兆円?)は、最終的に自社が拠出しなければなりません。拠出と支援のタイミングが同じであれば、特に問題は生じませんが、もらう方の利益計上が先行すれば、おかしなことになります。機構というダミー組織を使った架空取引という解釈もできます。少なくとも、支援を受ける金額のうち、最終的な東電負担分は利益から除外する処理をすべきでしょう。
優先株1.6兆円も問題です。このうちの4分の1は東電が将来拠出するカネで賄うわけですから、その分は一種の見せ金です。理屈から言うと、無効な増資です。そんな取引が認められるのでしょうか。他の上場企業がそんなことをすれば、不適切な第三者割当増資だと言って、大変な批判を浴びることでしょう。
「東電の決算は、11年3月期は約8千億円の純損失(赤字)に陥るが、赤字は4年間で解消。14年度以降に社債発行を再開し、18年度には配当再開も目指すとしている。」
8000億円の損失で済むのであれば、特別な支援は不要だと思うのですが、やはり政治力でしょうか。被害者への賠償目的であればともかく、東電の株主への配当のために、電力料金が値上げされるのも納得できません。
原発賠償4兆円 政府試算 さらに上積みも(産経)
東電の賠償、電気料値上げで…政府・民主容認へ(読売)
福島第1原発:東電の賠償負担、総額に上限なし…政府(毎日)
「最終的な総額に上限を設けない一方、毎年の賠償額については東電が債務超過に陥らない範囲内に抑える方向で最終調整に入った」とありますが、前にも書いたとおり、損害賠償の損失計上は、現金主義ではないので、毎年の支払額を範囲内に抑えたからといって、損失計上が減るわけではありません。いったい、どんな会計処理を想定しているのでしょうか。
(業法の規則に基づく決算ということで、なにか理屈に合わない例外を認めるのかもしれません。ただし、将来IFRSが適用になった場合に、特例が認められるかどうかはわかりません。やや飛躍しますが、もしかすると、東電救済のため、IFRS導入延期もありうるのでしょうか。)
原発補償問題、政府が枠組み案公表へ(WSJ)
東電 損害賠償限度で配慮要望(NHK)
東電は、社長が土下座する一方で、賠償金を値切るような要望書を出しています。
最近の「企業会計」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
2000年
人気記事