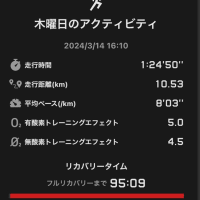続きを。
坂道での練習が続く予定でしたが、吹奏楽部の楽器の搬出のため学校前の坂道が使えなくなったのでアスファルトの平地へ。吹奏楽部は自分たちの「運搬用トラック」を持っていました(笑)。すごい話です。まーそれくらい高い頻度であちこちで演奏するのだと思います。いつもTVで拝見させてもらっています(笑)。
平地にマークを置いての走練習。意図する部分は異なるかもしれませんがこの部分はうちの学校でもやっています。マークの間を速く切り替えて進んでいく。マーク走の難しい部分は「速く動く」だけになってしまうことです。以前失敗した部分。何度か書いていますが「ピッチを上げる」ためにマーク走をかなりやりました。切り替えを意識して行うのですがシーズン前になってこれまでやっていたマークの距離が遠く感じるということでした。「速く動ける」けど「前に進んでいない」のです。15年くらい前でしょうか。それ以後、色々と考えながらやっています。ここに関してもっと話を聞ければよかったなと思うのですが、動きの感じを見る限り「やりたいこと」は同じ方向性だなと。接地の時に「遅れない」こと。ピッチだけに頼るのではなくマークを越えるときに膝が引き出されて重心の移動が生まれる。道具を使うことで意識しやすくなる。
これも段階的に距離が伸びていきます。そのなかで動きは変わらない。進むようになっていきます。私はずっとこの手の練習スタイルが良いなと思っています。ぶつ切りのように「思い付き」で練習を組み込んでいくのではなく「1」「2」「3」という感じで前の段階ができてから次の動きに進む。「準備動作」というか「スプリント」をするためにどうするのかというのが重要。いきなり走っていい動きができるともっといいのかもしれませんがそれは難しい。だから準備して積み重ねる。マークをなくして走ることで「意識づけした感覚」が自然にできるようになる。ずっと「マーク」を置いていたら当然ながら走れます。意識しやすいので。しかし、実際のレースではそれはできない。だから最終的にはマークをなくして走る。
最後に数本、アスファルトの上で走ることに。勝ち上がり、負け下がりのような感じで。うちの選手、思っていた以上に走れていました。後ろの組からスタートして前の組に上がっていく選手も。最大は2組目まで上がっていました。勝てるとかではないかもしれませんがこうやって一緒に走らせてもらうことで多くのことを感じることができます。もちろん、練習の流れや疲労度などもあるので一概に「戦えるレベルまで来た」とは思いません。ただ、全くついていけないという感じではなかった。それは大きなことだと思っています。フィニッシュ地点で見ていたysd先生も「強いね」と言ってくださいました。社交辞令であったとしても少し自信になります。通常この時期に「めちゃくちゃ走れる」というのは少ないと思っています。昨年と比べると「ベースアップ」が確実にできています。
前回来た時には本当に「見るだけ」でした。選手を連れてきていなかったので。今回は自分のところの選手も一緒なので「明らかな差」を感じることができます。選手たちにとっても「刺激」は大きい。まだまだ「シビアさ」や「正確性」で大きな差があるのは確かです。しかし、影を踏むまではいかなくても風を感じることくらいはできるかもしれません。
アスファルトを走ってからグランドでウインドスプリント。そこからまた補強。これも段階的な刺激です。最初に腸腰筋に負荷をかけておいてから「大きなもも上げ」をする。それも「リズム」を示すことで「速く動きすぎない」ようにしていました。大きく前まで持って来る。入れ替えのタイミングを意識できるようにしながらです。前の「予備負荷」の段階でかなり速く動いています。そのリズムのままもも上げとすると「小さく速く」になってしまって走りに生きてこない。だから意図的に「リズム」を作って「大きく」「切り替える」ことをしながら動かすのかなと。そこからチューブを使って「大きく速く」動く。低い位置で足を入れ替えるのではなく高い位置で入れ替える。最後に20mの坂道を走る。これを数セット。
これだけ「流れ」があると面白いですね。やりたいことが明確。単純に補強をすることが目標ではない。あくまで「走るため」補強でないといけない。「補強が強い」ことと「スプリントが速い」ことは完全にイコールではありません。補強が弱くても速い選手はいます。補強が強くても走れない選手はいます。その「補強」の位置づけがどうなるかだと思っています。強豪校がやっているからその補強をやる。当然ながらあり得る話だと思っています。しかし、その「組み立て」がきちんとしていなければその目的は果たせません。「補強が強い」という選手を育てたいわけではないですから。だからこそkyttbnで実施している「補強」の流れが良いんだと思います。「鍛えて終わり」「刺激を入れて終わり」ではない。明確な狙いがあってそこに向けて「準備」をする。そして必ず「走るために」という部分に落ち着く。重要なことだと思っています。そこが一番の重要な部分。
本当にずっと見ていられるなと感じました。見ていて楽しいんです。そこに潜む「意図」を感じながらそれを行う選手の様子を見る。変化していく感じをみる。それだけで時間が有効に使えます。私自身、こういう形の練習をしています。もちろん、地方の無名な学校でやっていることなので正直「妄想」といわれるでしょうが(笑)。それでも「やりたいこと」が明確な練習を見るということは本当に面白いんです。1か月間ずっと見ていても飽きないと思います。その都度色々と質問しながら見続けることができたら幸せだろうなと。
午前中の練習はここまで。あっという間に時間が過ぎてしまいました。なんてもったいないんだ(笑)
また書きます。