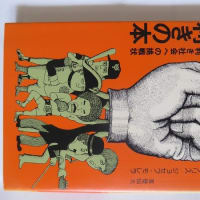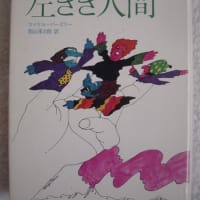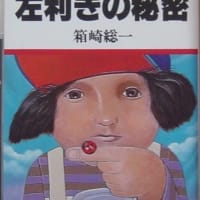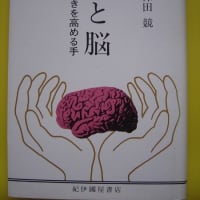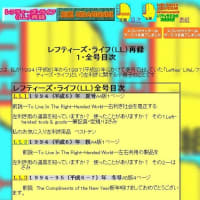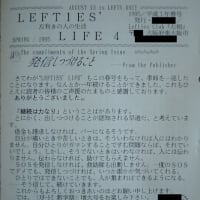古典から始める レフティやすおの楽しい読書 別冊編集後記
2022(令和4)年2月15日号(No.312)「私の読書論154-
荒俣宏『喰らう読書術』から~本は出会い」
------------------------------------------------------------------
◇◆◇◆ 古典から始める レフティやすおの楽しい読書 ◆◇◆◇
------------------------------------------------------------------
2022(令和4)年2月15日号(No.312)「私の読書論154-
荒俣宏『喰らう読書術』から~本は出会い」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
先人の読書論や読書術のノウハウ本を読み、紹介を兼ねて、
私なりの読書論を語るシリーズ、というところでしょうか。
今回は、高校生時代に翻訳書を読み、
それ以来、その活躍ぶりを拝見してきました、
私と共通する読書の好みを持つ作家である
荒俣宏さんの本・読書に関する著書『喰らう読書術』から――

(画像:荒俣宏さんの若かりし頃の団精二名義の翻訳書『征服王コナン』『異次元を覗く家』ハヤカワSF文庫)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- 私の読書論154 -
◆ 読書 ◆
~ 本は出会い ~
荒俣宏『喰らう読書術』から――
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●荒俣宏『喰らう読書術』
作家・博物学者の荒俣宏さんの読書術の本

荒俣宏『喰らう読書術――一番おもしろい本の読み方』
ワニブックスPLUS新書 2014/6/9
から、気になる部分を紹介します。
まず本書について――(《》内は、出版社の紹介文より)
《「知の巨人」荒俣宏、初めての読書術本!》で、
さすがにちょっと通り一遍の、自分のオススメ本を並べるといった
読書ノウハウ本とは異なります。
知的好奇心をくすぐる「本」の魅力の部分を語り、
《どんな本でも面白く読め、頭の栄養になる読書の極意を伝授します!》
というものです。
ただAmazonのレヴューにもあるように、やや散漫な部分、特に後半、
だんだん読書術的なノウハウ本というより、
ご自身の読書体験に基づき「本」の持つ魅力を語る、
という内容になって、荒俣ファン以外には、
ちょっと読みにくいものになっているかもしれません。
私は楽しく読みましたが、一般的な読書ガイドや読書本にありがちな、
必読書ガイドといったものはなく、
ご自身のお好みの本、影響を受けた本を紹介し、
たぶんに人の薦めない、しかしご自身の認める本を、
一人でも多くの人に知ってもらいたい、という熱意で書かれています。
●本を置く生活のノウハウ
冒頭の「はじめに――読書はおもしろいはずだが、実際はつらい」に、
《身の回りにいつも本を置く生活のノウハウ》のポイントとして、
三つあげています。
・本を読むという手間を惜しまない
・本棚には読まなくても本を並べる楽しみがある
・真の読書は、読むことに直接の利益を期待しないことである
(p.6)
「本」「読書」というのは、「頭の栄養」摂取だといいます。
毎日ご飯を食べるように、本を読む。
読書にはそれだけの価値があるといいます。
ただバーチャルな食べ物なので、いくらでも食べられる。
そこで、つい食べ過ぎになる。
本を読みすぎると、変になる、とも書いています。
そこで「ダイエット」も必要だと説いています。
で、そんなに本を読んでどんな偉い人間になったのか、
という問いに対して、
荒俣さんの答えが「らしい」ものになっています。
《正直に、はっきり申します。
聖人にも、悪人にも、また偉い物知りにも、なれません。
ただ一つ、メリットといえば、人生に退屈せずに済んだことです。》
(p.8)
いかにも荒俣さんらしいでしょ。
ただし、そういう実績ではなく、
可能性に目をむければ、大きな可能性が秘められている、と。
《私には、まだ知りたいこと、したいことがたくさんあるからです。
それが実現する方向へ手助けをしてくれるのが、
このやっかいで場所塞ぎだけれども、
手元に置いて大事にするべき本の山である、
といってよろしいかと思います。
仲良くなった本は、
自分をどこかに導いてくれる「先達」にも変身できる、
ということでしょう。》(p.8)
●「読書」と「本」を知る7つの「急所」
第一章で<「読書」と「本」を知る7つの「急所」>として、
7項目を挙げ、それぞれについて説明しています。
とりあえず項目を挙げておきましょう。
・急所その1
読書は「精神の食事」――でも、食わなくても死なない!
・急所その2
頭が要求する「栄養」は、かならずしも読書だけではない
・急所その3
本は全部読まないと、わからない
・急所その4
本は自腹で買え それだけ真剣に読みたくなる
・急所その5
世界の見方を一変させる「目から鱗」の本を探せ
・急所その6
毒本、クズ本でも、薬に変えられる
・急所その7
読書をおもしろくさせる「おもしろ感度」を磨け
今後、これらからいくつか気になる点を随時見ていこうと思います。
●読書も本との出会いから始まる
まずは、今回は、その一回目、
手始めにこんな言葉について見ておきましょう。
その6で、恋と同じで、読書も本との出会いから始まる、といいます。
で、《自分でみつけることが大切です。》(p.54)と。
そして、ここがキモだといい、
《「よい本だけに巡り合うのではない」からこそおもしろのです。》
(p.54)と。
さらに、
《「品質」には関係ない、ある種の魅力がかならずある、
と考えています。本はクズでも宝になり得るのです。》(p.55)
といい、
《クズか宝かを決めるのは、自分である》(p.62)といいます。
《まわりの評価を最終的には優先させるな》といいます。
世間ではもう相手にしなくなった本であって、
そこに自分だけの価値を見いだすこともある、というわけです。
人によって、何を求めるかが異なります。
当然、価値観も違い、本の“宝物観”も異なってくるでしょう。
自分だけの宝物となる本もあるというわけです。
そして、それをどこで知るか、どうやって見つけるか、
という問題があります。
そのためには、勘を磨かなければいけない、
この本は、何かを見つけられそうな本だなあ、という勘を。
本は全部読んでみないと分からないものです。
それは、人の場合と同じでしょう。
人との出会いと。
どういう人なのかは、ぱっと見だけではわかりません。
実際に交際してみないと本当のところは分からないものです。
それでも、この人は? という勘をもっていれば、
第一印象でもある程度のところは分かるものです。
第一印象というのは、すべてを信用してはいけませんが、
思えば「結構当たっている」というものではないでしょうか。
本の場合も同じで、ある程度の勘を持っていれば、
自分の必要とする本かどうかは、大まかなところはわかるものです。
で、そういう本は、とりあえず買っておく。
今すぐ読まなくても、いずれ時が来れば、読めますし、
読んでよかった、という気になるものです。
・・・
本日はこの辺で。
当初書こうとしていた内容とは異なったものになりました。
次回、7つの急所から、
「本は、全部読まないとわからない」「本は、自腹で買え」
について書いてみます。
できれば、本のメリット・デメリットなども。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★創刊300号への道のり(12) 2019(平成31/令和元)年(12年目)
239.
2019(平成31)年1月15日号(No.239)-190115-
「私の読書論115-私の年間ベスト2018(後編)フィクション系」
●私の今年2018年〈フィクション系〉ベスト1
~ 母の愛と魔法の時 ~『紙の動物園 ケン・リュウ短篇傑作集1』
ケン・リュウ 古沢嘉通編訳 ハヤカワ文庫SF
240.
2019(平成31)年1月31日号(No.240)-190131-「古代中国編―
中国の古代思想を読んでみよう(27)
古代中国における「天」の思想について」
241.
2019(平成31)年2月15日号(No.241)-190215-
「私の読書論116-楽しみのための読書〈怪盗ニック〉退場」
242.
2019(平成31)年2月28日号(No.242)-190228-「古代中国編―
中国の古代思想を読んでみよう(28)『荀子』性悪説と異端の儒家」
243.
2019(平成31)年3月15日号(No.243)-190315-
「私の読書論117-『荀子』「勧学篇」から学問のすすめ」
244.
2019(平成31)年3月31日号(No.244)-190331-「古代中国編―
中国の古代思想を読んでみよう(29)『荀子』性悪説と現実主義」
245.
2019(平成31)年4月15日号(No.245)-190415-
「私の読書論118-読書の仕方あれこれ~ペラペラ読み」
246.
2019(平成31)年4月30日号(No.246)-190430-「古代中国編―
中国の古代思想を読んでみよう(30)『韓非子』 」
247.
2019(令和元)年5月15日号(No.247)-190515-
「私の読書論119-読書生活&書籍購入50年」
248.
2019(令和元)年5月31日号(No.248)-190531-「古代中国編―
中国の古代思想を読んでみよう(31)『韓非子』後編」
249.
2019(令和元)年6月15日号(No.249)-190615-
「私の読書論120-読書生活&書籍購入50年(2)私のお気に入り」
250.
2019(令和元)年6月30日号(No.250)-190630-
「2019年岩波文庫フェア「名著・名作再発見!」小さな一冊...」
「2019年 岩波文庫フェア「名著・名作再発見!」
小さな一冊をたのしもう」から芥川竜之介『羅生門・鼻・芋粥・偸盗』
251.
2019(令和元)年7月15日号(No.251)-190715-
「私の読書論121-読書生活書籍購入50年(3)短編集が好き」
252.
2019(令和元)年7月31日号(No.252)
「新潮・角川・集英社<夏の文庫>フェア2019から」
253.
2019(令和元)年8月15日号(No.253)
「私の読書論122-空海/弘法大師に関する本」
254.
2019(令和元)年8月31日号(No.254)
「お休みのお知らせ&少し空海のお話を」
255.
2019(令和元)年9月15日号(No.255)
「私の読書論123-追悼・横田順彌-明治SFを読む」
256.
2019(令和元)年9月30日号(No.256)-190930-「古代中国編―
中国の古代思想を読んでみよう(32)『孫子』前編」
257.
2019(令和元)年10月15日号(No.257)
「私の読書論124-蔵書と人生」
258.
2019(令和元)年10月31日号(No.258)-191031-「古代中国編―
中国の古代思想を読んでみよう(33)『孫子』後編」
259.
2019(令和元)年11月15日号(No.259)「私の読書論125-
読書生活書籍購入50年(4)初期(20代前半)リアル編ベスト3」
260.
2019(令和元)年11月30日号(No.260)
「クリスマス・ストーリーをあなたに~(9)
『その雪と血を』ジョー・ネスボ」
261.
2019(令和元)年12月15日号(No.261)「私の読書論126-
読書生活書籍購入50年(5)リアル編
-50代以降・世界の四聖編ベスト3(前編)」
262.
2019(令和元)年12月31日号(No.262)「私の読書論127-
読書生活書籍購入50年(6)50代以降リアル編ベスト3(後編)」
~【「世界の四聖編」ベスト3ぐらい】(順位はありません)~~
(1)孔子:『論語』
(2)ブッダ:『原始仏典(初期仏典)』から『スッタニパータ』
(3)ソクラテス:プラトン“ソクラテス対話篇”から「クリトン」
・・・
この年の月末「古典紹介編」は、引き続き古代中国の思想・哲学編で、
諸子百家を読み進めています。
月半ばの発行号の「私の読書論」では、5月に入り平成から令和へと
御代代わりしたのに合わせて、「読書生活&書籍購入50年」と題して、
私の読書生活および書籍購入50年の歴史を少しひもといてみました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本誌では、「私の読書論154-荒俣宏『喰らう読書術』から~本は出会い」をお届けしています。
今回も、全編公開しました。
・・・
言い訳になりますが、今月は、2月10日が<左利きグッズの日>ということで、週刊誌やテレビで左利き関連の情報が流れ、それに関する記事をブログに挙げていました。
その原稿書きなどで時間を取られ、こちらの原稿書きおよびそれに先立つ資料読みなどがおろそかになり、思うように書けませんでした。
「毎度のことや!」という声も聞こえそうですが、内容の薄いものになりました。
次回に「乞う、ご期待!」ということで……。
・・・
では、弊誌を面白いと思われた方は、購読のお申し込みを!
*本誌のお申し込み等は、下↓から
(まぐまぐ!)『(古典から始める)レフティやすおの楽しい読書』
『レフティやすおのお茶でっせ』
〈メルマガ「楽しい読書」〉カテゴリ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
--
『レフティやすおのお茶でっせ』より転載
私の読書論154-荒俣宏『喰らう読書術』から~本は出会い-楽しい読書312号
--
2022(令和4)年2月15日号(No.312)「私の読書論154-
荒俣宏『喰らう読書術』から~本は出会い」
------------------------------------------------------------------
◇◆◇◆ 古典から始める レフティやすおの楽しい読書 ◆◇◆◇
------------------------------------------------------------------
2022(令和4)年2月15日号(No.312)「私の読書論154-
荒俣宏『喰らう読書術』から~本は出会い」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
先人の読書論や読書術のノウハウ本を読み、紹介を兼ねて、
私なりの読書論を語るシリーズ、というところでしょうか。
今回は、高校生時代に翻訳書を読み、
それ以来、その活躍ぶりを拝見してきました、
私と共通する読書の好みを持つ作家である
荒俣宏さんの本・読書に関する著書『喰らう読書術』から――

(画像:荒俣宏さんの若かりし頃の団精二名義の翻訳書『征服王コナン』『異次元を覗く家』ハヤカワSF文庫)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- 私の読書論154 -
◆ 読書 ◆
~ 本は出会い ~
荒俣宏『喰らう読書術』から――
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●荒俣宏『喰らう読書術』
作家・博物学者の荒俣宏さんの読書術の本

荒俣宏『喰らう読書術――一番おもしろい本の読み方』
ワニブックスPLUS新書 2014/6/9
から、気になる部分を紹介します。
まず本書について――(《》内は、出版社の紹介文より)
《「知の巨人」荒俣宏、初めての読書術本!》で、
さすがにちょっと通り一遍の、自分のオススメ本を並べるといった
読書ノウハウ本とは異なります。
知的好奇心をくすぐる「本」の魅力の部分を語り、
《どんな本でも面白く読め、頭の栄養になる読書の極意を伝授します!》
というものです。
ただAmazonのレヴューにもあるように、やや散漫な部分、特に後半、
だんだん読書術的なノウハウ本というより、
ご自身の読書体験に基づき「本」の持つ魅力を語る、
という内容になって、荒俣ファン以外には、
ちょっと読みにくいものになっているかもしれません。
私は楽しく読みましたが、一般的な読書ガイドや読書本にありがちな、
必読書ガイドといったものはなく、
ご自身のお好みの本、影響を受けた本を紹介し、
たぶんに人の薦めない、しかしご自身の認める本を、
一人でも多くの人に知ってもらいたい、という熱意で書かれています。
●本を置く生活のノウハウ
冒頭の「はじめに――読書はおもしろいはずだが、実際はつらい」に、
《身の回りにいつも本を置く生活のノウハウ》のポイントとして、
三つあげています。
・本を読むという手間を惜しまない
・本棚には読まなくても本を並べる楽しみがある
・真の読書は、読むことに直接の利益を期待しないことである
(p.6)
「本」「読書」というのは、「頭の栄養」摂取だといいます。
毎日ご飯を食べるように、本を読む。
読書にはそれだけの価値があるといいます。
ただバーチャルな食べ物なので、いくらでも食べられる。
そこで、つい食べ過ぎになる。
本を読みすぎると、変になる、とも書いています。
そこで「ダイエット」も必要だと説いています。
で、そんなに本を読んでどんな偉い人間になったのか、
という問いに対して、
荒俣さんの答えが「らしい」ものになっています。
《正直に、はっきり申します。
聖人にも、悪人にも、また偉い物知りにも、なれません。
ただ一つ、メリットといえば、人生に退屈せずに済んだことです。》
(p.8)
いかにも荒俣さんらしいでしょ。
ただし、そういう実績ではなく、
可能性に目をむければ、大きな可能性が秘められている、と。
《私には、まだ知りたいこと、したいことがたくさんあるからです。
それが実現する方向へ手助けをしてくれるのが、
このやっかいで場所塞ぎだけれども、
手元に置いて大事にするべき本の山である、
といってよろしいかと思います。
仲良くなった本は、
自分をどこかに導いてくれる「先達」にも変身できる、
ということでしょう。》(p.8)
●「読書」と「本」を知る7つの「急所」
第一章で<「読書」と「本」を知る7つの「急所」>として、
7項目を挙げ、それぞれについて説明しています。
とりあえず項目を挙げておきましょう。
・急所その1
読書は「精神の食事」――でも、食わなくても死なない!
・急所その2
頭が要求する「栄養」は、かならずしも読書だけではない
・急所その3
本は全部読まないと、わからない
・急所その4
本は自腹で買え それだけ真剣に読みたくなる
・急所その5
世界の見方を一変させる「目から鱗」の本を探せ
・急所その6
毒本、クズ本でも、薬に変えられる
・急所その7
読書をおもしろくさせる「おもしろ感度」を磨け
今後、これらからいくつか気になる点を随時見ていこうと思います。
●読書も本との出会いから始まる
まずは、今回は、その一回目、
手始めにこんな言葉について見ておきましょう。
その6で、恋と同じで、読書も本との出会いから始まる、といいます。
で、《自分でみつけることが大切です。》(p.54)と。
そして、ここがキモだといい、
《「よい本だけに巡り合うのではない」からこそおもしろのです。》
(p.54)と。
さらに、
《「品質」には関係ない、ある種の魅力がかならずある、
と考えています。本はクズでも宝になり得るのです。》(p.55)
といい、
《クズか宝かを決めるのは、自分である》(p.62)といいます。
《まわりの評価を最終的には優先させるな》といいます。
世間ではもう相手にしなくなった本であって、
そこに自分だけの価値を見いだすこともある、というわけです。
人によって、何を求めるかが異なります。
当然、価値観も違い、本の“宝物観”も異なってくるでしょう。
自分だけの宝物となる本もあるというわけです。
そして、それをどこで知るか、どうやって見つけるか、
という問題があります。
そのためには、勘を磨かなければいけない、
この本は、何かを見つけられそうな本だなあ、という勘を。
本は全部読んでみないと分からないものです。
それは、人の場合と同じでしょう。
人との出会いと。
どういう人なのかは、ぱっと見だけではわかりません。
実際に交際してみないと本当のところは分からないものです。
それでも、この人は? という勘をもっていれば、
第一印象でもある程度のところは分かるものです。
第一印象というのは、すべてを信用してはいけませんが、
思えば「結構当たっている」というものではないでしょうか。
本の場合も同じで、ある程度の勘を持っていれば、
自分の必要とする本かどうかは、大まかなところはわかるものです。
で、そういう本は、とりあえず買っておく。
今すぐ読まなくても、いずれ時が来れば、読めますし、
読んでよかった、という気になるものです。
・・・
本日はこの辺で。
当初書こうとしていた内容とは異なったものになりました。
次回、7つの急所から、
「本は、全部読まないとわからない」「本は、自腹で買え」
について書いてみます。
できれば、本のメリット・デメリットなども。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★創刊300号への道のり(12) 2019(平成31/令和元)年(12年目)
239.
2019(平成31)年1月15日号(No.239)-190115-
「私の読書論115-私の年間ベスト2018(後編)フィクション系」
●私の今年2018年〈フィクション系〉ベスト1
~ 母の愛と魔法の時 ~『紙の動物園 ケン・リュウ短篇傑作集1』
ケン・リュウ 古沢嘉通編訳 ハヤカワ文庫SF
240.
2019(平成31)年1月31日号(No.240)-190131-「古代中国編―
中国の古代思想を読んでみよう(27)
古代中国における「天」の思想について」
241.
2019(平成31)年2月15日号(No.241)-190215-
「私の読書論116-楽しみのための読書〈怪盗ニック〉退場」
242.
2019(平成31)年2月28日号(No.242)-190228-「古代中国編―
中国の古代思想を読んでみよう(28)『荀子』性悪説と異端の儒家」
243.
2019(平成31)年3月15日号(No.243)-190315-
「私の読書論117-『荀子』「勧学篇」から学問のすすめ」
244.
2019(平成31)年3月31日号(No.244)-190331-「古代中国編―
中国の古代思想を読んでみよう(29)『荀子』性悪説と現実主義」
245.
2019(平成31)年4月15日号(No.245)-190415-
「私の読書論118-読書の仕方あれこれ~ペラペラ読み」
246.
2019(平成31)年4月30日号(No.246)-190430-「古代中国編―
中国の古代思想を読んでみよう(30)『韓非子』 」
247.
2019(令和元)年5月15日号(No.247)-190515-
「私の読書論119-読書生活&書籍購入50年」
248.
2019(令和元)年5月31日号(No.248)-190531-「古代中国編―
中国の古代思想を読んでみよう(31)『韓非子』後編」
249.
2019(令和元)年6月15日号(No.249)-190615-
「私の読書論120-読書生活&書籍購入50年(2)私のお気に入り」
250.
2019(令和元)年6月30日号(No.250)-190630-
「2019年岩波文庫フェア「名著・名作再発見!」小さな一冊...」
「2019年 岩波文庫フェア「名著・名作再発見!」
小さな一冊をたのしもう」から芥川竜之介『羅生門・鼻・芋粥・偸盗』
251.
2019(令和元)年7月15日号(No.251)-190715-
「私の読書論121-読書生活書籍購入50年(3)短編集が好き」
252.
2019(令和元)年7月31日号(No.252)
「新潮・角川・集英社<夏の文庫>フェア2019から」
253.
2019(令和元)年8月15日号(No.253)
「私の読書論122-空海/弘法大師に関する本」
254.
2019(令和元)年8月31日号(No.254)
「お休みのお知らせ&少し空海のお話を」
255.
2019(令和元)年9月15日号(No.255)
「私の読書論123-追悼・横田順彌-明治SFを読む」
256.
2019(令和元)年9月30日号(No.256)-190930-「古代中国編―
中国の古代思想を読んでみよう(32)『孫子』前編」
257.
2019(令和元)年10月15日号(No.257)
「私の読書論124-蔵書と人生」
258.
2019(令和元)年10月31日号(No.258)-191031-「古代中国編―
中国の古代思想を読んでみよう(33)『孫子』後編」
259.
2019(令和元)年11月15日号(No.259)「私の読書論125-
読書生活書籍購入50年(4)初期(20代前半)リアル編ベスト3」
260.
2019(令和元)年11月30日号(No.260)
「クリスマス・ストーリーをあなたに~(9)
『その雪と血を』ジョー・ネスボ」
261.
2019(令和元)年12月15日号(No.261)「私の読書論126-
読書生活書籍購入50年(5)リアル編
-50代以降・世界の四聖編ベスト3(前編)」
262.
2019(令和元)年12月31日号(No.262)「私の読書論127-
読書生活書籍購入50年(6)50代以降リアル編ベスト3(後編)」
~【「世界の四聖編」ベスト3ぐらい】(順位はありません)~~
(1)孔子:『論語』
(2)ブッダ:『原始仏典(初期仏典)』から『スッタニパータ』
(3)ソクラテス:プラトン“ソクラテス対話篇”から「クリトン」
・・・
この年の月末「古典紹介編」は、引き続き古代中国の思想・哲学編で、
諸子百家を読み進めています。
月半ばの発行号の「私の読書論」では、5月に入り平成から令和へと
御代代わりしたのに合わせて、「読書生活&書籍購入50年」と題して、
私の読書生活および書籍購入50年の歴史を少しひもといてみました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本誌では、「私の読書論154-荒俣宏『喰らう読書術』から~本は出会い」をお届けしています。
今回も、全編公開しました。
・・・
言い訳になりますが、今月は、2月10日が<左利きグッズの日>ということで、週刊誌やテレビで左利き関連の情報が流れ、それに関する記事をブログに挙げていました。
その原稿書きなどで時間を取られ、こちらの原稿書きおよびそれに先立つ資料読みなどがおろそかになり、思うように書けませんでした。
「毎度のことや!」という声も聞こえそうですが、内容の薄いものになりました。
次回に「乞う、ご期待!」ということで……。
・・・
では、弊誌を面白いと思われた方は、購読のお申し込みを!
*本誌のお申し込み等は、下↓から
(まぐまぐ!)『(古典から始める)レフティやすおの楽しい読書』
『レフティやすおのお茶でっせ』
〈メルマガ「楽しい読書」〉カテゴリ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
--
『レフティやすおのお茶でっせ』より転載
私の読書論154-荒俣宏『喰らう読書術』から~本は出会い-楽しい読書312号
--