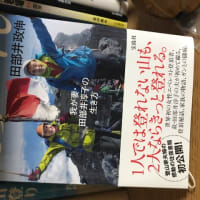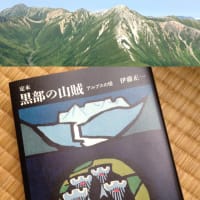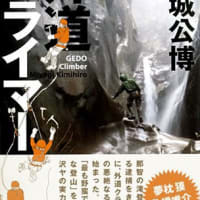年末に一挙再放送していた「ブラッシュアップライフ」。
改めて見て脚本の完成度に惚れ惚れしてしまったので、このドラマの脚本のどこがすごいのか、ちょっと考えて書いてみたいと思う。
(私は職業がディレクターですが、あくまで一視聴者としてこのドラマを見た感想です。)
最初のうちは、「女子トークのわかり味」とか「地元あるある」とか、5分に1度は笑える小ネタ満載の快作という風情で、
それだけでも十分面白かったし毎週楽しみにしていた。ところが終盤に向かう8話で、一気に物語の位相をガラッと変わってしまう事実が発覚。
この「ターニングポイント」と、そこで明かされる物語の「本当の目的」が衝撃的で、一気に感動作に姿を変えたところが、本当に鮮やかで、
「素晴らしい脚本」という印象を残したんだと思う。
(もちろん、このターニングポイントを圧巻の演技で表現した安藤サクラさんあっての素晴らしさだとも思う。)
ここで生じてきたのが、この構成、一体どんなテンプレを使っているのだろう?という疑問だ。
一般に日本の物語のテンプレは「起承転結」、西洋のテンプレは「三幕構成」というのがよく言われるところ。
実はこのテンプレ、フィクションの世界にとどまらず、事実を扱うドキュメンタリーの世界でもよく使われている。
ある程度既存のフォーマットを使ってシーンを組み立てていくことで、バラバラに存在していた事実や情報が
「ストーリー」という一本の線になり、見る側により強いメッセージを伝える効果があるからだと思う。
意識的にせよ、無意識的にせよ、プロの制作者はある程度、こうしたテンプレを使って、日々物語を紡いでいる。
ここでブラッシュアップライフに戻ると、この物語は「起承転結」スタイルに近いのではないかと感じた。
いわゆる「ハリウッド作品」などは「三幕構成」がベースになっていて、一つの物語の中に2つの大きな山場を作る構成が基本だ。
この構成を使うことで、同じ時間でもジェットコースターのように緩急の差がはっきりするため、物語の緊張感を維持しやすくなる。
テレビ制作の現場で使われる「ペタペタ」という付箋を並べた構成表で見るとこの傾向は明らかで、
30分でも60分でも、視覚的に二つの山ができるように付箋の分量を整えていくと、確かに見やすくなっていくから不思議だ。
一方、「起承転結」スタイルは、基本的には一山のため、「転」に至るまでは、よりゆるやかに物語が展開する傾向がある。
ざっくりいうと、こうした違いがあるため、少し構成論をかじった日本の制作者は、「三幕構成」に利があるように考えがちだし、
実際多くの人が取り入れようと試みている。
ところが、「ブラッシュアップライフ」の1話~10話を一つの物語として見ていくと、
立ち上げはシャープで明快ながら、そのあとは割と平坦な道のりが続き、6話目の後半あたりから徐々に上昇、
9話目、10話目で一気に山場を迎える「一山スタイル」に見える。
これはつまり「起承転結」スタイルとみることができるのではないか。
しかも起承転結は、下手をすると中だるみを招く難易度の高いものとされる中、この脚本はうまく乗り切っている。
なぜなのか?それを可能にしているのが、この物語の「特殊性」にあると思う。
それは、物語の本当の目的を、かなり終盤まで明かさない、という点だ。
通常、物語の「鉄則」とされるのは、冒頭部分で「主人公と、置かれた環境、その人物が果たすべき目的=セントラルクエスチョンを明確にする」ことだ。
これがすんなり打ち込めれば、その後は、幾多の試練をこえて、主人公はそれを達成できるのか?という目線で見ていくことができる。
銀河に平和を取り戻すため反乱軍に加わったルーク・スカイウォーカーしかり、
ドラゴン・ボールを探して旅に出る孫悟空しかり、通常は冒頭から主人公の目的はかなりはっきりしている。
逆に、この「セントラルクエスチョン」さえはっきりしていれば、日常のどんなささやかな出来事も物語化できる。
「3歳の子供が初めてのおつかいに成功できるのか」、という目的があれば、
信号の横断や、買い物袋のにおいをかぐ猫の登場、といった平凡な出来事も、立ちはだかる壁として見ることができるからだ。
しかし「ブラッシュアップライフ」に関しては、肝心のセントラルクエスチョンが不明瞭なまま、後半まで物語が進んでいく。
一応「人間に生まれ変わるために徳を積む」という目的は提示されるものの、その手段もはっきりしないし、
主人公も職業など目先を変えてはみるものの、なぜか根本解決に向かっているようには見えない。
この状態は、ふつうに考えたら物語を進める上では不利なはずだ。
ところが終盤、「親友の死」という隠されていた真実が明かされることで、物語は一気に動き出す。
私自身、「死ぬのは毎回主人公の側」という思い込みを抱いていたため、これには結構衝撃を受けた。
さらに、何度生まれ変わっても、職業を変えてみても、本質的にたいして成長していなかった主人公が、
この最後の大転換によって、初めて自分にとっての人生の意味に気づき、本気で生きなおす展開は、
最初に見えていた「ちょっと笑えるお話」の枠を大きく飛び越えて、強いメッセージ性を帯びていたと思う。
そんな濃密な展開が、最後の「転」のあとに一気に展開したことで、それまでのゆるやかな時間の流れもある種の伏線となり、
最後の人生をより強烈に見せていたのだ。
構成の話に戻ると、「三幕構成」の方が盛り上がるから使う、という考えはありだとは思うけれど
そこに頼らなくても面白くする手段はあるし、もともと日本が持っていた「起承転結」の構成も、使い方によっては
すごく可能性あるんじゃないか、というのがこの脚本から感じたことだ。
YOASOBIの「アイドル」も、ドメスティックな「よなぬき音階」を使いながら、世界にアピールする洗練された音に仕上げたともいわれるが、
日本人が習慣的に持ってる物語のテンプレにも、色んな可能性があるんじゃないかと思うのだ。
そんなちょっと壮大なことをつらつら考えてしまうくらい、ブラッシュアップライフの脚本はすごかった。
そして、そんな面白い脚本に触発されて、役者もスタッフも全力でモノづくりしたから、こんな素敵な作品に仕上がったんだろうな、と思う。
改めて見て脚本の完成度に惚れ惚れしてしまったので、このドラマの脚本のどこがすごいのか、ちょっと考えて書いてみたいと思う。
(私は職業がディレクターですが、あくまで一視聴者としてこのドラマを見た感想です。)
最初のうちは、「女子トークのわかり味」とか「地元あるある」とか、5分に1度は笑える小ネタ満載の快作という風情で、
それだけでも十分面白かったし毎週楽しみにしていた。ところが終盤に向かう8話で、一気に物語の位相をガラッと変わってしまう事実が発覚。
この「ターニングポイント」と、そこで明かされる物語の「本当の目的」が衝撃的で、一気に感動作に姿を変えたところが、本当に鮮やかで、
「素晴らしい脚本」という印象を残したんだと思う。
(もちろん、このターニングポイントを圧巻の演技で表現した安藤サクラさんあっての素晴らしさだとも思う。)
ここで生じてきたのが、この構成、一体どんなテンプレを使っているのだろう?という疑問だ。
一般に日本の物語のテンプレは「起承転結」、西洋のテンプレは「三幕構成」というのがよく言われるところ。
実はこのテンプレ、フィクションの世界にとどまらず、事実を扱うドキュメンタリーの世界でもよく使われている。
ある程度既存のフォーマットを使ってシーンを組み立てていくことで、バラバラに存在していた事実や情報が
「ストーリー」という一本の線になり、見る側により強いメッセージを伝える効果があるからだと思う。
意識的にせよ、無意識的にせよ、プロの制作者はある程度、こうしたテンプレを使って、日々物語を紡いでいる。
ここでブラッシュアップライフに戻ると、この物語は「起承転結」スタイルに近いのではないかと感じた。
いわゆる「ハリウッド作品」などは「三幕構成」がベースになっていて、一つの物語の中に2つの大きな山場を作る構成が基本だ。
この構成を使うことで、同じ時間でもジェットコースターのように緩急の差がはっきりするため、物語の緊張感を維持しやすくなる。
テレビ制作の現場で使われる「ペタペタ」という付箋を並べた構成表で見るとこの傾向は明らかで、
30分でも60分でも、視覚的に二つの山ができるように付箋の分量を整えていくと、確かに見やすくなっていくから不思議だ。
一方、「起承転結」スタイルは、基本的には一山のため、「転」に至るまでは、よりゆるやかに物語が展開する傾向がある。
ざっくりいうと、こうした違いがあるため、少し構成論をかじった日本の制作者は、「三幕構成」に利があるように考えがちだし、
実際多くの人が取り入れようと試みている。
ところが、「ブラッシュアップライフ」の1話~10話を一つの物語として見ていくと、
立ち上げはシャープで明快ながら、そのあとは割と平坦な道のりが続き、6話目の後半あたりから徐々に上昇、
9話目、10話目で一気に山場を迎える「一山スタイル」に見える。
これはつまり「起承転結」スタイルとみることができるのではないか。
しかも起承転結は、下手をすると中だるみを招く難易度の高いものとされる中、この脚本はうまく乗り切っている。
なぜなのか?それを可能にしているのが、この物語の「特殊性」にあると思う。
それは、物語の本当の目的を、かなり終盤まで明かさない、という点だ。
通常、物語の「鉄則」とされるのは、冒頭部分で「主人公と、置かれた環境、その人物が果たすべき目的=セントラルクエスチョンを明確にする」ことだ。
これがすんなり打ち込めれば、その後は、幾多の試練をこえて、主人公はそれを達成できるのか?という目線で見ていくことができる。
銀河に平和を取り戻すため反乱軍に加わったルーク・スカイウォーカーしかり、
ドラゴン・ボールを探して旅に出る孫悟空しかり、通常は冒頭から主人公の目的はかなりはっきりしている。
逆に、この「セントラルクエスチョン」さえはっきりしていれば、日常のどんなささやかな出来事も物語化できる。
「3歳の子供が初めてのおつかいに成功できるのか」、という目的があれば、
信号の横断や、買い物袋のにおいをかぐ猫の登場、といった平凡な出来事も、立ちはだかる壁として見ることができるからだ。
しかし「ブラッシュアップライフ」に関しては、肝心のセントラルクエスチョンが不明瞭なまま、後半まで物語が進んでいく。
一応「人間に生まれ変わるために徳を積む」という目的は提示されるものの、その手段もはっきりしないし、
主人公も職業など目先を変えてはみるものの、なぜか根本解決に向かっているようには見えない。
この状態は、ふつうに考えたら物語を進める上では不利なはずだ。
ところが終盤、「親友の死」という隠されていた真実が明かされることで、物語は一気に動き出す。
私自身、「死ぬのは毎回主人公の側」という思い込みを抱いていたため、これには結構衝撃を受けた。
さらに、何度生まれ変わっても、職業を変えてみても、本質的にたいして成長していなかった主人公が、
この最後の大転換によって、初めて自分にとっての人生の意味に気づき、本気で生きなおす展開は、
最初に見えていた「ちょっと笑えるお話」の枠を大きく飛び越えて、強いメッセージ性を帯びていたと思う。
そんな濃密な展開が、最後の「転」のあとに一気に展開したことで、それまでのゆるやかな時間の流れもある種の伏線となり、
最後の人生をより強烈に見せていたのだ。
構成の話に戻ると、「三幕構成」の方が盛り上がるから使う、という考えはありだとは思うけれど
そこに頼らなくても面白くする手段はあるし、もともと日本が持っていた「起承転結」の構成も、使い方によっては
すごく可能性あるんじゃないか、というのがこの脚本から感じたことだ。
YOASOBIの「アイドル」も、ドメスティックな「よなぬき音階」を使いながら、世界にアピールする洗練された音に仕上げたともいわれるが、
日本人が習慣的に持ってる物語のテンプレにも、色んな可能性があるんじゃないかと思うのだ。
そんなちょっと壮大なことをつらつら考えてしまうくらい、ブラッシュアップライフの脚本はすごかった。
そして、そんな面白い脚本に触発されて、役者もスタッフも全力でモノづくりしたから、こんな素敵な作品に仕上がったんだろうな、と思う。