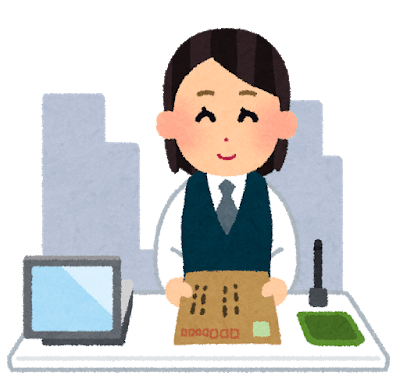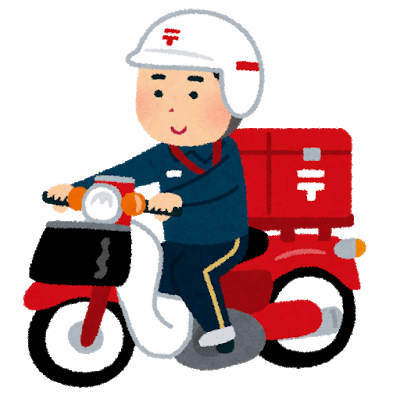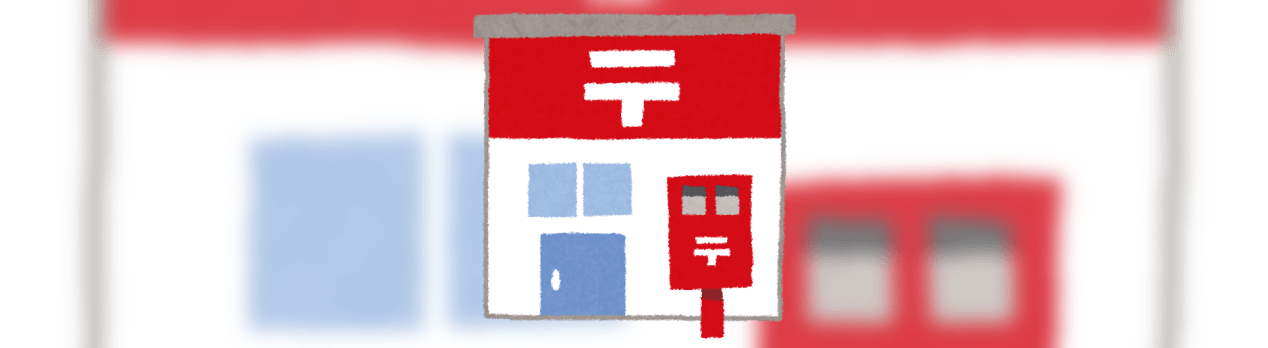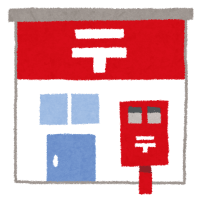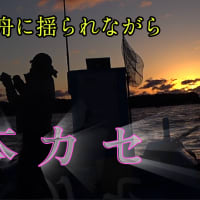「郵便局」赤字転落で蠢く「再国営化」の大愚策
フォーサイト-新潮社ニュースマガジン
時事通信
「郵便局は国営に戻さないと維持できない」
最近、そんな声を永田町で耳にすることが増えた。「日本郵政」の増田寛也社長が有力国会議員などを回り、「窮状」を訴えていることが背景にある。
日本郵政が11月13日に発表した9月中間期の連結決算では純利益が1789億円と24.4%減り、子会社で郵便事業を営む「日本郵便」の純損益は65億円の赤字となった。中間期で赤字に転落するのは3年ぶりのことだ。
新型コロナウイルスの蔓延で、「アマゾン」など宅配サービスが大きく伸びた中で、日本郵便は赤字に転落したのだ。
中略
もともと銀行と保険の金融2社は「民業圧迫」を避けるために、政府が日本郵政を通じて保有している株式を売却、「完全民営化」するはずだった。民主党政権下でその期限が先送りされ、自民党政権に復帰しても、ゆうちょ銀行とかんぽ生命の2社は政府の「孫会社」のままだった。ようやくそれから脱却するとしたのである。
子会社から外れない限り、新規事業の開始などに制約があるため、株式売却は金融2社にとっても念願である。しかし、金融2社と日本郵政の親子関係が薄れれば、郵便局に委託している事務手数料の支払いが一段と減っていくことが予想される。そんなこともあってか、独立行政法人への拠出金は子会社でなくなっても支払い義務が残るとされている。
それでも、ジワジワと郵便局維持のために金融2社から入ってくる収入は減ることは避けられないだろう。さらに、かんぽ生命の不正の影響が、2021年度に一気に現れてくることになれば、金融収益で郵便局網を支えるという長年の「構造」が限界にくる。もはや郵政グループの収益だけで、郵便局を維持することは難しい。だからこそ、郵便局を維持するには「再国営化」しかない、というわけだ。
日本郵政からそうした内情を明かされ、「郵便局は地域の拠点として重要」
「雇用を維持する上でも守る必要がある」と言われた政治家は、「確かにそうだ」と思うに違いない。自民党の大物議員の1人も、「郵政が大変なことになっている」と語っていた。
自民党のベテラン議員からすれば、郵便局が長年「集票マシン」として機能してきたという思いもある。何としても郵便局網を残すことが重要だ、と感じるに違いない。
下がる存在意義
だが、全国に2万4000近くある郵便局に税金を投入して維持する必要は本当にあるのだろうか。
インターネットが普及する中で郵便の取扱量は大きく減り、小包も民間事業者の宅配荷物に押されている。さらに、インターネットバンキングの普及や、非現金決済の広がりで、「郵便局」という拠点の重要性も落ちている。
銀行でさえ、リアル店舗を閉鎖したり、最近ではATM(現金自動預け払い機)も減らしたりしている。
にもかかわらず、日本郵便はビジネスモデルをほとんど見直していない。
直営郵便局は、この8年で2万176から2万47に129減っただけだ。外部に委託してきた簡易郵便局は281減っているが、直営郵便局は金融収益からの「ミルク補給」によって、まったく見直されずに存続してきたのである。
地方に行くと、町おこし関係者のほとんどは、コンビニエンス・ストアが欲しい、と口を揃える。郵便局を残して欲しい、という声は、関係者以外からはほとんど聞かれない。コンビニならばATMもあり、手紙を出すポストもある。
70歳以上でパソコンを触らない人もいるが、あと10年もすれば大半の人が、インターネットでほとんどの金融取引ができるようになる。確実に郵便局の存在意義は下がっていく。そこに税金を投じる意味はまずないだろう。
中略
しかも、そうした民営化会社の多くに「官業」へのノスタルジーがくすぶり続けている。人口減少が鮮明になり、事業自体が成り立たなくなる中で、そうした「官業回帰」への思いは一段と強くなっているように見える。(2020年12月)
【筆者紹介】1962年生れ。早稲田大学政治経済学部卒。87年日本経済新聞社に入社し、大阪証券部、東京証券部、「日経ビジネス」などで記者。その後、チューリヒ支局長、フランクフルト支局長、東京証券部次長、「日経ビジネス」副編集長、編集委員などを務める。現在はフリーの経済ジャーナリスト。著書に『2022年、「働き方」はこうなる』 (PHPビジネス新書)、『国際会計基準戦争 完結編』、『ブランド王国スイスの秘密』(以上、日経BP社)、共著に『株主の反乱』(日本経済新聞社)、『破天荒弁護士クボリ伝』(日経BP社)、編著書に『ビジネス弁護士大全』(日経BP社)、『「理」と「情」の狭間――大塚家具から考えるコーポレートガバナンス』(日経BP社)などがある。
【 所 感 】
『財政健全化』も『郵政民営化』も、要は必要がなかったし、意味のない論調だったことが近年明らかとなってきたわけだ。
『聖域なき(=何でもありの)構造改革』と名のもと、小泉純一郎・竹中平蔵路線を国民に煽ってきたのは小奴らマスメディアであって、当記事の日経新聞元記者の論など、煽り運転した奴が開き直ったような言い草をしているようにしか思えない。
バブル当時、民間レベルでは高収入を上げバカ騒ぎしている中、郵便局員の人たちは公務員の立場にあって、ひたすらに定収入でありながらも真面目にコツコツと業務を果たされてきたわけだ。ところが、バブル崩壊後は民営化されたことで、安定収入を得られない民間レベルに追いやられ、今度は公務員がバラ色という捻れをまともに喰らっているという現状をまずは考慮すべきだ。
ところが何だっ!。経済を語る連中からは、こうした実務に携わる人たちの立場に立った論調が全くといって聞こえてこないではないか。
それでよく、経済ジャーナリストとか名乗れたものだ。
そして、当初より、「郵政民営化はあかんやろう」といっていた知識人たちも大勢いてたわけだから、そうした人たちの言葉も改めて取り上げるべきではないのか。
とにもかくにも、以前、東京都知事選にも出馬されていたメガネのよく似合うおじさん・増田寛也社長には是非とも頑張っていただきたい。
また、この経済ジャーナリストのいうネット環境が整った社会とやらだけで、いざ何かしらの有事が発生した場合において、果たして地域住民を守ることに繋がるのかどうか、甚だ疑問である。
なんのためのインフラ整備なのか、なんのための税金投入なのか、そのあたりももっとよく学ぶべきであろう。