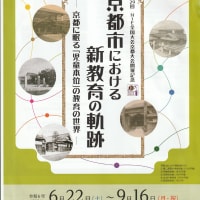ここからは公判の状況を見ていきたい。
予審決定書を受けて、翌27(昭和2)年4月4日、京都地方裁判所第一号法廷において京都学連事件の公判が行われた。
しかし早くも、公判第二日目の4月5日に法廷内が混乱する。混乱の原因を作ったのはこの裁判を担当している荒井裁判長の言動であった。荒井裁判長は被告の学生達に対し「お前」という言葉を連呼した。それに対し大浦梅夫らが猛反発をしたのだ。このことが原因となり、公判では被告学生たちの抗議を収めることや、これ以上の混乱を回避するために特に審議は行われずに終了する。(注1)
公判第三日目の4月6日、この日の証言者は山崎雄次と鈴木安蔵とであったが、二人とも予審調書作成時に検事により肉体的・精神的苦痛を受けさせられ、予審調書を作成されたという発言を行った。
山崎は「予審調書昨年一月我々の友人二十余名を拘束して外部との交通をたち検事は誘導手段によつて我々の精神並に肉体を苦しめて造りあげたものを故相違の点があるプリントの『テーゼ』が大会の席上配布」されたとし、鈴木は「第二回大会(中略)当日警察のスパイ並に学生監が出席して我々の行動を監視して休憩後も我々の一挙一動に監視の目を放たぬ行為から予審廷の取調べに際し当該某予審判事は予審判事といふものは裁判所の番頭の如きもので検事の指揮による調書に基いて法律に適応するやうに調書を作成するのが職務であると言つて調書に拇印を余儀なくされた点並に検事調べに於ける慰撫的、罵倒的取調べ法に不法」であると主張した。(注2)
公判第四日目の4月 7日、この日の証言者も予審調書作成時に検事によって苦痛を受けたことを証言した。
村尾薩男はテーゼについて「本件には何等関係もないのに関係あるものの如く検事が扱はれた点には皮相な努力の跡が見える」とし、野呂栄太郎は「学校当局は絶えず警察側と気脈を通じて我々の行動につき微に入り細に亘つて報告する」といい、秋笹正之輔は「自分が常任委員会に出席せぬのにした如く調書に現はれてゐることは如何にして作られたものか不満に思ふ」とし、実川清之は「野呂の供述を以て私の供述として調書され飽く迄も治安維持法に問はんとした点が見えたので半日間も予審判事と論戦した」といい、衣谷賀真は関東連合総会に(中略)閉会前に赴き(中略)如何なることが上程され又如何なることが議決されたかは一向に知らぬ私に対してその模様を御訊ねになるとは至当を欠くものではあるまいか」と言った。(注3)
また、同じ公判第四日目には、裁判所の速記係への不満も出る。石田英一郎は「我々は一見一句は速記に於て書かれてゐるものと思ふが若し供述に相違点を見たときは如何なる策を講ずべきか」といい、淡徳三郎は「係書記は我々の供述を書くにあたつて時にはペンをやすめて人の顔を見てゐるやうなことがあるが之では相違を来たれす処があるから裁判長からもよく申付けて厳重に書き認めて貰ひたい」と発言し、公判の公平性について疑問を呈している。(注4)
公判第五日目の4月8日、この日も予審調書作成時の検事側の態度が問題とされた。
熊谷孝雄は「プロカル運動に関するテーゼ作成のために委員が挙げられた云々のことは明確に記憶がない点から本事件勃発当時被告が単なる出版法違反として検挙され検事廷での取調べにあたりわつてもつて治安維持法違反に結び付けられた道程には甚だしきトリツクが存してゐた、予審廷では我々の正しき行動を一定の法に引き入れんとする努力に対して一言した所予審判事は『これも職業の悲哀ですかね』と答へビジネスライフの本領を示して検事の調書そのまゝを引き写してゐたと主張し予審調書に記載の供述相違点並に治安維持法に亘つて」述べ、泉隆は「十月十八日開いた研究会の会合に出席した有無のみにつき十数回検事から誘導尋問をうけ遂に意識朦朧の折柄心ならずも虚構の事実を陳述し併せて官憲が事実をまげて治安維持法違反に陥入れんとした非合法的行為を真向から」指摘した。(注5)
以上のように、被告学生たちはいずれも予審調書や公判についての公平性や疑問、強引さについて問題視し、自分達の正当性、検察側の不当性を訴えた。
公判第九日目の4月14日、今度は検察側の主張が行われた。古賀検事正がこの事件を「(第一)学生運動一般状勢 (第二)組織及び機構 (第三)学生運動の内容 (第四)無産者教育協会 (第五)特殊運動 (第六)運動の目標 (第七)法律の論点 (第八)現状 (第九)刑の量定」と整理分類し(注6)、南部主席検事が上記の問題点の整理を受けて、予審調書作成時の取り調べの正当性、該事件が治安維持法に抵触しているということを述べ、被告全員に禁固一年~三年を求刑した。
治安維持法の判決を見ていけば、そのほとんどが第一条違反で懲役刑にされている。しかし、京都学連事件においては、国内初の治安維持法適用で、まだ刑をどれくらいにするのか定まってなく、また、確たる証拠もない状況での検挙、国内に日本共産党が存在していない時点での検挙であったため、求刑は比較的軽い禁固刑にされた。
そして公判第十日目の4月16日以降、被告弁護側の証言がはじまる。初日には三人の弁護人が証言。今村力三郎弁護人は「第一、治安維持法の解釈 第二、被告事件たる事実の見解 第三、階級闘争 第四、司法権の行使とその影響 第五、思想と刑罰 第六、重刑主義反対」の6点について述べ、また予審決定書を、検事と予審判事との合作であるという指摘などを行なった。次に弁護人片山哲は「第一、治安維持法適用の不当 第二、内務省司法省の説明曖昧 第三、同法に対する矛盾点 第四、本法は手段が違法なりや否やによりて決定すべきもの 第五、衆議院議員の職務行為と不法問題 第六、立法の沿革 第七、新聞紙法と出版法の対照」などに言及し、弁護人三輪壽壮は「第一、治安維持法の制定に関する私見 第二、私有財産制度の否認実行に対する解釈 第三、本件『協議云々』に対して法的には問題にならざる点 第四、第二回全国大会に於ける会合は検事局側の所謂秘密会ではない点 第五、本件は全く政策的検挙であつた」などを言及した。(注7)
翌日の弁護二日目には、細迫兼光が「裁判所はマルキストの社会的行動は凡てこれを罰せんとするものなるや裁判所は階級闘争に参加せんとするものなりや」の2点を裁判所側へ質問し、そしてこの公判の意味を「被告等は今も現もマルキストたることを主張してゐるのであるから必ず有罪たるを免れない、(中略)即ち本件の根本はマルキストだから問題にされたのである」と指摘し、「運動(注-学連が行なっている無産階級運動)が違法であれば本隊としての無産者自身が行つてゐる解放運動も違法でなければならぬ」として、裁判所側の認識やこの公判の矛盾点を指摘した。(注8)
最終弁護では弁護人清瀬一郎が、無産者運動を何種類かに分類し、その中で学連が行なった無産者運動は「啓蒙運動の一部」とし「治安維持法はかようなものに適用さるべきであろうか」とし、「これが即ち本件の要点であるが同法の本旨は私有財産制度の否定それ自身の実行であつて本件の如き思想の普及即ち啓蒙運動の実行には決して適用さるべきでない治安維持法の適用範囲は政治運動に限られたもので現に経済運動即ち労働組合運動などには本法は少しも適用されてゐない」として、無罪を主張した(注9)
公判は以上で終了するが、判決が出るまでの間の4月27日、唯一不敬罪も適用され起訴された石田英一郎について、京都地方裁判所は大赦令を理由として不敬罪については免訴とする措置をとる。
石田が不敬罪で起訴された原因は何であったか。それは石田の日記にあった。
「一 犯罪事実概要 大正十一年七月中北海道各地巡遊の際、自己の日誌に、「国家主義的忠君愛国ノ偽罔教育ノ不当ナル事、及皇太子殿下御来道ニ際シ国旗掲挙セルヲ見テ、前途遼遠ダト思惟セシ事」を記載し、且つ同年十月三十一日自己の日誌に「第一高等学校ニ於ケル天長節祝日拝賀式ニ参列シタル際ノ感想トシテ、御真影ニ向テ頭ヲ低ク下ゲタリ、勅語朗読ヲ謹聴サセラレタリ、余リノ馬鹿馬鹿シサニ泣キ度クナリシ事、君ガ代ハ歌ハザリシモ憤リト悲シミトテ胸ハ燃ユル許リトナリ、スツカリ反逆者トナリシ」旨を記載したるものなり」(注10)
しかし、この不敬罪というものは「諸刃の剣」であった。不敬罪で検挙するのは非常に簡単なことである。だが公判では検察側もその言動を慎み、言葉を選びながら公判を進めないと自分たちが不敬な言動をしてしまって、取り返しが付かなくなってしまう。そのために不敬罪で検挙したとしても、取り調べの最中で容疑を別のものに切りかえて審理することが多かった。
5月30日、京都学連事件の判決が出る。禁固一年を筆頭に全員有罪であった。この判決は非常に軽いものであった。その理由は今まで述べてきたとおり、この事件にはかなりの無理があったからである。しかし被告側は無罪を主張して即日控訴。(注11)
検察側も判決が軽すぎるとして6月6日に控訴をしている。(注12)
その後、京都学連事件の被告たちは、ある者は三・一五事件に関与し、ある者は無産者新聞に参加していくなどして活動していく。そしてその事件の判決と合わさり、京都学連事件での第二審の判決も非常に重いものへとなっていく。
そして河上肇事件、瀧川事件を経て学生運動は解体され、それまでのような目立った活動は見られないようになっていく。
(注1)「京都日出新聞」1927(昭和2)年4月6日付
(注2)「京都日出新聞」1927(昭和2)年4月7日付
(注3)、(注4)「京都日出新聞」1927(昭和2)年4月8日付
(注5)「京都日出新聞」1927(昭和2)年4月9日付
(注6)「京都日出新聞」1927(昭和2)年4月15日付
(注7)「京都日出新聞」1927(昭和2)年4月17日付
(注8)「京都日出新聞」1927(昭和2)年4月18日付
(注9)「京都日出新聞」1927(昭和2)年4月20日付
(注10)1928年8月「自大正10年至昭和2年不敬事件」 『秘 思想研究資料 第八輯』(『社会問題資料叢書 第1輯 第98回配本』 東洋文化社 1980年3月20日) 18頁
(注11)「京都日出新聞」1927(昭和2)年5月31日付
(注12)「京都日出新聞」1927(昭和2)年6月7日付
(注2)「京都日出新聞」1927(昭和2)年4月7日付
(注3)、(注4)「京都日出新聞」1927(昭和2)年4月8日付
(注5)「京都日出新聞」1927(昭和2)年4月9日付
(注6)「京都日出新聞」1927(昭和2)年4月15日付
(注7)「京都日出新聞」1927(昭和2)年4月17日付
(注8)「京都日出新聞」1927(昭和2)年4月18日付
(注9)「京都日出新聞」1927(昭和2)年4月20日付
(注10)1928年8月「自大正10年至昭和2年不敬事件」 『秘 思想研究資料 第八輯』(『社会問題資料叢書 第1輯 第98回配本』 東洋文化社 1980年3月20日) 18頁
(注11)「京都日出新聞」1927(昭和2)年5月31日付
(注12)「京都日出新聞」1927(昭和2)年6月7日付
この稿おわり