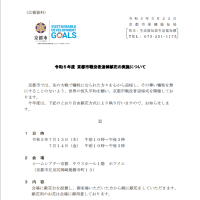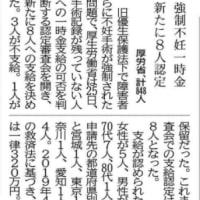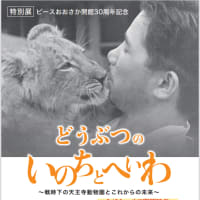予科練精神と宗教心 堀井甚九郎
私はさる二月二日の木曜夕刊の宗教欄で「武士道とは死ぬこととみつけたり」という一文を見て私が青春をささげた予科練時代を回顧して見たいと思いました。「人の為に死んで自己を活かす」という精神は、私達日本人が戦時中に求めた精神的支柱であり、葉隠論語は武士道精神として軍人精神の鑑(かがみ)であったからだと思います。東洋的伝統精神というか仏教や禅の精神に通じるものである。筆者はイエス・キリストの崇高な死をあげられました。何れにしても宗教的理想として永遠に生きる精神であると思います。平和な現代においてはいうはやすく行なうは難しでありますが、戦時中、私が予科練を志願した時の心境は、その様な純粋無雑な心に通ずるものがあったと思います。
昭和十八年十月一日、私は海軍甲種飛行予科練習生として美保航空隊に入隊しました。入隊時、氏神で入隊のあいさつをしました。その要旨を述べ予科練精神を考えたいと思います。「太平洋戦争は益々熾烈を極め今や戦局は重大時機に直面しました。一刻も早く祖国の安泰と人類のために一死以て君恩に報ぜんと決意しました。私は帝国海軍の搭乗員として攻撃精神と犠牲的精神を双翼にこめて一機一艦敵空母に体当り立派に死ぬ覚悟であります」以上のようなものであったと思います。 次に予科練習生として訓練中、その「訓育」という精神訓話の時間を回想して見たい。その時に葉隠論語に「武士道とは死ぬ事と見つけたり」という言葉を聞き鍋島藩士の武士の心構えを説いたものである事を教えられた事が今なお私の頭から離れていなかったと思います。だから、久しぶりになつかしい言葉を目にしてこの投稿を思い立ちました。武士道の根本は己れを捨てる事にある。「身を捨ててこそ浮かぶ瀬もあれ」という諺のあるように死に身になって生きる葉隠武士の心であると思う。私達の海軍生活の中では、犠牲的精神の発揮という事であると思う。自分さえ良ければそれでよいのではない、みんなが良くなければダメなのである。私達、練習生は、自分の班全体のために進んで働きに出る事によって、喜びを見出しました。一回の訓練を終わり温習時間の最後の五分間、五省を唱え自分自身を反省したのであります。それを次に挙げて見ます。一,至誠に悖(もと)るなかりしか 二,言行に恥(は)ずるなかりしか 三,努力に恨(うら)みなかりしか 四,気力に恨みなかりしか 五,無情に亘(わた)るなかりしか いじょうであります。
現在平和な社会生活の中で自分を犠牲にしてみんなのたるに積極進取に働く人間として自分は生きているかと自問した時、もはやそんな余裕も心もありえないと告白しなければならない。自分自身の利害と打算にのみ執着せんとする自分の心を見つめる時、そこから宗教心を求める心が出てくるのではないでしょうか。私の予科練精神は宗教心となって甦ったというべきではないかと思います。(京都市東山区山科四ノ宮川原町一番地 会社員 四十歳)(「京都新聞」 1967年3月2日)