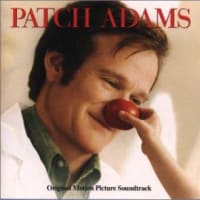https://blog.goo.ne.jp/0345525onodera/e/4ade0a4539483751ec2241efd9f7fc60
「宗教的感情の本質というものは、どんな論証にもどんな過失や犯罪にも、どんな無神論にもあてはまるものじゃないんだ。そんなものには、何か見当ちがいなところがあるのさ。いや、永久に見当ちがいだろうよ。そこには無神論などが上っ面(うわっつら)をすべって永久に本質をつかむことができない、永久に人びとが見当ちがいな解釈をするような、何ものかがあるんだ......」
(『白痴』第2編第4「ムイシュキン公爵の言葉より」
『美ーー美という奴は恐ろしいおっかないもんだよ!つまり,杓子定規に決めることが出来ないから,それで恐ろしいのだ。なぜって,神様は人間に謎ばかりかけていらっしゃるもんなあ。美の中では両方の岸が一つに出会って,すべての矛盾が一緒に住んでいるのだ。俺は無教育だけれど,このことはずいぶん考えぬいたものだ。実に神秘は無限だなあ!この地球の上では,随分沢山の謎が人間を苦しめているよ。この謎が解けたら,それは濡れずに水の中から出てくるようなものだ。ああ美か!その上俺がどうしても我慢できないのは,美しい心と優れた理性を持った立派な人間までもが,往々聖母(マドンナ)の理想を懐いて踏み出しながら,結局悪行(ソドム)の理想を持って終わるという事なんだ。
いや、まだまだ恐ろしい事がある。つまり悪行(ソドム)の理想を心に懐いている人間が,同時に聖母(マドンナ)の理想をも否定しないで,まるで純潔な青年時代のように,真底から美しい理想の憧憬を心に燃やしているのだ。いや実に人間の心は広い,あまり広すぎるくらいだ。俺は出きる事なら少し縮めてみたいよ。ええ畜生,何が何だか分りゃしない、本当に!
理性の目で汚辱と見えるものが,感情の目には立派な美と見えるんだからなあ。一体悪行(ソドム)の中に美があるのかしらん?........しかし,人間て奴は自分の痛いことばかり話したがるもんだよ。
~ドストエフスキー「カラマーゾフの兄弟」第三篇の第三,熱烈なる心の懺悔.....詩
『キリスト教での地獄は一般的に、死後の刑罰の場所または状態、霊魂が神の怒りに服する場所とされる。他方、地獄を霊魂の死後の状態に限定せず、愛する事が出来ない苦悩・神の光に浴する事が出来ない苦悩という霊魂の状態を指すとし、この世においても適用出来る概念として地獄を理解する見解が正教会にある。この見解はドストエフスキーの『カラマーゾフの兄弟』に登場するゾシマ長老の台詞にもみえる。(管理人注:偉大なる罪人の台詞)地獄を死後の場所に限定せず、霊魂の状態として捉える理解は、楽園が霊魂の福楽であると捉える理解と対になっている。』(Wiki地獄より)
ダンテと地獄
地獄界の構造
アケローン川 - 冥府の渡し守カロンが亡者を櫂で追いやり、舟に乗せて地獄へと連行していくという。カロンは酒が好きらしいので酒を飲ませてやれば彼岸へ連れて行ってくれるかも?チョーヤの梅酒でも持ってくか(爆)。
村上春樹はいう.....
『村上は1990年代後半より、しきりに「総合小説を書きたい」ということを口にしている。「総合小説」というとき村上が引き合いに出すのはドストエフスキー『カラマーゾフの兄弟』であり、村上自身の言葉によれば「総合小説」とは「いろいろな世界観、いろいろなパースペクティブをひとつの中に詰め込んでそれらを絡み合わせることによって、何か新しい世界観が浮かび上がってくる」 ような小説のことを言う。』
生贄の場は,子どもたちの悲鳴のゆえにヒンノムと呼ばれ,これは叫ぶを意味する言葉ナハムに由来する。太鼓を意味する言葉トフから,トフェトと呼ばれることもある。イエルサレムに近いヒンノムの谷にあるトフェトで,一部のユダヤ人が律法に背いてモロクに子どもを生贄として捧げた。イゼベル(列王記に出てくる北イスラエルの王,アハブの妻)がモロクに生贄を捧げ,450人の預言者を養ったことが列王記には面々と語られている。
聖書ものがたり・列王記参照
ベン・ヒンノムの谷(VALE OF HINNOM)はかつて屠殺の谷と呼ばれた。......王はベン・ヒノムの谷にあるトフェトを汚し,だれもモレク(モロク)のために自分の息子,娘に火の中を通らせることのないようにした。(列王記Ⅱ第23章10節)・またベンヒンノムの谷にあるトペテ(あるいはトフェト)の高き所を築いて、むすこ娘を火に焼いた。わたしはそれを命じたことはなく、またそのようなことを考えたこともなかった。(エレミア・Jeremiah7:31)
墓地トペテ
Vale(Valley)of Hinnom(ベン・ヒンノムの谷)はゲヘナ(地獄)の語源。
ペルーでも行われた生贄
時近ければなり その6参照
<「罪」について>
原文
1.「限りない神さまの愛を使いはたしてしまおうとするような人間に、そんな大きな罪が犯せるものではない。それとも神さまの愛でさえ追っつかぬような罪があるじゃろうか!」
(米川正夫訳。『カラマーゾフの兄弟』の第2編第3のゾシマ長老の言葉より。新潮文庫の上巻のp96。)
※、上の言葉でゾシマ長老(ドスト氏)が言おうとしていることには、たいそうハッとするものがあります。
2.「しかし、神はロシアを救ってくださるであろう。なぜなれば、いかに民衆が堕落して、悪臭ふんぷんたる罪業を脱することができぬとしても、彼らは神が自分の罪業をのろっておられる、自分はよからぬ行ないをしている、ということを承知しているからである。わが国の民衆は、まだまだ一生けんめいに真理を信じている。神を認めて感激の涙を流している。ところが、上流社会の人はぜんぜんそれと趣きを異にしている。彼らは科学に追従して、おのれの知恵のみをもって正しい社会組織を実現せんとしている。もはや以前のごとくキリストの力を借りようとせず、もはや犯罪もない罪業もないと高言している。もっとも、彼らの考え方をもってすれば、それはまったくそのとおりである。なぜなれば、神がない以上、もう犯罪などのあろう道理がない!」
(米川正夫訳。『カラマーゾフの兄弟』の第6編第2のゾシマ長老の言葉。新潮文庫の中巻のp101~p102。)
3.「お母さん、ぼくはさらに進んでこう言います、――ぼくたちはだれでもすべての人にたいして、すべてのことについて罪があるのです。そうのうちでもぼくが一ばん罪が深いのです。 ―途中、略― ぼくがすべてのものにたいして罪人となるのは、自分でそうしたいからですよ。ただ、腑(ふ)に落ちるように説明ができないだけなんです。だって、それらのものを愛するにはどうしたらいいか、それすらわからないんですもの。ぼくはすべてのものに罪があったってかまやしません、その代わり、みんながぼくをゆるしてくれます。それでもう天国が出現するのです。」
(『カラマーゾフの兄弟』の第6編第2のゾシマ長老の兄マルケルの言葉。新潮文庫の中巻のp53~p54。)
「人間というものは罪深いものだ。」
(評論「ロシア文学論」より。)
「ぼくは、もしかしたら、あの人たちに対してずいぶん罪なことをしているのかもしれない!……
みんな罪がある、みんな罪があるんだ……だから、みながそのことに気がつきさえすれば!……」
(『悪霊』のシャートフの言葉。新潮文庫の下巻のp384。)
「まずすべての人を、常に赦(ゆる)しましょう……そして、ぼくらも赦(ゆる)してもらえるという希望をもちましょう。そうですよ、だれでもみなおたがいに罪を犯しているものですものね。万人が罪人(つみびと)なのですから!……」
(『悪霊』のステパン氏の言葉。新潮文庫の下巻のp478。)
※、上の3のマルケルの言葉は、
ロシア正教の教えを踏まえた、「罪の共同体(ソボールノスチ、相互の罪の自覚とゆるし合い)」
というドスト氏の思想がもっともよく表現されている箇所。
4.「犯罪は社会機構のアブノーマルに対する抗議だ。」
「犯罪には《環境》というものが大きな意味を持っている。」
(『罪と罰』の3部の第5より。新潮文庫の上巻のp448、p450。)
A < 信仰告白の言葉 >
ドストエフスキーの言葉より
1. 「わたしは子供のようにキリストを信じ、宣伝するのではない。わたしのホザナ(神への讃歌)は、疑惑の溶鉱炉をくぐってきたのだ。」
(死の直前に記した「手帳」より。)
※、この言葉は、『カラマーゾフの兄弟』(第11編第9「悪魔。イワンの悪魔」。新潮文庫の下巻のp257。)では、かつてのイワンの分身たる紳士(悪魔)の言葉として、「人生にとってホザナだけでは不足だ、そのホザナが懐疑の試練を経ることが必要なのだ。」と表現されている。
2. 「各編(=『カラマーゾフの兄弟』の前身たる「偉大なる罪人の生涯」という題で構想されていた大小説の各編)を通じて一貫している問題は、わたしが生涯にわたって意識的にも無意識的にも苦しんできたもの、つまり神の存在ということです。」
(1870年3月25日付のマイコフ宛の書簡より。)
3. 「わたしは自分のことを申しますが、わたしは世紀の子です。今日まで、いや、それどころか、棺を蔽(おお)われるまで、不信と懐疑の子です。この信仰に対する渇望は、わたしにとってどれだけの恐ろしい苦悶(くもん)に値したか、また現に値しているか、わからないほどです。その渇望は、わたしの内部に反対の論証が増せば増すほど、いよいよ魂の中に根を張るのです。とはいえ、神様は時として、完全に平安な瞬間を授けてくださいます。そういう時、わたしは自分でも愛しますし、人にも愛されているのを発見します。つまり、そういう時、わたしは自分の内部に信仰のシンボルを築き上げるのですが、そこではいっさいのものがわたしにとって明瞭かつ神聖なのです。このシンボルはきわめて簡単であって、すなわち次のとおりです。キリストより以上に美しく、深く、同情のある、
理性的な、雄々(おお)しい、完璧なものは、何ひとつないということです。単に、ないばかりではなく、あり得ない、とこう自分で自分に、烈(はげ)しい愛をもって断言しています。のみならず、もしだれかがわたしに向かって、キリストは真理の外にあることを証明し、また実際に真理がキリストの外にあったとしても、わたしはむしろ真理よりもキリストとともにあることを望むでしょう。」
(1854年2月下旬、ナタリヤ‐ドミートリエヴナ‐フォンヴージン夫人への書簡より。
河出書房新社版全集の第16巻のp153。)
※、書簡のこの箇所は、研究者がドスト氏の信仰を論ずる場合、必ずといっていいほど引用する有名な文章。下から3~1行目は、のちに、小説『悪霊』の中(第1部第1章の第7。新潮文庫の上巻のp392。)では、シャートフが直接聞いたかつてのスタブローギンの言葉として、「たとえ真理はキリストの外にあると数学的に証明するものがあっても、自分は真理とともにあるよりは、むしろキリストとともにあるほうを選ぶだろう。」と表現されている。1~2行目の箇所は、ドスト氏のうちの不信仰の存在を証する箇所として、評者によってしばしば引用されるが、そのあとの箇所との文脈的つながりを十分押さえて理解すべきでしょう。
4. 「貴女は、分裂ということを書いていらっしゃいますね? しかし、それは人間に、ただし、あまり平凡な人間ではありませんが……人間にきわめて多く見られる普通の精神現象です。一般的に、人間の本性に固有の特質ですが、
しかし貴女のように強い程度のものは、あらゆる人の本性に見られるというわけにいきません。つまり、そういう意味において、貴女は小生(しょうせい)にとって肉身なのです。貴女の内部分裂は、まさしく小生にあるものと同一です。小生には、一生を通じてそれがありました。それは大きな苦しみでもありますが、大きな享楽でもあります。それは強烈な意識であり、自己検討の要求であり、おのれ自身と人類に対する精神的義務の要求が、貴女の本性に存在することを示すものであります。これがすなわちこの分裂の意味するものであって、もし貴女の知性がそれほど発達しておらず、いますこし凡庸(ぼんよう)なものであったら、貴女はそれほど良心的でなく、そうした分裂もなくてすんだでしょう。それどころか、ひどいうぬぼれが生まれたに相違ありません。しかし、なんといっても、この分裂は大きな苦しみです。尊敬してやまぬ愛すべきカチェリーナ‐フョードロヴナ、貴女はキリストとその聖約をお信じになりますか? もし信じておいでになれば(それとも、信じようと熱望しておられれば)、心からキリストに帰依しなさい。そうすれば、この分裂の苦しみもずっと柔(やわ)らいで、精神的に救いが得られます。しかも、これが肝要なことなのです。」
(1880年4月11日、カチェリーナ‐フョードロヴナへの書簡より。河出書房新社版全集の第18巻のp367。)
5. 「神は、永遠に愛することのできる唯一の存在ですから、それだけでもう私にはどうしても必要なのです。」
(『悪霊』より。)
6. 「世界を支配しているのは神と神の掟である。」
(『作家の日記』〔1877年5・6月号〕より。小沼文彦訳。ちくま文庫「作家の日記4」のp471。)
※、米川正夫訳では「この世界を支配しているのは、神とその法則である。」と訳している。(河出書房新社版全集の巻15のp191。)
7. 「神のうちに不死もまた存するのです。」
(『カラマーゾフの兄弟』のアリョーシャの言葉。第3編の8。新潮文庫の上巻のp254の5行目。)
「もし神が存在するとすれば、このぼくも不死なのです。」
(『悪霊』のステパン氏の言葉。第3部第7章の3。新潮文庫の下巻のp507の10行目。)
8. 「不死の観念こそ――まさに生命そのものであり、生きた人生であり、その最終的な公式であり、人類にとって真理と正しい認識の最大の根源なのだ。」
(『作家の日記』より。)
「霊魂の不滅こそ一切の救いの基である。」
(『作家の日記』より。)
9. 「人間存在の法則は、ことごとく一点に集中されています。ほかでもない、人間にとっては、常に何か無限に偉大なものの前にひざまずくことが必要なのです。人間から無限に偉大なものを奪ったなら、彼らは生きていくことができないで、絶望の中に死んでしまうに相違ない。無限にして永久なるものは、人間にとって、彼らが現に棲息(せいそく)しているこの微少な一個の遊星と同様に、必要欠くべからざるものなのです。」
(米川正夫訳。『悪霊』のステパン氏の言葉。)
10. 「世界を救うのは、道徳でもキリストの教えでもない。<ことば(ロシア語では、スローヴオ)>は肉体なり、と信じる、その信仰だけが救えるのです。」
(トルストイの『わが懺悔』を読んで聞かせたトルストイ夫人に向けて、
11.「キリストはこの大地が神を生み出しえた限りの、紛れもない神である。」
(「メモ・ノート(1876~1877年)」より。
『ドストエフスキー未公刊ノート』(小沼文彦訳、筑摩書房1997年7月刊)のp152。)
「キリストの来臨までは戦争が絶えることはないだろう。これは予言されたことである。」
(「メモ・ノート(1875~1876年)」より。
『ドストエフスキー未公刊ノート』(小沼文彦訳、筑摩書房1997年7月刊)のp74。)
12.「すべては神の御手に委(ゆだ)ねられていることなので、僕はお前にただ、神のお導きに期待をかけながらも、 自分でもせいぜい気をつけるようにする、とだけ答えておく。」(書簡集より。)
「人は計画するが、これを決めるのは神の思(おぼ)し召し。」(評論集より。)
「神の御意志によることは、どんな力でも変えられるものてはありません。――運命というものはたいていこの世界を、まるで玩具(おもちゃ)のように弄(もてあそ)んでいるものなのです。――運命は人類にそれぞれの役割を振り当てますが……しかし運命は何も見ていません。――けれども神様はきっとあらゆる不幸から逃れることのできる道を示して下さることでしょう。」(書簡集より。)
13. 「神のない生活は――苦しみでしかないのだよ。」
(『未成年』のマカール老人の言葉。第3部第2章の3。)
G<「美」について>
1.「美しさを批評するのはむずかしいことです。私にはまだその用意ができていないのです。
美しさというのは、謎ですからね。」
(『白痴』で、令嬢アグラーヤの美しさに対するムイシュキン公爵の言葉。新潮文庫の上巻のp142。)
2.「世界を救うものは、美だ。」
(『白痴』で、ムイシュキン公爵の言った言葉としてイポリートが述べる言葉。新潮文庫の下巻のp113。)
3. 「こういう美しさは力ですわ。こんな美しさがあったら、世界をひっくり返すことだってできるわ!」
(『白痴』で、ヒロインのナスターシャ-フィリッポヴナの写真を見ての、エパンチン家の令嬢アデライーダの言葉。新潮文庫の上巻のp150。)
4.「もっとも単純なものは、もうそれだけで美しい。」
(『未成年』より。)
5.「美ってやつは、こわい、恐ろしいものだ! はっきり定義づけられないから、恐ろしいのだし、定義できないというのも、神さまが謎ばかり出したからだよ。」
(『カラマーゾフの兄弟』のドミートリイの言葉。新潮文庫上巻のp203。
6. 「 ―途中略― よく覚えておくがいい、イギリス人がいなくても人類はなお生存することができる、ドイツ人がなくても同様である、ロシヤ人なんかいなくてもそれこそなんの差しさわりもありやしない、科学がなくても平気だし、パンがなくても大丈夫だ。ただひとつ美がなければそれはそれは絶対に不可能である。なぜならば、この世にまったくなにもすることがなくなってしまうからである! すべての秘密はここにある、すべての歴史はここにあるのだ! 科学ですらも、美がなかったら一刻も存続することはできないのだ。 ―以下、略― 」
(『悪霊』のステパン氏の言葉。第3部の第1章の4内。)
トルストイ復活第59章
世間に最も広く流布されている迷信の一つは,人間というものはそれぞれ固有の性質を持っているものだということである。すなわち、善人とか,悪人とか,愚者とか,精力的な者とか,無気力な者とかに分かれて存在しているという考え方である。
だが,人間とはそのようなものではない。ただわれわれはある個人について,あの男は悪人でいるときよりも善人でいるときのほうが多いとか,馬鹿でいるときよりもかしこいときのほうが多いとか,無気力でいるときより精力的であるときのほうが多いとか,あるいはその逆のことがいえるだけである。
かりにわれわれがある個人について,あれは善人だとか利口だといい,別の個人のことを,あれは悪人だとか馬鹿だとかいうならば,それは誤りである。それなのに,われわれはいつもこんなふうに人間を区別しているが,これは公平を欠くことである。
人間というものは河のようなものであって,どんな河でも水には変りがなく,どこへ行っても同じだが,それぞれの河は狭かったり,流れが速かったり,広かったり,静かだったり,冷たかったり,濁っていたり,暖かだったりするのだ。
人間もそれと全く同じ事であり,各人は人間性のあらゆる萌芽を自分の中に持っているのであるが,あるときはその一部が,またあるときは他の性質が外面に現れることになる。そのために,人々はしばしばまるっきり別人のように見えるけれども,実際には,相変わらず同一人なのである。