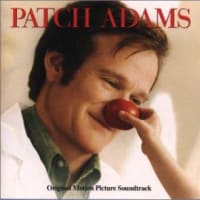本田勝一はいう。『狼が羊を食うとき,どのようにして近ずき,どのようにして襲い,どこに最初に噛み付き,殺したあとどこから食べ始める~ということは,たいへん正常で,かつ論理的だ。狼にとっては,この正しさと論理性は何の疑問もさしはさむ余地はない。狼にとっては,羊は食べられる運命であり,そのように創造された生物だ。
だが羊の論理は,そうではない。狼の視点から正常かつ論理の一貫した世界は,全部異常かつ非論理的である。.......日本ほど平等な国はないと思っている超高級花嫁学校の正常な生徒たちよ。....超高級花嫁学校に,超高級授業料を払って,ますます正常な人間へと自分を堕落させてゆくことのアホらしさに気ずくだろう。反対に羊の論理にあくまで目をつぶって「見えない人間」の存在を無視するのであれば,もはや「正常」と「異常」とが力関係を逆転されるときまで,すなわちいやでもわからせられるときまで,そのアホらしい,たぶんシアワセな生活を,このままつずけることだ』と。こういうRATIOで生きているのが人間の世界
この動画を見ていて思ったこと。76歳の老人は管理人と年齢は同じ。奥さんから慰謝料を請求されることもなく実に平和な暮らしをしています。数年前近所で山羊の除草を見たことがありますが実に穏やかな風景でした。それに比べ人間の世界はなんと愚かなことでありましょうか
恩義で結ばれた愛はいとも簡単に断ち切られる。「女はいつ請求書を出そうかとばかり考えている」とはヘミングウエイの「日はまた昇る」の中の言葉。
https://news.yahoo.co.jp/pickup/6436657
高額慰謝料を請求されたセレブ一覧
https://www.elle.com/jp/wedding/wedding-celebrity/g110903/wce-mostexpensivesettlements-18-0402/
セレブ達の離婚慰謝料
この人たちはお金を使うのでなくお金に使われている不幸な人たちです。拙稿で記事にしましたがオーストラリアの富豪が全てを寄付して月10万円の生活を始めたら幸せになったとのことです。
『狭い門から入りなさい。滅びに通じる門は広く,その道も広々として,そこから入る者が多い。しかし,命に通じる門はなんと狭く,その道も細いことか。それを見出す者は少ない』<ルカ:13:24>
ハルメンの笛吹きがフリードリッヒ・ヴィルヘルム王のプロシア声をまねると,それまでぼんやり立っていた大衆は,機械的ににわかに動き出す。このようにして大衆に行わしめる展開によって,ちゃんと大衆についてこさせることができる。しかし,大衆は近道をしなければ指導者に追いつくことができず,破滅にいたる広い道の上(ルカ13:24狭い門参照)に展開することによって,はじめて隊伍をととのえて行進する余地を見出すことが出来る。生命を求めるために,どうしても破滅への道を歩まなければならないとすれば,しばしば不幸な結果に終わるとしても,驚くに当たらない。その為にはヤコブの梯子(旧約聖書の創世記28章12節「ヤコブの夢」参照)が必要ということでしょう。でもそれは人としての質を高める作業で誰でも出来るということではありません。
2006/11/5
僕は長いことヨーロッパとか仏領ポリネシアなどで仕事をしてきました。僕が出家(在宅)する前の10年間はシンガポールやタイで10年間雇われ経営者として現地法人の社長をさせていただいたわけです。
真剣勝負の日々が続きました。書きたいこと,書きたくないこと半々位でしょうか。僕の記憶と言うコンピューターに入っているものを少しずつ書いて行きましょう。
それまで給料を頂くという立場にあったのが,今度は自分で社員に給料を払うという立場になって驚いたことがあります。給料を頂く立場のほうが圧倒的に楽だということです。
下の写真は僕がタイにいた頃ネーシオンという,どちらかというと反体制側の英字新聞(体制側と評判の英字紙はバンコック・ポスト)に掲載されたチェンマイのSUAN BUAK HADという公園にいたストリート少女です。僕は知人のネーシオン紙の記者にこの写真が作りものでないことを確認しました。
このブログの命題は「17歳迷い道・通りゃんせ」です。冒頭にこの写真が入っています。極楽的平和を享受する日本では考えられない光景ですね。でも現実です。よく見てください。子供をわずか15,000バーツでブローカーに売ってしまう鬼のような親も後を断たないのです。
この子たちはバンコックのチャイナ・タウンに再び売られ,処女という縁起を担ぐ奇矯な華僑たちによって高値で買われるのです。そして商品価値がなくなった彼女たちは,パッポンというゴーゴーバーに流れ着き,エイズになって死んで行きます。バンコック郊外ロッブリにある寺院には今日も順番待ちをした幼い患者が列をなしています。
死んだ少女たちは火葬され,迎えにくる人もなく僧侶によって番号を付けられた麻袋にひっそりと包まれて,生まれてはじめて安息の時を迎えるのです。寺院に収容されるだけでも幸運なことです。いまでも一万人をこえる心に傷を負った少女たちが順番待ちをしています。

僕は問いたい。自らは安全地帯にいて,守護霊とか,癒しとか,救いとか,精神世界とか,瞑想とかなんとかわけのわからないことをしている人たちがもしこの光景をみたら,どう反応するのか?人間って生かされているんじゃあないんだよ。必死に生きているんだ。その薄幸な運命さえ受け入れようとしてね。生成の誤謬と戦っている。極楽トンボの馬鹿者達よ。僕は知りたい。聞きたい。あんた達はにせもの,いんちき,付け焼刃ってことさ。独立個人以外はね。


谷内六郎作 子供が話を聞いているのはお釈迦様か?
後ろの山は聖なる「須弥山」であることは確かだ。

栄華を極めたソロモンでさえ,この苔やきのこたちほどにも
着飾っていなかったろう。

藤原新也:祷りより

カナダのコヨーテ









大摩邇さんに転載された拙稿一覧
http://blog.livedoor.jp/genkimaru1/archives/cat_47849.html
「日はまた昇る」 アーネスト・ヘミングウェイ

「日はまた昇る」は、アーネスト・ヘミングウェイを語る上でもっとも重要な作品とよく言われる。ベストに挙げる声も少なくない。
今回、割と丁寧に再読したので率直な感想を書こうと思う。
まず、とても読みやすい。スーっと頭の中に文章が入ってきて、登場人物たちの顔や風景が映像として立体的に鮮やかに立ち上がる。もちろん、ヘミングウェイのシンプルな文体の魅力によるのだが、「日はまた昇る」を手に取る前にフィリップ・ロスを読んでいたことも少しばかり影響している。ロスの小説は具がぎゅうぎゅうに詰まっている上に癖が強く、とにかく精力的。それに読み疲れていたところでのヘミングウェイだったので、その淡白な文体が清涼剤のように効いたというのもある。
「日はまた昇る」はどのような話かと言うと…
ワインを呑み、旅をし、ワインを呑み、釣りへ行き、ワインを呑み、眠り、ワインを呑み、祭りへ行き、ワインを呑み、喧嘩をし、ワインを呑む、といった話だ。ワインワインと連発したが、時々アブサン(リキュールの一種)やビールも呑む。
アルコールを節制したり、仕事に精を出したりすることはない。登場人物は、ほぼ全員が酔っ払いである。
ストーリーらしいストーリーもない。女1人、男4人が闘牛を観るためにスペインのパンプローナを旅するだけの話だ。

「日はまた昇る」(原題:The Sun Also Rises)というタイトルだけ見ると、「復活への熱き思い」などと勘違いしそうになるが、むしろその逆でエンドレスな虚しさのニュアンスが漂う。
再読のせいかもしれないが、読後に感動の余韻のようなものは今回はそれほど残らなかった。登場人物たちの奢りが鼻についたというのもある。闘牛への傾倒ぶりにも同化できなかった。ヘミングウェイは闘牛のプロでも何でもなく、一ファンに過ぎないのに、上から目線で語ってくることにやや違和感を覚えてしまった。
それでも、全体としては長編デビュー作と思えないほどスタイリッシュである。影響を受けた当時の若者たちがファッションや行動を真似し、パンプローナを聖地化した気持ちはよくわかる。ロストジェネレーション(失われた世代)の実態を描き出した、とかそういった理屈は正直どうでもいいかな。突き放すような書き方と思われるかもしれないが、この小説の真髄はそこじゃないという気がしている。確か著者本人も本作をそんな風に語っていた記憶がある。
とにかく自然の描写、祭りの描写がリアルで瑞々しい。一つ一つの描き方に濁りや嘘がなく、心理描写に寄ることもなく、終始一定のペースで淡々と描いている。(おそらくは推敲を繰り返した結果なのだろう) 最初から最後まで、思考を軽視したフィジカルさで貫かれている。

よく知られたことだが、「日はまた昇る」は実在の人物が登場するモデル小説である。名前こそ変えてあるものの、誰をモデルにしたかは明らかで、実際にパンプローナで過ごした数日間が物語のベースになっている。どうしたって、読んだ人はすべてが実話と受け取るだろう。でも、話の中身は創作部分が多い。虚実まぜこぜで、起きてないことや事実と反することもかなり書かれている。
モデルにされた連中にとってはたまったものじゃない。特に、バカにされまくるストーカー男として描かれたハロルド・ローブは、怒り狂ってヘミングウェイを○○そうとしていたという話まである。
顰蹙をかうことを予想できたはずなのに書かずにいられない。ヘミングウェイは、こうした虚実混在型モデル小説(そんなジャンルはないけど)の常習犯なので、人間関係を壊してしまったことも一度や二度ではないだろう。この小説の元になったパンプローナ旅行で、実際にはヘミングウェイは妻のハドリーを同伴している。そこで、小説のヒロインとして描かれている女友達に惹かれ夢中になってしまったという。(なんという自制心の無さ) しかもそれを小説化し、ハドリーと離婚した際に印税を慰謝料として渡している。(どういう気持ちで?) 小説は素晴らしいが、どうしようもないエゴイスト。こう非難されても仕方ないだろう。
まあ、いろいろ書いたが、「蝶々と戦車」などの名作短編と比べるとやや抑制に欠けるが、若き透明な感受性の魅力があってやはり特別な作品だとは思う。私もヘミングウェイに多少の思い入れのある人間だが、どこか一つゆかりの地に行けるとしたなら、オークパークでもキー・ウェストでもキューバでもなく、パンプローナを選ぶと思う。いつか、パリ経由で行ってみたい。
とにかく、未読の人に一度は味わってほしい名作だ。読み終えたばかりだが、もう再読したいと思っている。次は原書にチャレンジするつもりだ。
転載元