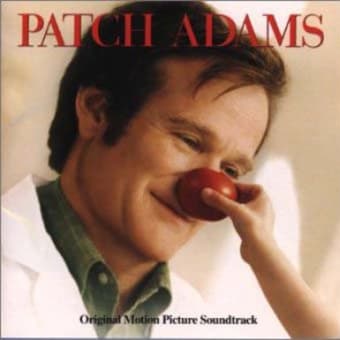(ウラジミール・ジャン・ケレビッチ「死」)より

La Mort(死)の目次
■Jankelevitch, Vladimir[ヴラジミール・ジャンケレヴィッチ]1966, La Mort, Flammarion, Editeur,
=19780306, 仲沢紀雄訳, 『死』, みすず書房,vi 514p. 5000 oi
[amazon]/[kinokuniya] ※
■目次
死の神秘と死の現象
第一部 死のこちら側の死
第一章 生きている間の死
第二章 器官-障碍
第三章 半開
第四章 老化
第二部 死の瞬間における死
第一章 死の瞬間は諸範疇の外にある
第二章 死の刹那のほとんど無
第三章 逆行できないもの
第四章 取り消しえないこと
第三部 死の向こう側の死
第一章 終末論流の未来
第二章 後生の不条理さ
第三章 虚無化の不条理さ
第四章 事実性は滅びることはない。取り消しえないものと逆行できないもの
関連記事:人称別の僕
http://6707.teacup.com/gamenotatsujinn/bbs/2720

森有正氏は「砂漠に向かって」の中でジャンケレヴィッチをこうコメントしています
『人間の永遠のテーマである〈死〉を主題として奏でるポリフォニックな思索世界。
三つのモチーフ〈死のこちら側の死〉〈死の瞬間における死〉〈死のむこう側の死〉
の展開によって、完璧に、精妙に演じられる一大交響曲といえよう。
〈昨日『死』を読み始めた。一挙に私は、密度が高く胸の高鳴る文章に熱中し、魅了された。ソルボンヌ大学で彼の講義をしばしば聴講し、私の内的苦悩に照応する稀な哲学者の一人だという印象を得た。この本もそれを証拠立てている。
私の心を打つのは、人間的経験のさまざまな秩序だ。この差異が内的に深く「人格」の差異と結びついている。この間題は、日本語文法の人称の問題を取扱う必要のあった時、
私の心を占めていたことだ。「実存」の問題がはじめから記述の中心に位置している。
「経験」の単独性は、死の事実によって否み難く実証される。それは経験の最も鋭い特徴ではないか。愛と死の近似性に私は強い関心をもっている。
それがどうあろうと、それを深める前に先ず、この驚くべき書物を読まねばならぬ。
読書がそれ程までに私を熱中させることはめったにない〉。
(森有正『砂漠に向かって』より) 』

森有正氏の基本的な考え方
その著書の中でO君と出てくるのが仲澤紀雄氏で「死」の翻訳者。
中澤氏がエールフランス日本・韓国・太平洋地区支配人をしていた時に思い立って企画したフランス我が旅(中央公論社で出版された)。氏は巴里で哲学を学ぶ傍らエールフランス本社で生活の糧を得た。

http://megalodon.jp/2009-0318-0258-25/angel.ap.teacup.com/gamenotatsujin/288.html
朝吹登水子さんからの手紙(文中名前が登美子さんになっていますが間違いです)
http://web.archive.org/web/20071228213151/http://angel.ap.teacup.com/gamenotatsujin/38.html
松本弘子さんからの手紙
http://web.archive.org/web/20080102162306/http://angel.ap.teacup.com/gamenotatsujin/34.html
上のお二人共もうこの世におられません。
カスタマーレビューは以下の通り
この大著を読んだ後、死について何を言おう。死という思考の対象となりえないもののうちで思考の対象となりうるものすべてを思考すること、著者がしたのは、まさにそれだ。
著者は「死」が何であるかを語らず、何でないかを語るところから始める。そして、同じことだが、自分は「死」が何であるかを知らないと率直に告白することをためらわない。
けれども、著者は「死のことなんかわかるわけないさ」と嘯く懐疑論者でもなければ、「死はこれこれしかじかのものである」と「死」を実体めかして語るペテン師でもない。ジャンケレヴィッチ先生は、まさに生と死のあわいで、身をよじるようにして思考すべきものを徹底的に思考し、言うべきことはもう何もないという地点まで読者の思考を導く。
そして、あることを述べた後、すぐに言い直し、表現を変え、さっき自分の発した言葉に自分でためらいを覚え、言い淀み、また前言撤回することを厭わない(そうした思考は先生の僚友エマニュエル・レヴィナスの思索を彷彿とさせる)。言ってみれば先生の叙述は、難問に繰り返しアンダーラインを引くようなものなのである。あるいは武道家甲野善紀先生の言葉を借りれば、「矛盾を矛盾なく扱う」思考と言えようか。
しかしながら、本書は、書斎に閉じこもって、「死」は自分だけは襲わないと確信している人の作品ではない。この「私」が死ぬ。そして、死んだらそれっきりという許し難い事実に直面して、怯え、慄き、怒りを覚える一人の人がそこにはいる。そこから、それらの恐怖や怒りを鎮め、慰めると称する慰めを一つひとつ丹念に点検し、まやかしは全て退ける。著者は人生の喜びや悲しみを知る人であるが、同時に徹底的に知的な方でもある。
死が何であり、それにまつわる様々の迷信や慰めを縦横無尽に検討した果てに見出す結論は、驚くなかれ、とても自明で、常識的なものだ。「そんな簡単なことは誰もが知っている」と言いそうで、その実しばしば忘れがちのことだ。それは「生きたという事実性」だ。人は死ぬ。しかし、その人が生きたという事実、これは取り消すことができない。「存在したという事実は、つまり、文字どおり永遠の瞬間だ」。
愛し、そして生きたということ、それこそが実存の神秘の全てだ。それはまやかしの慰めであり、まったく粗末なあてがいだと言う人もいよう。しかし、「この粗末なあてがいこそもっとも貴重な路銀なのだ」、そうジャンケレヴィッチは言う。人が現実に私から存在を奪うことはできても、存在したという事実を無と化すことはできない。そのことを最後に正しく強調している点で、本書は本当の希望と慰めのありかがどこにあるかを示唆している。
最後に訳者について触れよう。訳者の仲澤紀雄氏は、若き頃、森有正先生の薦めに背中を押され、また前田陽一先生の紹介状を携えて、渡仏し、ジャンケレヴィッチに論文の指導を仰いだ方である。この『死』の翻訳を思い立った時、出版社への仲介の労を取られたのは、森先生である。また、森先生もジャンケレヴィッチへの深い尊敬の念を抱いていたことが『砂漠に向かって』などの手記から推し量れる。本書が日本で出版されるまでに、翻訳者と原著者の間に介在した様々な人の出会いと働きも忘れるべきではないだろう。そのような出会いがあったという事実に心暖まる思いを抱かせられる。それらは言ってみれば、大きな贈与である。私は、それにどう応えようか。そんな思いにさせられた読書であった。
コメント |
By Tod
「哲学は死の練習である」とソクラテスは言い、「死がなければ哲学もなかったであろう」とショーペンハウアーは言った。『哲学の教科書』の冒頭で中島義道も断言している通り、死が哲学の、否人生の最大問題であることは疑う余地がない。
にもかかわらず、死そのものを真正面から論じた哲学書は少ない。それは死があまりにも巨大かつ空虚であるがために、論じるのが極めて困難、というより不可能だからであろう。死は間接的かつ消極的に表現されるのみであり、死を語る言葉をわれわれは持っていない。
本書はその不可能に挑戦したジャンケレヴィッチの名著である。
冒頭でジャンケレヴィッチは自ら問う。そもそも死は哲学の問題たりうるのだろうか、と。「人口は出生によって増加し、死亡によって減少する。そこにはいかなる神秘もない」然り、三人称の死は日常茶飯事であり、何も問題はない。しかし二人称の死は、そして一人称の死は……。
「われわれ」などという一人称複数形が矛盾した化け物に過ぎないことを、死を前にして人は思い知ることになる。だれもがたった一人で、生まれて初めての死を即興もしくは不準備のまま演じるほかない。なぜなら「私」は自分が死ぬことを知ってはいるが、それを信じてはいないからだ。
豊富な知識と語彙を背景にあらゆる方向へと自由に展開する叙述は、哲学的な論理性というよりも音楽的な芸術性にあふれているが、理屈とは無縁な死を論じるにはこの文体の方がよりふさわしい。読者はどこから読んでも思索の深みを体感することができる。
だれもが知っているのにだれも知らない「死」。永遠の謎を解き明かそうと試みたジャンケレヴィッチ畢生の一大哲学作品は人類の至宝といっても過言ではなく、この名著の邦訳が入手困難な現状は理解に苦しむ。復刻もしくは文庫化を切に望む。
管理人注:私が仲澤氏からいただいた「死」は非常に小さなページ数も少ない本でしたがもう紛失してしまいましたがアマゾンの中古で1万円前後しますので復刻版を希望しています。
参考書籍:ジャンケレヴィッチ・境界のラプソディー
http://www.msz.co.jp/book/detail/07056.html
http://ccfi.jp/contents/lib/ninsyou.htmlさまより
▽ ジャンケレヴィッチのいう「死の人称」とは
『近頃どうも 哲分 が足りないためか 知 の巡りが悪いので、久しぶりにジャンケレヴィッチの『死』(みすず書房,1978)を手に取りました。ジャンケレヴィッチといえばよく引用されるのが「死の人称」ですが、前々からどうももうひとつよく分かっていなかったのが「二人称の死」と「三人称の死」の境目はどこかという点です。
「人称」を辞書で引くと次のようにあります。
【人称】話し手との関係を表す文法範疇。話し手自身を指す一人称(自称)、話しかける相手を指す二人称(対称)、それ以外を指す三人称(他称)の三種に分ける。…広辞苑 第五版,岩波書店
これ自体はよく知られたことで、中学校の英語の授業で習う「I・you・it」をよく例示として引き合いに出されます。「死の人称」についても例えばwikipediaでは「死」の項目4-2で「三人称の死」について「三人称の死:英語での人称「it」「he」「she」などにあたる。いわばアカの他人の死。二人称の死が取り替えのきかない存在なのに対し、他の他人の死でも置き換えられる点に特徴がある。…」と説明されています。
しかしジャンケレヴィッチは「死」においてこう述べます。
…第三人称の死は、死一般、抽象的で無名の死、あるいはまた、たとえば一人の医者が自分の病気を検討する、ないしは自分自身の症状を研究する、あるいは自分自身に診断を下すという場合のように、個人の立場を離れて概念的に把えられたものとしての自分自身の死だ。(p25)
wikipediaの説明の後半はともかくとして、前半はどうなのでしょう。葬儀士の立場を例に取って具体的に考えるなら、さっき連絡を受けて病院に迎えに行き始めて出合った「現在目の前にいる死者の死」は二人称か三人称か、という問題です。医師から見た患者、という例では医師が「○○の病気に罹っている患者」という場合については三人称だと言えるでしょうが、「この患者」という時にそれが「it」であるからといって「三人称の関わり」であると言えるでしょうか。 ジャンケレヴィッチの定義からすると、その死者の唯一性があるかぎり、つまりは人格的な存在の認識という点においてその死者がその死者でしかないならば、その死は「抽象的で無名の死」と言えないのではないか、という疑問が湧くわけです。すなわちジャンケレヴィッチの言う第三人称は代名詞「彼」ではなく「誰か」であると言えるのではないでしょうか。
では例示した死が「二人称の死」であるかといえば、それも正しくはないようです。ジャンケレヴィッチによれば二人称の死とは次のようなものであると述べられています。
…第三人称の無名性と第一人称の悲劇の主体性との間に、第二人称という、中間的でいわば特権的な場合がある。遠くて関心をそそらぬ他者の死と、そのままわれわれの存在である自分自身のとの間に、近親の死という親近さが存在する。たしかに”あなた”は第一の他のもの、直接に他である他、”わたし”との接点にあるわたしならざるもの、他者性の親近の限界を表象する。そこで、親しい存在の死は、ほとんどわれわれの死のようなもの、われわれの死とほとんど同じだけ胸を引き裂くものだ。…(p29)※太字部は原書では傍点
これからすると、葬儀士が目の前に現にいる死者に対して「胸を引き裂かれるほどの衝撃を覚えなければ」、それは二人称の死とも言えません。つまり二人称の死とは「親密性の認識」をその基準としているのであって、相手が「代名詞でどう表現されるか」が問題なのではないということになります。
さて、根本的な問題として冒頭に引用した文法範疇としての「人称」と、哲学的な存在認識としての「人称」のズレが生じていることはわかります。図にすると次のようになるでしょうか。
一人称の死においては文法上も哲学上も変わりはありませんが、二人称以下はほとんど違うものを指しているようです。この状態で三人称の死を「he」などにあたる、というのはあまり適切ではないと思えるのです。
このジャンケレヴィッチにいう「二人称の死」と「三人称の死」の間に浮遊する「彼」にひとつの解決を見出そうとしたのは、ノンフィクション作家の柳田邦男(民俗学者の柳田國男ではない)という人物だそうで、彼の提案したのは「2.5人称の死」という概念でした。彼は医師から見た治療対象としての患者などについて、それが人称の分類状は「三人称の死」でしかないという前提に立ちながら、しかしその患者の大事な場面で密接な関わり合いを持つ医師は決して三人称ではなく、より二人称に近い「2.5人称の関係性」にあると呼ぶことを提案したい、と述べています。(参考ページ)柳田もその提言の下敷きとしてジャンケレヴィッチの「死の人称」を引用しています。そのため「2.5人称」の位置する場所も文法上の二人称と三人称の境目(図のAライン)ではなく、存在認識としての人称における二人称と三人称の境目(図のBライン)上にあると考えてよいと思います。
しかし先般の表では結局のところジャンケレヴィッチ自身が浮遊する「彼」をどう位置付けたのか…いやそもそもジャンケレヴィッチが文法上の「人称」と違う概念に対し「なぜ同じ『人称』という言葉を用いたのか」が説明できません。私は何を誤解しているのでしょうか。
ジャンケレヴィッチは『死』の中でこの「人称」についてこうも述べています。
…一方、すべての人でありながらだれでもない無名の《ひと》と、他方、わたし自身との間には、《わたし自身》ということばでわたしなるもの、つまり、第一人称という文法上の概念ではなくて、端的純粋に《自分》、冠詞なしのわたし、まさにこの場でこの瞬間に”わたしが…”と言う自分を理解するとき、その相違はまことに形而上学の分野に属する。語るわたしは、他のすべての死すべき者と同じ一人の死すべき者でも、生きとし生けるものの間の一個の生けるものでも、一人のどれでもよいカイウスでもなく、説明しようがないほどに特権的な一人の人間なのだ。…(p22)※下線は筆者が追加
…もっと明確に三つの人称、つまり三つの視角を区別しよう。第三人称および第二人称は他者(かれあるいはあなた)に対するわたしの観点あるいは他者のわたし自身(他者の第三人称あるいは第二人称とみなされたわたし)に対する観点であり、たがいに相手となる二者は、モナドとしても、また個人としても、異なった二つの主体のままだ。わたしのわたしに対する観点、あなたのあなたに対する観点、そして一般的には各人の自分自身に対する《再帰的》観点である第一人称、この観点は遠近法および視覚距離を放擲するものだから、かろうじて《観点》と言えるものだが、この視角が、実際のところ、意識の対象と《死ぬ》の主語とが合致する自分自身の死の生きた経験だ。…(p24)※下線は筆者が追加
………。 なんのこっちゃ (ナイアガラの滝汗
この二つ目の引用の直後に、初め引用した「第三人称の死は…」という文が続きます。そしてそのしばらく後、
…わたしにとってのあなた及び彼である第二人称、第三人称も、自身に対してはわたしではないだろうか。各人称はその人称自体にとっては、つまりそれ自体として、それ自体の観点から見て、再帰的に第一人称ではないだろうか。わたし自身ではないが、かれ自身にとってはわたしである他者、この他者は、単に《わたしのよう》であるにすぎない。この角度から、間接的に自分自身の死はふたたび普遍的なものとなる。…(p26)
こういうことでしょうか。
ジャンケレヴィッチが死を考える際に、その登場人物は自分(A)しか存在しない。いや現実には存在するけれどその存在は結局のところ「その人にとっての自分(A')」であるから意味をなさない。AはAに対して「死」を語るが、その際に対象とされる「死」が「Aの死」である場合は一人称、「Aでない(あるいは特定できない)人の死」であれば三人称、「まるでA自身の死であるかのようにA自身に感じられる死」が二人称の「死」である。
すると誤解しているのは、ジャンケレヴィッチが「死の人称」と言ったのは認識者と死者との関係性の話ではなく、その「死」の、認識者からの距離であるということではないでしょうか。認識される「対象」はあくまでも「死」であって、「死者」ではないのではないでしょうか。
そうだとするとつまり、「一人称の死は自分の死、二人称の死は大事な人の死、三人称の死はどうでもいい人の死」というよく聞かれる説明はある意味で誤りでしょうし、「現在目の前にいる死者の死は二人称か三人称か」という設問自体もジャンケレヴィッチの「死の人称」を土台に考えるには 的外れ なのです。
もしこの通りだとすれば、ジャンケレヴィッチのいう「死の人称」において「2.5人称」や「4人称(※)」などは当然ありえないわけです。「自分でなく」「自分以外のものでない」死について、自己と他者の境目、その線上にあるという「あいまいな」死のみをジャンケレヴィッチは「二人称の死」と呼んだのですから。
(※)柳田の言う2.5人称を3人称と再定義して、ジャンケレヴィッチの言う3人称を「4人称」と呼ぶ人もいるそうなのです。
ではなぜ我々は「2.5人称の死」などを想定しなければならなかったのでしょう。それは我々の想定した「人称」が「死」のものではなく「葬送」のものだったからではないでしょうか。つまり、ジャンケレヴィッチにおける「死の人称」は聞き手が語り手自身であるのに対し、「葬送の人称」は聞き手が「死者」であることに違いがあるわけです。つまり2.5人称や4人称の発生は、認識される対象としての「死」と「葬送」の間の「揺らぎ」だったのだと結論付けられるのではないでしょうか。
この前提に立って再定義するなら、
第一人称の葬送 = 自分の葬送 「私の葬送」
第二人称の葬送 = 死者の個別性(人格)が認識されている葬送 「ある人の葬送」
第三人称の葬送 = 特定されない葬送一般、抽象的な概念としての葬送 ただの「葬送」
となるでしょう。
こうすることでまた、「葬送の人称」において2.5人称や4人称は存在しえなくなり、浮遊する「彼」の葬送についても確定します。たとえ「その死者」がどこの誰かわからなかったとしても、「今目の前にいる」という事実によってその死者の個別性は確認されるからです。
そうすれば「小数点以下の死者区分」が無制限に増殖していくこともありませんし、そのことによって「死者や葬送の重要度ランク付け」が行われることも防ぐことができます。
ところでここで気付くのは、上記のように再定義した場合、「具体的に実行される葬送はすべて第二人称の葬送でしかありえない」ということです。考えてみれば至極当然の話ですが、改めて言葉にしてみると面白いですね』転載おわり
死とは何か
http://16339209.at.webry.info/201109/article_1.html
ジャンケレヴィッチ『死とはなにか』(1)
<< 作成日時 : 2011/09/15 11:18 >>
ブログ気持玉 0 / トラックバック 0 / コメント 0
[注釈]
* l’existence de quelqu’un : あとの言い換えからすると「誰かが存在したこと」existence は、文脈によっては「生活」ほどの意味になることもあります。「実存」となるのは、かなり特殊な文章においてです。
* la moindre ide’e : moindre に定冠詞がついていますから、ここは最上級表現です。何度か出てきたように、最上級表現にはときに「譲歩」の意味が込められることがあるので、注意が必要です。
* Alors, il me reste pour tout viatique ce message : 死という事実は人智を以てしては計りがたい。「だから」私たちにはメッセージが残される、ということでしょうね。il reste...は、非人称構文です。ここの viatique は、secours indispensable の意味ととりました。以前どこかでジャック・ラカンの「生誕と死は思考の埒外だ」という趣旨の言葉を読んだ記憶があります。ここで Janke’le’vitch がいう「メッセージ」とは、そうした謎に向き合うための「ヒント」のようなものなのでしょうね。
[試訳]
死とは、取り返しのつかない、やり直しようのないものでありながら、この出来事はある人の生存を、その人が生きていたという事実を永遠に封印してしまう。それは、誰にも代わることのできない、滅びることのない、打ち消しようのない事実です。それはメッセージです。もちろん、死者は死んだままです。ですが、このメッセージの滅びることのない性質のうちに、私は、人間にとって超自然的な、説明不能な、考えられさえしないある要素を見ています。でも、実のところ、それはたぶん大変単純なものでしょう。ですが、私たちはそれをどう考えればよいのかまったくわからない。というのも、そこで問われているのはまったく別の次元のことだからです。ただ、私たちはそのことに納得がゆかない。なぜなら、私たちは経験的な思考の型にこだわっているからです。なにか確かなものを期待しているからです。是が非でも、なにか具体的なものを思い描きたいのです。なぜなら、問われているのはまったく別次元の事柄であるのですが、そのことが私たちにはまったく飲み込めないし、考えもつかないのです。ですから、そこにはペテン師がつけ入る隙がまだあるのです。そうだからこそ、私には頼みの綱としてこのメッセージが残されています。人が生きていたという事実、単純な神秘でありながらも、それ自体深い神秘に包まれた事実が。ただ、私たちは、問いを自らに課し、こうしたこと全ての理由を問うほどの十分知的な能力を備えているのですが、この謎に答えるに十分な能力は持ち合わせていないのです。ただ問いを自らに課すことができるだけなのです…。
*non-sens : これは文脈にふさわしい訳語を考えるしかありませんね。misayoさんの「不条理」というのも、いいかもしれません。
*Pluto^t avoir ve’cu : ここは、後者を選ぶよりは「むしろ」ということですから、une ve’ritable vie, une existence de’fini d’amourのことです。
文末の内容に関しては、語られていることが当たり前すぎて、かえってその論理が見えづらいかもしれません。試訳を参照ください。
[試訳]
死とは命の条件であるのだろうか?
死ぬことは、生きてあることの条件そのものです。死こそが、生から意味を奪いながらも、そこにある意味を与えるのだ、と多くの人が言いましたが、私もその列に加わることになります。死は、命に意味を与える意味ならざるものなのです。ある意味を与えながらも、その意味を否定する意味ならざるもの。それが、短く苛烈な生にあって、はかなく熱い生にあって、死の役割が明らかにするものです。そんな生において、力と強度を与えるのが死なのです。それは逃れることのできない二者択一なのです。私たちはともすると生の激しさと同時に永遠をものぞみます。でもそれは思考不能なことであり、人間にはでき過ぎた虫のいい話で、人間の身分に相応しいものではありません。
ですから、私たちに許された二者択一とは、こうです。はかない、けれども真実の、愛のある命。そうでなければ、果てのない、愛もない、まったく命とは呼べない、永遠の死のようなもの。もしこうした二者択一が示されたら、私の考えでは、後者を選ぶ人はほとんどいないでしょう。むしろ、たとえ夏のひと日であっても、蜻蛉のように果てることを選ぶでしょう。というのも、こうして見ると、長いも短いも同じことだからです。たとえ私は命を失わなければならないとしても、少なくとも命を経験しているはずです。そうでしょう。命を失わなければならないということは、それをすでに生きたということですから。
……………………………………………………………………………………………
今回も、また本の話になりますが、池澤夏樹『春を恨んだりはしない』(中央公論新社)を読み、夏休み明けの大学の授業で紹介もしました。仙台若林地区に叔母夫婦が住んでいた著者が、何度も被災地に入り、物資の運搬などにも手を貸しながらまとめたルポルタージュでもあり、文明論としても読める一冊です。少しだけ引用しておきます。
「自然には現在しかない。事象は今という瞬間にしか属さない。だから結果に対して無関心なのだ。人間はすべての過去を言葉の形で心の内に持ったまま今を生きる。記憶を保ってゆくのも想像力の働きではないか。過去の自分との会話ではないか。」(p.24)
言葉という、精妙な、けれどもか細い糸を通じて過去と繋がっていなければ、私たちは今この時を十全に、ゆたかに生きることはできません。そのことを忘れて、転変する社会状況に適合することに、あるいは未来に設定された目標をのみを見つめること、私たちは文字通り「我を忘れて」いるのではないか。そんなことを思いながら、同書を読んでいました。
文芸誌『新潮』10月号に掲載された、古井由吉・平野啓一郎の対談「震災後の文学の言葉」も、相前後して大変興味深く読みました。
死とは何か?
http://allisjiga.exblog.jp/13520272
「死とは、神秘であって、秘密ではない。秘密とは発見される性質を持つ。が、死には秘密がない。死は、死それ自体を純粋に主張するのみで、謎が一つもないのだ。」
ヴラジミール・ジャンケレヴィッチという哲学者の死に対する考え方である。
これ以上の説明を〈生の論理〉ではすることができない。
言うまでもなく、〈死〉とは、〈生の時間〉の内部では、経験不可であり、語ることも、思考することすらもできない性質を持つ、〈一点〉のことを指す。言い換えれば、〈生の秩序〉とはまったく違う〈絶対的な秩序〉を持っている。
当然、〈死〉は、〈生〉の「結果」ではない。
〈生の苦しみ〉の総量が〈死〉に関連することもない。
〈死〉は〈生〉に永遠に無関心である。
〈死〉は〈死そのもの〉なので、〈生〉がなくても存在できるのだ。
その証拠に、〈生の時間〉内部での死への過程の経験のはげしさに比べて、死がもたらした外観は、実にあっけないものである。
死体を見るがいい。
死の瞬間を形容しようと、人間はさまざまな比喩を持ち出すが、どれもまったくぴったりこない。
蝋燭の炎をふっと消すように。違う。
やすらかに眠るように。もっと違う。
人生的陰影も、数秒は死体に宿っているかもしれない。が、それも数分後には、なんの意味も意義もない物質への還元でしかないことに気づかされる。
人間の〈人生〉が、まったく法則的に反映されない、ゆえに、対立すらさせてもらえない、絶対的な秩序。なんの形容もない。だから、〈死〉は〈神秘〉なのだ。
「死後」から見て、死ぬ一秒前は「はるか以前」であり、それ以降は、秩序の変化により、「死後」とすら呼べないだろう。時空間という概念は消え去り、〈無〉という、いわば〈可能性〉の〈可能性〉になるばかりだろう。
それは、意識的世界とは比べ物にならないくらい、途方もなく〈秘められている〉〈在り方〉なのではないか。
ここからは〈賭け〉の話になる。
〈死〉と比較できるものはないが、〈死後〉と比較できるものはある。
それは〈生まれる前〉である。
死んだ後のことを、死後の論理では、「死後」という区分で定義しないだろう。かつまた、生まれる以前を、「生前」という区分で定義できるだろうか。
では、自分が「生まれていないとき」という時空間が存在した、と仮定できるかどうか。
自分が「生まれていないとき」が存在しなければ、自分という〈意識〉が発生する〈可能性〉があるだろうか?
ここに、〈死〉についての些少のヒントがある。
というよりも、〈死〉は、むしろ、〈死〉以降の世界の「秘められた存在の在り方」のヒントに過ぎないのだろう。
視点を現存する世界に戻すと、一方で、この世界の本質は、〈思考する存在〉なのではないか、ということに気づく。
どういうことか。簡潔に言えば、真理というものは、新たに発見されるものではなく、あらかじめ世界がすべて経験しているのではないか、という考え方である。例えば、ピタゴラスの定理は、必ずしも、ピタゴラスという人物を必要としただろうか? そして、ピタゴラスが死んだ後、ピタゴラスの定理は、消滅しただろうか? そうはなっていない。おそらく世界終焉の前後でも、三角形の内角の和はニ直角に等しいだろう。もしかりに、それを語り継ぐ人間がいなくなっても、その定理は、そのまま世界に存在することだろう。
〈思考する存在〉は、先験的な秩序を完成しているに違いない。少なくとも、人間が生きている間の世界において、いまだ存在していないものなどなく、すべて存在している状態からはじまっているし、終わることもまたない。ただ、人間は記憶喪失であって、長くも短い人生を通して、定理や公式などを「思い出している」に過ぎない。
考えてみれば、死の存在に気づき、死について思考し、死について悩むのは、いまのところ人間だけなのだ。ただし、死に対しては、それ以上の存在でもなく、それ以下の存在でもない。
そんな人間にとって、最初で最後の〈詩)が、「死」である。
詩は書かれるものでもなく、読まれるものでもない。
詩は詩そのものを主張するだけである。
死の哲学書 5冊の紹介
http://www.sogi.co.jp/sub/kenkyu/book2.htm