という決めゼリフを駆使する特番形式のオカルト番組が
時折、テレビ放送されますが、玉石混淆ならまだしも、
おそらくは限りなく100%に近い確率でガセネタである疑い
を持ちながらも、興味本位で面白半分にみている人の数
は存外に多い気がします。
もっとも、「信じるも信じないもアナタの勝手です」と言って
いるわけですから、そこに裏付ける証拠や何かを保証する
ものがあるわけではありません
そもそもが、そうした実証性の乏しい超自然的で神秘的な
現象や不可思議で時に非倫理的な背徳性を帯びた内容の
疑似的な似非科学が持ち味のオカルティズムですから …
「科学的でないもの」は、すべからくオカルト
というカテゴリーに詰め込まれることになります。
言うなれば、この記事は完全なるオカルトです
そして、
いわゆる正統派のキリスト教会の信仰体系から逸脱した
異端宗教や異教もオカルトと呼ばれていたわけで、
その趣旨からはダ・ヴィンチは正真正銘の生粋の
オカルティストだとも言えるでしょう
科学も含めた「万能の天才」と称される彼にしても
オカルティストの汚名
と言っても、
ダ・ヴィンチが活躍していた時代にそう呼ばれていたわけ
ではなく、現代的な視点から彼の作品群(素描や手稿類)を
見る限りでは、オカルティックな一面とサイエンティフィックで
ユニークな素顔が想像されるという意味です。
言わば、マイノリティー ≒ オカルティスト
という偏見と差別が世の中の底辺に流れる思想背景
としてあるわけですが …
少なくとも、
ダ・ヴィンチが教会や修道会とは一線を画く態度に終始し
対立姿勢を崩さなかったのは、彼が「無神論者」だったから
ではなく、まったく別の観点から「神」を崇めていたものと
思われます。
『謎の肢』の稿でも触れたように、聖母マリアに神性
を賦与し、マリア崇拝に変貌した「マリア教」たる
ローマ・カトリックの真の姿に絶望と嫌悪を抱いていた
ことは疑いようもなく、ひいては「神」の存在はともかく
イエスの存在そのものに対しても少なからざる疑問を
感じていたのではないかと思われるのです。

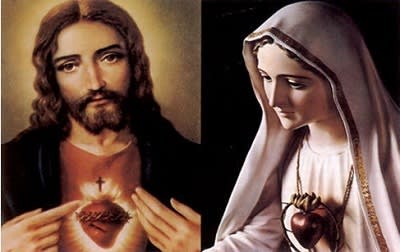
さて、
『ダヴィンチの罠』と冠して、予告版も含めると
前回までに10の副題を配して解説をしてまいりましたが …
時事を絡めながらの説明に焦点がややボケてしまった
感が否めないので復習も兼ねて大まかな部分だけサラッと
おさらいをしてみたいと思います。
まず、核となる壁画『最後の晩餐』においては …


NHK復元CG版
『ダ・ヴィンチ・トラップ(ダ・ヴィンチの罠)』を
暴(あば)く手始めとして、下記の3つのミステリー が
封印を解く鍵になると申し上げました。
そのなかの

①ペテロの手か、②ユダなのか、③ヨハネの異常
に長い腕なのか、それとも④「神」or「悪魔」の象徴か

以上の4つの可能性を示しました。

「裏切り者は1人ですか
傷あとに指を入れようとするポーズなのか
プラトニズム(二つがひとつ)の暗喩なのか
侮辱・侮蔑を意味するサイン(F〇ck you)か

以上、4つの意味合いが想定できるとしたわけですが、
、これから解説する予定ですが、こちらにもさまざまな人物
の名前が登場しますが、これだと特定したり限定したりする
ことはできません。
ズルイと言われようが卑怯だと罵られようが、明確な解答
を示すことはできないのです
何となれば、想定されるものすべてが答えであり、真実で
あって、ダ・ヴィンチの目的を意図するものだからです。

「すべては、すべてから来る。すべては、すべてから
創られて、すべては、すべてに戻っていく。すべては、
すべてに包み込まれる」
また、
「私の芸術を真に理解できるのは数学者だけである」
とも、
「同じ眼でながめた対象が、あるとき
は大きく、あるときは小さく見える」
つまり、そのときの状況や気分次第で、見え方や感じ方
が違ってくると言っています。

従って、
真偽を見極め、嘘とまことを知るために重要なのは、
「最後の最後」にあるとして …
「十分に終わりのことを考えよ。
まず最初に終わりを考慮せよ」
という言葉を残しているわけで、一連の罠の封印を解く
鍵のありかは終わりにあることを示唆しています。

最後の作品とされる『洗礼者聖ヨハネ』
さらに、
「猫はどんなに小さくても
最高傑作である」
と教会に対し、犬の如く忠実で従順に生きる方法を選択
せずに自由奔放な猫の生き方に共感を寄せるとともに、
「希望が死ぬと願掛けが始まる」
とばかりに「神」にすがる絶望を拒否しています。
そして、
何よりも「神」にすがる愚かしさを雄弁に語るのが、
「解剖してわかったことだが、
人間は死ぬようにできている」
というダ・ヴィンチの言葉です。
ところで、肝心の
彼(ヨハネ)なのか、彼女(マグダラのマリア)なのか
と、喧騒も甚だしい人物の正体とは …

『ダ・ヴィンチ・コード』 以来、喧(かまびす)しく
語られるマグダラのマリア説の根拠とされるM字構図
イエス、ヨハネ、ペテロ、そしてユダへと連なる人物の輪郭
がマリアとミステリーを意味するMのかたちを構成している
というのですが、真偽のほどは不明です。
サブタイトルを『謎の人』とした今回の主たるテーマは
、使徒ヨハネとされる人物の正体を探ることが目的ですが、

その前に『最後の晩餐』と名づけられた壁画が
『ダヴィンチの罠』を構成する中核であることを、
まずは理解してください。
そして、「そんな小さな空間に全宇宙の姿を
抱えることができるなど誰が信じるだろう」
というダ・ヴィンチの言葉が、この実験的な壁画のなかに
詰め込まれていることを想像してみてください。
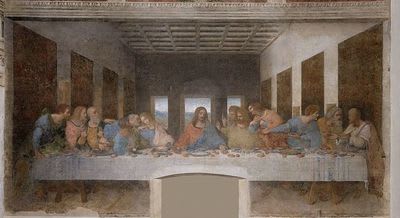
『最後の晩餐(謎の迷宮)』に記したように、
この壁画は最後の晩餐の場面構成を装いながら、
この小さな空間に天地創造から未来までの地球(全宇宙)
の姿を捉えようとした意欲的な実験作だったのです。
ですから、
問題の謎の人物は最後の晩餐のシーンでは、
本命が使徒ヨハネであり、対抗馬がマグダラのマリアで、
穴馬が夜の魔女リリスであるとか …

イエスが復活したあとの顕現の朝餉(あさげ)の
シーンでは、使徒ヨハネでもあり、マグダラのマリアでも、
聖母マリアでもリリスでも、鑑賞者の想像が及ぶものなら
誰でも構わないわけです。
前述のように、天地の創造から未来までをひとつの空間
に表現するとなれば、登場人物はそれぞれに一人何役と
いう複数の人物を演じなくてはなりません。
前記の2つの場面以外の各時代のシーンでは、アダムや
エヴァ、さらには、モーゼやイエスやサタン(ルシファー)で
あったり、その時代、時代を代表する男女の人物だったり
と、男も女も兼ねる役割として使徒ヨハネやフィリポなどが
配置されているわけで …
「想像は感覚に作用する。だから思考と想像力
は感覚によって舵と手綱の働きをする」
とは、そのことを指して言っているのです。
そして、
「どんな部分も、全体に組み込まれる
ようにできている。だからそれ自体は
未完成から逃れられる」
とは、素描も含めたすべての作品がそれぞれに関連して
ひとつの大きな作品としての『ダ・ヴィンチの罠』を
構成する一部分であることを示しているわけで、
換言すれば、
“未完の集大成”が『ダヴィンチの罠』で
あるということになります。
「あらゆるものは他のあらゆるものと
関連する」 かたちで逐一、還元されて …
「すべては、すべてから来る。
すべては、すべてから創られ、
すべては、すべてに戻っていく。
すべては、すべてに包み込まれる」
ようにして昇華していくというわけです。
思考や想像力が思い描く人物です。
アナタが想像する人物が、すべからく使徒ヨハネに
相当する対象者であり該当者になり得るのです。
同様に、
で、「未完の大作」がそれぞれに独自の意思を持つ
かたちで完成されていくというプロセスが、精緻に計算つく
されたダ・ヴィンチの意図するプロットだったのです。
それをして、初めて、
「自分の芸術を真に理解できる
のは数学者だけである」
と言わしめたわけで、それは、一点透視法や空気遠近法
とか、黄金の三角構図や3対1または6対1(3:3:1:3:3)など
の構図の数学的配分を指して言ったものではなく、

「芸術の科学と科学の芸術
を研究せよ」
さすれば、『ダ・ヴィンチの罠』の真意が解ける
であろうと豪語するかのようなダ・ヴィンチの心の叫び声
でもあったのです
さてさて、
この科学者にしてオカルティストたるダ・ヴィンチの間口の
広さが、「万能の天才」たらしめているわけですが、
その分だけ浅い探究にならざるを得ないのは必定です。
しかしながら、浅いとは言っても奥行きは広く深いわけで、
同じルネサンス期のノストラダムスの予言(四行詩)
の持つ(どうにも都合よく解釈できる)曖昧さとは、ひと味も
ふた味も違うものです。
ダ・ヴィンチ(1452-1519)の方が半世紀ほど早く生まれ
ていますが、ほぼ同時代の2人を比べるとノストラダムス
(1503-1566)は誰でも水浴びが可能な遠浅の海水浴場
で、ダ・ヴィンチは遊泳禁止のエリアがある遠浅のビーチ
で、あまり深入りすると危険なうえに随所に離岸流という
「罠」が待ち受けているような浜辺です
面白いことに、ノストラダムス(ミシェル・ド・ノートルダム)
の生まれた1503年に『モナ・リザ』が描かれている
わけですが、彼の本名、ミシェルは大天使ミカエルに由来
し、ノートルダムはフランス語で「我らの貴婦人」と
いう意味で聖母マリアを指しています。
何かそこに因縁めいたものを感じずにはいられないのは
ダ・ヴィンチが生涯にわたり手放さなかった3枚の絵画との
関連性です。
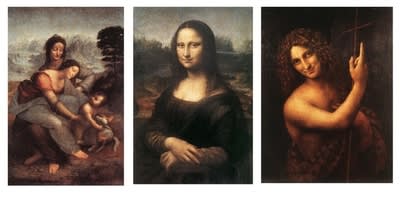
『聖アンナと聖母子』 『モナ・リザ』 『洗礼者聖ヨハネ』
次回は、その辺りに迫ってみたいと考えていますが …

イエスとユダとの関係にしょうかとも思い迷っています。
ムチャクチャな見解のうえに、牽強して付会をする解釈で
煙に巻くような内容には、オカルト以前に、およそ信じるに
足らない疑心を抱かせるものとは思いますが …
(えいしょえんせつ)が生まれないとは限りません
「マズイことになるかと心配したが、ノストラダムス
とやらの予言に大衆が嵌っているうちは安泰だな」

「だが、これ以上、この件には
深入りして欲しくないものだ」
… to be continue !!
単に、オカルトだとして切り捨ててしまうと玉石同砕
(ぎょくせきどうさい)の恐れが大ですよ
こうしてペテロの油断を誘っておいて、実は …
なんていう思わぬ展開が待っているのかも、
『罠』 とは、よくよくそうしたものですので …
まあ、信じるも、信じないも、
アナタ次第ですが ・・・















