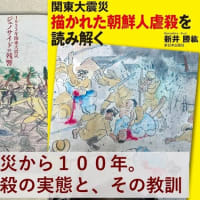20世紀初頭、義和団事件で中国が混乱している隙間に侵入して火事場泥棒の如き西欧列強が北京を侵略し様々な国宝を強奪していたときに日本軍は清帝国の国宝を守ったと言う真実。
このねずさんの独り言と言うブログの内容を見ればわかりますよ。
https://nezu3344.com/blog-entry-4131.html
義和団事件と大陸出兵
2019/05/16
誰しも子や孫を持ってみたらわかることですが、子や孫の幸せを願わない父母や祖父母なんてこの世にいません。
まして個人主義などといういかがわしいものがまだ存在せず、人が共同体として生きることが当然とされていた少し前までの日本では、常に誰に対してもどこに対しても、愛し愛され、ともに平和を守ってより良い時代を築きたいというという意思は、国民共通の意思であり覚悟でさえありました。
そんな日本は戦前まで、中国大陸に兵を出していました。だから日本は中国を侵略したのだという人がいます。
とんでもない言いがかりです。
そんな日本は戦前まで、中国大陸に兵を出していました。だから日本は中国を侵略したのだという人がいます。
とんでもない言いがかりです。

日露戦争が起こる四年前の明治三十三(1900)年のことです。
北京で「義和団事件」が起こりました。
義和団というのは中国の伝統的な武芸と宗教が結びついた拳法結社です。
なんとこれを信仰して拳を行えば、刀で斬られても槍で突かれても銃で撃たれても、体は傷つかず、死ぬこともないという、これまたすごい宗教結社だったわけです。
そして当時、義和団は、まさに不死身の肉体を使って「扶清滅洋(清国を助け、西洋を滅ぼせ)」をスローガンにし、外国人や中国人のキリスト教信者などを襲撃していたのです。
こうした義和団のような結社が中国国内で暴れた最大の理由は、明治27(1894)年の日清戦争による清国の敗北があります。
中国共産党の毛沢東は、実は歴史の変造の名人で、中国混乱のきっかけを阿片戦争に置いたりしていますが、これは大きな間違いです。
第一に当時の阿片は、世界中どこも麻薬のような御禁制の品物という認識を持っていません。
睡眠導入や痛み止めなどの効果のある嗜好品として、普通に一般の商店で売買されていた品物です。
特に英国が経営するインド産の阿片は上物とされて世界中で歓迎されていましたから、阿片は英国の輸出用の主要特産物でした。
ところがあまりにも中国でこの阿片が売れるものだから中国で中国産の偽造粗悪品が出回り、一方で清朝当局が英国との貿易赤字解消のために英国からの阿片輸入を規制して、自国産の阿片流通を独占しようとしたものだから、争いになったものです。
英国は北京近くまで軍艦をすすめ、結果として清国は英国の言い分を飲んで一件落着となりましたが、事件自体は清王朝の存続を何ら揺るがすような大事には至っていません。
ところが日清戦争による清朝の敗北は、清国というよりも欧米列強に強い影響を与えました。
中国における利権拡大を目論む列強に、日本の存在がきわめて大きな障害と認識されるようになったのです。
このことはすこし考えたらわかることです。
日本と清朝がもし手を結べば、欧米列強にとっては、それは東洋最大の脅威を招くからです。
ですから三国干渉をして、日本に遼東半島を返還させ、それをロシアがとりあげ、イギリスは威海衛を分捕っただけでなく、フランスとの均衡のためと主張して香港島対岸の九龍を奪い、そのフランスは広州湾を奪い、ドイツは膠州湾と青島をそれぞれ清国からむしりとっています。
中国の民衆からしたら、こうした列強による領土の侵蝕は不快なものです。
その民衆の不快と不安に対するひとつの応答が、拳法結社としての義和団であったわけです。
北京で「義和団事件」が起こりました。
義和団というのは中国の伝統的な武芸と宗教が結びついた拳法結社です。
なんとこれを信仰して拳を行えば、刀で斬られても槍で突かれても銃で撃たれても、体は傷つかず、死ぬこともないという、これまたすごい宗教結社だったわけです。
そして当時、義和団は、まさに不死身の肉体を使って「扶清滅洋(清国を助け、西洋を滅ぼせ)」をスローガンにし、外国人や中国人のキリスト教信者などを襲撃していたのです。
こうした義和団のような結社が中国国内で暴れた最大の理由は、明治27(1894)年の日清戦争による清国の敗北があります。
中国共産党の毛沢東は、実は歴史の変造の名人で、中国混乱のきっかけを阿片戦争に置いたりしていますが、これは大きな間違いです。
第一に当時の阿片は、世界中どこも麻薬のような御禁制の品物という認識を持っていません。
睡眠導入や痛み止めなどの効果のある嗜好品として、普通に一般の商店で売買されていた品物です。
特に英国が経営するインド産の阿片は上物とされて世界中で歓迎されていましたから、阿片は英国の輸出用の主要特産物でした。
ところがあまりにも中国でこの阿片が売れるものだから中国で中国産の偽造粗悪品が出回り、一方で清朝当局が英国との貿易赤字解消のために英国からの阿片輸入を規制して、自国産の阿片流通を独占しようとしたものだから、争いになったものです。
英国は北京近くまで軍艦をすすめ、結果として清国は英国の言い分を飲んで一件落着となりましたが、事件自体は清王朝の存続を何ら揺るがすような大事には至っていません。
ところが日清戦争による清朝の敗北は、清国というよりも欧米列強に強い影響を与えました。
中国における利権拡大を目論む列強に、日本の存在がきわめて大きな障害と認識されるようになったのです。
このことはすこし考えたらわかることです。
日本と清朝がもし手を結べば、欧米列強にとっては、それは東洋最大の脅威を招くからです。
ですから三国干渉をして、日本に遼東半島を返還させ、それをロシアがとりあげ、イギリスは威海衛を分捕っただけでなく、フランスとの均衡のためと主張して香港島対岸の九龍を奪い、そのフランスは広州湾を奪い、ドイツは膠州湾と青島をそれぞれ清国からむしりとっています。
中国の民衆からしたら、こうした列強による領土の侵蝕は不快なものです。
その民衆の不快と不安に対するひとつの応答が、拳法結社としての義和団であったわけです。
その義和団は、明治三十三(1900)年五月、二〇万の大軍となって北京南西八キロにある張辛店を襲い、駅舎に火を放って電信設備を破壊しました。
当時の北京には、清国王朝と外交交渉をするための欧米の列強外交団が滞在していました。
外交団は、清国政府に暴徒を鎮圧するように要求しました。
そしてその一方で天津港に停泊する列国の軍艦から、各国の海軍陸戦隊四百名余を、急遽北京に呼び寄せました。
このとき日本からも、軍艦愛宕から二十五名の将兵が北京に入っています。
人数を考えたらわかるのですが、この時点で列強は、清王朝による暴徒鎮圧を期待していました。
だからこそ防衛のために呼び寄せたのは、十一カ国の兵員の合計が、わずか四百だったのです。
ところが清王朝は何もしない。何も動かない。
動かないまま六月四日には、北京〜天津間を結ぶ鉄道が、義和団によって破壊されてしまいます。
これはたいへんなことです。
なぜなら鉄道の破壊は、北京に滞在している各国の外交団が、陸に孤立することになるからです
当時、北京にある公使館職員の最初の犠牲者は、日本の杉山書記官でした。
彼は救援部隊が来ないかと北京城外に出て戻ろうとしたところを、なんと清国の警備部隊に捕まり、生きたまま心臓を抉り抜かれてしまったのです。
この事件によって、北京在住の十一カ国の外交公使団は、頼みの綱の清国の官憲までが義和団の側に立っていることを知ります。
五月十三日、公使館区域に四〜五百人の義和団が襲いかかってきました。
列強の陸戦隊の兵士たちは、銃で果敢に応戦し、これを撃退します。
けれど、防衛にあたってくれているはずの清国官兵は何も動こうとしない。
翌十四日になると、今度は義和団の暴徒は、外国公使館区域に隣接する中国人のキリスト教信者たちが住む地域を襲います。
そこは列強の陸戦隊の守備の外側です。
男たちの凄まじい怒号と女たちの悲鳴が、遠くはなれた公使館区域まで聞こえたそうです。
そしてこの日一日で惨殺された中国人キリスト教徒は、千人を超えたものとなりました。
六月十九日になると、清国政府は、二十四時間以内に外国人全員が北京から退去するようにと通告してきました。
周囲をぐるりと義和団に包囲されているのです。
ようやく堡塁を築いて銃で応戦しているのに、そこを出て行けとなれば、それは即、死を意味します。
あまりの通告に、ドイツの大使が抗議に赴いたのですが、清国政府に到着する前に、清国兵にいきなり銃撃されて即死しています。
そして翌二十日からは、命令に背いたことを理由に、地域の警備についていた(何もしなかった)清国兵たちが、堂々と義和団と一緒になって外国人公使街への攻撃を始めました。
義和団の暴徒たちの武器は、青龍刀や槍などですけれど、清国兵は正規軍です。
彼らは堂々と大砲まで持ち出して、公使館区域を攻撃しはじめたのです。
こうしてはじまった義和団事件は、単に義和団という民間拳法結社の暴動にとどまらず、ついには清国の権力者だった西太后によって、首都・北京在住の外国人を人質にとって、諸外国への宣戦布告、外国人公使街への清国正規軍の投入に至りました。
北京の外国人公使街というのは、東西に約九百メートル、南北が約八百メートルの四角く囲まれた小さなエリアです。
そこに英・米・仏・露・独・墺(オーストリア)・伊・蘭・ベルギー・スペインの欧米十カ国と日本公使館が置かれていました。
そこには約四千人の外国人公使、およびその子女たちがいました。
防備にあたった各国の海軍陸戦隊の兵隊さんたちの数は、全部合わせてもたったの四百です。
そこに義和団の二20万、清国正規軍10万が投入され、攻撃をしかけてきました。
戦いは約百日続きました。
このとき、各国の公使やその妻子たちが絶賛したのが、わずか25名の日本兵でした。
とにかく強い、強い。
当時、英国公使館は各国の公使館の中でも、もっとも壮大な建物でした。
そこには各国の婦女子が収容されていました。
その英国公使館の正面を清国兵が砲弾で破り、開いた穴をめがけて数百の義和団の暴徒たちが青龍刀や牛刀を振りかざし、奇声をあげて襲いかかって来たのです。
正面を守り銃で応射していた英国兵も、その迫力に後退を余儀なくされました。
「このままでは、英国公使館がやられる」
誰もがそう思ったとき、どこからともなく、わずか8名の日本兵が、その場にやってきました。
先頭にいたのが安藤大尉です。
彼は暴徒の前に躍り出ると、たちまち抜き打ちざまに手にした軍刀で義和団の暴徒を切り伏せます。
たちまち安藤大尉の前に、義和団の暴徒たちの死体が転がる。
目にも止まらぬ早業です。
のこりの日本兵たちも。声もたてずに暴徒を切り伏せます。
そのあまりの凄さに、暴徒たちは浮き足立ち、われさきにと壁の外に逃げ出しました。
この安藤大尉たちの奮戦は、イギリス公使館に避難していた人々の目の前で行われたため、日本兵の勇敢さは賞賛の的となり、のちのちまで一同の語りぐさとなっています。
ピーター・フレミングという米国人のジャーナリストが、このとき北京にいて、その一部始終を目撃し、それを「北京籠城」という本にしているのですが、その中に、「あるイギリス人の義勇兵が見た、とても人間業とは思えない光景」というのがあります。
「そのとき、私は隣の銃眼で監視立っている日本兵の頭部を銃弾がかすめるのを見ました。瞬間、真赤な血が飛び散りました。ところが彼は後ろに下がろうとはしません。軍医を呼ぼうともしない。『くそっ』というようなことを叫んだ彼は、手ぬぐいを取り出すと、はち巻の包帯をして、そのまま何でもなかったように敵の看視を続けたのです。」
「戦線で負傷し、麻酔もなく手術を受ける日本兵は、ヨーロッパ兵のように泣き叫んだりしませんでした。彼は口に帽子をくわえ、かみ締め、少々うなりはしたが、メスの痛みに耐えました。手術後も彼らは沈鬱な表情一つ見せず、むしろおどけて、周囲の空気を明るくしようとつとめていました。日本兵には日本婦人がまめまめしく看護にあたっていたが、その一角はいつもなごやかで、ときに笑い声さえ聞こえていました」
「長い籠城の危険と苦しみです。欧米人たち、なかでも婦人たちは暗くなりました。中には発狂寸前の人もいました。だから彼女たちは日常と変わらない日本の負傷兵の明るさに接すると心からほっとし、看護の欧米婦人は、みんな日本兵のファンになってしまいました」
「戦略上の最重要地点である王府では、日本兵が守備のバックボーンであり、頭脳であった。日本軍を指揮した柴中佐は、籠城中のどの士官よりも勇敢で経験もあったばかりか、誰からも好かれ、尊敬された。当時、日本人とつきあう欧米人はほとんどいなかったが、この籠城をつうじてそれが変わった。日本人の姿が模範生として、みなの目に映るようになった。」
ピーター・フレミングの「北京籠城」は全米で大ヒットとなり、その後、なんとチャールトン・ヘストン主演で、「北京の55日」という名のハリウッド映画になりました。この映画でチャールトン・ヘストンは、アメリカ軍将校として大活躍するのですが、実は、この役の現実のモデルが、指揮をとっていた柴五郎中佐(後に陸軍大将)です。
北京に、救援のための各国混成連合軍がやっと到着したのが8月13日です。
総勢1万6千のうちの約半数は、日本から駆けつけた福島安正少将旗下の第五師団です。
その他ロシア3千、英米が各2千、フランスが800などです。
日本軍の数が多いのはあたりまえのことです。
日本が地理的にいちばん近い。
救援隊がやってくると、翌日には西太后の一行が北京から西安に向けて逃げ出しました。
清国の首都北京から、政府がなくなってしまったのです。
このため北京市内では生残った義和団や清国兵による暴力や略奪が横行しました。
そんな中で、各国との協議によって日本に割り当てられた占領区は、いちはやく治安が回復します。
日本軍は横行する強盗や窃盗、無頼漢らを容赦なく捕えて厳罰に処したのです。
また暴行・略奪をした外国人兵士(その筆頭がロシア兵)を捕え、彼らの軍司令部に突き出しました。
そのため他国の占領区域から、日本占領区域に移り住む市民が後を絶たず、町は日に日に繁昌したといいます。
さらに日本は、清国を守るために、清国皇族の慶親王に「一刻も早く北京に戻り、列国と交渉を始めなければ、清国はその存立が危ない」と使者を送り、一日も早い清国の安定のための努力もしています。
いまでは考えられないことですが、この時代、世界で認められた公式な政府がない地域は「無主地」として、列国が分け取りにしてよい、というのが世界のルールだったのです。
実際、義和団鎮圧後になって、北京での義和団事件にまったく参加していなかったドイツが、治安の回復後になって続々と大軍を送り込み、北京で稼ぎそこなった分を他の諸都市で略奪しはじめていました。
またロシアは、義和団事件直後に、2万の兵力を満州に送り込んでそこを占領し、各国の軍隊が引き上げたあとも、そこに居座り続けました。
事件後、ようやく政府機能を取り戻した清国と、各国は賠償会議を開きました。
このとき最大の賠償金を吹っかけたのがロシアで、一番少なかったのが日本です。
イギリスは日本の五倍、戦後にやってきたドイツがイギリスの2倍、わずかな兵を出しただけのフランスは日本の2倍(出兵数の比では日本の100倍)を要求しています。
義和団の乱に乗じて、自分の政治権力の強化をはかった西太后は高い代償を払うことになったのです。
この事件後の会議で、攻められた側の11カ国と攻めた側の清国が交わした条約が
「北清事変に関する最終議定書」です。
略して「北京議定書」とも呼ばれます。
欧米では「Boxer Protocol」、
現代中国ではその年をとって「辛丑条約」とも呼んでいます。
「北京議定書」によって交わされた条約内容は、およそ次のような内容でした。
[1]日本,ドイツへの謝罪使の派遣
[2]責任者の処罰
[3]賠償金四億五千万両の支払い
[4]公使館区域の設定と同地域における外国軍の駐兵
[5]北京=山海関等十二の要地における外国軍の駐屯
[6]天津周辺二十里以内での中国軍の駐留禁止
[7]外国人への殺害が行われた地域での五年間の科挙停止
[8]排外主義的団体への中国人の加入禁止
[9]各地の官吏に対する排外暴動鎮圧の義務化
この中に書かれた賠償金4億5千万両というのは、利払いまで含めると総額が8億5千万両にものぼるたいへんな金額です。
当時の清国は、年間予算が約1億両です。
時代はこの後、日露戦争(1904)、第二次世界大戦(1914)、支 那事変(1937)、大東亜戦争(1941)と進みますが、昨今よく聞かれる、「日本の軍がなぜ中国にいたのか」という疑問に対する答えが、この義和団事件と、事件後に交わされた「北京議定書」です。
清国はこの議定によって、まさに天文学的な賠償金を支払うことになりました。
たとえ国母という圧倒的な清国内の政治的地位があったとしても、いかがわしい新興宗教団体と手を握り、暴徒を挑発して他国の公使館を攻めるなどという行為は、いかなる時代にあっても許されるべきことではありません。
西大后の軽挙によって、清国は政治運営のための経済までも追いつめられてしまうのです。
政府の弱化は、結果として中国国内の治安をますます悪化させることになりました。
国内には腐敗した軍閥が割拠し、その後も外国人への襲撃が相次ぎます。
そして日本を含む列国は、居留民や領事館保護のために、中国各地への駐兵を余儀なくされたのです。
一方、この事件後に混乱に乗じて満州を軍事占領したロシアは、その後も着々と満州の兵力を増強していきました。
当時のロシアは、国家予算も兵力も、日本の10倍です。
さらにロシアが朝鮮北部の旅順にまで軍事要塞を構築するにおよぶと、このまま黙視すれば、ロシアの極東における軍事力は日本が太刀打ちできないほど増強されることが明らかになります。
日本政府は、手遅れになることをおそれ、ついにロシアとの開戦を決意します。
こうして起こったのが日露戦争です。
(著者注)義和団事件の模様には伊勢雅臣氏の「国際派日本人養成講座二二二号」、経緯については自由社刊「新しい歴史教科書」を参考にさせていただきました。
当時の北京には、清国王朝と外交交渉をするための欧米の列強外交団が滞在していました。
外交団は、清国政府に暴徒を鎮圧するように要求しました。
そしてその一方で天津港に停泊する列国の軍艦から、各国の海軍陸戦隊四百名余を、急遽北京に呼び寄せました。
このとき日本からも、軍艦愛宕から二十五名の将兵が北京に入っています。
人数を考えたらわかるのですが、この時点で列強は、清王朝による暴徒鎮圧を期待していました。
だからこそ防衛のために呼び寄せたのは、十一カ国の兵員の合計が、わずか四百だったのです。
ところが清王朝は何もしない。何も動かない。
動かないまま六月四日には、北京〜天津間を結ぶ鉄道が、義和団によって破壊されてしまいます。
これはたいへんなことです。
なぜなら鉄道の破壊は、北京に滞在している各国の外交団が、陸に孤立することになるからです
当時、北京にある公使館職員の最初の犠牲者は、日本の杉山書記官でした。
彼は救援部隊が来ないかと北京城外に出て戻ろうとしたところを、なんと清国の警備部隊に捕まり、生きたまま心臓を抉り抜かれてしまったのです。
この事件によって、北京在住の十一カ国の外交公使団は、頼みの綱の清国の官憲までが義和団の側に立っていることを知ります。
五月十三日、公使館区域に四〜五百人の義和団が襲いかかってきました。
列強の陸戦隊の兵士たちは、銃で果敢に応戦し、これを撃退します。
けれど、防衛にあたってくれているはずの清国官兵は何も動こうとしない。
翌十四日になると、今度は義和団の暴徒は、外国公使館区域に隣接する中国人のキリスト教信者たちが住む地域を襲います。
そこは列強の陸戦隊の守備の外側です。
男たちの凄まじい怒号と女たちの悲鳴が、遠くはなれた公使館区域まで聞こえたそうです。
そしてこの日一日で惨殺された中国人キリスト教徒は、千人を超えたものとなりました。
六月十九日になると、清国政府は、二十四時間以内に外国人全員が北京から退去するようにと通告してきました。
周囲をぐるりと義和団に包囲されているのです。
ようやく堡塁を築いて銃で応戦しているのに、そこを出て行けとなれば、それは即、死を意味します。
あまりの通告に、ドイツの大使が抗議に赴いたのですが、清国政府に到着する前に、清国兵にいきなり銃撃されて即死しています。
そして翌二十日からは、命令に背いたことを理由に、地域の警備についていた(何もしなかった)清国兵たちが、堂々と義和団と一緒になって外国人公使街への攻撃を始めました。
義和団の暴徒たちの武器は、青龍刀や槍などですけれど、清国兵は正規軍です。
彼らは堂々と大砲まで持ち出して、公使館区域を攻撃しはじめたのです。
こうしてはじまった義和団事件は、単に義和団という民間拳法結社の暴動にとどまらず、ついには清国の権力者だった西太后によって、首都・北京在住の外国人を人質にとって、諸外国への宣戦布告、外国人公使街への清国正規軍の投入に至りました。
北京の外国人公使街というのは、東西に約九百メートル、南北が約八百メートルの四角く囲まれた小さなエリアです。
そこに英・米・仏・露・独・墺(オーストリア)・伊・蘭・ベルギー・スペインの欧米十カ国と日本公使館が置かれていました。
そこには約四千人の外国人公使、およびその子女たちがいました。
防備にあたった各国の海軍陸戦隊の兵隊さんたちの数は、全部合わせてもたったの四百です。
そこに義和団の二20万、清国正規軍10万が投入され、攻撃をしかけてきました。
戦いは約百日続きました。
このとき、各国の公使やその妻子たちが絶賛したのが、わずか25名の日本兵でした。
とにかく強い、強い。
当時、英国公使館は各国の公使館の中でも、もっとも壮大な建物でした。
そこには各国の婦女子が収容されていました。
その英国公使館の正面を清国兵が砲弾で破り、開いた穴をめがけて数百の義和団の暴徒たちが青龍刀や牛刀を振りかざし、奇声をあげて襲いかかって来たのです。
正面を守り銃で応射していた英国兵も、その迫力に後退を余儀なくされました。
「このままでは、英国公使館がやられる」
誰もがそう思ったとき、どこからともなく、わずか8名の日本兵が、その場にやってきました。
先頭にいたのが安藤大尉です。
彼は暴徒の前に躍り出ると、たちまち抜き打ちざまに手にした軍刀で義和団の暴徒を切り伏せます。
たちまち安藤大尉の前に、義和団の暴徒たちの死体が転がる。
目にも止まらぬ早業です。
のこりの日本兵たちも。声もたてずに暴徒を切り伏せます。
そのあまりの凄さに、暴徒たちは浮き足立ち、われさきにと壁の外に逃げ出しました。
この安藤大尉たちの奮戦は、イギリス公使館に避難していた人々の目の前で行われたため、日本兵の勇敢さは賞賛の的となり、のちのちまで一同の語りぐさとなっています。
ピーター・フレミングという米国人のジャーナリストが、このとき北京にいて、その一部始終を目撃し、それを「北京籠城」という本にしているのですが、その中に、「あるイギリス人の義勇兵が見た、とても人間業とは思えない光景」というのがあります。
「そのとき、私は隣の銃眼で監視立っている日本兵の頭部を銃弾がかすめるのを見ました。瞬間、真赤な血が飛び散りました。ところが彼は後ろに下がろうとはしません。軍医を呼ぼうともしない。『くそっ』というようなことを叫んだ彼は、手ぬぐいを取り出すと、はち巻の包帯をして、そのまま何でもなかったように敵の看視を続けたのです。」
「戦線で負傷し、麻酔もなく手術を受ける日本兵は、ヨーロッパ兵のように泣き叫んだりしませんでした。彼は口に帽子をくわえ、かみ締め、少々うなりはしたが、メスの痛みに耐えました。手術後も彼らは沈鬱な表情一つ見せず、むしろおどけて、周囲の空気を明るくしようとつとめていました。日本兵には日本婦人がまめまめしく看護にあたっていたが、その一角はいつもなごやかで、ときに笑い声さえ聞こえていました」
「長い籠城の危険と苦しみです。欧米人たち、なかでも婦人たちは暗くなりました。中には発狂寸前の人もいました。だから彼女たちは日常と変わらない日本の負傷兵の明るさに接すると心からほっとし、看護の欧米婦人は、みんな日本兵のファンになってしまいました」
「戦略上の最重要地点である王府では、日本兵が守備のバックボーンであり、頭脳であった。日本軍を指揮した柴中佐は、籠城中のどの士官よりも勇敢で経験もあったばかりか、誰からも好かれ、尊敬された。当時、日本人とつきあう欧米人はほとんどいなかったが、この籠城をつうじてそれが変わった。日本人の姿が模範生として、みなの目に映るようになった。」
ピーター・フレミングの「北京籠城」は全米で大ヒットとなり、その後、なんとチャールトン・ヘストン主演で、「北京の55日」という名のハリウッド映画になりました。この映画でチャールトン・ヘストンは、アメリカ軍将校として大活躍するのですが、実は、この役の現実のモデルが、指揮をとっていた柴五郎中佐(後に陸軍大将)です。
北京に、救援のための各国混成連合軍がやっと到着したのが8月13日です。
総勢1万6千のうちの約半数は、日本から駆けつけた福島安正少将旗下の第五師団です。
その他ロシア3千、英米が各2千、フランスが800などです。
日本軍の数が多いのはあたりまえのことです。
日本が地理的にいちばん近い。
救援隊がやってくると、翌日には西太后の一行が北京から西安に向けて逃げ出しました。
清国の首都北京から、政府がなくなってしまったのです。
このため北京市内では生残った義和団や清国兵による暴力や略奪が横行しました。
そんな中で、各国との協議によって日本に割り当てられた占領区は、いちはやく治安が回復します。
日本軍は横行する強盗や窃盗、無頼漢らを容赦なく捕えて厳罰に処したのです。
また暴行・略奪をした外国人兵士(その筆頭がロシア兵)を捕え、彼らの軍司令部に突き出しました。
そのため他国の占領区域から、日本占領区域に移り住む市民が後を絶たず、町は日に日に繁昌したといいます。
さらに日本は、清国を守るために、清国皇族の慶親王に「一刻も早く北京に戻り、列国と交渉を始めなければ、清国はその存立が危ない」と使者を送り、一日も早い清国の安定のための努力もしています。
いまでは考えられないことですが、この時代、世界で認められた公式な政府がない地域は「無主地」として、列国が分け取りにしてよい、というのが世界のルールだったのです。
実際、義和団鎮圧後になって、北京での義和団事件にまったく参加していなかったドイツが、治安の回復後になって続々と大軍を送り込み、北京で稼ぎそこなった分を他の諸都市で略奪しはじめていました。
またロシアは、義和団事件直後に、2万の兵力を満州に送り込んでそこを占領し、各国の軍隊が引き上げたあとも、そこに居座り続けました。
事件後、ようやく政府機能を取り戻した清国と、各国は賠償会議を開きました。
このとき最大の賠償金を吹っかけたのがロシアで、一番少なかったのが日本です。
イギリスは日本の五倍、戦後にやってきたドイツがイギリスの2倍、わずかな兵を出しただけのフランスは日本の2倍(出兵数の比では日本の100倍)を要求しています。
義和団の乱に乗じて、自分の政治権力の強化をはかった西太后は高い代償を払うことになったのです。
この事件後の会議で、攻められた側の11カ国と攻めた側の清国が交わした条約が
「北清事変に関する最終議定書」です。
略して「北京議定書」とも呼ばれます。
欧米では「Boxer Protocol」、
現代中国ではその年をとって「辛丑条約」とも呼んでいます。
「北京議定書」によって交わされた条約内容は、およそ次のような内容でした。
[1]日本,ドイツへの謝罪使の派遣
[2]責任者の処罰
[3]賠償金四億五千万両の支払い
[4]公使館区域の設定と同地域における外国軍の駐兵
[5]北京=山海関等十二の要地における外国軍の駐屯
[6]天津周辺二十里以内での中国軍の駐留禁止
[7]外国人への殺害が行われた地域での五年間の科挙停止
[8]排外主義的団体への中国人の加入禁止
[9]各地の官吏に対する排外暴動鎮圧の義務化
この中に書かれた賠償金4億5千万両というのは、利払いまで含めると総額が8億5千万両にものぼるたいへんな金額です。
当時の清国は、年間予算が約1億両です。
時代はこの後、日露戦争(1904)、第二次世界大戦(1914)、支 那事変(1937)、大東亜戦争(1941)と進みますが、昨今よく聞かれる、「日本の軍がなぜ中国にいたのか」という疑問に対する答えが、この義和団事件と、事件後に交わされた「北京議定書」です。
清国はこの議定によって、まさに天文学的な賠償金を支払うことになりました。
たとえ国母という圧倒的な清国内の政治的地位があったとしても、いかがわしい新興宗教団体と手を握り、暴徒を挑発して他国の公使館を攻めるなどという行為は、いかなる時代にあっても許されるべきことではありません。
西大后の軽挙によって、清国は政治運営のための経済までも追いつめられてしまうのです。
政府の弱化は、結果として中国国内の治安をますます悪化させることになりました。
国内には腐敗した軍閥が割拠し、その後も外国人への襲撃が相次ぎます。
そして日本を含む列国は、居留民や領事館保護のために、中国各地への駐兵を余儀なくされたのです。
一方、この事件後に混乱に乗じて満州を軍事占領したロシアは、その後も着々と満州の兵力を増強していきました。
当時のロシアは、国家予算も兵力も、日本の10倍です。
さらにロシアが朝鮮北部の旅順にまで軍事要塞を構築するにおよぶと、このまま黙視すれば、ロシアの極東における軍事力は日本が太刀打ちできないほど増強されることが明らかになります。
日本政府は、手遅れになることをおそれ、ついにロシアとの開戦を決意します。
こうして起こったのが日露戦争です。
(著者注)義和団事件の模様には伊勢雅臣氏の「国際派日本人養成講座二二二号」、経緯については自由社刊「新しい歴史教科書」を参考にさせていただきました。
これこそ真実ですよ。