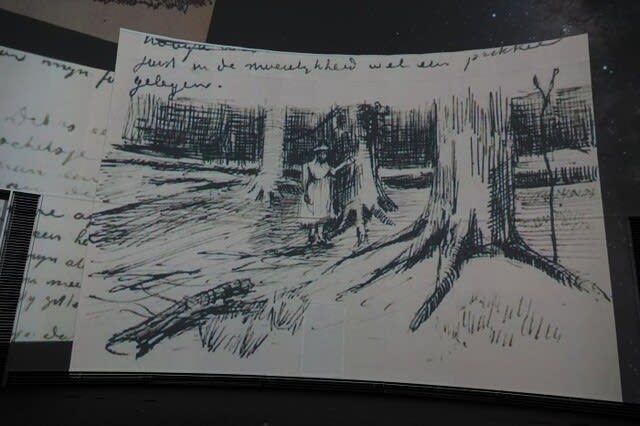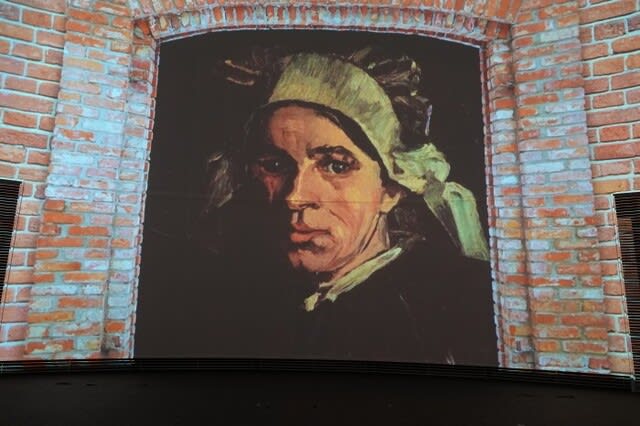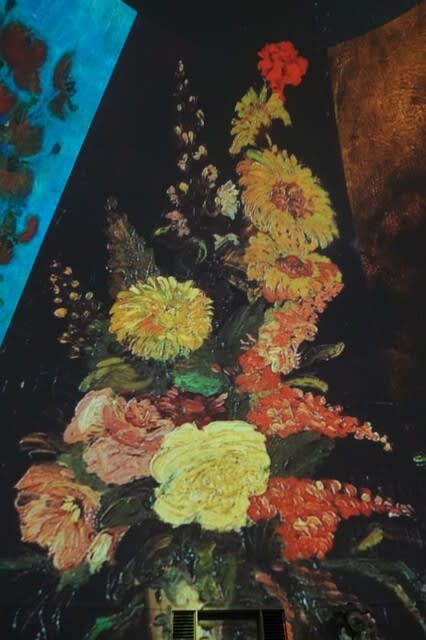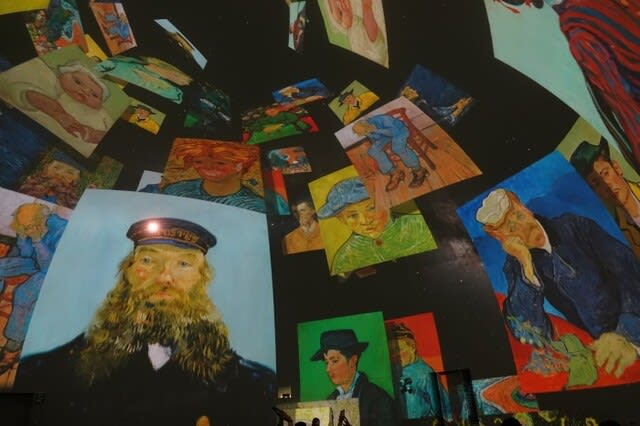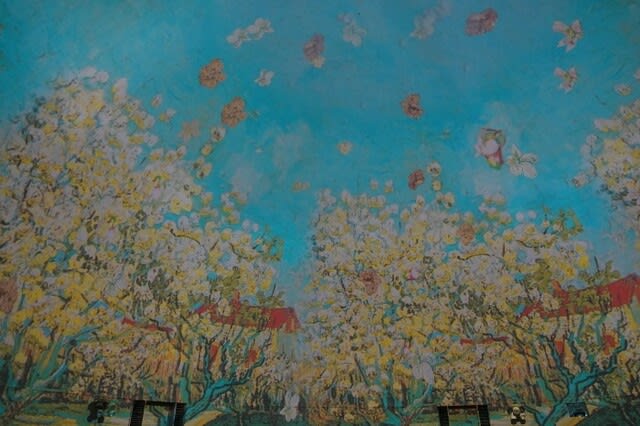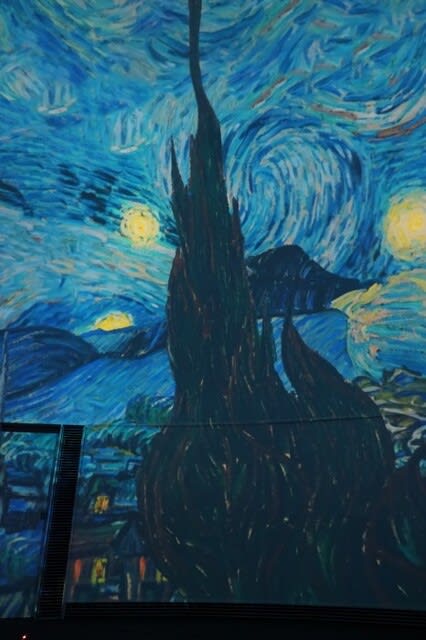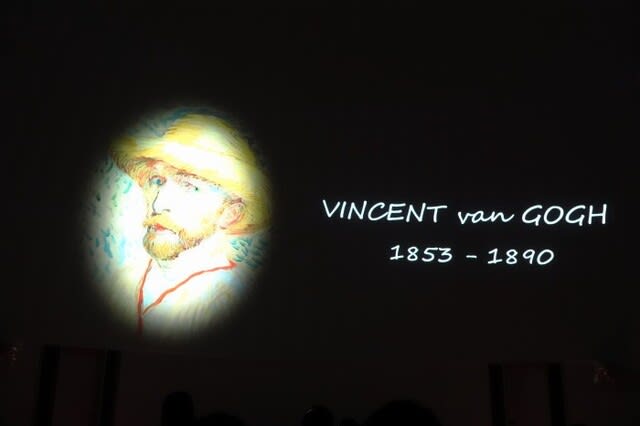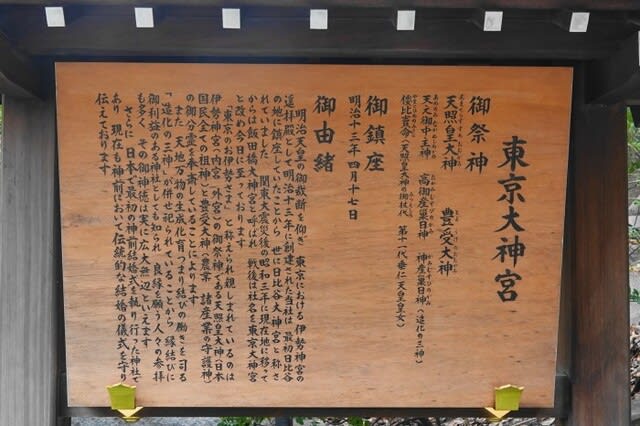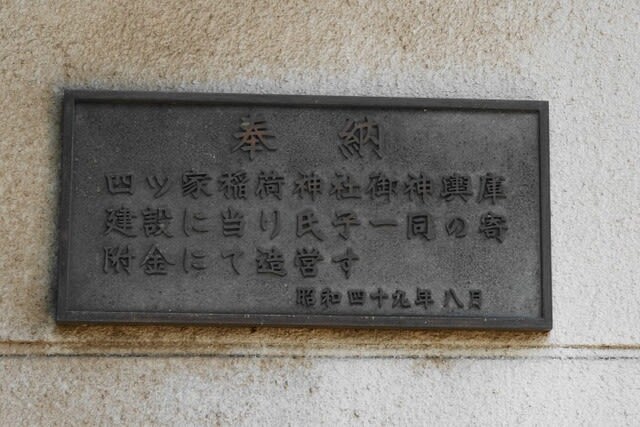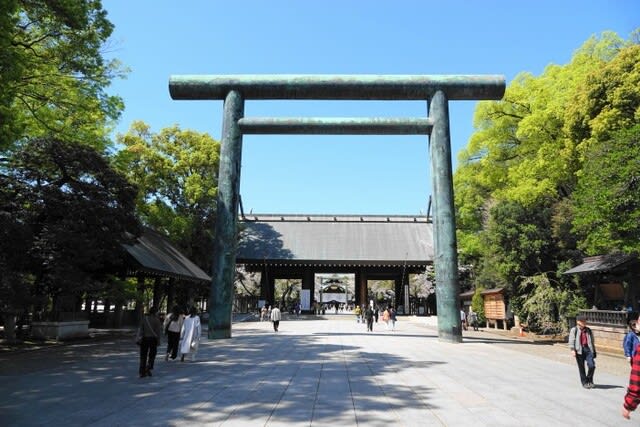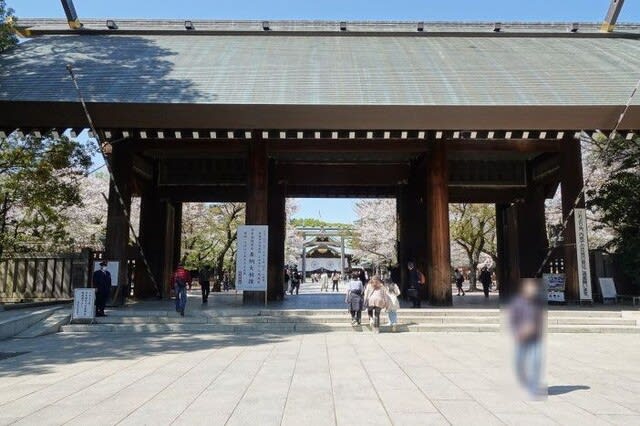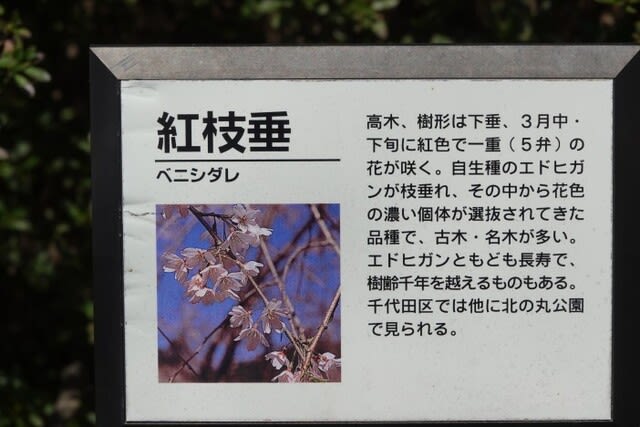干支ツリー〈巳 巳年〉〈東京国際フォーラム〉 干支ツリー2025
干支ツリー
2024〈辰〉[Click here !↗]
2023〈卯〉[Click here !↗]
2022〈寅〉[Click here !↗]
2020〈子〉[Click here !↗]
2019〈亥〉[Click here !↗]
2018〈戌〉[Click here !↗]
2017〈酉〉[Click here !↗]
2015〈未〉[Click here !↗]
2014〈午〉[Click here !↗]
干支ツリーの場所 東京都千代田区丸の内3-5-1:東京国際フォーラム地下一階 [Click here !↗]
巳〈干支ツリー〉 令和6年12月6日撮影
有楽町寄りのツリー 巳の色は赤 お腹は紅白のボーダー




東京駅寄りののツリー 巳の色は緑




東京駅と有楽町駅の中間のツリー 巳は緑と赤で半分ずつ




干支ツリー
2024〈辰〉[Click here !↗]
2023〈卯〉[Click here !↗]
2022〈寅〉[Click here !↗]
2020〈子〉[Click here !↗]
2019〈亥〉[Click here !↗]
2018〈戌〉[Click here !↗]
2017〈酉〉[Click here !↗]
2015〈未〉[Click here !↗]
2014〈午〉[Click here !↗]
干支ツリーの場所 東京都千代田区丸の内3-5-1:東京国際フォーラム地下一階 [Click here !↗]
巳〈干支ツリー〉 令和6年12月6日撮影
有楽町寄りのツリー 巳の色は赤 お腹は紅白のボーダー




東京駅寄りののツリー 巳の色は緑




東京駅と有楽町駅の中間のツリー 巳は緑と赤で半分ずつ