
鈴木修(スズキ自動車CEO)ウィキペディア
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%88%B4%E6%9C%A8%E4%BF%AE_(%E5%AE%9F%E6%A5%AD%E5%AE%B6)
私個人も鈴木会長みたいに最後の最後まで役に立つ人間でありたいのが本音です。
鈴木修氏の苦悩
2011年09月14日10時00分
<script src="http://platform.twitter.com/widgets.js" type="text/javascript"></script>
自動車のスズキの鈴木修会長は提携していたフォルックスワーゲン社との提携の解消に動き出しました。提携そのものは2009年末にある意味衝撃的に発表され、ノリに乗っているフォルクスワーゲン幹部と鈴木会長の仲良く映った写真が印象的でした。
一方、鈴木会長は氏を直接知る人から「変わり者だよ」と教えられました。この意味は発想が日本的ではなく、ユニークだということかもしれません。或いは「スズキ自動車商店」のオヤジがいつの間にか、世界第三の自動車会社からラブコールされる会社になったことにちょっと気持ちを良くしたのかもしれません。
一方、当時のフォルックスワーゲンはインド市場制覇が一つの大きな戦略でした。既に中国自動車市場は戦国時代を迎えていたことから次の時代を担う大きな市場であるインドには勝ち組として残ることは企業として使命であります。ご承知の通り、フォルクスワーゲンはアウディ、ランボルギーニ、ベントレーを傘下に収めると共にポルシェも子会社化して自動車ブランドのデパートと化しています。
スズキはインド市場で長年の努力が実り、圧倒的強みを見せていることからフォルックスワーゲンとしては相対的規模の小さいスズキの株式取得を通じて支配下に置き、フォックスワーゲンの一ラインアップとするつもりでした。
が、鈴木会長は最近、日産自動車のゴーン会長がロシアのアフトワズや中国の東風汽車との提携により業績に実を結ぶ効果があったことと自社のフォルックスワーゲンとの提携を比較し、無意味、無効果な提携を悔いている発言がありました。鈴木会長はたたき上げの商店主であるのですからそう簡単に自分の築き上げたブランドを他人にほいほい渡すわけにはいかないという強い気持ちのあらわれでしょう。もともと2009年に提携関係に入ったときは自社のキャパシティを考えながら「自分の描く提携」を模索したのだろうと思います。
海外の会社と手を結ぶというのは実に大変で相手の能力をどう引き出すか、その手腕はトップの国際人としてのセンスにかかっています。例えば僕が以前勤めた会社で買収したアメリカの某ホテルがいかにコントロールするのに苦労したか、じかに感じているのでわかります。
あの時はアメリカ人は買収した日本の親会社をなめてかかっていたと思います。そして、それに戦いを挑めたのはトップを含めたごくわずかの人だけでした。つまり、日本側数人で社員何千人もいる相手を経営的に唸らせるのは腰掛程度では絶対に無理だったということを僕なりに実感させてもらいました。特に日本人とアメリカ人の間にコミュニケーションのみならず、考え方のギャップがあり、それが埋め尽くせなかった、という感じがします。
一方、日産ゴーン会長はもとからブラジル系フランス人であるが故に欧米社会にナチュラルに入り込めるし、相手方も受け入れるというアドバンテージがあります。これは残念ながら否定できない事実です。
唯一、僕がこれぞ立派な日本企業による買収と思ったのがブリジストンのファイアストン買収。これはある意味、経営的にも苦しかったファイアストンをブリジストンの社長がたしか年の三分の二ぐらいをアメリカ、ファイアストン社の本社に駐在し、日米の真の意味での合体を遂げたケースです。トップが乗り込んでいき、直に指揮を執るぐらいでないと欧米の会社を自分の都合よくコントロールするのは難しいという良い例かと思います。
スズキ自動車のケースは日本の外国会社との提携の難しさを改めて見せ付けたような気がします。これを糧に日本企業は大いに学んでもらいたいと思います。
今日はこのぐらいにしておきましょう。
一方、鈴木会長は氏を直接知る人から「変わり者だよ」と教えられました。この意味は発想が日本的ではなく、ユニークだということかもしれません。或いは「スズキ自動車商店」のオヤジがいつの間にか、世界第三の自動車会社からラブコールされる会社になったことにちょっと気持ちを良くしたのかもしれません。
一方、当時のフォルックスワーゲンはインド市場制覇が一つの大きな戦略でした。既に中国自動車市場は戦国時代を迎えていたことから次の時代を担う大きな市場であるインドには勝ち組として残ることは企業として使命であります。ご承知の通り、フォルクスワーゲンはアウディ、ランボルギーニ、ベントレーを傘下に収めると共にポルシェも子会社化して自動車ブランドのデパートと化しています。
スズキはインド市場で長年の努力が実り、圧倒的強みを見せていることからフォルックスワーゲンとしては相対的規模の小さいスズキの株式取得を通じて支配下に置き、フォックスワーゲンの一ラインアップとするつもりでした。
が、鈴木会長は最近、日産自動車のゴーン会長がロシアのアフトワズや中国の東風汽車との提携により業績に実を結ぶ効果があったことと自社のフォルックスワーゲンとの提携を比較し、無意味、無効果な提携を悔いている発言がありました。鈴木会長はたたき上げの商店主であるのですからそう簡単に自分の築き上げたブランドを他人にほいほい渡すわけにはいかないという強い気持ちのあらわれでしょう。もともと2009年に提携関係に入ったときは自社のキャパシティを考えながら「自分の描く提携」を模索したのだろうと思います。
海外の会社と手を結ぶというのは実に大変で相手の能力をどう引き出すか、その手腕はトップの国際人としてのセンスにかかっています。例えば僕が以前勤めた会社で買収したアメリカの某ホテルがいかにコントロールするのに苦労したか、じかに感じているのでわかります。
あの時はアメリカ人は買収した日本の親会社をなめてかかっていたと思います。そして、それに戦いを挑めたのはトップを含めたごくわずかの人だけでした。つまり、日本側数人で社員何千人もいる相手を経営的に唸らせるのは腰掛程度では絶対に無理だったということを僕なりに実感させてもらいました。特に日本人とアメリカ人の間にコミュニケーションのみならず、考え方のギャップがあり、それが埋め尽くせなかった、という感じがします。
一方、日産ゴーン会長はもとからブラジル系フランス人であるが故に欧米社会にナチュラルに入り込めるし、相手方も受け入れるというアドバンテージがあります。これは残念ながら否定できない事実です。
唯一、僕がこれぞ立派な日本企業による買収と思ったのがブリジストンのファイアストン買収。これはある意味、経営的にも苦しかったファイアストンをブリジストンの社長がたしか年の三分の二ぐらいをアメリカ、ファイアストン社の本社に駐在し、日米の真の意味での合体を遂げたケースです。トップが乗り込んでいき、直に指揮を執るぐらいでないと欧米の会社を自分の都合よくコントロールするのは難しいという良い例かと思います。
スズキ自動車のケースは日本の外国会社との提携の難しさを改めて見せ付けたような気がします。これを糧に日本企業は大いに学んでもらいたいと思います。
今日はこのぐらいにしておきましょう。













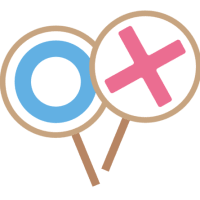






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます