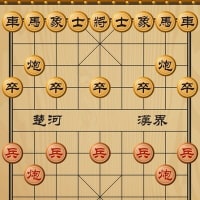「第3回アジアインドアゲームズ」は、10月30日~11月8日、ベトナムのハノイを中心に開催されますが、この大会に日本オリンピック委員会(JOC)から派遣されるシャンチー(中国象棋)の日本代表選手が、「派遣前ドーピング検査」を受けました。
この派遣前ドーピング検査はJOCがこの大会に出場する選手に義務付けているもので、検査を受けたのは派遣が内定している所司和晴、曽根敏彦、秋吉一功の3選手。日本のシャンチーの歴史において、JOCの派遣で国際大会に選手を送り出すのは初めてのことであり、シャンチーのプレーヤーがドーピング検査を受けるのも初めてのことです。
ドーピングとは「競技能力を高めるために薬物などを不正に使用すること」とされており、スポーツの世界においてドーピングが禁止されていることは周知のとおりです。ドーピングが禁止される理由として、「スポーツ固有の価値を損なう」、「不誠実(アンフェア)」、「社会悪である」、「競技者自身の健康を害する」の4つが挙げられています。(財団法人アンチドーピング機構ホームページ「アンチ・ドーピングQ&A」より)
http://www.anti-doping.or.jp/qa/index.html
ドーピングがシャンチーなどのマインドスポーツに対してどのように競技能力を高める効果があるのか議論のあるところでしょうが、私たちが長年にわたって「シャンチーはスポーツである」と主張し(中国ではもちろんシャンチー、チェス、囲碁はスポーツです)、シャンチーが健全なスポーツとして日本社会に定着することを目指している以上、スポーツの価値を高めるために、スポーツ一般に適用されるルールを遵守することは当然のことです。
その意味で、シャンチーの選手がドーピング検査を受けることは、シャンチーが紛れもなくスポーツであるとJOCから認定されたことの証でもあり、私たちシャンチー愛好者にとって慶賀すべきことだといえるでしょう。
検査は、国立スポーツ科学センター(北区西ヶ丘)内にある「財団法人アンチ・ドーピング機構(JADA)」で実施されました。日本シャンチー協会では、検査前に事務局長がJADAに出向いて、実施方法、注意事項について事前説明を受けました。その中で「(JADAでは)選手をその競技のトップアスリートとして敬意を持って扱いますので安心して受けてください」、「選手がクリーンであることを証明する機会だと考えてください」という言葉が特に印象的でした。
検査場所は、待合室、検査室、採尿室と3つがつながっており、検査室までは競技団体の同伴者が立ち会うことができます。採尿室は選手と検査員だけが入ることができます。採尿用カップやサンプルキットは複数用意された中から選手自身が選択するようになっていたり、カップやキットに開封された痕跡や破損がないか確認を求められたり、あらゆる段階で(検査する側も含めて)不正が行われないように厳格に実施されていることがよく分かりました。時間は一人約20~30分でした。
今回の検査は「競技会外検査」と呼ばれるものですが、実際の競技会においては、ルール上は「いつでも、誰に対しても」行われる可能性があるということです。この日の検査は、日本のシャンチー界にとって貴重な体験でした。日本のシャンチーのプレーヤーがドーピング検査を受けるまでになったかと思うと(繰り返しになりますがそれはシャンチーがスポーツとして認定を受けたことの証です)感慨深い一日でした。
この派遣前ドーピング検査はJOCがこの大会に出場する選手に義務付けているもので、検査を受けたのは派遣が内定している所司和晴、曽根敏彦、秋吉一功の3選手。日本のシャンチーの歴史において、JOCの派遣で国際大会に選手を送り出すのは初めてのことであり、シャンチーのプレーヤーがドーピング検査を受けるのも初めてのことです。
ドーピングとは「競技能力を高めるために薬物などを不正に使用すること」とされており、スポーツの世界においてドーピングが禁止されていることは周知のとおりです。ドーピングが禁止される理由として、「スポーツ固有の価値を損なう」、「不誠実(アンフェア)」、「社会悪である」、「競技者自身の健康を害する」の4つが挙げられています。(財団法人アンチドーピング機構ホームページ「アンチ・ドーピングQ&A」より)
http://www.anti-doping.or.jp/qa/index.html
ドーピングがシャンチーなどのマインドスポーツに対してどのように競技能力を高める効果があるのか議論のあるところでしょうが、私たちが長年にわたって「シャンチーはスポーツである」と主張し(中国ではもちろんシャンチー、チェス、囲碁はスポーツです)、シャンチーが健全なスポーツとして日本社会に定着することを目指している以上、スポーツの価値を高めるために、スポーツ一般に適用されるルールを遵守することは当然のことです。
その意味で、シャンチーの選手がドーピング検査を受けることは、シャンチーが紛れもなくスポーツであるとJOCから認定されたことの証でもあり、私たちシャンチー愛好者にとって慶賀すべきことだといえるでしょう。
検査は、国立スポーツ科学センター(北区西ヶ丘)内にある「財団法人アンチ・ドーピング機構(JADA)」で実施されました。日本シャンチー協会では、検査前に事務局長がJADAに出向いて、実施方法、注意事項について事前説明を受けました。その中で「(JADAでは)選手をその競技のトップアスリートとして敬意を持って扱いますので安心して受けてください」、「選手がクリーンであることを証明する機会だと考えてください」という言葉が特に印象的でした。
検査場所は、待合室、検査室、採尿室と3つがつながっており、検査室までは競技団体の同伴者が立ち会うことができます。採尿室は選手と検査員だけが入ることができます。採尿用カップやサンプルキットは複数用意された中から選手自身が選択するようになっていたり、カップやキットに開封された痕跡や破損がないか確認を求められたり、あらゆる段階で(検査する側も含めて)不正が行われないように厳格に実施されていることがよく分かりました。時間は一人約20~30分でした。
今回の検査は「競技会外検査」と呼ばれるものですが、実際の競技会においては、ルール上は「いつでも、誰に対しても」行われる可能性があるということです。この日の検査は、日本のシャンチー界にとって貴重な体験でした。日本のシャンチーのプレーヤーがドーピング検査を受けるまでになったかと思うと(繰り返しになりますがそれはシャンチーがスポーツとして認定を受けたことの証です)感慨深い一日でした。