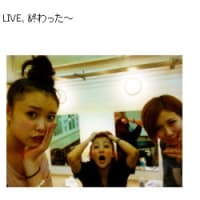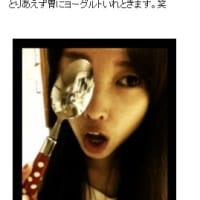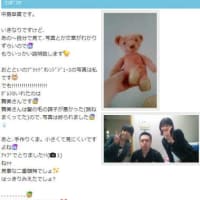誤算続き…「空港外資規制」先送り 国交省甘い見通し(産経新聞) - goo ニュース
空港外資規制は「外為法改正」で対応するのが国際ルール(ダイアモンド・オンライン)
上場の意味が問われる「空港外資規制」 見送りは賢明な判断(ダイアモンド・オンライン)
空港会社の外資規制見送りは当然だ(日本経済新聞)
島国である日本では、相当数の割合の外国人は、空港を通って日本にやってきます。成田空港にしろ、
関西空港にしろ、世界に開かれている空港です。
しかし、いざ投資対象として空港ビルの会社へ投資しようとした場合、外国人は入国拒否されかねない
状況にありました。それが「空港外資規制」と呼ばれる問題です。もともとは、羽田空港のビルを所有する
「日本空港ビル」の筆頭株主が、オーストラリアの投資銀行で、主に公共部門への投資に実績を持っている
マッコーリー・グループになったことが発端です。この状況を見た国土交通省は、「安全保障上の問題」を
盾にして、あれやこれやと外資規制を導入しようとしました。これが海外投資家が東証から手を引きつつ
状況下にあって、一部閣僚から「日本の市場が閉鎖的に見られてしまう」という理由で反対、「内閣不一致」と
呼ばれる状況になりました。
外資が大株主になったから、それに対して対抗策を出す、この構図はどこかで見たものです。そう、それは
昨年の上半期に話題になったスティール・パートナーズの問題と似ているように思えてきます。言ってしまえば、
「後出しじゃんけん」でこの場を凌ごうという魂胆が見えてくるのです。
スティールの場合には、企業は新株発行権などで対抗しましたが、今回、国土交通省が出してきた対抗策は、
「安全保障」です(自国の軍隊が2度も自国民が乗る罪のない漁船を沈めるような国が「安全保障」を
主張するのもどれだけ不毛なことか!)。海外の会社が、空港ビルを運営する会社を買収するのは
「安全保障」に関わる問題なんだそうです。そうであるならば、上場させるどころか、はじめから民営化せず、
国なり地方自治体が空港ビルの運営をすればいいだけです。何のために成田空港公団が民営化したのかが
わからなくなります。
日経新聞はこの問題が出て以降、頑なに反対を主張していましたが、その中のひとつに、「海外の」企業が
空港ビル会社を買収したら、安全保障の問題が出て、「日本の」企業が買収したら問題にならないという理論が
おかしいというものもありました。仮にそうした事態が発生しても、国土交通省は「日本の会社だから安心」という
理由だけで、何も動かなかったでしょう。しかしその企業が「安全保障」を脅かす存在だったらどうするのでしょうか。
「外資=ハゲタカ」という、もはや時代遅れにもなりかねない思考回路が霞ヶ関を支配しているようです。
結局、国土交通省がやろうとしたことは、サッポロやブルドックソースなどがやったことと本質的には同じことです
(サッポロやブルドックが防衛策を出したことと、それ自体が正しいことかどうか、あるいは株主総会がその提案を
可決したことは、個々の会社の問題だと考えています)。それを国家としてやろうとし、海外からの投資をさせまいと
していました。これも多くのところで書かれていることですが、今回マッコーリーが株を買った会社は「空港ビル」、
平たく言うのであれば「パルコ」のような会社であり、管制塔など本当に空の安全、もっというのであれば、
安全保障に関わる問題とは違います。
こんな調子で資本主義、市場経済を考えているようであれば、本当に欧米から来る飛行機は日本に着陸しない、
文字通りの「ジャパン・パッシング」になりかねません。

空港外資規制は「外為法改正」で対応するのが国際ルール(ダイアモンド・オンライン)
上場の意味が問われる「空港外資規制」 見送りは賢明な判断(ダイアモンド・オンライン)
空港会社の外資規制見送りは当然だ(日本経済新聞)
島国である日本では、相当数の割合の外国人は、空港を通って日本にやってきます。成田空港にしろ、
関西空港にしろ、世界に開かれている空港です。
しかし、いざ投資対象として空港ビルの会社へ投資しようとした場合、外国人は入国拒否されかねない
状況にありました。それが「空港外資規制」と呼ばれる問題です。もともとは、羽田空港のビルを所有する
「日本空港ビル」の筆頭株主が、オーストラリアの投資銀行で、主に公共部門への投資に実績を持っている
マッコーリー・グループになったことが発端です。この状況を見た国土交通省は、「安全保障上の問題」を
盾にして、あれやこれやと外資規制を導入しようとしました。これが海外投資家が東証から手を引きつつ
状況下にあって、一部閣僚から「日本の市場が閉鎖的に見られてしまう」という理由で反対、「内閣不一致」と
呼ばれる状況になりました。
外資が大株主になったから、それに対して対抗策を出す、この構図はどこかで見たものです。そう、それは
昨年の上半期に話題になったスティール・パートナーズの問題と似ているように思えてきます。言ってしまえば、
「後出しじゃんけん」でこの場を凌ごうという魂胆が見えてくるのです。
スティールの場合には、企業は新株発行権などで対抗しましたが、今回、国土交通省が出してきた対抗策は、
「安全保障」です(自国の軍隊が2度も自国民が乗る罪のない漁船を沈めるような国が「安全保障」を
主張するのもどれだけ不毛なことか!)。海外の会社が、空港ビルを運営する会社を買収するのは
「安全保障」に関わる問題なんだそうです。そうであるならば、上場させるどころか、はじめから民営化せず、
国なり地方自治体が空港ビルの運営をすればいいだけです。何のために成田空港公団が民営化したのかが
わからなくなります。
日経新聞はこの問題が出て以降、頑なに反対を主張していましたが、その中のひとつに、「海外の」企業が
空港ビル会社を買収したら、安全保障の問題が出て、「日本の」企業が買収したら問題にならないという理論が
おかしいというものもありました。仮にそうした事態が発生しても、国土交通省は「日本の会社だから安心」という
理由だけで、何も動かなかったでしょう。しかしその企業が「安全保障」を脅かす存在だったらどうするのでしょうか。
「外資=ハゲタカ」という、もはや時代遅れにもなりかねない思考回路が霞ヶ関を支配しているようです。
結局、国土交通省がやろうとしたことは、サッポロやブルドックソースなどがやったことと本質的には同じことです
(サッポロやブルドックが防衛策を出したことと、それ自体が正しいことかどうか、あるいは株主総会がその提案を
可決したことは、個々の会社の問題だと考えています)。それを国家としてやろうとし、海外からの投資をさせまいと
していました。これも多くのところで書かれていることですが、今回マッコーリーが株を買った会社は「空港ビル」、
平たく言うのであれば「パルコ」のような会社であり、管制塔など本当に空の安全、もっというのであれば、
安全保障に関わる問題とは違います。
こんな調子で資本主義、市場経済を考えているようであれば、本当に欧米から来る飛行機は日本に着陸しない、
文字通りの「ジャパン・パッシング」になりかねません。










![[短評]感謝の念](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/46/52/7102007b8dd5e319bdf1a8751a29f717.jpg)