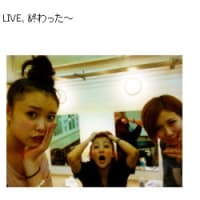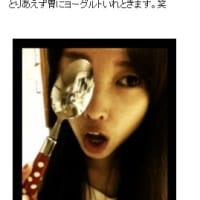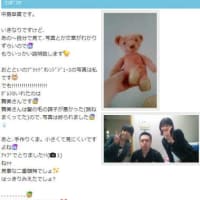その1から続く;
宍道からディーゼルカーで木次線に乗ると、すぐに中国山地らしい風景の中を走ります。前線通じて18個しか
駅はないけど、数少ない直通列車に乗ると2時間半以上かかります。これでもかつては急行が走っていたのですが。
列車の中では子供たちが走り回り、外ではのどかな光景が広がる中、列車はどんどんと山奥へと向かいます。
宍道を出発してから1時間ほどで「亀嵩(かめだけ)」に到着。松本清張の砂の器で出た駅として非常に有名ですが、
同時に駅舎が蕎麦屋になっていることでも有名です。本当ならばここの「そば弁当」を食べたかったのですが、
電話が繋がらなかったため諦めました。列車からはそばを食べている人がこっちを見ています。
そういえば、この駅に近づいたときに列車が急停止しました。熊が出たのかと思ったら近所のおばあちゃんでした。
こんなところで人身事故により遅延なんかになったらそれはもう大変。
「亀嵩」の次が「出雲横田」。この沿線では1・2を争う大きな駅です。ここで後ろに繋がれていた回送車両は切り離し。
この駅では10分近く停車するので、駅の外にちょっとだけ出てみました。立派な構えの駅!ここからが木次線の
クライマックスです。同時に、「出雲横田」の次「八川」から終点まで完成させるのがどれだけ大変だったか
(というようなことを小学生を連れた先生が話していた)がわかるところです。
食料を買い付けて列車に戻り、いよいよ勾配越えに挑戦。これがあったために、この部分が開通して、木次線が全線
開通するまで20年も掛かったわけです。そんなことも考えず、出雲そばを食べるとお餅を食べる自分。中間地点の
折り返すところに列車が止まり、運転士が移動して、さらに山登りをします。そうすると、眼下にさっき止まった
出雲坂根駅が見えます。ディーゼル音をうならせながら、稜線沿いに作ったのであろうカーブをトンネルを抜けながら
走っていきます。
やっと上りきろうとしたところに、今度は奥出雲おろちループが現れます。これは国道のループ橋なのですがすごく圧巻!!
木々しかない山の中にこれほどまでの完璧すぎる人工物ができるのか!!というものです。これは車で走ってみたい
感情にさせてくれます。逆に、このループ橋ができたために、こんなスイッチバックを繰り返してまで走る木次線の
不要論も出てきてしまうのですが、どちらも建設当時の英知を絞り、いくつもの苦労を重ねて造ったものと言えるでしょう。
このループ橋を過ぎたあたりが分水嶺になっているので、ここから先は一気に下っていきます。そして終点の備後落合に
到着・・・したのですが、この駅がまたすごいというか、降りると言葉が出ないくらいの山間部にある駅です。この駅は、
芸備線と木次線の接続駅ですが、駅以外には何もないんじゃないかというくらいのところに駅だけがあるのです。
こんな山の中にある駅なので、大雪で木次線が運休したり、今でも芸備線のこの駅から広島へ向かう方面が豪雨で運休したりと、
数々の不便も強いられてしまいます。
後で知ったのですがそんな秘境の無人駅にノートが置いてあって、訪問者がいろいろと書き込んでいくようです。
しかし乗換の時間がわずかしかないのでそちらはパスしました。
たぶんその3に続く
宍道からディーゼルカーで木次線に乗ると、すぐに中国山地らしい風景の中を走ります。前線通じて18個しか
駅はないけど、数少ない直通列車に乗ると2時間半以上かかります。これでもかつては急行が走っていたのですが。
列車の中では子供たちが走り回り、外ではのどかな光景が広がる中、列車はどんどんと山奥へと向かいます。
宍道を出発してから1時間ほどで「亀嵩(かめだけ)」に到着。松本清張の砂の器で出た駅として非常に有名ですが、
同時に駅舎が蕎麦屋になっていることでも有名です。本当ならばここの「そば弁当」を食べたかったのですが、
電話が繋がらなかったため諦めました。列車からはそばを食べている人がこっちを見ています。
そういえば、この駅に近づいたときに列車が急停止しました。熊が出たのかと思ったら近所のおばあちゃんでした。
こんなところで人身事故により遅延なんかになったらそれはもう大変。
「亀嵩」の次が「出雲横田」。この沿線では1・2を争う大きな駅です。ここで後ろに繋がれていた回送車両は切り離し。
この駅では10分近く停車するので、駅の外にちょっとだけ出てみました。立派な構えの駅!ここからが木次線の
クライマックスです。同時に、「出雲横田」の次「八川」から終点まで完成させるのがどれだけ大変だったか
(というようなことを小学生を連れた先生が話していた)がわかるところです。
 | 「出雲坂根」に到着。ここから次の駅までの間に、木次線が存続しえる、 一方で廃止の理由にもなりえる三段スイッチバックがあります。つまり、 宍道から来た列車がこの駅で一回向きを変えて山を登り、途中でもう一度 向きを変えて(つまりこの時点で最初来たときと同じ向きになる)、 160メートルを上るのです。これこそが、電車ヲタを肥薩線のループ&スイッチバックと 同じくらいにこの路線を引き付け、存続しえる要因なのです。 その前に列車は休憩。この駅には「延命水」という有難い湧き水があるのですが、 それを飲み損ねました。でも駅の外にある売店でそば弁当とあんこ餅を購入。 やっと昼飯にありつけました。ちょうどとなりのホームにはトロッコ列車も止まっていました。 |
食料を買い付けて列車に戻り、いよいよ勾配越えに挑戦。これがあったために、この部分が開通して、木次線が全線
開通するまで20年も掛かったわけです。そんなことも考えず、出雲そばを食べるとお餅を食べる自分。中間地点の
折り返すところに列車が止まり、運転士が移動して、さらに山登りをします。そうすると、眼下にさっき止まった
出雲坂根駅が見えます。ディーゼル音をうならせながら、稜線沿いに作ったのであろうカーブをトンネルを抜けながら
走っていきます。
やっと上りきろうとしたところに、今度は奥出雲おろちループが現れます。これは国道のループ橋なのですがすごく圧巻!!
木々しかない山の中にこれほどまでの完璧すぎる人工物ができるのか!!というものです。これは車で走ってみたい
感情にさせてくれます。逆に、このループ橋ができたために、こんなスイッチバックを繰り返してまで走る木次線の
不要論も出てきてしまうのですが、どちらも建設当時の英知を絞り、いくつもの苦労を重ねて造ったものと言えるでしょう。
このループ橋を過ぎたあたりが分水嶺になっているので、ここから先は一気に下っていきます。そして終点の備後落合に
到着・・・したのですが、この駅がまたすごいというか、降りると言葉が出ないくらいの山間部にある駅です。この駅は、
芸備線と木次線の接続駅ですが、駅以外には何もないんじゃないかというくらいのところに駅だけがあるのです。
こんな山の中にある駅なので、大雪で木次線が運休したり、今でも芸備線のこの駅から広島へ向かう方面が豪雨で運休したりと、
数々の不便も強いられてしまいます。
後で知ったのですがそんな秘境の無人駅にノートが置いてあって、訪問者がいろいろと書き込んでいくようです。
しかし乗換の時間がわずかしかないのでそちらはパスしました。
たぶんその3に続く










![[短評]感謝の念](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/46/52/7102007b8dd5e319bdf1a8751a29f717.jpg)