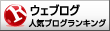遠目で見ると綺麗だが、見頃は過ぎ。
いつもはGW中に出かけていたので黄色い藤は少しの開花だったが、今回は満開かな?

黄色いトンネルも綺麗だった。
まだ黄色は年数がないのか完全に覆っていない。

白い藤のトンネルもまだ綺麗に見れる。
霞がかって見えて綺麗だった。

これは八重の藤
遠くから見るとブドウのようだ

通所の紫の藤は遠目ならまだ綺麗に見える。

しかしどこを見ても人人。。。。
うんざり。。。。

その後で、分福茶釜の茂林寺へ
境内には至る所に狸が


これが狸が化けた茶釜

茶釜の話は以下
「当山は分福茶釜の寺として知られております。寺伝によると、開山大林正通に従って、伊香保から館林に来た守鶴は、代々の住職に仕えました。
元亀元年(1570)、七世月舟正初の代に茂林寺で千人法会が催された際、大勢の来客を賄う湯釜が必要となりました。その時、守鶴は一夜のうちに、どこからか一つの茶釜を持ってきて、茶堂に備えました。ところが、この茶釜は不思議なことにいくら湯を汲んでも尽きることがありませんでした。守鶴は、自らこの茶釜を、福を分け与える「紫金銅分福茶釜」と名付け、この茶釜の湯で喉を潤す者は、開運出世・寿命長久等、八つの功徳に授かると言いました。
その後、守鶴は十世天南正青の代に、熟睡していて手足に毛が生え、尾が付いた狢(狸の説もある)の正体を現わしてしまいます。これ以上、当寺にはいられないと悟った守鶴は、名残を惜しみ、人々に源平屋島の合戦と釈迦の説法の二場面を再現して見せます。
人々が感涙にむせぶ中、守鶴は狢の姿となり、飛び去りました。時は天正十五年(一五八七)二月二十八日。守鵜が開山大林正通と小庵を結んでから百六十一年の月日が経っていました。
後にこの寺伝は、明治・大正期の作家、巌谷小波氏によってお伽噺「文福茶釜」として出版され、茶釜から顔や手足を出して綱渡りする狸の姿が、広く世に知られる事になりました。」
※茂林寺HPより
これが元になって童話になったようだ。
裏には県指定天然記念物の茂林寺沼低地湿原があるが結構広い。
風が気持ちよかった

そのまま近くにある「館林野鳥の森フラワーガーデン」
芝桜が綺麗なようだけどすでに終わっていた。
奥にはネモフィラが満開

ここはまだ出来て4年なのかな?エントランスを今作っていたり。まだまだ整備の途中って感じだった
来年は芝桜の時期に行ってみよう。