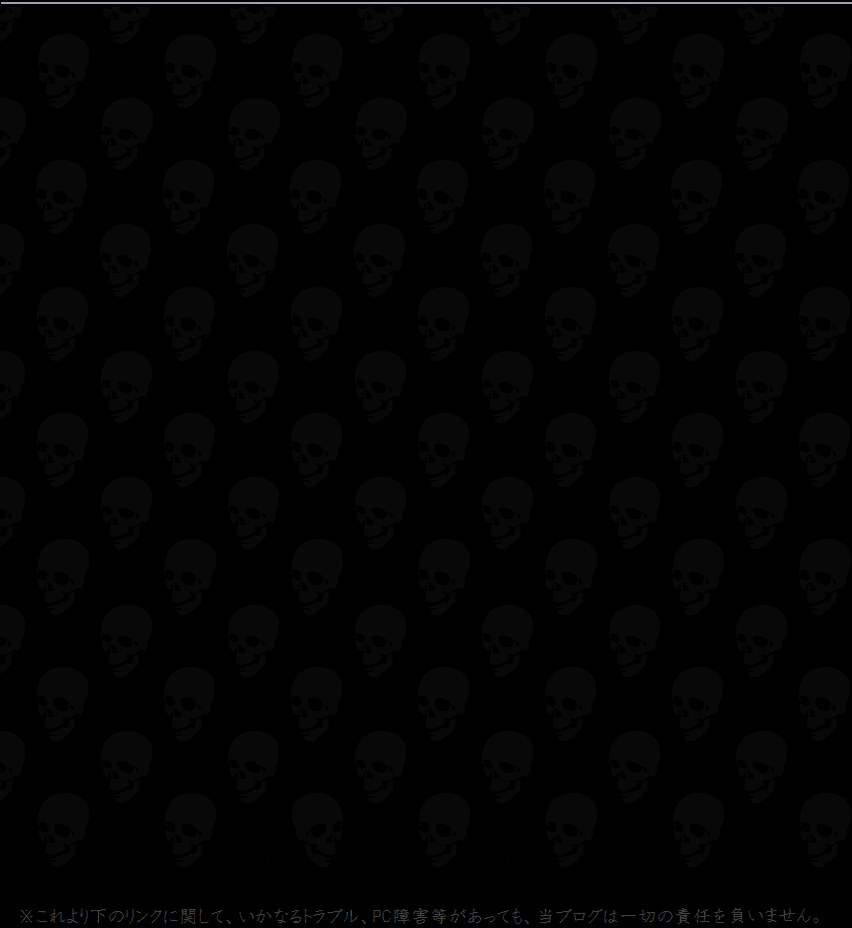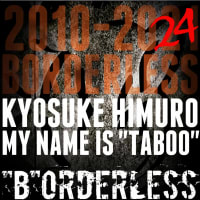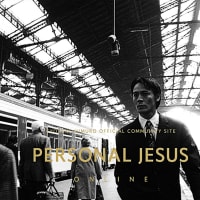「あれからもう1年か・・・、いや、まだ1年かな。」
どこかで聞いたそんなセリフだが、
あの周南での氷室京介の衝撃の発言から1年が経った。
俺がそれを知ったのは、氷室の情報のみを粛々と更新する、
一切の癖を持たない氷室ファンの方のブログ。
いつものように新着情報を期待して開いてみると、
目に飛び込んで来たのは「訃報」を感じるような活字の数々だった。
そのいきなりの話に、
「なんで今なんだ?」と戸惑った記憶があるが、
それは俺達にその兆候の一切を感じさせなかったという、
氷室京介のプロフェッショナル魂がそう魅せていたのだろう。
しばらくして、「終わったな・・・」と、人生の一つの節目を感じて、
その空虚な気持は、涙という形さえも許さない程、
俺を「何も無し」の真っ白な状態にさせた。
それ以降は、ひたすら氷室の曲だけを聴いていた記憶があるけれど、
涙を流して、、声を出して泣いたのは、
それから数日後のことだった。
http://blog.goo.ne.jp/midnight_xxx/e/ba9ba70ffa43f07a144ed9afe81cf101
今月、20日の日にWOWOW氷室京介スペシャルでもOAされるが、
KING SWING No.55の会報では、更に詳しくその経緯や思い等が語られていて、
そこには、様々な氷室京介の姿が垣間見えている。
ちょっと話の本筋とは離れるけれど、
氷室のその覚悟を事前に伝えられていたのは、
御存じ、TAMA氏こと、氷室の奥様と、
代官山PJカフェの店長だったマネージャーと、
そして、、
BOØWY時代からの氷室の仲間で、
今も氷室の事務所のスタッフとして一緒に仕事をしている、ゾンビ鈴木氏だけだった。
先日、たまたまBOØWY関係の本を読んでいたら、
その、ゾンビ氏と氷室との馴れ初めが書かれていることに気付く。
時は1983年。
BOØWYがユイ音楽工房と契約する直前の、まだブレイクする前の話である。
以下、『B-PASS SPECIAL EDITION BOØWY』より抜粋。
この年(1983年)、奇妙な少年が彼らの旅に加わった。
地方に向かうおんぼろハイエースの運転席に座っていたのは、
まだ19才のゾンビ鈴木少年だった。
彼は高校2年のときからBOØWYのライヴに通いつづけていた。
友人に聴かせてもらった『モラル』の感激は、
それまで聴いていたARBやモッズ以上のものがあった。
ライヴが終わってもじっと待っていると、メンバーが楽器を運び出してくる。
「手伝わしてください」と言うのに最初は勇気がいったが、
二度目からはずいぶんラクになった。
メンバーと言葉を交わす。楽器運びを手伝う。
それだけで自分も少しかっこよくなったような気分になった。
初めて楽屋に入ったときに氷室に、
「おまえゾンビみたいだなあ」と言われて以来、
彼はゾンビ鈴木といわれている。
ボロボロに破いた服と逆立てた髪がマズかったかなと思ったが、
アダナそのものは気に入った。
やがて高校を卒業すると、仲間は、就職したり家業をついだりする。
しかし彼は今までの生活を止めたくなかった。
アルバイトをしながらBOØWYのチケットを買い、楽器運びを手伝っていた。
いっしょに仕事をやっているだけでかっこいいという気持ちで彼は、
そのあともずっとBOØWYについていくことになる。
(略)
1984年。
ユイ音楽工房とBOØWYとの正式契約は、東北ライヴから帰ってきて数日後のことだった。
氷室たちの心の中は、疑心と期待が交差していた。
ただ、この一年間で自分たちの考えていることは言ってきたし、
あとはやってみるしかないと思っていた。
もしかするとこれが最後の賭けになるのかもしれない。
ただひとつ。
ゾンビとワンワン(関口)もスタッフとして迎え入れてほしいと付け加えるのだけは忘れなかった。
文■中川隆夫氏
そして今も氷室京介と共に仕事をしている、ゾンビ氏。
そして、そのゾンビ氏には伝えていた、氷室京介の決意。
周南前に聞いた氷室の覚悟に、ゾンビ氏は何を思ったのだろうか。
或いは、走馬灯のように駆け巡ったかもしれぬ、
ブレイク前のBOØWY時代からの氷室との記憶は、
ゾンビ氏にとってもまた、人生の節目と、
俺達以上の大きな空虚の心を持たせたことだろう。
そう、
氷室京介という人が、
今も尚、あの頃の仲間を律儀に思うという、
その情の厚さに触れつづけていたゾンビ鈴木氏だからこそ分かる虚しさが、
きっと彼を支配していたのではないだろうか。