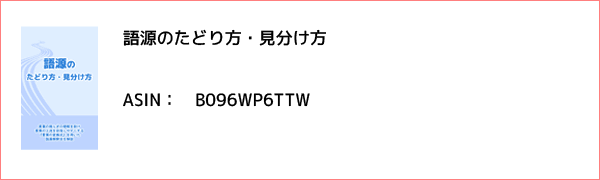ここまでの研究からのとりあえずのまとめなので
そのうち結論が変わる可能性はあります。
これまでの言葉の研究によると、
どうも古代人は、『だらっ』と『たれる』もの、
『だ』らっと『た』れるものを『t』音であらわしたようです。
傷口からたらっとたれる『チ(血)』。
木や天井からたらっとたれる『チ(蛇)』。
そして、体からだらっとたれる『テ(手)』。
この『テ』に、経年で区別をつけたくなって現れたのが、
上の手で『う 手』。『うで』となる言葉です。
下の手は『ご 手』。『ごて』となる言葉です。
この『ごて』がいっぱいあると、『百ごて』、『むごて』の
『百手(むかで)』という言葉が生まれるのだと思います。
足をあらわす『ごて』は子音では『g t』。
言葉において母音は揺らぐものですから、
すこし揺らしてみると『geto』。『げと』。
『t』音は『s』音や『k』音と混じりやすいので
これを考えると……出てくるのは『げそ』。
イカのゲソや、刑事ドラマの『ゲソ痕跡』は、
『足(ごて)』の揺らぎ発音であると考えられるのです。
足につける『下足(げそく)』も『具足(ぐそく)』も、
おそらくは『ゴテ』→『ゲソ』となった『足』から来ていて、
本来は『下足(げそ)』や『具足(グソ)』で
あったものなのでしょう。
言葉の音が変わるわけがない、意味がわからないというのであれば
参考文献はこれを。
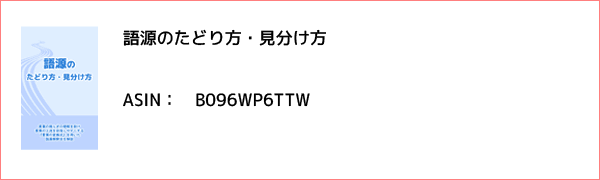
そのうち結論が変わる可能性はあります。
これまでの言葉の研究によると、
どうも古代人は、『だらっ』と『たれる』もの、
『だ』らっと『た』れるものを『t』音であらわしたようです。
傷口からたらっとたれる『チ(血)』。
木や天井からたらっとたれる『チ(蛇)』。
そして、体からだらっとたれる『テ(手)』。
この『テ』に、経年で区別をつけたくなって現れたのが、
上の手で『う 手』。『うで』となる言葉です。
下の手は『ご 手』。『ごて』となる言葉です。
この『ごて』がいっぱいあると、『百ごて』、『むごて』の
『百手(むかで)』という言葉が生まれるのだと思います。
足をあらわす『ごて』は子音では『g t』。
言葉において母音は揺らぐものですから、
すこし揺らしてみると『geto』。『げと』。
『t』音は『s』音や『k』音と混じりやすいので
これを考えると……出てくるのは『げそ』。
イカのゲソや、刑事ドラマの『ゲソ痕跡』は、
『足(ごて)』の揺らぎ発音であると考えられるのです。
足につける『下足(げそく)』も『具足(ぐそく)』も、
おそらくは『ゴテ』→『ゲソ』となった『足』から来ていて、
本来は『下足(げそ)』や『具足(グソ)』で
あったものなのでしょう。
言葉の音が変わるわけがない、意味がわからないというのであれば
参考文献はこれを。