・・・・・新生児の、酵素系、消化器系統、免疫系、体温の調節機能など、どれも、いちじるしく不安定だ。免疫系の十分な発達には約一年を必要とし、また骨の発達も、類人猿の新生児と同程度になるのに約一年はかかる。生後六か月間は、最低限の成長しかとげていない状態がつづき、こどもが立ち上がろうとする生後七~八ヵ月目に、ようやく成長が早くなる。新生児の全身のプロポーションは、まさに胎児のときのままであり、生後一年目の終わりごろになって、ようやく体の比率が変わる。そして幼児が、小型の大人のようになる。これと対照的なのが類人猿の新生児で、頭骨と顔面の成長を除けば、彼らの新生児はもうほとんど大人に似ている。
脳の成長は別として、人ほど成長の遅い哺乳類はいない。生後、成長にこれほど時間がかかり、これほど長い諸発達段階をもつものはいない。人と類人猿とを比べれば、幼児期、小児期、思春期、熟年、老年といった各発達段階が、いずれも人では大幅に延長されている。ただし、妊娠期間は一つの例外だ。大型類人猿の妊娠期間は、平均して二~三週間の違いはあるが、いずれにしても人とほとんど変わらない。
霊長類の進化において、妊娠期間は、他の発達期間が延長されれば同様に延長される、という一般的な傾向がある。そこで、人では、妊娠期間以外のすべての発達段階が類人猿よりずっと延長されているわけだから、それに伴って妊娠期間も延長されているだろうと考えたくなる。しかし、事実はそうなっていない。くわえて、人の幼児の生まれたときの未熟な状態を考えれば、人は、早産で生まれていて、本当はもう一年やそこら子宮内で過ごすべきだったとさえ考えざるをえない。
・・・・・人の長い幼年期は、結局、胎児が未熟なまま生まれてしまうことを、一部うめあわせているのだと見ることができる。胎児と母体の安全にとって、ひいては人類という種が生き残るためには、その時期に生まれてしまわなければならない。人類進化の初期、森林から開けた平野に生きる場所を移すことで新奇な挑戦を受け、それらの適応の過程で、道具製作や食物採集狩猟、そして、それにともなう直立二足歩行と関連して、脳が肥大するいっぽう、骨盤の出口については、それほど適応的ではなくなった。
急速な脳の成長とともに頭が大きくなり、くわえて直立姿勢の結果、女性の骨盤は、ある種の変化を起こし、分娩がかなり長引くことになった。なぜなら、骨盤が幅広くなるいっぽうで、弯曲した骨盤をつくりだした。このため、胎児の頭は、骨盤の両側につきだした棘(坐骨棘)の間を通過しなければならなくなった。出産時での困難は、ここで生じる。胎児の頭は正しい角度で前方に曲がり、膣の軸に沿って進まなければならない。
これと対象的なのが霊長類の胎児で、彼らはもっと楽に通過することができる。というのは、骨盤が弯曲していないからだ。類人猿のより小さな頭は、骨盤がゆるむこともてつだって、坐骨棘の間というよりはむしろ後方を、簡単に通過することができる。
人の幼児が無力であり、また類人猿と比べて約一年ほども未熟に生まれるという事実は、人類の社会の進化に対し、人類の形態に対するのと同じく、決定的な影響を与えてきた。類人猿では、幼児の世話をし、食物を与えるのは、もっぱら母親の方だ。
ところで、人の女性においては、周期的な発情周期は、月経の周期にとって代わられ、女性は、継続して性的に受け入れが可能となった。その結果、ウェストン・ラバーがいうように『男は家に帰り、そして、留まる』。ほかの霊長類の雌たちでは、発情周期によって、性行動は短期間の繰り返しにとどまっている。しかし、女性は、そのような生理的例隷従からカイホウサレ、同時に、男にとって女は常時『入手可能』となった。そしてそのことが一夫一婦制の起源となった。ひらけた平原に生きる場所を求めた人類にとって、この新しい『家族単位』は、自然選択上、かなり有利にはたらいてきただろう。(いまのところも・・・・・。)
というのは、この『母』と『父』からなる安定した社会単位は、それぞれのやり方で、こどもの生存と発達に寄与しながら、長期間、こどもの世話をおこなうからだ。こどもを育てる間に、世代の重複がある。そして、世代間の密接なかかわりによって、こどもが、彼らの文化へ社会的に参加することを可能にしている。
・・・・・幼形成熟・『ネオテニー』より

















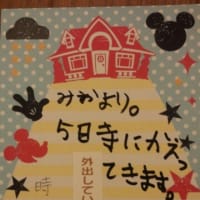


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます