
長い間、更新もせず、訪れて下さっていた皆さんには不義理をしてしまいました。
今朝から活動を再開します。
今回は、高野山のレヴューを。
高野山、それは四国の人間にとっては心の中にしっかりと根付いた存在といえるでしょう。
なぜなら、四国遍路八十八ヶ所の始まりとも終わりともいうべき場所が高野山なのですから。
高野山の縁起は、弘仁七年(816年)の嵯峨天皇の勅許のもと、弘法大師が高野の地に修禅の一院を建立したことに始まります。
以来1200年近く、真言密教の本山として続いています。
先日、ふと思い立ってこの高野山に行ってきました。
午前三時過ぎに眼が覚めて、始発の電車に乗って、午前十時過ぎには高野山の金剛峯寺前に立っていました。
我ながら、この行動力というか、思い切りの良さに驚きます。
金剛峯寺や大塔、苅萱堂、奥の院などを回りました。
さすが高野山、標高が高いためか、下界よりは涼しく、修禅にはもってこいの場所であろうと思いました。
今回の画像は、奥の院の一箇所で撮ったものです。
奥の院の大師御廟では、外陣に入ってありがたい読経を拝聴させていただきました。・・・が、外陣の天井にスピーカーがあって、そこから読経の声が聴こえて来るのには、なんだか興ざめしたものです。
総数五十を超える宿坊寺院を擁する高野山、さすがに一日では観きれるものではなく、いくつかの名所巡りのみとなってしまった今回の高野行き。
次回は、宿坊に泊まり、もっとじっくり観たいものです。
今朝から活動を再開します。
今回は、高野山のレヴューを。
高野山、それは四国の人間にとっては心の中にしっかりと根付いた存在といえるでしょう。
なぜなら、四国遍路八十八ヶ所の始まりとも終わりともいうべき場所が高野山なのですから。
高野山の縁起は、弘仁七年(816年)の嵯峨天皇の勅許のもと、弘法大師が高野の地に修禅の一院を建立したことに始まります。
以来1200年近く、真言密教の本山として続いています。
先日、ふと思い立ってこの高野山に行ってきました。
午前三時過ぎに眼が覚めて、始発の電車に乗って、午前十時過ぎには高野山の金剛峯寺前に立っていました。
我ながら、この行動力というか、思い切りの良さに驚きます。
金剛峯寺や大塔、苅萱堂、奥の院などを回りました。
さすが高野山、標高が高いためか、下界よりは涼しく、修禅にはもってこいの場所であろうと思いました。
今回の画像は、奥の院の一箇所で撮ったものです。
奥の院の大師御廟では、外陣に入ってありがたい読経を拝聴させていただきました。・・・が、外陣の天井にスピーカーがあって、そこから読経の声が聴こえて来るのには、なんだか興ざめしたものです。
総数五十を超える宿坊寺院を擁する高野山、さすがに一日では観きれるものではなく、いくつかの名所巡りのみとなってしまった今回の高野行き。
次回は、宿坊に泊まり、もっとじっくり観たいものです。










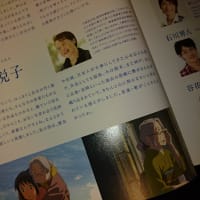
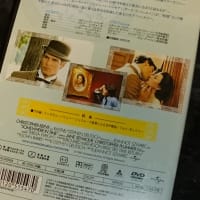

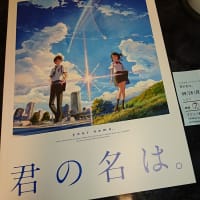






 Name; Melville
モットーは「Bygones!」
JAPAN辺境四国在住。
Name; Melville
モットーは「Bygones!」
JAPAN辺境四国在住。




