もう直ぐ、学生さんたちは卒業を迎えます。中学生や一部小学生は、受験というイヴェントが控えてはおりますが。その様なものは、さしたる難事ではありません。
しかし、高校生にとっては、事件が多発したと言えるでしょう。そう、未履修問題です。いまだ、尾を引いていますもの。
教職に携わっていた者として、言わせていただけば、「アレ」は、詰まるところ教育に中央が介入しすぎた結果、起きるべくして起きたことです。
そもそも、学校で何を教え、どのようなカリキュラムを組むかについては、中央から指導がある。
『学習要領』という、いわば聖典です。
神聖にして、侵すべからざる書。学校の行動についての『大原則』。それが学習要領。もちろん、他にも様々な要綱はございますが。
私も、授業の年間計画を組む際、先輩教師に「学習要領に則っていれば、万事OKですよ」とアドヴァイスをいただいた。
で、実際に組んだ。すると、あら不思議。削れるんですよ、時間が。
何コマか、余る。そして、さらに検討すると、もっとコマ数が削れる。
余ったコマは何に使うか? 私は、日野原重明さんの特集や、自然環境の悪化、生存圏縮小、人類の始祖といったNHK特集の理系映像教材を用意して、生徒達に見せて、調べものをさせたりしてレポート提出形式の授業に使いました。
自宅ではアニメしか見ないのでは困りますから、ね。
若い時分にこそ、さまざまなモノを見なければならないというのが、私の信条です。
さて、『余る時間』というのは、つまり『他に廻せる時間』ということでもある。
便法として、『Aという教科について使う時間を、Bという教科に廻せる、またはCという教科でも代用してよい』というのは、『ゆとり教育』が産まれた時に隠し玉として、学校にも与えられておりました。
正直、それを今更論議する教育界には、「アフォっちゃうか」と思います。
私は、親族には、「学校には何も期待せず、躾も学問も出来るだけ家庭やでやってくださいね」と言っております。それが、2004年のこと。2007年の現在でも、それが分かっていないご家庭が多いのは、不思議です。
話がズレましたが、私が言いたいのは、受験も大事なのですが、それと同じほどに、今この時間も大事なのだということ。
『学生さんたちは、残された学校生活を十二分に満喫してほしい』…ということ。
「一生付き合える友人は、高校で出来る」とか、「あの学校に行けば、もっと楽しい」とか、言われます。
しかし、幸せというものは、目の前にあっては気づき難いもの。
今の周りにいる、学校の友人。先生。授業。・・・あるいは、学び舎、それそのもの。
それは、二度とは手に入らぬものばかり。二度とは戻れぬ日々がいま、学生さんたちの前で通り過ぎているのです。
「過去や未来に、極度にかかづらうな。今を、よく生きよ」とは、ウィリアム・オスラーの言葉です。
そうなのです、未来に輝く希望を視るのも大事なのですが、今周りで輝いているものも多いのです。それを視るのも、大事なのです。
過ぎていく、消えていく、今の時間。
失ってから気づくのでは、もったいない。どうか、学生さんたちには、今の幸せな日々を充分にいとおしんでいただきたい。
そう、願うばかりです。










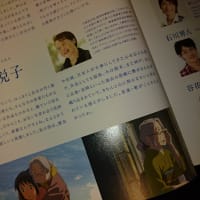
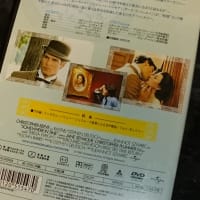

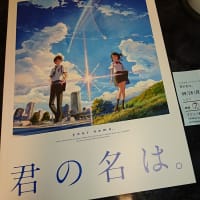






 Name; Melville
モットーは「Bygones!」
JAPAN辺境四国在住。
Name; Melville
モットーは「Bygones!」
JAPAN辺境四国在住。




