
テレビドキュメンタリーを中心に活躍し、ギャラクシー大賞を筆頭にさまざまな賞を獲得してきた久保田直がメガホンを取ったヒューマンドラマ。東日本大震災によって故郷を失ってしまった家族が、さまざまな試練を乗り越えながらも絆を強めていく姿を追い掛けていく。『マイ・バック・ページ』などの松山ケンイチ、『共喰い』などの田中裕子、『今日子と修一の場合』などの安藤サクラら、実力派が共演する。自然や家族を深く見つめたテーマ性に加えて、オールロケを敢行して捉えられた福島の緑あふれる風景も見もの。

<感想>物語の舞台は2011年3月11日に発生した東京電力福島第一原子力発電所の爆発事故で、まき散らされた放射能物質によって、強制退去に処せられた福島県の山村を舞台にしている。ロケーションには旧緊急時避難準備区域の川地村が選ばれ、俳優への綿密な方言指導によって、その土地に暮らしていたある家族の物語がリアルに描かれている。
園子温監督の「希望の国」では防護服に身を包み、みるみる数値の上がるガイガーカウンターに叫びながら20キロ圏内に向かう。「フタバから遠く離れて」では避難先の場所からの声が。
人が暮らしてきた町がある日、無人になる。その静かな恐ろしさを原発事故後、私たちは報道などの映像を通して目にしてきたのだが、人がいないだけで、家や自然はそのままである。そんな不思議で不条理で、絶望的ともいえる光景のなかに、防護服を着ることもなく土を耕す人がいるとしたら。

ここでは、コメという主題を全篇につらぬきながら、一つの大きな選択を選ぶ青年をフィクションの中に配置する。強制退去の処された放射線量の高い故郷の村に帰り、認知症を発生した母親と共に野を耕し、コメを作りながら緑のなかで生きると言うこと。その優しくはない選択は、松山ケンイチ演じる青年に託された。それがこの映画の表明であり、こんな生き方があってもいい、と映画は語ってくれる。

冒頭からしたたるような緑の樹木と田園風景が視界に広がってくる。この染み入るような新緑は、ラストまで「家路」という作品の大きなイメージとして目に焼き付く。その主人公の母親を演じた田中裕子の演技が自然でとてもいい。「共喰い」では戦争で手首を失い、義手を付けた手で魚をサバクたくましい母親を演じ、対照的に「はじまりのみち」では、脳卒中で倒れ身動きができない母親を演じた。その時息子の加瀬亮の背中におんぶした田中裕子、この作品の中でも松山ケンイチに背負われて、山の緑の中を歩くシーンが印象的でした。

狭い仮設住宅に住んでいる4人家族。土地を奪われ、生活の糧(農業)を奪われ、毎日狭い仮設住宅のトイレの前に座り込んでいる。長男の総一を演じた内野聖陽は、どこにもはけ口のない状態の苦しさというものを、本当に現地の人の苦しみを代弁するかのような役回りでした。
そんな夫の代わりに、妻の安藤サクラがデリヘリをして働いている。義母の田中裕子には、弁当屋で働いていると嘘をついているのだ。孫娘の世話をしている義母。
買い物から帰る田中裕子と孫娘、同じような仮設住宅が並ぶ光景に、立ちすくむシーンがある。意気消沈と困惑、今までの畑を耕し野菜を作り、コメを作る毎日だったのに。農作業もないこの生活に、よるべなさと狂気がないまぜとなり、いつしか田中裕子の表情にはボケという認知症が忍び寄ってくる。

放射能汚染の土地、国からの立ち入り禁止命令、自分の土地に足を踏み入れられない苛立ちを何処へぶつけたらいいのだろう。長男総一の同級生が、放射能汚染の自分の田んぼの土をトラックに積んで、捨てに行く途中で自殺をしてしまった。誰にも届かない心の叫びを感じ取る。

けれども中学の同級生、山中崇が松山ケンイチに告げるように、その選択はおそらく「ゆっくりと自殺するようなもの」なのであり、これからどのような健康被害が出るかは、今なお未知数なのである。人が避難して放置されるには、あまりにも美しい緑と共に、その選択を理想化することは、今福島で起きている現実と離れたところでこの映画を観ている人たちに、映画はそのことの重さと残酷に薄情に、あるいはセンセーショナルに、描いても過ぎることはなかったのだろう。そこには、故郷が帰れない場所になってしまった家族が選択した、ある再生の形が提示されている。
そこには生きる人々へと向けられた、あるいは放射性物質が降り注ぐ村の美しい緑へとカメラは向けられていく。フィクションの向こうに、実在する福島と、くつがえせない現実があるのだ。そのリアルさを求めようとすればするほど、けれども現実はするすると手の平からこぼれ落ちてゆく。
この作品から導かれた正直な感想は、そのようなものだった。悲しく厳しい現実に対して、フィクションとしてのドラマが向き合うには、まだまだ難しい状況がつづいている、そう感じざるを得ないと思った。
2014年劇場鑑賞作品・・・52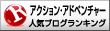 映画(アクション・アドベンチャー) ブログランキング
映画(アクション・アドベンチャー) ブログランキング

<感想>物語の舞台は2011年3月11日に発生した東京電力福島第一原子力発電所の爆発事故で、まき散らされた放射能物質によって、強制退去に処せられた福島県の山村を舞台にしている。ロケーションには旧緊急時避難準備区域の川地村が選ばれ、俳優への綿密な方言指導によって、その土地に暮らしていたある家族の物語がリアルに描かれている。
園子温監督の「希望の国」では防護服に身を包み、みるみる数値の上がるガイガーカウンターに叫びながら20キロ圏内に向かう。「フタバから遠く離れて」では避難先の場所からの声が。
人が暮らしてきた町がある日、無人になる。その静かな恐ろしさを原発事故後、私たちは報道などの映像を通して目にしてきたのだが、人がいないだけで、家や自然はそのままである。そんな不思議で不条理で、絶望的ともいえる光景のなかに、防護服を着ることもなく土を耕す人がいるとしたら。

ここでは、コメという主題を全篇につらぬきながら、一つの大きな選択を選ぶ青年をフィクションの中に配置する。強制退去の処された放射線量の高い故郷の村に帰り、認知症を発生した母親と共に野を耕し、コメを作りながら緑のなかで生きると言うこと。その優しくはない選択は、松山ケンイチ演じる青年に託された。それがこの映画の表明であり、こんな生き方があってもいい、と映画は語ってくれる。

冒頭からしたたるような緑の樹木と田園風景が視界に広がってくる。この染み入るような新緑は、ラストまで「家路」という作品の大きなイメージとして目に焼き付く。その主人公の母親を演じた田中裕子の演技が自然でとてもいい。「共喰い」では戦争で手首を失い、義手を付けた手で魚をサバクたくましい母親を演じ、対照的に「はじまりのみち」では、脳卒中で倒れ身動きができない母親を演じた。その時息子の加瀬亮の背中におんぶした田中裕子、この作品の中でも松山ケンイチに背負われて、山の緑の中を歩くシーンが印象的でした。

狭い仮設住宅に住んでいる4人家族。土地を奪われ、生活の糧(農業)を奪われ、毎日狭い仮設住宅のトイレの前に座り込んでいる。長男の総一を演じた内野聖陽は、どこにもはけ口のない状態の苦しさというものを、本当に現地の人の苦しみを代弁するかのような役回りでした。
そんな夫の代わりに、妻の安藤サクラがデリヘリをして働いている。義母の田中裕子には、弁当屋で働いていると嘘をついているのだ。孫娘の世話をしている義母。
買い物から帰る田中裕子と孫娘、同じような仮設住宅が並ぶ光景に、立ちすくむシーンがある。意気消沈と困惑、今までの畑を耕し野菜を作り、コメを作る毎日だったのに。農作業もないこの生活に、よるべなさと狂気がないまぜとなり、いつしか田中裕子の表情にはボケという認知症が忍び寄ってくる。

放射能汚染の土地、国からの立ち入り禁止命令、自分の土地に足を踏み入れられない苛立ちを何処へぶつけたらいいのだろう。長男総一の同級生が、放射能汚染の自分の田んぼの土をトラックに積んで、捨てに行く途中で自殺をしてしまった。誰にも届かない心の叫びを感じ取る。

けれども中学の同級生、山中崇が松山ケンイチに告げるように、その選択はおそらく「ゆっくりと自殺するようなもの」なのであり、これからどのような健康被害が出るかは、今なお未知数なのである。人が避難して放置されるには、あまりにも美しい緑と共に、その選択を理想化することは、今福島で起きている現実と離れたところでこの映画を観ている人たちに、映画はそのことの重さと残酷に薄情に、あるいはセンセーショナルに、描いても過ぎることはなかったのだろう。そこには、故郷が帰れない場所になってしまった家族が選択した、ある再生の形が提示されている。
そこには生きる人々へと向けられた、あるいは放射性物質が降り注ぐ村の美しい緑へとカメラは向けられていく。フィクションの向こうに、実在する福島と、くつがえせない現実があるのだ。そのリアルさを求めようとすればするほど、けれども現実はするすると手の平からこぼれ落ちてゆく。
この作品から導かれた正直な感想は、そのようなものだった。悲しく厳しい現実に対して、フィクションとしてのドラマが向き合うには、まだまだ難しい状況がつづいている、そう感じざるを得ないと思った。
2014年劇場鑑賞作品・・・52









