パリの高級アパルトマンで暮らす音楽家の老夫婦の姿を描いた『愛、アムール』。

監督・脚本は1942年生まれで70歳のミヒャエル・ハネケ。前作『白いリボン』に続き本作と2作品連続でカンヌ国際映画祭のパルムドール(最高賞)に輝く快挙を果たした。本作は米アカデミー賞やゴールデン・グローブ賞の外国語映画賞を受賞するなど数々の賞を受賞する話題作である。
妻を自宅で献身的に支える夫ジョルジュを演じたのは1930年生まれで82歳の「暗殺の森」のジャン=ルイ・トランティニャン。ハネケ監督はトランティニャンが演じることを前提に脚本を書いたという。「彼なしではこの映画を撮らなかった」と語るほどだ。妻アンヌを演じたのは1927年生まれで85歳の、「二十四時間の情事」のエマニュエル・リヴァ。米アカデミー賞では主演女優賞に史上最高齢でノミネートされた。
注意:内容がネタバレになっているのでご注意ください。

<感想>アカデミー賞の外国語映画賞を受賞した作品。パリ中心部に建つ重厚なアパルトマン。しかしその全景は最後まで映されることはない。部屋は決して広くもなく豪華でもないが、隅々まで主の神経が行き届いた美しい空間である。調度品の一つ一つも、本棚をびっしりと埋める本も、絶妙なあんばいで配置された数点のアンティークな壁の絵も、静かで落ち着いた部屋の空気に見事に溶け込んでいる。そして、主役のポジションを占めるのは一台の艶やかなピアノ。それは貴婦人のごとくに存在し、あたりを支配しているかのようである。
ここに住むジョルジュとアンヌ夫妻はともに音楽家だが、すでに80歳を超えて現役から退いている。
ピアノ教師だったアンヌの愛弟子である若手ピアニストの演奏会が開かれたシャンゼリゼ劇場に二人で出かけ、帰宅したところから物語はスタートする。二人とも演奏には満足した様子だが、その興奮に冷水をかけるようなことが起こった。重厚な玄関のカギ穴を誰かがこじ開けようとした形跡を見つける。怖くて死にそうという妻のアンヌに、せっかく気分のいい夜だから忘れようという夫。
そして画面は真っ暗になり、何故か長く感じるくらい続き観客が不安になる。やがてジョルジュの声がして二人がベッドで寝ていることが分かるのだが、ジョルジュはアンヌの異変に気づき「どうした」と声をかけるが、アンヌは「なんにも」と答える。そして悲劇の始まりとなる朝を迎える。この暗闇にさえぎられて、妻アンヌの様子が目に見えなかったので、どう解釈していいやら。

それにしても、ハネケといえば、人間の非情、邪悪、弱さを冷徹に観察する難解な監督として知られるけれど、これは、これまでとちょっと趣が違う。恐怖の描写はミヒャエル監督の得意とするところだが、本作での怖がらせ方は、ホラー映画顔負けのえげつなさすら感じさせる。プロローグでいきなり息絶えているアンヌの姿を見せることからして意表を突き過ぎという感じがしないでもないが、こういう手法が実は本作を巷にあふれる老老介護の残酷物語と一線を画すところなのだと分かってくる。つまり、状況を説明するものではなく、芸術的に描かれた感性の物語なのだと。

パリのアパートで穏やかな老後を送る音楽家夫妻のゆったり流れる日々は、ある日突然妻の発病により暗転する。手術は失敗に終わり、半身不随となった妻を自宅へ連れ帰り、「もう決してどこにもやらないで」と懇願する妻に、「病院へは二度と入れない」と約束する夫。ジョルジュにとって神の言葉となったが、しかし、神はジョルジュに耐えがたい試練を与えるようになる。
初めは静かに本を読んでいるおとなしい病人であったアンヌは、病気の進行と共に容姿はやつれ、自制心を失くしていくのである。苦しげにうめき声を上げるアンヌは、ジョルジュにとって見慣れぬ生き物、無礼な侵入者に他ならない。老いの美しさを感じさせたアンヌが、老いの醜い塊となってジョルジュに襲い掛かってくる。この残酷な描写こそ、これがハネケだと言わざるを得ない。その介護生活の繊細な起伏を映画は、夜の寝息や水滴の落ちる音さえも見逃さぬかのように丹念に見つめていく。
やがて心身は極度に衰弱してゆき、言葉も発せず、もう終わりにしたいとつぶやく妻に、夫はなだめるかのように夢うつつに、懐かしい少年時代の思い出を淡々と語り続ける。夫がタバコを吸うために開け放した窓から入ってきた鳩を、毛布で覆いこんでしまうシーンも印象的で、これが最後の妻に対する伏線となっているんですね。

妻を枕で圧迫死させた翌朝、かつての朝のように、妻が朝食の支度をする音がドア越しに聞こえてきて、夫は目覚める。台所へ恐る恐る入っていくと、いつものように妻は皿を洗っていて、夫に靴を履きコートを着て出かけるように笑顔で促す。用意を整えた二人は玄関の扉を開け、家の外へと消えてゆく。
断崖の淵をすれすれに衰弱しきった体で立ちつつ、死と向き合い続けなくてはならない二人の姿は、見る者すべての未来と重なってくるはずです。病い、孤独、衰え、痛み、滅び、・・・人生の終わりに洪水のように押し寄せてくる厄介で、複雑な問題と直面した時、自分ならどうするだろうか。

自分の愛する者がそのような事態になった時、どう対処するだろうか。一人娘は出てくるのだが、自分で引き取り母親の介護をしようとは言わない。病院か施設に預けるように父親に言うだけ。
映画の中で夫を演じるジャン=ルイ・トランティニャンと、妻を演じるエマニュエル・リヴァ。二人の名優により繰り広げられる物語は、容赦なく息もつかせずに、終りまで突っ走ってゆく。
ミヒャエル・ハネケ監督がこの映画を作ったのは、同様のことが彼の家族にも起こったからだという。しかしそのような残酷さや、悲惨さにもかかわらず映像は慎み深く、清く新しさを失うことはない。
主人公の愛の究極の形を、私たちは認めるわけにはいかないのだが、そこには私たちを考え込ませずにはおかない、老老介護の重い問いかけがあると思った。
2013年劇場鑑賞作品・・・51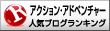 映画(アクション・アドベンチャー) ブログランキングへ
映画(アクション・アドベンチャー) ブログランキングへ

監督・脚本は1942年生まれで70歳のミヒャエル・ハネケ。前作『白いリボン』に続き本作と2作品連続でカンヌ国際映画祭のパルムドール(最高賞)に輝く快挙を果たした。本作は米アカデミー賞やゴールデン・グローブ賞の外国語映画賞を受賞するなど数々の賞を受賞する話題作である。
妻を自宅で献身的に支える夫ジョルジュを演じたのは1930年生まれで82歳の「暗殺の森」のジャン=ルイ・トランティニャン。ハネケ監督はトランティニャンが演じることを前提に脚本を書いたという。「彼なしではこの映画を撮らなかった」と語るほどだ。妻アンヌを演じたのは1927年生まれで85歳の、「二十四時間の情事」のエマニュエル・リヴァ。米アカデミー賞では主演女優賞に史上最高齢でノミネートされた。
注意:内容がネタバレになっているのでご注意ください。

<感想>アカデミー賞の外国語映画賞を受賞した作品。パリ中心部に建つ重厚なアパルトマン。しかしその全景は最後まで映されることはない。部屋は決して広くもなく豪華でもないが、隅々まで主の神経が行き届いた美しい空間である。調度品の一つ一つも、本棚をびっしりと埋める本も、絶妙なあんばいで配置された数点のアンティークな壁の絵も、静かで落ち着いた部屋の空気に見事に溶け込んでいる。そして、主役のポジションを占めるのは一台の艶やかなピアノ。それは貴婦人のごとくに存在し、あたりを支配しているかのようである。
ここに住むジョルジュとアンヌ夫妻はともに音楽家だが、すでに80歳を超えて現役から退いている。
ピアノ教師だったアンヌの愛弟子である若手ピアニストの演奏会が開かれたシャンゼリゼ劇場に二人で出かけ、帰宅したところから物語はスタートする。二人とも演奏には満足した様子だが、その興奮に冷水をかけるようなことが起こった。重厚な玄関のカギ穴を誰かがこじ開けようとした形跡を見つける。怖くて死にそうという妻のアンヌに、せっかく気分のいい夜だから忘れようという夫。
そして画面は真っ暗になり、何故か長く感じるくらい続き観客が不安になる。やがてジョルジュの声がして二人がベッドで寝ていることが分かるのだが、ジョルジュはアンヌの異変に気づき「どうした」と声をかけるが、アンヌは「なんにも」と答える。そして悲劇の始まりとなる朝を迎える。この暗闇にさえぎられて、妻アンヌの様子が目に見えなかったので、どう解釈していいやら。

それにしても、ハネケといえば、人間の非情、邪悪、弱さを冷徹に観察する難解な監督として知られるけれど、これは、これまでとちょっと趣が違う。恐怖の描写はミヒャエル監督の得意とするところだが、本作での怖がらせ方は、ホラー映画顔負けのえげつなさすら感じさせる。プロローグでいきなり息絶えているアンヌの姿を見せることからして意表を突き過ぎという感じがしないでもないが、こういう手法が実は本作を巷にあふれる老老介護の残酷物語と一線を画すところなのだと分かってくる。つまり、状況を説明するものではなく、芸術的に描かれた感性の物語なのだと。

パリのアパートで穏やかな老後を送る音楽家夫妻のゆったり流れる日々は、ある日突然妻の発病により暗転する。手術は失敗に終わり、半身不随となった妻を自宅へ連れ帰り、「もう決してどこにもやらないで」と懇願する妻に、「病院へは二度と入れない」と約束する夫。ジョルジュにとって神の言葉となったが、しかし、神はジョルジュに耐えがたい試練を与えるようになる。
初めは静かに本を読んでいるおとなしい病人であったアンヌは、病気の進行と共に容姿はやつれ、自制心を失くしていくのである。苦しげにうめき声を上げるアンヌは、ジョルジュにとって見慣れぬ生き物、無礼な侵入者に他ならない。老いの美しさを感じさせたアンヌが、老いの醜い塊となってジョルジュに襲い掛かってくる。この残酷な描写こそ、これがハネケだと言わざるを得ない。その介護生活の繊細な起伏を映画は、夜の寝息や水滴の落ちる音さえも見逃さぬかのように丹念に見つめていく。
やがて心身は極度に衰弱してゆき、言葉も発せず、もう終わりにしたいとつぶやく妻に、夫はなだめるかのように夢うつつに、懐かしい少年時代の思い出を淡々と語り続ける。夫がタバコを吸うために開け放した窓から入ってきた鳩を、毛布で覆いこんでしまうシーンも印象的で、これが最後の妻に対する伏線となっているんですね。

妻を枕で圧迫死させた翌朝、かつての朝のように、妻が朝食の支度をする音がドア越しに聞こえてきて、夫は目覚める。台所へ恐る恐る入っていくと、いつものように妻は皿を洗っていて、夫に靴を履きコートを着て出かけるように笑顔で促す。用意を整えた二人は玄関の扉を開け、家の外へと消えてゆく。
断崖の淵をすれすれに衰弱しきった体で立ちつつ、死と向き合い続けなくてはならない二人の姿は、見る者すべての未来と重なってくるはずです。病い、孤独、衰え、痛み、滅び、・・・人生の終わりに洪水のように押し寄せてくる厄介で、複雑な問題と直面した時、自分ならどうするだろうか。

自分の愛する者がそのような事態になった時、どう対処するだろうか。一人娘は出てくるのだが、自分で引き取り母親の介護をしようとは言わない。病院か施設に預けるように父親に言うだけ。
映画の中で夫を演じるジャン=ルイ・トランティニャンと、妻を演じるエマニュエル・リヴァ。二人の名優により繰り広げられる物語は、容赦なく息もつかせずに、終りまで突っ走ってゆく。
ミヒャエル・ハネケ監督がこの映画を作ったのは、同様のことが彼の家族にも起こったからだという。しかしそのような残酷さや、悲惨さにもかかわらず映像は慎み深く、清く新しさを失うことはない。
主人公の愛の究極の形を、私たちは認めるわけにはいかないのだが、そこには私たちを考え込ませずにはおかない、老老介護の重い問いかけがあると思った。
2013年劇場鑑賞作品・・・51









