http://nezu621.blog7.fc2.com/blog-entry-3878.html 2018年09月12日
歴史戦を変えるものとは ねずさんのひとりごとさん


歴史というのは過去の事実の筋書きです。
「ライオンがシマウマを倒した」というのが事実であっても、それを何日も獲物にありつけずにいた哀れなライオンの勇敢な戦いと勝利という筋書きにするのか、いきなり襲われたシマウマの抵抗と悲劇という筋書きに仕立てるのか、それは幾通りもの筋書き仕立ての可能性があるわけです。
歴史は国家や民族のアイデンティティのもとになるものであり、民族や国家ごとに歴史に求める筋書きが異なるわけですから、その筋書きのどちらが正しいかを議論しても結論は出ません。
なぜならそれは、ライオンが好きか、シマウマが好きかの議論にしかならないからです。
そうではなく、事実そのものを検証し再現していくこと。
それが本来の議論のあり方であろうと思いますし、我々日本人のもっとも得意とするところになると思います。
いまの学校には世界史の授業がありますが、戦前にはありませんでした。
代わって東洋史と西洋史がありました。
実は両者はまったく異なるもので、世界史とひとくくりにはできないものです。
どういうことかというと、歴史は過去にあった事実をストーリー仕立てにして記したものを言います。
ところが東洋史と西洋史とでは、ストーリーに対する考え方がまったく異なるのです。
東洋史は、王朝の交替史で、新しい王朝が立つと、前の滅んだ王朝の歴史を記した史書が書かれました。
記述の仕方はパターン化されていて、前の王朝の初代皇帝はとても優れていた人で天命を受けて王朝を開いたけれど、歴代世襲が行われる中でだんだんと皇帝の質が落ち、国が荒れたので天命がいまの王朝に移りました、めでたしめでたしという筋書きです。
要するに「だからいまの王朝は天命を得た正統な王朝なのだ」と言いたいわけです。
これに対し西洋史は王朝の正統性を問題にしません。
ヨソから強大な帝国が攻めてきて、王様以下みんなで奮戦したけれど武運つたなく全員死んでしまった。
そして帝国の圧政によって民衆が苦しめられたとき、ひとりの英雄(ヒーロー)が立ち上がって帝国に敢然と挑み、ついには帝王を殺し、美女を手に入れて、素晴らしい王国が築かれましたとさ、めでたしめでたし、という筋書きです。
だから「我々の国が存在しているのだ」といいたいわけですし、英雄である王の言うことを聞け、というわけです。
このように歴史を記述するうえでの筋書きがまるで異なるわけですから、両者を一緒にしたら混乱します。
だから戦前戦中までは、世界史という分野はなくて、東洋史と西洋史に分かれて学んでいたわけです。
ところが戦後に日本に入ってきたGHQは、国史(日本史)の授業を禁止する一方で、強引に東洋史と西洋史を一緒にしてしまいました。
これは当然のことで、米国で歴史といえば、西洋史しかない。
彼らには、日本人が東洋史と西洋史に分けて学習していること自体が意味がわからなかったのです。
そういうわけで戦後はいまでも世界史という授業が行われているわけですが、授業をするには、西洋史と東洋史をひとつの教科書にまとめなければなりません。
ところが根っこのところで歴史に対する基本的な考え方がぜんぜん異なるものを一緒にしてもわけがわからなくなります。
それはまるで水と油をひとつの教科書でごた混ぜにしているようなものだからです。
そこでやむなく採られたのが、両者を単に年表のような時系列で、事件名や国名をただ覚えるというだけの教科書であり、授業です。
結果、世界史の授業といえば、すっかりただの暗記科目になり、生徒の側からしたら、暗記さえすれば簡単に良い点のとれる科目という認識になります。
ところがどんなに成績が良かったとしても、肝心の「どうしてその王国が成立したのか」、「どうしてその王国は滅んだのか」といった、東洋史、西洋史の醍醐味(だいごみ)にあたるところを学んでいないわけです。
どうしてそうなったのかがわからなければ、歴史を人生に活かしたり、社会人として事業や行政などに活かすこともできません。
これは本当に残念なことで、小中高と、人生を営むための知識を吸収するためのいちばん大切な時期に、ただ年号と事件名を三度もくりかえしているだけなのです。
まるっきり役に立たないとまでは言いませんが、学校教育で世界史が得意科目でしたという人でも、その歴史の知識が人生に活かされない、活かすことができないような知識なら、無用の知識を得ただけになってしまいます。
ネットが普及してくると、たとえば「ローマ帝国が成立したのは何年?」、「唐が滅んだのは何年」などといった年号は、いつでもどこでもスマホで簡単に検索できてしまいます。
iPhoneなら、そのように話しかけるだけで、曖昧な記憶よりもはるかに正確な答えをすぐに探してくれます。
すごい時代になったものです。
教育基本法には、第一条に教育の目的が書かれています。
*******
第1条(教育の目的)
教育は、
人格の完成をめざし、
平和的な国家及び社会の形成者として、
真理と正義を愛し、
個人の価値をたつとび、
勤労と責任を重んじ、
自主的精神に充ちた
心身ともに健康な国民の育成を期して
行われなければならない。
*******
まさに名言です。
しかしその目的は、ただ年号を暗記すれば達成することができるものなのでしょうか。
理数系の科目は知識の積み上げなので、最先端の科学技術分野の開拓のためには、基礎から高等教育まで順番に積み上げていかなければならないと思います。
ようやく足し算や引き算を覚えたばかりの子に、いきなり微分積分は無理なことでしょう。
けれど文系の、なかでも歴史教育というのは、歴史学者にならなくても、過去の様々な出来事に、自分自身が当事者となって様々な思考を繰り広げることで、それが活きた知恵になるものです。
それがただの年号の丸暗記であったり、異なる筋書きを一緒くたにしたのでは身につきにくいと思います。
冒頭で、世界史は東洋史と西洋史に分かれると書きましたが、国史もまたそれら海外の史観とはまったく異なるものです。
我が国は万世一系の天皇をいただく国ですから、Chinaや西欧諸国のような王朝交替がありません。
したがって王朝の正統性を歴史で説く必要はなく、英雄(ヒーロー)も必要ありません。
では我が国の国史(日本史)をどうして学ぶのかといえば、それは、過去の様々な出来事を通じて、現代を生き抜き、人生に起こる様々な難局に対処し、よろこびあふれる未来を切り開くためです。
そうであれば、当然のことながら、歴史には事実が求められます。
でたらめな筋書きや、事実誤認があれば、それは正確な情報たりえず、現在をひらく鍵とはなりえないからです。
日本におけるこうした歴史への姿勢は、冒頭に記した東洋史や西洋史にはないものです。
東洋に西洋にせよ、彼らにとって必要な歴史は、王の正統性や国家の存在理由としての歴史です。
あくまでも目的的な歴史認識ですから、そこに必要なことは、事実そのものよりも、事実をどう見るかであって、
「本当はこうだったのだ」
という理屈は、彼らにとっては迷惑なものでしかないわけです。
ところが日本人は歴史にファクト(事実)を求める。
けれど根幹として、歴史に求めるものが異なるわけですから、その根幹の議論を抜きにして、どちらが正しいかを議論しても答えが出ることはないし、むしろ意見が割れて摩擦の原因になるだけの結果になります。
歴史というのは過去の事実の筋書きです。
「ライオンがシマウマを倒した」というのが事実であっても、それを何日も獲物にありつけずにいた哀れなライオンの勇敢な戦いと勝利という筋書きにするのか、いきなり襲われたシマウマの抵抗と悲劇という筋書きに仕立てるのか、それは幾通りもの筋書き仕立ての可能性があるわけです。
歴史は国家や民族のアイデンティティのもとになるものであり、民族や国家ごとに歴史に求める筋書きが異なるわけですから、その筋書きのどちらが正しいかを議論しても結論は出ません。
なぜならそれは、ライオンが好きか、シマウマが好きかの議論にしかならないからです。
そうではなく、事実そのものを検証し再現していくこと。
それが本来の議論のあり方であろうと思いますし、我々日本人のもっとも得意とするところになると思います。
人は、信じるか信じないか、好きか嫌いかなど、議論の次元が低くなればなるほど感情的になります。
筋書きでは感情的になり、議論にならないのです。
国家間あるいは民族間の歴史論争について、議論をあきらめろと申し上げているのではありません。
それでも議論をしていく必要があります。
ところが振り返ってみると、戦後の日本における歴史教育は、まさに、そうした議論にならないところのみをターゲットにした教育になっていました。
年号と事件名。そこで何が起きたかという事実だけにスポットライトを当てた歴史教育は、筋書きを無視しているだけに、歴史教育の名には値しないものといえます。
しかし、その教育のあり方は、見方を変えると、民族や国家を越えて歴史を再現するのに最も抵抗のない・・・つまり争いを生まない巧妙な歴史教育であったともいえるわけです。
おもしろさはありません。
けれど、事実のみに的を絞るという姿勢は(そうばかりではないところが問題なのですが、そこを除けば)、世界の歴史認識を変えるインパクトを内在させるものでもあるのです。
お読みいただき、ありがとうございました。
Blog
http://nezu621.blog7.fc2.com/blog-entry-3878.html
2018年09月12日
歴史戦を変えるものとは ねずさんのひとりごとさん
◆【お知らせ】◆
<東京・倭塾、百人一首塾他>
9月15日(土)18:30 百人一首塾 第29回
9月23日(日)13:30 第54回 倭塾・東京 第54回

・知らなかった!広島原爆の投下直後に、日本政府が出した「アメリカを糾弾する文書」更新
・日本的なよろこびとは ねずさんのひとりごとさんより
tps://blog.goo.ne.jp/sakurasakuya7/e/5075e0d75ca549aedd81082e779c3763










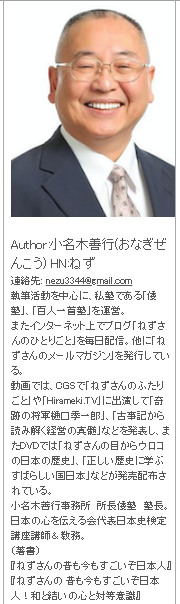






・天然の災害に対処できる国つくりを ねずさんのひとりごと