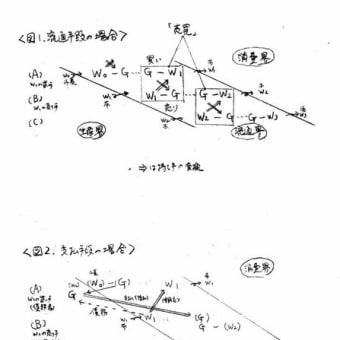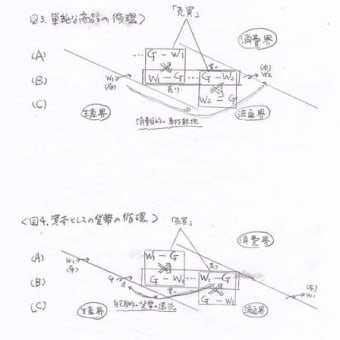「読む会」だより(22年12月用)文責IZ
(11月の議論など)
11月の「読む会」は20日に開催されました(和室しか確保できず申し訳ありませんでした)。
(10月の議論)の部分では、「資本家的な生産に置き換わるということは、労働者の剰余労働を剰余価値として取得するということなのか」という質問が出ました。
チューターは、第2節で「資本が剰余労働を発明したのではない。いつでも、社会の一部の者が生産手段の独占権を握っていれば、いつでも労働者は、自由であろうと不自由であろうと、自分自身を維持するために必要な労働時間に余分な労働時間をつけ加えて、生産手段の所有者のために生活手段を生産しなければならない」とあったように、近代の労働者をはじめとする直接的生産者は、階級社会に入って以来は、支配階級のための剰余労働を行なってきた。その反面で被支配階級の剰余労働が集中されることで、少数の支配階級には労働から遊離した自由な時間がもたらされ、それによってはじめて科学等が生まれ、生産力が発達したと言える。剰余労働の問題は、単に道徳的に評価すべきではなく、近代の労働者にあっては、生産力と主体的能力の発展の下で、生産手段の階級的独占を打ち破ることができるならば、剰余労働を労働不能者などへの社会的控除のためにのみ支出する可能性があるのであり、その場合には剰余労働も現在とは違った意義を持つだろう。
またその後では、「とはいえ、ある経済的社会構成体のなかで生産物の交換価値ではなく使用価値のほうが重きをなしている場合には、剰余労働は諸欲望の狭いにせよ広いにせよとにかくある範囲によって制限されており、剰余労働にたいする無制限な欲望は生産そのものの性格からは生じないということは明らかである。それだから、古代でも、交換価値をその独立の貨幣姿態で獲得しようとする場合、すなわち金銀の生産では、恐ろしいまでに過度労働が現われる」と述べられている。資本の下での生産の特徴は、それが諸使用価値の取得を目的としてなされるのではなくて、第4章で示されたように、価値(交換価値)をつまり抽象的富の無際限な取得(量的増大)を目的としてなされ点にある。このために、一方で過度な剰余労働の強制が常態化するが、他方では以後の章で述べられるように生産力の上昇が強制されことになる。こうした点から言って、剰余労働を剰余価値として取得することが、それを剰余生産物や単なる労働給付として取得する旧来の生産様式とは異なる、資本主義の特徴と言えるのではないかと説明しました。
説明(1)の部分では、「補足部分に『資本主義的生産に内在的な“諸”法則とは、交換者の意図とは独立に諸現象の中で貫徹される、価値法則に基づく必然的傾向のこと』とあるが、例を挙げてほしい」いう質問が出ました。
チューターは、議論のあるところだろうが、個人的には価値法則が様々な条件の中で貫徹されていく場合の法則的な傾向のことだろうと思っている。資本論の中では価値法則以外に法則と名がついているものに、第3巻で取り上げられる「利潤率の傾向的低下の法則」というのがあるが、それだけではないと考えている。というのは、クーゲルマンあての手紙の中で、マルクスは「科学の本領は、まさに、この価値法則がどのようにして貫徹されてゆくかを展開することにある」と述べている。だからこれまでの例で言えば、たとえば「価値の価格への転化」なども自分としては一つの法則とみなしてよいのではないかと思っている。この例から言えば、以前も触れたように、生産者の一人がこのボールペンの生産に100労働時間を支出したのだからそれは例えば100円に値すべきだと考えたとしても、多くの生産者がそれに50時間しか支出していないのであれば、そのボールペンの価値は50時間として評価され、それに対応した例えば50円といった価格として表示されるほかない、といったことを例として挙げられるかもしれない。
ただし、ここでは自由競争に関連して言われているので、多分、例として挙げるべきなのは、先ほど挙げたあたりで出てくる、一般的利潤率(平均利潤率)の形成と商品価値の生産価格への転化に関連したものと思われるが、準備していないと述べました。(大まかに言えば、各生産部面はその資本の構成にしたがって利潤率が異なるが、資本の移動が自由であるかぎり、それは平均利潤率を生み出す。他方、資本の増殖・蓄積とともに資本構成は可変資本に対して不変資本の方が相対的に増大していく。このため、平均利潤率は相対的に低下することになり、資本は一層の資本蓄積による生産力増大を強制されることになる、といったものです。第9章にも法則という言葉が使われている部分がありますので、参考にしてください。)
ここでは他に「社会主義の下では様々な文化的行為などは労働時間と見なされないのか」という質問が出ました。チューターは、若かりし頃労組の交流会の中でスポーツ大会への参加なども労働時間として要求すべきといった意見があったように覚えている。資本主義の下での労働者の要求ならばそれもあり得ないとは思わないが、社会主義の下でとなると、労働時間は極めて重要な問題になってくる。それは生産的な労働に振り向けられた労働時間であり、またその労働時間に対応して(社会的控除は差し引かれるが)誰もが平等に分配を受けるというように、キチンと考えないといけないだろうと答えました。別の参加者からは「社会主義の下で労働時間が十分に短縮されれば、そのなかで様々な文化的行為も可能になるのではないか」という意見が出されました。
説明(2)の部分では、「海外での生産や生産委託が増えている現在、それらの国々で労働時間の規制が緩く割増賃金を払わないなど、安い労働力で働かせる問題が起きているのではないか」という意見がありました。チューターは、よく考えていないが直接投資なのか貿易なのかによって問題点は違ってくるように思う。安い労働力ということでは、自分の職場にも海外からの実習生が5名ほどいるが、いわゆる出稼ぎ先として、アジアではマレーシアや韓国、中国(香港を含む)などに比して日本の地位が低くなっていると聞く。安い労働力といっても少なくとも日本・韓国と中国・マレーシアなどとの間では差はずいぶんと縮まってきているのではないだろうか、最近は為替の問題もあるし、と答えました。問題は賃金が高い安いというよりも、程度の差はあれ資本主義に共通な劣悪な労働条件なのではないでしょうか。ここでは別の参加者から「孫から聞くのだが、日本はどこもブラック企業ばかりで、労働環境は悪く収益も上がらないようだ。何とかならないものかと思う。」という意見も出されました。
時間切れとなってしまったために、説明(3)と付録の部分は、次回に第9章と一緒に取り上げさせていただきます。
(説明)第9章「剰余価値率と剰余価値量」
(1.剰余価値量に関する三つの法則)
剰余価値量の第一の法則とは次のようなものです。
・「そこで次のような<剰余価値量の>第一の法則が出てくる。<すなわち>生産される剰余価値の量は、前貸しされる可変資本の量に剰余価値率を掛けたものに等しい。……[言い換えれば、まさしくそれは、一個の労働力の価値にその搾取度<剰余価値率>をかけ、さらに同じ時に充用される労働力の数を掛けたものに等しい]。
……だから、可変資本の減額は、それに比例する労働力の搾取度の引き上げによって、または従業労働者数の減少は、それに比例する労働日の延長によって、埋め合わされ得るのである。したがって、ある限界のなかでは、資本によって搾り出されうる労働の供給は労働者の供給には依存しないものになる。反対に、剰余価値率の減少は、それに比例して可変資本の大きさまたは従業労働者数が増大するならば、生産される剰余価値の量を変えないのである。」(P400~)
生産される剰余価値の量(М)は、前貸しされた可変資本の量(V)に剰余価値率(m/v)を掛けたものに等しい、というのが第一の法則です。数学(?)的には同義で無意味に見えるかもしれませんが、その内容は、必要労働時間を越える労働時間の量によって剰余価値の大きさが規定されるということの延長です。後半にあるように、労働日の延長(労働の強度の強化による事実上の延長を含め)によって「ある限界の中では」、「絞りだされうる労働の供給<量>」すなわち剰余労働の量は(したがって剰余価値の量は)、労働者数に(可変資本の大きさに)依存しなくなります。このために一見すると、生み出される剰余価値の量は、可変資本の量と無関係なもので、むしろ生産手段の生産力に依存するものであるかに見えることになります。
なお搾取度と剰余価値率との関係は、労働力の搾取度を直接に表わすのは、総労働時間のうちの(剰余労働時間)/(必要労働時間)なのですが、それが実際に現れるのは商品交換(流通)を介した貨幣表現においてであり、したがって剰余価値率すなわち(剰余価値量)/(可変資本量)という姿としてである、ということだと思われます。
また剰余価値量の第二の法則とは次のようなものです。
・「本来つねに24時間よりも短い平均労働日の絶対的な限界は、可変資本の減少を剰余価値率の引き上げによって補うことの、または搾取される労働者数の減少を労働力の搾取度の引き上げによって補うことの、絶対的な限界をなしているのである。@
この分りきった<剰余価値量の>第二の法則は、後に<相対的剰余価値の生産において>展開される資本の傾向、すなわち資本の使用する労働者数または労働力に転換される資本の可変成分をできるだけ縮小しようとする資本の傾向、すなわち<これまでに述べてきたような労働日の延長によって>できるだけ大きな剰余価値量を生産しようという資本のもう一つの傾向とは矛盾した傾向から生ずる多くの現象を説明するために、重要なのである。逆に、使用される労働力の量または可変資本の量が増えても、その増え方が剰余価値率の低下に比例していなければ、生産される剰余価値の量は減少する。」(P402)
社会的に規定される労働日は、1日の自然的な限界である24時間を超えることができないという制限を持つばかりではなくて、1労働日には常にその一部分として必要労働時間部分が含まれるという制限があることを忘れてはなりません。
生産される剰余価値を拡大するためには、第一の法則から言えば可変資本(支払い賃金、したがって労働者数)を増大させねばならないということになります。しかし、絶対的に増大させうる労働日には制限があるために、生産力を高めて(それは不変資本の増大に結果しますが)労働日のうちの必要労働時間部分を減らすという方法でこの制限を乗り越え、可変資本部分を縮小しながらも剰余価値を増大させていこうとする資本の傾向が出てくる、と言うのです。
さらに、剰余価値量の第三の法則とは次のようなものです。
・「<剰余価値量の>第三の法則は、生産される剰余価値の量が剰余価値率と前貸可変資本量という二つの要因によって規定されているということから生ずる。@
剰余価値率または労働力の搾取度が与えられており、また労働力の価値または必要労働時間の長さが与えられていれば、可変資本が大きいほど生産される価値と剰余価値との量も大きいということは自明である。労働日の限界が与えられており、その必要<労働時間>成分の限界も与えられているならば、1人の資本家が生産する価値と剰余価値との量は、明らかに、ただ彼が動かす<ことのできる>労働量だけによって定まる。ところが、この労働量は、与えられた仮定の下では、彼が搾取する労働力量または労働者数によって定まるのであり、この数はまた彼が前貸しする可変資本の大きさによって規定されている。つまり、剰余価値率<ないし労働力の搾取度>が与えられており労働力の価値<ないし必要労働時間>が与えられていれば、生産される剰余価値の量は、前貸しされる可変資本の大きさに正比例するのである。@
ところで、人の知るように、資本家は自分の資本を二つの部分に分ける。一方の部分を彼は生産手段に投ずる。これは彼の資本の不変部分<その価値は生産物に引き継がれて資本家に還流するだけで増殖しない>である。他方の部分を彼は生きている労働力に転換する。この部分は彼の可変資本<その価値は剰余労働が加わることで増殖して資本家に還流する>をなしている。@
同じ生産様式の基礎の上でも、生産部門が違えば、不変成分と可変成分への資本の分割<割合>は違うことがある。同じ生産部門のなかでも、この割合は、生産過程の技術的基礎や社会的結合が変わるにつれて変わる。しかし、ある与えられた資本がどのように不変成分と可変成分とに分かれようとも、すなわち前者に対する後者の比が 1:2 であろうと、 1:10 であろうと、 1:x であろうと、<すなわち資本の構成比率の相違にかかわらず>いま定立された<「剰余価値率が与えられており労働力の価値が与えられいれば、生産される剰余価値の量は、前貸しされる可変資本の大きさに正比例する」という>法則はそれによっては動かされない。@
なぜならば、先の分析によれば、不変資本の価値は、生産物価値のうちに再現はするが、新たに形成される価値生産物の中には入らないからである。1000人の紡績工を使用するためには、もちろん、100人を使うためよりも多くの原料や紡錘などが必要である。しかし、これらの追加される生産手段の価値は、上がることも下がることも不変のままのことも、大きいことも小さいこともあるであろうが、それがどうであろうとも、これらの生産手段を動かす労働力の価値増殖過程<すなわちvとmの関係>には何の影響も及ぼさないのである。@
だから、ここで確認された<剰余価値量の第三の>法則は次のような形をとることになる。いろいろな資本によって生産される価値および剰余価値の量は、労働力の価値が与えられていて労働力の搾取度が等しい場合には、これらの資本の可変成分の大きさに、すなわち生きている労働力に転換される成分の大きさに、正比例する。
@
この<形を変えた第三の>法則は、およそ外観に基づく経験とは明らかに矛盾している。誰でも知っているように、充用総資本の百分比構成を計算してみて相対的に多くの不変資本と少ない可変資本とを充用する紡績業者は、だからといって、相対的に多くの可変資本と少ない不変資本とを運転する製パン業者よりも小さい利益または剰余価値を手に入れるわけではない。この外観上の矛盾を解決するためにはなお多くの中間項が必要なのであって、ちょうど0/0が一つの実数を表わしうることを理解するためには、初等代数学の立場からは多くの中間項が必要であるのと同じである。@
古典派経済学はこの<形を変えた第三の>法則を定式化したことはなかったにもかかわらず、本能的にこれに執着するのであるが、それはこの法則が価値法則一般の一つの必然的な帰結だからである。古典派経済学は、無理やりの抽象によって、この法則を現象の諸矛盾から救おうとしている。リカード学派がどのようにしてこの邪魔な石につまづいたかは、のちに<『剰余学説史』>示されるであろう。「本当は、何も覚えなかった」俗流経済学は、いつものようにここでも現象の法則を無視してその外観にしがみついている。それは、スピノザとは反対に、「無知は十分な根拠になる」と信じているのである。」(P402~)
生産手段(原材料と労働手段)のために支出される資本の不変部分は、その価値を生産物に引き継ぐことで資本家に還流するだけで、その価値を増殖するものではありません。このため資本によって生産される価値および剰余価値の量は、労働力の価値が与えられていて労働力の搾取度が等しい場合には、これらの個別資本の可変成分の大きさに、すなわち生きている労働力に転換される成分の大きさに、正比例するということになります。
しかしながら、このことはこの引用の最後にあるように現象(つまり資本構成に違いがあるにもかかわらず、資本が取得する利益の大きさはもっぱら資本の大きさに比例する)とは異なります。マルクスは、それは価値法則やそこから出てくる諸法則が間違っているからではなくて、なぜそれらの法則がそのような姿(現象)をとるのかを、諸要因の分析によって説明すること、これが科学なのだと語っているのだと思われます。
なお、流通を媒介する貨幣が、自己増殖する資本へと質的に転化するためには一定の量的制約がある、という点も重要でしょうからここで引用しておきます。説明は省きます。
・「剰余価値の生産についてのこれまでの考察から明らかなように、どんな任意の貨幣額または価値額でも資本に転化できるのではなく、この転化には、むしろ、1人の貨幣所持者または商品所持者の手にある貨幣または交換価値の一定の最小限が前提されているのである。@
可変資本の最小限は、一年じゅう毎日剰余価値の獲得のために使われる一個の労働力の費用価格<再生産費>である。@
この労働者が、彼自身の生産手段をもっていて、労働者として暮らすことに甘んじるとすれば、彼にとっては、彼の生活手段の再生産に必要な労働時間、たとえば毎日8時間の労働時間で十分であろう。したがって、彼に必要な生産手段も8労働時間分だけでよいであろう。@
これに反して、この8時間の他にたとえば4時間の剰余労働を彼にさせる資本家は、追加生産手段を手に入れるために追加貨幣額を必要とする。しかし、われわれの仮定の下では、この資本家は、毎日取得する剰余価値で労働者と同じに暮らすことができるためにも、すなわち彼のどうしても必要な諸欲望を満たすためにも、すでに2人の労働者<8時間/4時間>を使用しなければならないであろう。この場合には、彼の生産の目的は単なる生活の維持で、富の増加ではないであろうが、このあとのこと<富の増加>こそが資本主義的生産では前提されているのである。彼が普通の労働者のたった2倍だけ<8×2=16時間分=4人分>豊かに生活し、また生産される剰余価値の半分を資本に再転化<16÷2=8人分>させようとすれば、彼は労働者数とともに前貸資本の最小限を8倍に増やさなければならないであろう。@
もちろん、彼自身が彼の労働者と同じように生産過程で直接に手を下すこともできるが、その場合には、彼はただ資本家と労働者との間の中間物、「小親方」でしかない。資本主義的生産のある程度の高さは、資本家が資本家として、すなわち人格化された資本として機能する全時間を、他人の労働の取得、したがってまたその監督のために、またこの労働の生産物の販売のために、使用できるということを条件とする。手工業親方が資本家になることを、中世の同職組合制度は、一人の親方が使用してもよい労働者数の最大限を非常に小さく制限することによって、強圧的に阻止しようとした。貨幣または商品の所持者は、生産のために前貸しされる最小限が中世的最大限をはるかに超えるときに、はじめて現実に資本家になるのである。ここでも、自然科学におけると同様に、ヘーゲルがその論理学のなかで明らかにしているこの法則、すなわち、単なる量的な変化がある点で質的な相違に一変するという法則の正しいことが証明されるのである。……」(P404~)
(2.マルクス自身による第3篇の要点)
マルクスは「絶対的剰余価値の生産」と名付けられた第3篇を終わるにあたって、その要点をこう記しています。
・「われわれは、資本家と賃金労働者との関係が生産過程の経過中に受けた諸変化の詳細には、したがってまた資本そのもののさらにすすんだ諸規定にも、かかわらないことにする。ただ、わずかばかりの要点だけをここで強調しておきたい。
生産過程のなかでは<労働の客観的条件である>資本は労働にたいする、すなわち活動しつつある労働力または労働者そのものにたいする指揮権にまで発展した。人格化された資本、資本家は、労働者が自分の仕事を秩序正しく十分な強度で行なうように気をつけるのである。
資本は、さらに、労働者階級に自分の生活上の諸欲望の狭い範囲が命ずるよりも多くの労働を行なうことを強要する一つの強制関係にまで発展した。そして、他人の勤勉の生産者として、剰余労働の汲出者および労働力の搾取者として、資本は、エネルギーと無限度と効果とにおいていっさいのそれ以前の直接的強制労働にもとづく生産体制を凌駕しているのである。
資本は、さしあたりは、歴史的に与えられたままの労働の技術的諸条件をもって、労働を自分に従属させる。したがって、資本は直接には生産様式を変化させない。それだから、これまでに考察した形態での、労働日の単純な延長による剰余価値の生産は、生産様式そのもののどんな変化にもかかわりなく現われたのである。それは、古風な製パン業者でも近代的紡績業の場合に劣らず効果的だったのである。
生産過程を労働過程の観点から考察すれば、労働者の生産手段に関する関係は、資本としての生産手段にではなく、自分の合目的的な生産的活動のたんなる手段および材料としての生産手段にたいする関係だった。たとえば製革業では、かれは獣皮を自分のたんなる労働対象として取り扱う。彼が革をなめすのは、資本家のためにするのではない。@
われわれが生産過程を<資本の>価値増殖過程の観点から考察するやいなや、そうではなくなった。生産手段はたちまち他人の労働を吸収するための手段に転化した。もはや、労働者が生産手段を使うのではなく、生産手段が労働者を使うのである。生産手段は、労働者によって彼の生産的活動の素材的要素として消費されるのではなく、労働者を生産手段自身の生活過程<価値増殖>の酵素として消費するのである。そして、資本の生活過程とは、自分自身を増殖する価値としての資本の運動にほかならないのである。溶鉱炉や作業用建物が夜間休止していてもはや労働を吸収しないならば、それは資本家にとっては「ただの損失」である。それだからこそ、<資本としての>溶鉱炉や作業用建物は、労働力の「夜間労働にたいする要求権」を構成するのである。@
貨幣が生産過程の対象的諸要因すなわち生産手段に転化されるというただそれだけのことによって、<労働の客体的条件でしかない>生産手段は他人の労働および剰余労働にたいする権原および強制力原に転化されるのである。このような資本主義的生産に特有であってそれを特徴づけている転倒、実にこの、死んでいる<すでに支出されて価値の姿をとっている>労働と生きている労働との、価値と価値創造力との関係の転倒は、資本家の意識にどのように反映するか、このことを最後になお一つの例によって示しておこう。……
この西スコットランドの先祖伝来の資本頭脳にとっては、紡錘などという生産手段の価値<すなわちその生産のために支出された労働量>と、自分自身を価値増殖するという、すなわち毎日一定量の他人の無償労働を飲み込むという生産手段の資本属性との区別がまったくぼやけているのであって、そのために、このカーライル同族会社の社長は、自分の工場を売れば、自分には紡錘の価値だけではなく、その上に紡錘の価値増殖も支払われるのだと、すなわち、紡錘に含まれている同種の紡錘の生産に必要な労働だけではなく、紡錘の助けによって毎日ベーズリのけなげな西スコットランド人から汲み出される剰余労働も支払われるのだと、実際に妄想しているのであって、それだからこそ、彼は、労働日を2時間短縮すれば<剰余労働を生み出す手段としての>紡績機の12台ずつの売却価格も10台ずつのそれに縮まってしまう! と思うのである。」(P407~)
見られる通り、マルクスは資本主義(資本家的生産)の特徴を、「死んでいる労働と生きている労働との、価値と価値創造力との関係の転倒」であると、すなわち支出された労働と労働を支出する能力との関係の反転であり、ここでは人間が生産手段を使うのではなく、生産手段が人間を使うのであると(いわゆる人間の“疎外”であると)強調しています。
こうしたことが起こるのは、生産手段が単なる生産の客体的条件ではなくて、資本属性(他人の労働を吸収することによって自ら価値増殖する)を持つからにほかなりませんが、それはただ貨幣(すなわち個人の手の中にある一般的労働=他人の労働への支配権)が生産手段に転化され、生産手段が個人の私有物となるだけで(自由な労働者が前提されていれば、ですが)引き起こされるのです。そしてその結果、生産は労働者のみならず資本家の手からさえも自立化して、資本による資本そのものの価値増殖を目的とした生産という歴史的に特殊な生産様式を持つのです。