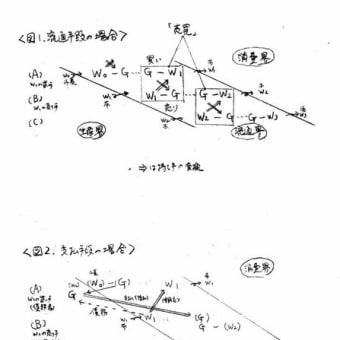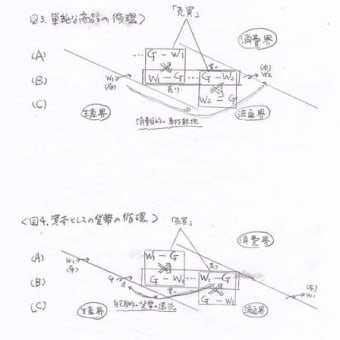「読む会」だより(24年11月用)文責IZ
(10月の議論など)
10月の「読む会」は20日に開催されました。
(9月の議論)の所では、『ゴータ綱領批判』の中で、“資本主義社会から生まれたばかりの共産主義”と“それ自身の土台の上に発展した共産主義”とが区別されているが、これはいわゆる二段階革命論ということか、という質問が出ました。チューターは、ここではむしろ資本の支配が廃絶され、生産手段の共有を基礎にして生産を自覚的に管理する社会が生まれるならば、その基礎の上でいわば“自然的に”共産主義が発展するだろう、と言われているのであって、二段階革命論とは全く逆だろう。いわゆる二段階革命論は、こうした社会主義革命は民族・民主革命なしには起こらないのだから、まずはブルジョア的な民族・民主革命を目指すべきというものだが、多くの国々ですでにブルジョア支配が完成している中では無意味であるし、歴史的にも──社会主義へと進めなかったにせよ──労働者が先導したロシア革命の現実の中で否定されているだろう、と述べました。
また、マルクスが国民経済学と言っているのは古典派経済学のことか、という質問が出ました。チューターは、スミス、リカードなどの古典派を指しているということで良いのでないかと答えました。しかし少し調べてみると、マルクスはたしかに「イギリス国民経済学」という言葉で古典派を指していますが(剰余価値学説史など)、これとは別に1840年代より「ドイツ国民経済学派」と呼ばれる潮流があり、ブルジョア経済学の中では国民経済学と言えばもっぱら後者のことを指すようです。不勉強で説明不足となり申し訳ありません。
第17章、2回目の(説明)の所では、前貸資本の“前貸”というのは資本家が当初持っていた貨幣が商品の販売を通じて回収されるからという意味でよいのか、という質問が出ました。チューターはそういう理解以外には考えたことがなかったので、少し調べてみたいと答えました。(資本の回転ないし循環という以外の意味は見当たりませんでした。)また、労賃のところは身近でもあって分かりやすかった、という感想が出ました。
(説明)第6篇労賃第18章時間賃金
(1.労賃の基礎にある労働力の価値および価格《価値の貨幣での相対的表現》は、必要生活手段の生産のために支出された労働量で計られる。「労働力の価格」は、資本主義的関係の中では「労働の価格=労賃」という姿をとるが、それはまずもって労働量に従った「時間賃金」という形態で現われる。「時間賃金」が労賃の基本形態であって、出来高賃金などの労賃形態はそれが変形して現われたものである)
まず冒頭で、この18章で検討すべき課題が次のように述べられます。
・「労賃はそれ自体また非常に様々な形態をとるのであるが、この事情は、素材<すなわち労賃>に対する激しい関心のために形態の相違には少しも注意を払わない経済学概説書からは知ることのできないことである。とはいえ、このような<労賃の>形態の全てについて述べることは、賃労働の特殊理論に属することであり、したがって本書の任務ではない。しかし、二つの支配的な形態についてはここで簡単に述べておかなければならない。
労働力の売りは、我々が記憶しているように<4章「貨幣の資本への転化」の第3節「労働力の売買」など>、つねに一定の時間を限って行われる<そうでなければ労働能力は商品ではなくなり、労働者は自分自身を売って奴隷になってしまうのだから>。それゆえ、<必要生活手段の価値すなわち支出労働量で計られる>労働力の日価値、週価値等々が直接にとる<労賃としての>転化形態は、「時間賃金」という形態、つまり日賃金等々なのである。」(全集版、P704)
ここで言われる「時間賃金」とはいわゆるパート労働などでの時給ばかりではなくて、日給や月給あるいは日給月給など、時間で計られて支払われる労賃の形態の全体を指します(いわゆる年俸は別でしょうが)。「労働力の価格」は、労賃という姿においては、労働者が実際に支出する労働の内、労働力自身の再生産に必要な必要労働時間=支払労働部分ばかりではなくて、剰余労働時間=不払い労働部分までもが支払われたものとして現われます。つまり「労働力の価格」が、「労働の価格」あるいは「労働そのものの価格」として現象したもの、これが労賃なのです。前章のタイトルにある「労働力の価値または価格の労賃<という現象形態>への転化」ということは、このような意味です。
この18章では、この「労働の価格」である労賃は、労働力がつねに一定の時間を限って売られるほかないがゆえに、より具体的な姿としては、まずもって日給とか週給とか時給とかの、直接に時間で区切られて支払われる「時間賃金」として現われるとまず説明されます。
(2.労賃は、名目的にはその貨幣量によって計られるが、実質的にはその貨幣量と引き換えに労働者が商品として受け取る生活手段の量で計られる。労働力の価格の場合と同じく、労賃は労働の生産力、労働の強度、労働日の長さ、という三つの要因によって変動する)
・「そこでまず言っておきたいのは、第15章で述べた労働力の価格と剰余価値との量的変動に関する諸法則は、簡単に形を変えることによって労賃の法則に転化するということである。同様に、労働力の交換価値とこの価値が転換される生活手段の量との相違も、今では名目労賃と実質労賃との相違として現われる。<労働力の価値や価格という>本質的形態ですでに説明されたことを現象形態で繰り返すことは、無益であろう。それゆえ、我々の説明も時間賃金を特徴づける僅かばかりの点に限ることにしよう。」(同)
ここで「第15章で述べた労働力の価格と剰余価値との量的変動に関する諸法則」と言われているのは、労働力の価格と剰余価値の大きさとに影響を与える、労働の生産力、労働の強度、労働日の長さ、という三つの要因にもとづく法則性について述べられた部分のことです。たとえば、第1節では「労働日の長さと労働の強度とが与えられていて労働の生産性が可変である場合」が取り上げられ、「与えられた長さの一労働日は……つねに同じ価値生産物に表わされる」等々の法則が示されました。
(3.労賃は、支出された労働に対する支払すなわち労働の価格として現われる。このため労賃は支払われるべき労働量によって“直接に”規定されたもの、すなわち「時間賃金」の姿をとる。「労賃=労働の価格」の尺度は、1労働時間に対する労働の平均価格であり、それは1労働日の労働力の平均的価値を平均的な労働日の時間数で除したものである)
・「労働者が自分の日労働や週労働などと引き換えに受け取る貨幣額は、彼の名目賃金、すなわち価値によって評価された労賃の額をなしている。しかし、明らかに、労働日の長さが違えば、つまり彼が1日に供給する労働量が違えば、それに応じて同じ日賃金や週賃金などが非常に違った労働の価格を、すなわち同量の労働に対する非常に違った貨幣額を表わすことがありうる。だから、時間賃金ではさらに日賃金とか週賃金とかいう労賃の総額と労働の価格<時間当たりの平均価格>とが区別されなければならないのである。では、この価格、すなわち或る与えられた量の労働の貨幣<で計られた>価値は、どのようにして見出されるのか? 労働の平均価格は、労働力の平均的な日価値を平均的な1労働日の時間数で割ることによって、得られる。@
たとえば、労働力の日価値は3シリングで、これは6労働時間の価値生産物<新価値>であり、1労働日は12時間だとすれば、1労働時間の価格は 3シリング/12=3ペンス <1/4シリング>である。このようにして見出される1労働時間の価格は労働の価格の尺度単位として役立つ。
それゆえ、<時間当たりの>労働の価格は引き続き下がっても日賃金や週賃金などは変わらないこともありうる、ということになる。例えば通例の1労働日は10時間で労働力の日価値は3シリング<36ペンス>だったとすれば、1労働時間の価格は3・3/5ペンスだったわけである。それは、1労働日が12時間に延びれば3ペンスに、また1労働日が15時間に延びれば2・2/5ペンスに下がる。それにもかかわらず、日賃金や週賃金は元のままで変わらない。これとは反対に、労働の価格<すなわち1労働時間当たりの価格>は変わらないか、または下がりさえしても、日賃金や週賃金は上がることもありうる。例えば1労働日が10時間で労働力の日価値が3シリングならば、1労働時間の価格は3・3/5ペンスである。仕事が増えたために労働者が元のままの労働の価格で12時間労働するとすれば、彼の日賃金は今度は労働の価格の変動なしに3シリング7・1/5ペンスに上がる。同じ結果は、労働の外延量ではなくその内包量<労働の強度>が増大しても、生ずることがあるであろう。……
しかし、<労賃の>一般的法則としては次のようになる。日労働や週労働などの量が与えられていれば、日賃金や週賃金は<時間当たりの>労働の価格によって定まり、労働の価格そのものは、労働力の価値の変動につれて、または労働力の価格が労働力の価値からずれるのにつれて、変動する。反対に、<時間当たりの>労働の価格が与えられていれば、日賃金や週賃金は日労働や週労働の量によって定まる。」(同、P704~)
1労働時間当たりの労働の価格が、労働者が受け取る種々の「労働の価格」の大きさの尺度(=度量単位)となるということは、さほど問題ではないでしょう。この「労働の価格」の尺度となる「1労働時間当たりの労働の価格」、たとえば3ペンスは、労働力の日価値3シリングを1労働日の労働時間である12で割った商として表現できます。この尺度を用いれば、たとえば半日の労働日=6時間であれば、その労働の価格は18ペンス=1・1/2シリングであるとか、12時間の6労働日の労働の価格は3×12×6=18シリングであるとかのように計ることができる、ということもさほど問題ではないでしょう。
しかし、なぜ「労働の“価格“」が「労働力の“価値”」で計られ得るのか、がまず問題になるでしょう。それは、貨幣価値や生活手段価値の変動を無視すれば、1労働時間の“価格”は1労働時間の労働力の“価値”に等しいものとして現われるからです。言い換えれば、価格すなわち価値の貨幣表現は、平均をとればその価値に一致せざるを得ないからです。ここでは「労働力の日価値は3シリングで」、とあるように、実際上は「労働力の価値(支出労働時間)」ではなくて「労働力の価格」として論じられています。
しかしながらなぜ、「労働の」“価格”、つまり労働者が支出した総労働時間の“価格”が、「労働力の」“価格”、つまり労働力の再生産に必要な生活手段の“価格”との比較で、言い換えれば総労働の一部分でしかないの必要労働部分(支払い部分)との比較で表わされ得るのか、という疑問が起こるかもしれません。しかし、「労働の価値」とか価格というものは、すでに語られてきたように同義反復的な無意味な言葉であって、それは「労働力の価値」という客観的なものが資本主義的関係の中で現われる現象形態にすぎません。それが意味を持つためには、客観的な意味を持つ「労働力の価値」と比較する他はないのです。言い換えれば、労賃という現象形態も単に需給関係で決まるのではなくて、その大きさが決まるための客観的な背景(本質的関係としての労働力の価値)を持つのです。
(3.時間当たりの労働の価格が与えられたものとして現われ、それが労賃の基本形態となるならば、労働日は一定の労働時間とは無関係なものとして現われ、労働日に含まれる支払い労働と不払労働との関係はいっそう不明となる。それは、資本家が労働者にその日価値を支払わずとも一定量の剰余労働を獲得するための手段となり、また労働者の過度労働や過少就業の原因ともなる)
・「時間賃金の度量単位、1労働時間の価格<すなわち1時間賃金>は、労働力の日価値を慣習的な1労働日の時間数で割った商である。@
仮に1労働日は12時間であり、労働力の日価値は3シリングで6労働時間の価値生産物だとしよう。1労働時間の価格はこの事情の下では3ペンス<3/12=1/4シリング>であり、その価値生産物は6ペンスである。ところで、もし労働者が1日に12時間よりも少なく(または1週に6日よりも少なく)、たとえば6時間か8時間しか働かされないとすれば、彼は、この労働の価格では、2シリングか1・1/2シリングの日賃金しか受け取らない。彼は、前提によれば、ただ自分の労働力の価値に相当する日賃金を生産するだけのためにも平均して6時間労働しなければならないのだから、また、同じ前提によれば、どの1時間のうちでも1/2時間だけ自分自身のために労働し、1/2時間は資本家のために労働するのだから、もし彼が12時間よりも少なく働かされるならば彼は<自分のために>6時間の価値生産物を取り出すことはできないということは、明らかである。人々は、前には過度労働の破壊的な結果を見たのであるが、ここでは労働者にとって彼の過少就業から生ずる苦悩の源泉を見出すのである。
もし1時間賃金が、資本家が日賃金や週賃金を支払う約束をしないでただ自分が働かせたいと思う労働時間の支払いだけを約束するという仕方で確定されるならば、資本家は最初に1時間賃金つまり労働の価格の度量単位の算定の基礎になった時間より短く労働者を働かせることが出来る。この<1時間賃金という>度量単位は 労働力の日価値/与えられた時間数の労働日 という比率によって規定されているのだから、それは、労働日が一定の時間数のものでなくなれば、もちろん何の意味もなくなってしまう。支払労働と不払労働との関連はなくされてしまう。今では資本家は、労働者に彼の自己維持のために必要な労働時間を許すことなしに、労働者から一定量の剰余労働を取り出すことが出来る。資本家は、就業の規則性を全く無視して、ただ便宜や気ままや一時的な利害にしたがって極度の過度労働と相対的または全部的失業とを代わる代わる引き起こすことが出来る。彼は、「労働の正常な価格」を支払うという口実の下に、労働日を、労働者には少しも相応の代償を与えることなしに、異常に延長することが出来る。それだからこそ、このような1時間賃金を押し付けようとする資本家たちの企てに反対して、建築部門で働くロンドンの労働者たちのまったく当然な暴動(1860年)も起きたのである。労働日の法的制限はこのような無法に終末を与える。といっても、もちろん、それは機械の競争や充用労働者の質の変化や部分的恐慌や一般的恐慌などから生ずる過少就労に終末を与えるものではないが。」(同、P706~)
分かりやすく述べられているので、タイトルの他には説明は必要ないと思われます。
(4.労賃すなわち労働の価格という分配形態は、いつでも一定の不払労働を含んでいる)
・「この<ロンドンの製パン業者の>泣き言が興味を引くのは、資本家の頭にはどんなに生産関係の外観だけしか映じないものかをそれが示しているからである。資本家は、労働の正常な価格もまた一定の不払労働を含んでいるということも、この不払労働こそは自分に利潤の正常な源泉であるということも、知ってはいないのである。剰余労働時間という範疇は彼にとっておよそ存在しないのである。なぜならば、それ<剰余労働時間>は、彼が日賃金のなかに含めて<全労働時間を>支払っていると信じている標準労働日の中に含まれているからである。とはいえ、彼にとっても時間外労働、すなわち労働の通例の価格に相応する限度を越えた労働日の延長は、やはり存在する。しかも、彼の安売り競争者に対しては、彼はこの時間外労働に対する割増払をさえも主張するのである。彼はまた、この割増払も通常の労働時間の価格と同様に不払労働を含んでいるということも知ってはいない。例えば、12時間労働日の1時間の価格は3ペンスで、1/2労働時間の価値生産物であるが、時間外の1労働時間の価格は4ペンスで、2/3労働時間の価値生産物であるとしよう。前の場合には資本家は1労働時間のうちの半分<1/2>を、後の場合には1/3を、代価を支払わずに取り込むのである。」(同、P713~)
この点は前章ですでに述べたとおりです。
(17章の末尾に、「とにかく、労働の価値および価格または労賃という現象形態は、現象となって現れる本質的な関係としての労働力の価値および価格として区別されるのであって……」とあります。チューターは、認識論は資本論にこそ学ぶべきと常日頃思っているので、労賃を例にとって、第4章からこの章に至るまでの叙述において、現象とその背後にある本質的な関係とがどのように述べられているのか検討する予定でしたが、うまくまとまりませんでした。)