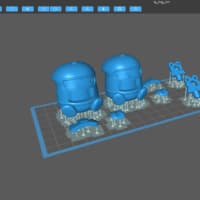自分はたいがいの場合、
案件に対して未知のスキルが必要であっても、
『面白そう』なら受けてしまいます。
3Dモデリング、Webデザイン、FLASH、サウンド
ゲームフローの作成とか...。
趣味程度で少しかじったものであれば、仕事はその延長。
未知の仕事に手を出す場合。
例えば液晶ゲームの案件があって、
『ドット絵制作』で携わっていれば、
どこかの業者が作った仕様書が手元に残ります。
この仕様書は宝物になります。
ノウハウの塊ですから。
次回は仕様書から担当できる算段がつきます。
結局『ゼロからイチ』の作業でなければ
『できる』と判断してしまう。
とはいえこの判断自体には、それなりにスキルが必要で、
なんでもかんでも流用できるわけではないし、
『同じような案件』が『全く違う案件』だったりもする。
ま、とはいえ『面白い』ものは受諾するのです(予算は意識するけど)。
最終的にできなきゃ、周りの誰かができるわけだし。
でもって、久しぶりにweb系の仕事をすることになったのだけど、
今更の理解なんだけど、
最近のwebページはCSSという技術を使っているようだ

このブログもまさにその技術そのもので、
デザイン情報を別データとして持っている。
各項目のレイアウトや、見出し・本文の文字のサイズ、
色や背景素材等...。
htmlでも設定できるのだけど、
ページが重複すると、全てのページにその情報を
書き込まなくては行けない。
これは...面倒だ。
ブログの場合クリスマスが近づけば、
『クリスマスバージョン』のフレームに着せかえたりできる。
全ページが着せかわる。
とっても簡単に。
確かにこれは技術として優れている

今更という感じだけれど、私がブログを始めた当初は、
何がすごいのか理解できなかった。
日記でしょ?日記は自分のwebページにあるし...。
と半信半疑で使っていたのだけど、
結果的に、いまやブログしか更新していないありさま。
ブログはユーザーの立場として『便利』なんです。
で、便利になっているということは、
そこに何らかの技術が盛り込まれている。
難解なものは、それを理解するのに知識を得なければ行けない。
知識を得る時点で、その技術をある程度理解できる。
結果そのスキルも身に付く。
逆に便利なものは、その便利さに依存しているわけで、
その背後にある技術やシステムを理解しようとは思わない。
で、CSSがスルーだった(おもいっきりユーザー目線だった模様)。
相変わらずのフレームで割ってーの、画像配置してーの、
たまにswf使って舞い上がってみーのといった感じ。
DW3どまり。
で、実際にCSSに直面して困っている。
CSSは、おもいっきりデザイナー視点だ

もう少し勉強しておけば良かったかな~...。