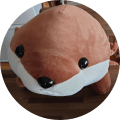◆石破さん
防災は良いかなと思った。南海トラフとか考えても必要だし。能登半島の復興が遅れたこともある。この付近も、災害あったらひどそうだからね。
そういえば、外国人観光客が地震とかに巻き込まれたらどうなるんだろうか。そのへんの保険とか。気になるよね。そういう細かいことやらんとあかんよね。
あと地方にも力入れてくれるのは良いかな。こないだ、東京のテレビ局のテレビ見てて、なんか、この程度の、仕事でお金もらってる人がいるんだ、というのと、こんな仕事で満足できるんだ?というのと、両方思った。
某フジテレビの件は、芸能人興味ないから書かなかったんだけど、夕方、テレビを付けたら『孤独のグルメ』以外すべてがフジをけちょんけちょんに言っていて、
井の中の蛙が喧嘩していて、無様だった。
仕事というのは、事に仕えると書くのだから、本当にそうであるのか、自身の良心に確認せねばならない。
また私は、慎太郎の堕落論を思い出したわ。
アメリカに対しては誰が総理でも同じことを言ったと思うから仕方がない。
そもそも、トランプさんどこまで務めるかわからんし。
概ね地味だけど全体的で良いのでは。
これ、野党にやらせると、1つだけに予算が偏ったりしそうだもんね。
アメリカの火災で、パックンのコーナーたまたま見たんだけど、そんな土地に住んでる方が悪いから自己責任でね、とかなりそうなの、すげー、さすがアメリカ。
そんなこと日本でやったらむちゃくちゃ叩かれそう。まぁでも、お金持ちの地域だから1つくらい別荘とかなくなっても大丈夫なのかも?と思った私はひどいですかね?だってスケール違いすぎるもん。
酒匂川があふれてもそのそばに工場建ててんのはおたくの会社の自己責任ですよ、って言われるようなもんだもんなぁ。びっくらぽんだわ。
日本人優しいよな。
そういえば、通り魔殺人で、この付近の警察からも応援とか一気に動いたのすごかったね。これからは、どこの都市というのではなく、日本の西で困っていたら東が助け、東が困っていたら西が助け、みたいなのが大事なのかもしれないね。
◆先生の仕事
昨日の授業参観の後にまた何やらあったらしいんだが、まぁそれは置いといて。先生方マジ大変。
PTAとかボランティアやってると、まぁまぁ主婦のできうる限界はやってるつもりなんだけど、その中でどうしてもできないところ、というのは、あって。それが、『先生』のお仕事なんだろうなと思うことはありました。親と子両方に働きかける。教育を学んでいる人ができること。それはね、先生でないとできないんだね。これが、習い事とか児童館でもできないことがあるんだ。
にぎやかな子の親さんも見たんですがまぁまぁ熱心に見ておられたのね。で、うちのクラスに共通してんのは、おそらく、オラオラ系の子はパパさんがオラオラ系なんだな。(うちのコ含む)
なので、先生はそれを把握した上での指導が必要になる。
年若い先生に自分の親に近い年齢(の人もいると思う)の保護者に対応しろというのは大変かもしれないけど。頑張ってほしいなと思いました。それがね、先生の仕事だから。
公立は死んだのか、というところで、そうではなく、やはりザワザワ感はあるのですが、高学年もそこそこうるさいみたいなので、棲み分けなんだろうなと思いました。
その中で、支援級と一緒に活動するのが、良いのか悪いのか、子供たちの表情を見ていると、この関わりがよい方向に向く子と、そうでない子が出てくるような気がします。なので、支援級で通常の学級に行きたくない子がいたら、私はそれでもいいんじゃないのかなと思います。(そのための教員等増員)
逆に、同じ時間を共有することでモチベーションが上がる子もいるかもしれませんから、それは個々の資質によるものではないかと思います。
単純に差別がよくないから支援級を一緒に、という考え方は乱暴で、支援級の子の立場に立っていない気がします。
好き勝手にできるとなれば、通常学級の子からしてみれば、何であの子は帰っていいのか、ということになるでしょう。
その、差異を親や教員等がどう話しているのか、というところは気になります。
こないだ、不登校の子の親のブログを読んでみたんですが、母親がやはり繊細でしたから、母親の価値観というものも影響はあるでしょうし、一人だけの考え方ではなく、様々なサイドからのアプローチが必要なのかなとは思います。
まー、ぶっちゃけリアルで友達おらん人は、子供もわりとそうなんで。リアルでママ友がうまくいってないところは、そういう現象も起きているのでは、と推測します。
私は同じ園の子にゆっくりめな子がいるのですが、子供にはこう話しています。
ゆっくりできるようになる子もいて、今はできなくても大人になればそんなに変わらんよ。って。
もちろん、それは、理想論で、現実的にそうでない子もいますが、子供にわかりやすく説明するには、大人ももっと勉強する必要があるのだと思いますし、私の今の認識ではそれが限界で。勉強不足なんだと思います。あと逆にね、支援級だから腫れ物に触るみたいな心根ではいかんと思うんですわ。
だから、公園で支援級の子を叱ったおじいちゃんのベースは、知らなかっただけで悪気があったとは私には思えないんですよね。
まぁ、プラスの気持ちがあれば何でもよくなるとは私も言いませんけど、世の中のちょっと『どうしようか』の気持ちが、『どうするのがこの場合いいんだっけ?』に変わるといいんじゃないかなぁと思いました。
わからないことは、支援級のママさんに聞いて対応したらいいのかなと思う。(もちろん、自分が勉強していればなお良いけど、なかなかそこまでできる人は少ないよね)
支援級の話しになってしまったけど、私が問題としているのはそこではなくて、
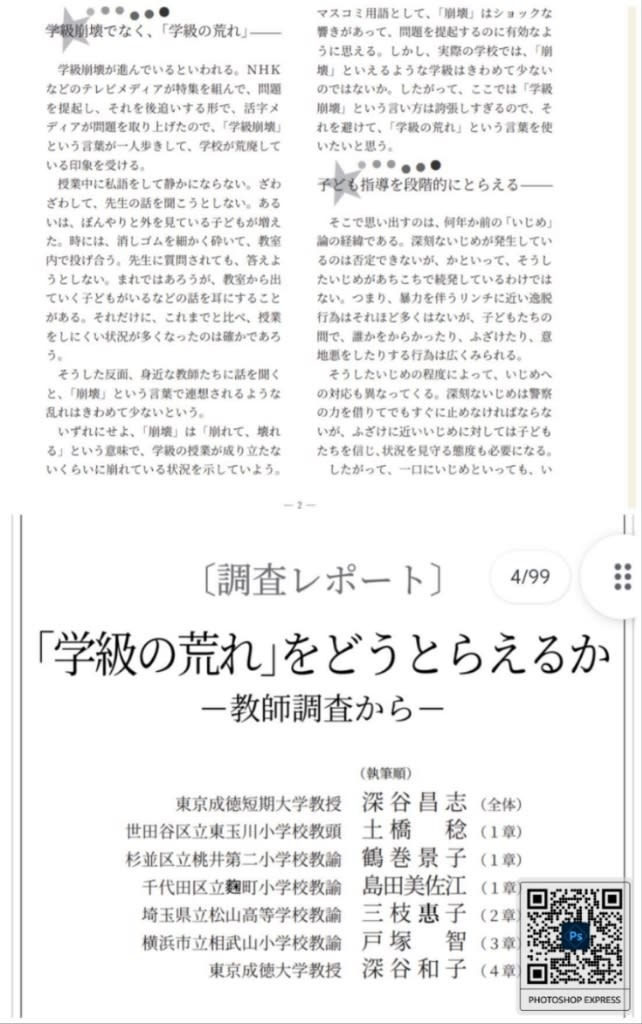
参考までに昔の資料を読んでみたんですけど、うーん。写真が結構昔なのと、有名人が松井とか出てくる時代なのであんまり参考にならないかなと思ったんですが、参考になったのは、
このアンケート内に書いてあるものが、小学4年生〜6年生なんですね。
ところが、そういう内容のことが、すでに2年生で現れている部分があって、考え方や感情表現、子供たちの内面が、昔よりずっと早い段階で発達あるいは、進化しているのかもしれない、ということを思いました。
なので、まだ2年生だから、可愛いもんだ、というのは本当にあるんでしょうけど、2年生、だからと、甘く考えてはいけないのだと思います。
うちの学校はPTAが簡易化されており、私も働くママさん達のためにかなり簡略化してきました。そのうえで、PTAは公立においては先生方と連携し子供たちを正しく親御さん達の理想を含んだ上で導いていくために、必要善と考えました。
他校のように、昔のようなやり方をしていては人は集まりません。(文句も出ます)
なので、時代と共に根本は変わらず、対応は臨機応変にすることが、教育の現場に求められていることで、そういった対応ができる学校がこれからも求められていくのではないかと思います。
何だか長くなってしまったけれど、やはり、教師には教師の尊ぶべきところがあるなぁと私が思ったものですから、学校に文句がある親さんもたくさんいるでしょうが、まずは、話してみて、まわりの親さんとも会話をするということが大事なのかなと思ったのでした。まぁ、会話拒否してる人もいますけどね。
私たち親が考えていくのは、常に子供たちの環境のことであって自分の主観でどこの親が嫌いだとか好きだとか、小さい世界に子供を縛り付けてはいかんのですよ。
ということがいいたい。
子供たちは世界に羽ばたける力をもっています。私は、自分の子供がそんなに出来がいいとは思っていませんが、うちの園長は子供たちを世界にって感じの人でしたから、私のような弱小な人もなんとなく、感化されているのかもしれません。
でも、子供たちをみていると、その小さな身体に大きな世界があるように思えるんですよね。だから、子供たちには、よい環境づくりをしたいのです。(もちろん、予算も限界もありますが)
なんか、色々グダグダ書いてしまって申し訳ないです。
世間の親さんはもっと頭脳明晰だと思うのですが凡人はこんな感じにとらえています、というのをメモっておきます。