それぞれの山河
―永遠の水面の光増す夢―
人は皆 山河に生まれ 抱かれ 挑み
人は皆 山河を信じ 和み 愛す
そこに 生命をつなぎ 生命を刻む
そして 終には 山河に還る
「山河」小椋桂・作詞 より冒頭部引用
今頃になって恐縮なのだが、小椋桂氏の「山河」、いい曲だと思う。なぜ今頃かといえば、当初耳に入ってきたころは、歌詞の一節「永遠の水面の光増す夢を河に浮かべたろうか」に背筋がゾクッときたが、一方、「あいするひとのめに、おれの山河はうつくしいかと」の一節にナルシスティックな違和感を覚え、直ちにCDを求めるまでの思いにいたっていなかったから。
最近、小椋さん本人が歌う「山河」をユーチューブで聞き、イメージが変わった。そこで遅まきながら、DCを買い、じっくり聞いたり、歌詞を目で確認したりしたところだ。たとえば「あいするひとのめに」は「愛する人の瞳に」であることを知った。「俺の山河」も「俺の個人的業績」というよりは「俺の歩んできた道のり」という自省的ニュアンスが作詞者の意図に近い気がしてきた。
「永遠の 水面の光 増す夢を河に浮かべたろうか」
「永遠の水面の光」とは神秘家やその研究者にとっては有名なイメージで、それは没我の境地で展開される意識内容、魂が還る意識の全体性、宗教家だと神からの恩恵、啓示など、意識の究極、超越的境位を表すイメージ。小椋氏はこの一節を書きたくてこの詩を作ったのかも。
かなり堅固な自我意識を時代のモードとしてもっている現代の我々にとって、「永遠の水面の光」は死後に魂が帰っていく究極の場所という意味合いが強い。その究極の全体性の地上端末として肉体に宿り、様々な経験を積んでいるのが生前の我々。その生涯が究極の全体性にどのような情報をもたらし、影響を残すか。その究極的なるものの予感として、少なくとも地上端末として在るとき、我々が自ら感得できる我々の生涯を貫く価値基準のひとつは「美」なのかもしれない。
「水面の光増す夢」
素粒子理論的に言えば、光、即ち光子はボーズ粒子であり、同じ位置に無限に同時存在できる性質をもっている。即ち光の輝きには限度がない。では、意識覚醒の究極的イメージである光る水面、あるいは一在的に躍動する生ける時空連続体的な水面の「光を増す」とはどんなことなのか。それは輝きに乏しい物質群に輝く時をもたらすことなのだろうか。自由で全方位的な躍動状態から定常波的ループ構造に落ち、全体との親和性が低下している物質群に再び共鳴的創造的躍動を喚起し、輝きをもたらすことではなかろうか。各々離散的に存在する物質群の持つ物質的特性を、より広い物質群との交響的共鳴、共存へと結び、美しいタペストリーを織り上げること。固有性を維持しながら、自由に他と交わること。固有の振動数を獲得し、安定し、慣性をもち、重力と反応する物質群の、その安定性を維持したままに、全体との共鳴を喚起し、調和的に共存させしめること、これが「永遠の水面の光を増す夢」を河に浮かべることではないか。
こむずかしい概念が並んでしまうが、要は、たとえば、路傍の紙片を砂丘の砂粒のごとく放置せず、ごみ箱に導き、資源リサイクルの循環の輪に復帰させること。こういった些細でありながら勇気のいる行為が美しい行為であり、永遠の水面の光を増すことなのではないか。物に問いかけ、物に命をあたえること、物に形と機能を与えること、意識の海に浮かべること。物を慈しむこと。物を厭離すべき汚れた存在とせず、人生の伴侶として慈しむこと。そして、これは「物」だけでなく「事」においても同様だろう。この世にあることで出会う様々な浮世事、その全体としてのこの世の生そのもの、これを苦として遠ざけるのではなく、苦は苦として味わい、快は快として味わうこと。
固有であり自由であるという一見対立する特性を調和させる比ゆ・メタファーに相応しいのは人の持つ「私」という概念の固有性と開放性である。このユニークな創造物を地球はいかにして獲得したのか。これを直感的に理解するために、再びメタファーを援用し、自己意識を可能にしている生命現象に学びたい。
私が私としての慣性と安定性を維持しているのは、肉体的自己の安定性に拠っている。では生物体としての自己同一性を生物はどう獲得し、維持しているのかといえば、重要なのは、高度な生命維持機能であるところの免疫機能である。これにより、生物は環境との複雑で高度な動的平衡状態を維持している。
意識の起源は生命にある。自意識の母は免疫学的生命維持機能であると推測する。即ち、生命体としての私が環境との絶えざる動的交渉にあることを起源として、自意識が生まれてきていると推測される。この免疫における生命の自己同一性維持原理、即ち免疫学的「自己」維持の原理は明確である。免疫的自己とは「非自己でないもの」である。一個の生物体を維持している膨大な物質循環、新陳代謝の機能と共存ができないものは、自己ではない「他」として排除される。即ち、自己に組み込めない「他者」は抗原抗体反応でもって体内から排除される。排除されるのは、免疫的自己と共存できない免疫的非自己である。そして逆に、非自己として排除されることのない物質群は生体内に取り込まれ、個体内の物質循環と共存し続ける。「非自己ではないもの」として、自己を構成する要素となる。「Aとは非Aではないものである」という二重否定が生命において動的平衡を維持し、新たな環境への適応を可能にしている。開かれた自己の起源は開かれた免疫機能にある。
我々の自己も同様である。私とは非私ではないものであり、この二重否定となる定義の開放性が自由という意識を生んでいる。因みにこの二重否定は宇宙の存在自体にも関わっていると推測する。「ゼロとは非ゼロではないものである」「ゼロとは1ではないものである」といった定義が時間軸を産み、時空の開闢を可能にしたのではなかろうか。
「AはBである」という硬直した定義には自由の発生する余地がない。それに対して、Bが「非Aでないもの」かどうかは直ちにはわからない。空間的直感だけではなく、時間的経過をみなければならない。たとえば、この異物が食えるかどうは実際に食べてみないことにはわからない。しかも体に悪いかどうかは直ちにはわからない場合もある。
ヨウ素と放射性ヨウ素を区別する免疫能力を生物は獲得していない。なぜなら、生命の長い歴史において放射性ヨウ素など遭遇することはほとんどなかったからだ。3.11以前にはヨウ素は有用で無害な物質として生体に蓄積され、利用されてきた。ヨウ素は生物学的な免疫学的自己を構成することの可能な原子であった。仮に放射性を出し続けるヨウ素が自然界に高頻度で存在していたならば、生物はヨウ素を生命活動と共存できる元素とはみなすことができず、ヨウ素の代わりになる元素を利用してきたことだろう。
生命体は二重否定原理によって固有の構造という緻密な拘束性と自由を共存させている。我々の自己もおそらくは同様の原理で、他者と共に世にありつつ、自由と自覚される開放を感じている。経験によって自己を形成し、様々なきめ細やかなきまりや法則性を自己と共存する原理として許容し、しなやかな自己を練り上げている。身体が絶えざる免疫学的交渉によって自己を維持しているように、我々は経験により自己を作り上げ、自己を発見、自己を創造している。この経験へと開かれた自己存在の様相を我々は自由と呼んでいる。その意味で、自由な社会とは安定した法治国家においてしか実現しないと考えたほうが確実である。禁止則が網の目のように張り巡らされた場にあって、その禁止則をすべて習得した時、人は自由を獲得できる。みんなが交通ルールを守って走行する道路と誰も交通ルールをまもらない道路でどちらが車を快適に乗り回せるかは自ずから明らかである。
場に張り巡らされている多くの禁止則をすべてマスターしたとき、我々は自由にその場でふるまうことができる。それはフィギアスケーターのあの自然な滑りが長期的訓練により獲得されることと似ている。そしてそのプロセスを経て、はじめて自発的で創造的な自由な行為が可能になる。いわば、この宇宙に存在する「理」を自らの拠る「理」として許容することにより、我々は宇宙の自由な住人となる。この理をわきまえ、自己を構成する要素としたうえで、なお開かれている無限の可能性を探求すること、より美しい宇宙へと宇宙を創造していくこと、宇宙の創造行為の先端として宇宙創造に参加すること。それが「永遠の水面の光を増す夢を河に浮かべること」ではないだろうか。苦行的学習を許容し、自然に、軽やかに、美しく。苦と快とは同じ紙面の裏表である。苦を苦と許容したとき、快は快として全的に訪れる。
―ふと想う 悔いひとつなく 悦びの
山を築けたろうか
くしゃくしゃに 嬉し泣きする かげりない
河をいだけたろうかー
(小椋桂 作詞 「山河」より引用)
結局、世界として我々が許容し、ともに生きているものたちとは、自己を構成する要素の裏返し、ゲシュタルトチェンジにおける、図と地の関係にあるものたちである。とすれば、机上のキーボードに「あなた」という態度で接することができたとき、路傍の芥に自己の影を思うことができたとき、我々の肉体を含む「固有の慣性をもつ物体たち」は、「時に、全体性の海へと喜んで飛び込み、時に、再び固有性へと回帰する」、という勇気を獲得するのかもしれない。愛がベースにあるときにのみ自己否定の勇気が可能となるのではないか。そのとき、「肉体次元を意志的に還元し、永遠の水面に回帰し、再び肉体次元の固有性に回帰する」という夢のような自由度を人は獲得できるのかもしれない。これは聖者の神秘体験と似ているし、テレポーテーションと呼ばれている能力とも似ている。これが特殊な個人の特殊な体験ではなく、地球に棲む人すべてが共有できるごく普通の経験となる時代、それが弥勒時代と呼ばれる時代かもしれない。
関連で付け加えれば、顧みられることなく隅に捨てられた紙片は銀河系の情報ネットワークから切り離されている天の川銀河系の辺縁の惑星、地球に似ている。
「二階の鐘樓一宇。
廿(二十)釣の洪鐘一口を懸ける。
右に、一音の覃所(たんしょ)は、千界に限らず、苦しみを抜きて、樂を興
え、普ねく皆平等なり。官軍と夷虜(いりょ)の死の事、古来幾多なり。毛
羽鱗介の屠(と)を受けし、過現無量なり。精魂は、皆他方の界に去り、骨
は朽ち、猶もって此土の塵となる。鐘の聲(ね)の地を動かす毎に、冤霊(え
んれい)をして、浄刹(じょうさつ)に導かさしめん。」
(「中尊寺落慶供養願文」より引用)
およそ千年前に奥州の地に安倍の血を引く藤原清衡が大乗仏教的知を基盤として平泉中尊寺を建立した。その際にその建立精神を述べた「中尊寺落慶供養願文」には敵味方の戦死者の魂だけではなく、人間により生命を落とした生きとし生けるものすべてを浄土に導くことが目指されている。全衆生が救済されない限り、自己の救済はありえない、とする古の大乗的仏教思想。そしてその日本的展開としての清衡の「生きとし生けるものすべてを浄土に導く」という浄土平泉の思想。その思想の延長上にある究極的思惟は全物質を済度せんとする弥勒の思惟である。その意味で、弥勒は究極の未来仏である。この未来仏が到来する時は仏教的には56億7千万年後といわれている。いつから数えて56億7千年後なのか。現代科学の知見では宇宙が誕生してから137億年、太陽系の年齢は46億年だという。
因みに核力による物質の崩壊、エネルギー化は物質の固有性自体を消滅させる技術である。エネルギーへと変換されてしまう物質たちは再び物質としての安定性と固有性を獲得することはない。彼らはエンタルピーとエントロピーのしじまのなかに消えていくのみである。仏教的概念で語れば、成仏せずに不浄なる存在のままに消されていく存在と比喩できる。この技術によりいわば「屠を受けし」物質たちを浄土に導く「鐘」は少なくとも現在の地球にはなく、生命原理と共存できない放射能を帯びた塵芥が山河を汚し続けている。人間活動への貢献により核廃棄物化した物質群を汚いものとして封じ込めたまま、次世代に遺していく営為は私には美しい行為とは思えない。他に糧を得る方法があるのであれば、そちらを選択することが人間的英知だろうと私は思う。経済性などというその場しのぎの甘言により見切り発車することと、刹那的ゲーム遊びに興ずる子供とに違いなどない。
こういった思考展開を許容するような哲学や宗教領域における究極的なイメージを歌に乗せてしまう小椋氏の醒めた感性はすばらしい。そして、そもそも「うた」とは古来自己の内と外にできた電位差を解放するスパーク、ささやかな発光現象だったはずで、小椋氏のうたづくりは古来のやまとうたの伝統を引き継いでいると言える。
「愛する人の瞳に俺の山河は美しいかと」
「愛するひとのめ」の「め」は目でも眼でもない瞳。自己と他者の明確な区別を前提とし、鋭い視線が交差し、主観と客観の対峙のかまびすしい「目」ではなく、瞳である。あたかもブラックホールのごとき無限のキャパシティで光を受け入れる瞳。
ナルシスティックな思いというのは主客峻別の誤解から生まれる妄想である。自己とは非自己でないものでしかなく、自己陶酔とはループ構造に落ち込んだなにものかのショートした幻想である。
「自分の輝かしい業績」といった妄想を連想させる「俺の山河」のギラツキと偏光は、しかし、「俺即ち自己」の座標をひとつ上げてしまうと、透明感がまし、違和感が薄れる。たとえば、「山河」とは「個人的業績」ではなく、故郷の究極である「地球そのもの」とみなす展望点に上昇してしまうというテクニックである。「俺の山河」とは「地球」のことだとしてしまう。とすれば、「自己」を見守る「愛する人の瞳」とは、広大な天の川銀河を共に旅する恒星、永遠の伴侶、即ち太陽となる。その地平に立つならば、「愛する人の瞳に俺の山河は美しいか」という一節は「永遠の伴侶たる太陽からみたときに、地球はより美しくなったろうか、美しく映るだろうか、という意味を持ってくる。「俺の山河」の「の」は所有を意味する言葉ではなく、「私の故郷」といった使い方、所属を意味する言葉となる。
もうひとつスケールを上げて、「愛する人の瞳」を「天の川銀河の中心・グランドサン」としたときには、「俺の山河」とは太陽系が属する天の川銀河全体となる。グランドサンという瞳にみえてくる光景、それは地球を含むこの太陽系全体を山河として生きる意識体にしかわからない光景だろう。それは、太陽がグランドサンを一周する2億2千6百万年を一年の年月として刻む意識体である。これはある意味、我々の抱く時間意識とは違ったスケールである。
とはいえ、その超大な時間軸を理解不能として把握不可能ととらえるのは早計ではないだろうか。掴むのではなく、触れること。比ゆ的イメージを抱くことは可能ではないか。物質の総体としての宇宙がフラクタルな構造をもっているとすれば、グランドサンと太陽との関係は太陽と地球との関係にフラクタルダウンできる。太陽を鏡として地球生活をおくることができているならば、それは同時に銀河中心と太陽との関係にもふれる境位となりえるだろう。太陽意識の境位に生きること。
因みに、この太陽意識をもって地球に棲まうとき、地球という惑星環境はどう把握されるのだろうか。太陽と月が同じ大きさとなって見える絶妙の均衡点にある惑星。その惑星の表面に非常に薄い水圏と大気圏をまとい、そこに無数の炭素ベースの生命体を抱えている地球。これは決して偶然の賜物ではない、との直感は素直で自然であると私は思う。宇宙全体を貫く何等かの意志的意識の存在が予感され、それが永遠の水面とイメージされるとすれば、それはそれでリーズナブルだろう。あたかも永遠の水面が地球に流れ込み、地球という山河を抱き、慈しみ、命を産み、刻み、うたかたの夢をその表面に描いているが如き印象を受ける。この星の在り様は意識的営為の極み。美しさが満ち溢れている。天の川銀河の中心で輝くグランドサンからみるならば、銀河の水面に一瞬結ばれ、浮かび消える泡沫のごとき一瞬の輝きと映るのではなかろうか。それは幼子が戯れに飛ばすシャボン玉のように美しく、はかない。シャボン玉のあの危うい薄さは地球における水圏大気圏の薄さに似ている。シャボン玉が日の光を受けて美しく輝くように、地球は太陽の光を浴びて、七色に輝く。銀河はこの一瞬の輝きを放つ泡沫にかくも美しい衣をまとわせてくれている。おそらく、美にとっては永遠も瞬間もない。永遠即瞬間。4次元時空連続体(特にも時間軸)に垂直に差し込む光のごとき存在が美。その意味で美は5次元的な存在である。
蛇足を覚悟で加えるならば、天の川銀河のセントラルサンからみれば、太陽のまわりを公転している地球は螺旋軌道を描く自転球体である。この球体表面に展開している生命圏はその全体が4次元時空連続体に垂直に差し込む生命次元の射影ともいえ、その意味では生命自体が5次元的存在である。
ひとは世に在ることを宿命としている。そこで時を重ね、何らかの軌跡を残す。その軌跡のうち重く沈殿していく分画を「山」と呼び、軽く流れていく分画を「河」と呼ぶ。もしくは、世と人との交渉において空間的形象を残すものを「山」と呼び、時間的軌跡を描くものを「河」と呼ぶことも可能だろう。とすれば、「山河」とは「私の生涯」という4次元的断面に刻まれた四次元的な結晶体のことである。この時空結晶体の意味での「山河」は美しいか、という問い。この問いは四次元結晶が第五の次元である美の次元にどう写像されているかを問う五次元的位相幾何学の問題を提起していることになる。この問いの純粋理性的な解釈は難しいのかもしれないが、実践理性的回答は充分に可能と思う。具体的には、その山河を美しく残すということは、自分のすまいを美しく保ち、行住坐臥を美しく保つことであろう。苦を苦として許容し、快を快として享受し、自然に、軽やかに、そして美しく。
古来、日本において、美とは単に空間的造形物として鑑賞したり、時間的造形物として音楽鑑賞の時を持ったりするだけではなく、生ける現実世界に展開され、日常化されるものであり続けてきている。そしてお茶をたてたり、花を活けたりする日常的行為において時空的に美しく結晶化させることを「道」として大切にされてきている。きわめて五次元的な営みである。
その永遠の今を美しく生きる行住坐臥とは、不断の自己開放、自己探求の痛みを受容することで実現される苦行でもある。快と苦はもともと同じ事態の裏表、透明な白色光のプリズム分光によりあらわれる赤と青のようなものなのだ。苦を快とし、快を苦とする境位に立つとき、我々は光となって輝くことができるのかもしれない。太陽意識とは、そしてその先の銀河意識とはこの光の境位にふれことができる美しき意識のメタファーではなかろうか。
3.11と平泉世界遺産登録を同時に経験した東北の山河にて










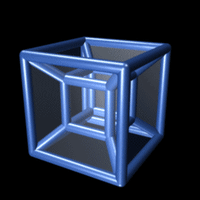




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます