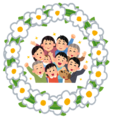成年後見制度とは、認知症などにより意思表示ができなくなった方(例えば高齢者)のために、
その高齢者の代理人として、入所施設などの契約や預貯金などの財産の管理を行う成年後見人を選ぶものです。
その成年後見制度の利用を検討する際の留意点を3つご紹介します。
①家庭裁判所に申し立てた後に取り下げはできない。
②後見が開始した後に制度利用をやめることはできない。
③予定していた後見人候補者が後見人に選任されるとは限らない。
少し詳しく見ていきます。
①家庭裁判所に申し立てた後に取り下げることはできない。
成年後見制度を利用するためには、家庭裁判所に申立書を提出します。
この申立書を提出した後に、親族の都合などでその申し立てを取り下げることはできません。
成年後見制度は、あくまで、認知症などになった高齢者のため、高齢者を保護するためのものなので
親族の都合によって後見制度の利用の可否を判断することはできないためです。
むしろ、後見制度を利用しなければならない可能性があったにもかかわらず、親族の都合で取り下げる
ということは、親族の意向に反してでも高齢者を守るために後見制度を利用したほうが良いのではないか、
と考えることもできます。
後見制度の申し立ての判断は慎重に行ってください。
②後見が開始した後に制度利用をやめることはできない
これは後見が開始した後の話です。
後見は、ある目的のために申し立てられることが多いです。
例えば、遺産分割協議のためだったり、不動産の売却、高齢者施設への入所等です。
後見制度はその目的のためというよりは、高齢者のため、高齢者を守ってより良い生活を送ってもらうためのものです。
そのため、申し立ての目的を達した後も、後見制度をやめることはできません。
基本的には、亡くなるまで後見制度は続くことになります。
この点に関して付随する課題は、コストです。
親族が後見人であれば報酬は発生しませんが、司法書士等の専門家が後見人となった場合、一定の報酬が発生します。
この報酬は年に1回、裁判所が決定します。
報酬額は、業務内容や財産額等によって異なるようですが、目安としては月額あたり2~3万円、年額だと
20~40万円のことが多いようです。
このコストが亡くなるまで生じることになります。
③予定していた後見人候補者が後見人に選任されるとは限らない。
後見制度を申し立てる際に、申立書に後見人候補者を記載することができます。
ただし、後見人を決定するのは家庭裁判所です。
必ずしも候補者が選任されるとは限りません。
財産額が大きかったり、親族が対立しているなどの事情がある場合は、
候補者に親族の後見人を記載していても、専門家後見人が選任されることがあります。
なお、専門家が選任された場合、やはり報酬というコストは発生します。
上記②と同じような金額が必要になります。
また、専門家が選ばれたとしても後見をやめることはできません。
なぜなら、高齢者のためには専門家を後見人として選任したほうがよいと家庭裁判所が判断したからです。
後見制度の趣旨は、高齢者のため、高齢者の保護です。
決して、高齢者が認知症などになったために親族が困ってしまっている課題を解決するための制度ではありません。
その点をしっかりと認識して制度利用を検討されることをお勧めします。
その高齢者の代理人として、入所施設などの契約や預貯金などの財産の管理を行う成年後見人を選ぶものです。
その成年後見制度の利用を検討する際の留意点を3つご紹介します。
①家庭裁判所に申し立てた後に取り下げはできない。
②後見が開始した後に制度利用をやめることはできない。
③予定していた後見人候補者が後見人に選任されるとは限らない。
少し詳しく見ていきます。
①家庭裁判所に申し立てた後に取り下げることはできない。
成年後見制度を利用するためには、家庭裁判所に申立書を提出します。
この申立書を提出した後に、親族の都合などでその申し立てを取り下げることはできません。
成年後見制度は、あくまで、認知症などになった高齢者のため、高齢者を保護するためのものなので
親族の都合によって後見制度の利用の可否を判断することはできないためです。
むしろ、後見制度を利用しなければならない可能性があったにもかかわらず、親族の都合で取り下げる
ということは、親族の意向に反してでも高齢者を守るために後見制度を利用したほうが良いのではないか、
と考えることもできます。
後見制度の申し立ての判断は慎重に行ってください。
②後見が開始した後に制度利用をやめることはできない
これは後見が開始した後の話です。
後見は、ある目的のために申し立てられることが多いです。
例えば、遺産分割協議のためだったり、不動産の売却、高齢者施設への入所等です。
後見制度はその目的のためというよりは、高齢者のため、高齢者を守ってより良い生活を送ってもらうためのものです。
そのため、申し立ての目的を達した後も、後見制度をやめることはできません。
基本的には、亡くなるまで後見制度は続くことになります。
この点に関して付随する課題は、コストです。
親族が後見人であれば報酬は発生しませんが、司法書士等の専門家が後見人となった場合、一定の報酬が発生します。
この報酬は年に1回、裁判所が決定します。
報酬額は、業務内容や財産額等によって異なるようですが、目安としては月額あたり2~3万円、年額だと
20~40万円のことが多いようです。
このコストが亡くなるまで生じることになります。
③予定していた後見人候補者が後見人に選任されるとは限らない。
後見制度を申し立てる際に、申立書に後見人候補者を記載することができます。
ただし、後見人を決定するのは家庭裁判所です。
必ずしも候補者が選任されるとは限りません。
財産額が大きかったり、親族が対立しているなどの事情がある場合は、
候補者に親族の後見人を記載していても、専門家後見人が選任されることがあります。
なお、専門家が選任された場合、やはり報酬というコストは発生します。
上記②と同じような金額が必要になります。
また、専門家が選ばれたとしても後見をやめることはできません。
なぜなら、高齢者のためには専門家を後見人として選任したほうがよいと家庭裁判所が判断したからです。
後見制度の趣旨は、高齢者のため、高齢者の保護です。
決して、高齢者が認知症などになったために親族が困ってしまっている課題を解決するための制度ではありません。
その点をしっかりと認識して制度利用を検討されることをお勧めします。