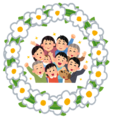前回の続きで、まずは、休眠担保は残っていたら問題なのか問題について。
答えは、問題ありです。
一番問題になるのが、休眠担保がついた不動産を売却するときです。
休眠担保とは言っても、抵当権です。
抵当権とは、もしかしたら債権者が競売を申し立てるかもしれない権利です。
そのような抵当権がついている不動産を買う人は、少なくとも一般の人はいません。
もう使用済みの抵当権です。大丈夫です。といったところで、だったら、抹消してから売ってください
と言われてしまします。
したがって、少なくとも売却の際は問題となり、抹消しなければなりません。
では、抹消してしまえばいいのではないか問題に移りますが、
その答えは、抹消しなければならないが、手続き的にそれがなかなか難しい、です。
抵当権の抹消登記手続きは、「不動産の所有者」と「債権者」が一緒に手続きをする必要があります。
簡単に言えば、申請書類に「不動産の所有者」と「債権者」のハンコが必要になります。
例えば、住宅ローンを完済した際に抵当権を抹消する場合は、マイホームの所有者と銀行ということなります。
そして、休眠担保も抵当権ということには違いはないので、同じように手続きをする必要があります。
ここで、田舎のおじいちゃんが先祖代々住んでいる実家をイメージしてください。
先祖代々、長男が守ってきた土地・家屋です。
一応登記はされていますが、これまでは当然に長男が継ぐものとされていましたから、相続登記(名義変更登記)などはされていません。
しかし、時代の波として、土地・家屋の売却話が持ち上がりました。
そこで、改めて登記簿を確認してみると・・
不動産の所有者 大正時代のご先祖様
抵当権者 まったく知らない〇山権兵衛という個人名
所有名義は、先々代くらいのおじいちゃんかと思いますが、そのほかに債権額10円でまったく知らない〇山権兵衛という債権者の
抵当権が設定されていました。
そして、不動産業者から、不動産の所有名義を現在の所有者さんに変更してもらうのと同時に、抵当権も抹消してくださいと
いわれました。
これが休眠担保の典型的なイメージです。
抵当権の抹消には「所有者」と「債権者」のハンコが必要になります。
当然、亡くなった方はハンコが押せませんので、ハンコが押せるように、登記名義を相続人に変更しなければなりません。
ここがとても難しい場合が多いのです。
所有者についても、簡単とは言えませんが、それでも身内ですから何とかできそうです。
一方、債権者(抵当権者)は、まったく心当たりがありません。
昔(戦前)は、個人からの借金も普通にあったようですが、この債権者も亡くなっていますので、ハンコをもらうためには
この債権者の相続人も探さなければなりません。
これが、休眠担保(権)の概要です。
かなりかみ砕いた書き方をしましたので、正確なところは、別途お問い合わせ等していただければと思います。
休眠担保を見つけたら、専門家にご相談されることをお勧めします。
答えは、問題ありです。
一番問題になるのが、休眠担保がついた不動産を売却するときです。
休眠担保とは言っても、抵当権です。
抵当権とは、もしかしたら債権者が競売を申し立てるかもしれない権利です。
そのような抵当権がついている不動産を買う人は、少なくとも一般の人はいません。
もう使用済みの抵当権です。大丈夫です。といったところで、だったら、抹消してから売ってください
と言われてしまします。
したがって、少なくとも売却の際は問題となり、抹消しなければなりません。
では、抹消してしまえばいいのではないか問題に移りますが、
その答えは、抹消しなければならないが、手続き的にそれがなかなか難しい、です。
抵当権の抹消登記手続きは、「不動産の所有者」と「債権者」が一緒に手続きをする必要があります。
簡単に言えば、申請書類に「不動産の所有者」と「債権者」のハンコが必要になります。
例えば、住宅ローンを完済した際に抵当権を抹消する場合は、マイホームの所有者と銀行ということなります。
そして、休眠担保も抵当権ということには違いはないので、同じように手続きをする必要があります。
ここで、田舎のおじいちゃんが先祖代々住んでいる実家をイメージしてください。
先祖代々、長男が守ってきた土地・家屋です。
一応登記はされていますが、これまでは当然に長男が継ぐものとされていましたから、相続登記(名義変更登記)などはされていません。
しかし、時代の波として、土地・家屋の売却話が持ち上がりました。
そこで、改めて登記簿を確認してみると・・
不動産の所有者 大正時代のご先祖様
抵当権者 まったく知らない〇山権兵衛という個人名
所有名義は、先々代くらいのおじいちゃんかと思いますが、そのほかに債権額10円でまったく知らない〇山権兵衛という債権者の
抵当権が設定されていました。
そして、不動産業者から、不動産の所有名義を現在の所有者さんに変更してもらうのと同時に、抵当権も抹消してくださいと
いわれました。
これが休眠担保の典型的なイメージです。
抵当権の抹消には「所有者」と「債権者」のハンコが必要になります。
当然、亡くなった方はハンコが押せませんので、ハンコが押せるように、登記名義を相続人に変更しなければなりません。
ここがとても難しい場合が多いのです。
所有者についても、簡単とは言えませんが、それでも身内ですから何とかできそうです。
一方、債権者(抵当権者)は、まったく心当たりがありません。
昔(戦前)は、個人からの借金も普通にあったようですが、この債権者も亡くなっていますので、ハンコをもらうためには
この債権者の相続人も探さなければなりません。
これが、休眠担保(権)の概要です。
かなりかみ砕いた書き方をしましたので、正確なところは、別途お問い合わせ等していただければと思います。
休眠担保を見つけたら、専門家にご相談されることをお勧めします。