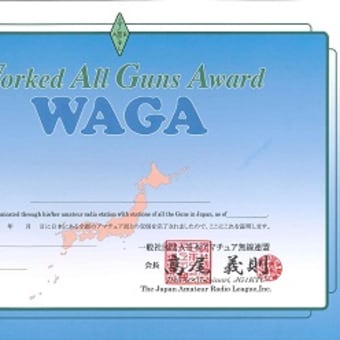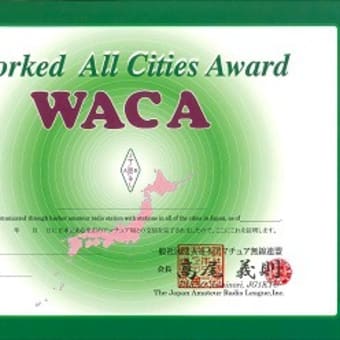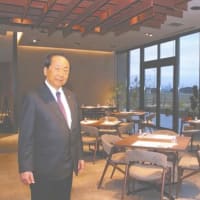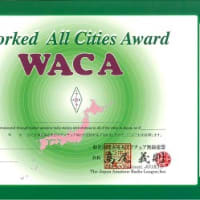近江は日本茶の発祥地である。比叡山を開山した伝教大師こと「最澄」が唐より持ち帰った茶の種子を比叡山麓、大津・坂本の地に播いたと言われる。
その中で今日、近江茶として土山茶、朝宮茶、政所茶が有名だが「膳所茶」(ぜぜちゃ)は、幕末に日本初めての対米輸出品となった緑茶があった。

膳所茶の歴史
江戸時代、近江の大津・膳所藩領内の山手の柿ヶ坂で良質の茶を産出していた。
江戸時代、近江の大津・膳所藩領内の山手の柿ヶ坂で良質の茶を産出していた。
嘉永6年(1853年)、浦賀にマシュー・ペリー率いる黒船が来航した際、幕府の全権林大学頭とその随行員5名がペリーの船室に招待された。ペリーから「貴国においてはコーヒーのような飲み物はないのか」と言われた際、随行の一人に膳所藩の儒者関藍梁(関研)が所持していた自藩の産品の茶を饗したところ、大変気に入られ、「貴国の生糸とこの茶が欲しい」と望まれた。
使命が終えた藍梁は、藩主に茶の生産を奨励することの必要性を説いた。それをきっかけに、元藩士の太田重兵衛に宇治で茶の製法等を習得させ、藩内での製茶に成功したため藩の御茶司に任命した。
更に、当時原野だった園山の十三町歩の土地を開墾し、藩の特産品に仕立てた。信楽焼の茶壷に入れて神戸、横浜から輸出し、初の対米輸出品となった。
そんな「膳所茶」は明治になっても生産を続けていたが、お茶の価格暴落や大規模な茶園が全国で開発されていったことから明治の終わりころには生産は中止されてしまいった。
その「膳所茶」を復活させて、膳所の名物にしようと取り組んでいるのが、膳所本町駅前の茶舗「富永園」だ。
富永園の富永良晴さんが、甲賀市朝宮の農家と契約栽培している膳所茶は、一般的なお茶の品種「やぶきた」ではなく、日本古来の品種である在来種を有機減農薬で加工している。
富永園の富永良晴さんが、甲賀市朝宮の農家と契約栽培している膳所茶は、一般的なお茶の品種「やぶきた」ではなく、日本古来の品種である在来種を有機減農薬で加工している。
富永さんの願いは、在来種の野生的で懐かしい香りが、膳所のまち興しにつながること。膳所の名物復活への取り組みが広がることは、膳所に元気を取り戻す大きな力になりそうだ。
黒船と膳所茶のお話(富永園茶舗)