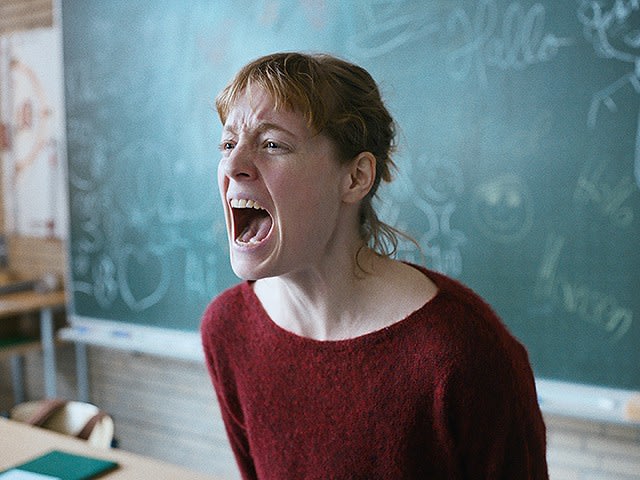映画「パンチ野郎」を名画座で観てきました。

映画「パンチ野郎」は1966年(昭和41年)公開の黒沢年男主演の東宝映画。いつも通り藤本真澄がプロデュースで、監督は「エレキの若大将」の岩内克己が引き続きメガホンをとる。実はこの映画の存在自体を知らなかった。名画座の特集で気付いた。dvdもない。主役の黒沢年男のWikipediaにもこの映画の記載がない。でも、東宝が黒沢年男を売り出そうとする試みが感じられて、星由里子も出演する。でも、加山雄三の恋人イメージを崩さないように、黒沢年男の先輩キャメラマンに過ぎない。
いかにも昭和の東宝コメディで、ストーリーはどうってことない。
若者の恋愛が二重三重に絡まる。
黒沢年男はキャパのようになりたいカメラマン、そのポン友が名脇役の砂塚秀夫、黒沢年男の妹役が後の加山雄三夫人の松本めぐみ。松本めぐみが好意を寄せる黒沢の友人でカーレースにのめり込む若者が和久田龍。黒沢年男の幼馴染で銀座のメンズショップの店員が沢井桂子で、沢井には和久田が好意を寄せる。
内田裕也が和久田のカーレースのライバルになる金持ちの息子で、内田は沢井桂子にも入れ込んでいる。星由里子は雑誌社のカメラマンで、黒沢年男の先輩になる。女性ドライバーで黒沢に入れ上げる高利貸しの娘藤あきみと黒沢年男と砂塚俊夫が通うバーの女性斎藤チヤ子が恋愛相関関係に絡んでいく。
1966年(昭和41年)の東京の熱気が伝わる掘り出し物の映画だ。
見どころが実に多い。ストーリーよりも背景を楽しむ。
映画が始まる前に、日産自動車とVANジャケットが協賛という表示が出る。ファッションはIVYルック全盛時代で、銀座4丁目の三愛にメンズショップがある設定だ。男性陣はアイビールックに身を包む。石津謙介のほくそ笑む顔が目に浮かぶ。車はハコ型フェアレディが全面的に登場する。
主人公黒沢年男が昭和41年の銀座の街を写真を撮りながら歩き回る。勤める雑誌社は平凡パンチの編集部を意識して、たまり場はオレンジ色の銀座線が渋谷で地下から地上に出るあたりの横に位置する。自宅は川のそば、これは隅田川だろうなあ?昭和40年代までは多かった外壁も木の平屋の家だ。エレキブーム到来でゴーゴークラブで若者がモンキーダンスのような踊りをする。音楽は一世を風靡した11PMのテーマ曲を作曲した三保敬太郎だけど、エレクトーン基調で今観るとドン臭い音楽だ。三保はレーサーとしても有名でマカオグランプリにも出場している。

⒈VANジャケット
いきなり砂塚秀夫がマドラスチェックのジャケットを着て登場する。これはVANだなと思いながら、その後もファッションはアイビーだ。みゆき族が話題になったのが1964年だけど、アイビールックは学生たちに根づいていたし、VANの全盛期だった。内田裕也が「エレキの若大将」に引き続き登場する。彼のアイビールックは後10年したら出演するエロティック路線を知っている我々からすると妙におかしい。自分がアイビーを知るのは中学生になってからでもう6年後だ。

主演格で現役の慶応の学生和久田龍が登場、いかにも慶応ボーイらしい彼もアイビールックだ。残念ながらこの一作で芸能界は退く。雑誌の編集長役が若大将シリーズの常連江原達怡で彼も慶応だ。この映画の音楽担当でレーサー役で登場する三保敬太郎とプロデューサーの藤本真澄含めて慶応出身者が並ぶ。身内びいきだが、直近で早稲田の学生紛争の映画を観ているので映画のレベルはともかく親しみをもって映画に入っていける。
⒉フェアレディ
実は1966年に日産自動車はプリンス自動車を合併して、スカイラインやグロリアも売るようになる。若大将シリーズでも新橋演舞場側の旧日産自動車本社が映る。この映画では、ダットサン箱型フェアレディを前面に押し出す。小学生だった自分から見ると,ヨーロッパ車には見劣りするが,フェアレディはかっこよく見えた。この映画のレースでライバル車となるのはポルシェで、乗り回すのは内田裕也だ。さすがに日産自動車協賛なので、フェアレディに軍配があがる。自分が最も好きな車のジャガーEタイプを金持ち娘が乗り回すのはうれしい。

飛ばす高速は第三京浜か?横浜新道か?当時のカーマニアからすると、冨士スピードウェーは羨望の眼差しで見る場所だった。映画ではレース場面のウェイトも高い。箱根の山のドライブの後、芦ノ湖で水上スキーをするのは若大将シリーズの二番煎じの香りがプンプンする。
⒊東宝の若手女優
星由里子以外の出演女優陣は見かけない女優が揃う。星由里子はすでに若大将シリーズでスターになっている。格でクレジットもトップ扱いとするけど、黒沢年男の恋人にはならない。恋人役が定まらないのは中途半端。東宝の看板内藤洋子はデビューしていたけどまだ16歳、酒井和歌子が17歳なのでちょっとこの映画には無理がある。むずかしい局面だ。黒沢年男の妹役は松本めぐみでなかったら、岡田可愛かな。
現在無名でも女優陣はみんな東宝らしい都会派の雰囲気を持っている。特にいいのが沢井桂子で東宝女優らしい気品がある。同じように東宝女優らしい美貌を持つ藤山陽子の方が少し年上だ。「お嫁においで」では加山雄三のお相手だったけど、この後内藤洋子と酒井和歌子の人気に押されてしまったのが残念。

現在でも、TOHOシネマに行くと、次回作紹介で福本莉子が出てくる。彼女を見ると伝統的東宝女優らしさってあるのかなと感じる。

映画「パンチ野郎」は1966年(昭和41年)公開の黒沢年男主演の東宝映画。いつも通り藤本真澄がプロデュースで、監督は「エレキの若大将」の岩内克己が引き続きメガホンをとる。実はこの映画の存在自体を知らなかった。名画座の特集で気付いた。dvdもない。主役の黒沢年男のWikipediaにもこの映画の記載がない。でも、東宝が黒沢年男を売り出そうとする試みが感じられて、星由里子も出演する。でも、加山雄三の恋人イメージを崩さないように、黒沢年男の先輩キャメラマンに過ぎない。
いかにも昭和の東宝コメディで、ストーリーはどうってことない。
若者の恋愛が二重三重に絡まる。
黒沢年男はキャパのようになりたいカメラマン、そのポン友が名脇役の砂塚秀夫、黒沢年男の妹役が後の加山雄三夫人の松本めぐみ。松本めぐみが好意を寄せる黒沢の友人でカーレースにのめり込む若者が和久田龍。黒沢年男の幼馴染で銀座のメンズショップの店員が沢井桂子で、沢井には和久田が好意を寄せる。
内田裕也が和久田のカーレースのライバルになる金持ちの息子で、内田は沢井桂子にも入れ込んでいる。星由里子は雑誌社のカメラマンで、黒沢年男の先輩になる。女性ドライバーで黒沢に入れ上げる高利貸しの娘藤あきみと黒沢年男と砂塚俊夫が通うバーの女性斎藤チヤ子が恋愛相関関係に絡んでいく。
1966年(昭和41年)の東京の熱気が伝わる掘り出し物の映画だ。
見どころが実に多い。ストーリーよりも背景を楽しむ。
映画が始まる前に、日産自動車とVANジャケットが協賛という表示が出る。ファッションはIVYルック全盛時代で、銀座4丁目の三愛にメンズショップがある設定だ。男性陣はアイビールックに身を包む。石津謙介のほくそ笑む顔が目に浮かぶ。車はハコ型フェアレディが全面的に登場する。
主人公黒沢年男が昭和41年の銀座の街を写真を撮りながら歩き回る。勤める雑誌社は平凡パンチの編集部を意識して、たまり場はオレンジ色の銀座線が渋谷で地下から地上に出るあたりの横に位置する。自宅は川のそば、これは隅田川だろうなあ?昭和40年代までは多かった外壁も木の平屋の家だ。エレキブーム到来でゴーゴークラブで若者がモンキーダンスのような踊りをする。音楽は一世を風靡した11PMのテーマ曲を作曲した三保敬太郎だけど、エレクトーン基調で今観るとドン臭い音楽だ。三保はレーサーとしても有名でマカオグランプリにも出場している。

⒈VANジャケット
いきなり砂塚秀夫がマドラスチェックのジャケットを着て登場する。これはVANだなと思いながら、その後もファッションはアイビーだ。みゆき族が話題になったのが1964年だけど、アイビールックは学生たちに根づいていたし、VANの全盛期だった。内田裕也が「エレキの若大将」に引き続き登場する。彼のアイビールックは後10年したら出演するエロティック路線を知っている我々からすると妙におかしい。自分がアイビーを知るのは中学生になってからでもう6年後だ。

主演格で現役の慶応の学生和久田龍が登場、いかにも慶応ボーイらしい彼もアイビールックだ。残念ながらこの一作で芸能界は退く。雑誌の編集長役が若大将シリーズの常連江原達怡で彼も慶応だ。この映画の音楽担当でレーサー役で登場する三保敬太郎とプロデューサーの藤本真澄含めて慶応出身者が並ぶ。身内びいきだが、直近で早稲田の学生紛争の映画を観ているので映画のレベルはともかく親しみをもって映画に入っていける。
⒉フェアレディ
実は1966年に日産自動車はプリンス自動車を合併して、スカイラインやグロリアも売るようになる。若大将シリーズでも新橋演舞場側の旧日産自動車本社が映る。この映画では、ダットサン箱型フェアレディを前面に押し出す。小学生だった自分から見ると,ヨーロッパ車には見劣りするが,フェアレディはかっこよく見えた。この映画のレースでライバル車となるのはポルシェで、乗り回すのは内田裕也だ。さすがに日産自動車協賛なので、フェアレディに軍配があがる。自分が最も好きな車のジャガーEタイプを金持ち娘が乗り回すのはうれしい。

飛ばす高速は第三京浜か?横浜新道か?当時のカーマニアからすると、冨士スピードウェーは羨望の眼差しで見る場所だった。映画ではレース場面のウェイトも高い。箱根の山のドライブの後、芦ノ湖で水上スキーをするのは若大将シリーズの二番煎じの香りがプンプンする。
⒊東宝の若手女優
星由里子以外の出演女優陣は見かけない女優が揃う。星由里子はすでに若大将シリーズでスターになっている。格でクレジットもトップ扱いとするけど、黒沢年男の恋人にはならない。恋人役が定まらないのは中途半端。東宝の看板内藤洋子はデビューしていたけどまだ16歳、酒井和歌子が17歳なのでちょっとこの映画には無理がある。むずかしい局面だ。黒沢年男の妹役は松本めぐみでなかったら、岡田可愛かな。
現在無名でも女優陣はみんな東宝らしい都会派の雰囲気を持っている。特にいいのが沢井桂子で東宝女優らしい気品がある。同じように東宝女優らしい美貌を持つ藤山陽子の方が少し年上だ。「お嫁においで」では加山雄三のお相手だったけど、この後内藤洋子と酒井和歌子の人気に押されてしまったのが残念。

現在でも、TOHOシネマに行くと、次回作紹介で福本莉子が出てくる。彼女を見ると伝統的東宝女優らしさってあるのかなと感じる。