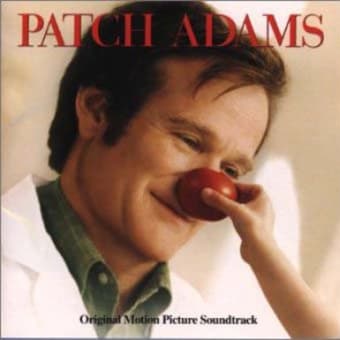管理人注:その道の天才はいるものである。山一証券からソロモン・ブラザーズ・アジア(現日興ソロモン・スミス・バーニー証券)へ移り副社長まで(ロンドン駐在)登りつめ退職金50億を受け取ったサムライ・明神茂
http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E6%98%8E%E7%A5%9E%E8%8C%82&search.x=1&fr=top_ga1_sa&tid=top_ga1_sa&ei=UTF-8&aq=&oq=
注の続き:日本の金融業界の天才
http://sougoushousha.seesaa.net/article/371714050.html
六月初旬。
数名の外資系投資銀行のバンカーが、埼玉県所沢市の西武鉄道本社を訪れていた。訪問の目的は「西武鉄道の買収交渉」。その外資とは、米系投資銀行のゴールドマン・サックス証券(以下、GS)である。この時、西武とGSは初の公式会合だった。しかし、その場に、GSのトップである持田昌典(50)と、みずほコーポレート銀行出身の後藤高志・西武鉄道社長(56)の姿は無かった。
「後藤社長と持田社長が、直接会って交渉することはあり得ないでしょう。なぜなら、二人の間には、絶対に埋めることが出来ない『溝』があるからです」(メガバンク幹部)
外資--。
不況にあえぐ日本経済を尻目に、外資系の投資銀行や投資ファンドが日本全土を席巻し、不動産、ゴルフ場、ホテル、そして一部上場企業をも買い漁っている。ニッポン放送株を巡るフジテレビとライブドアの争いの背後では、米系投資銀行のリーマン・ブラザーズが数百億円もの収益を上げたと言われている。
バブル崩壊後、都心の一等地に新築された巨大なオフィスビルには、決まって外資系金融機関が入居している。日本橋の東急百貨店の跡地にはメリルリンチ、恵比寿ガーデンプレイスにはモルガン・スタンレー、そして、六本木ヒルズにはGSとリーマン・ブラザーズ・・・。こう見ると、東京中が外資に「侵略」され、紅毛碧眼の外国人が荒稼ぎをしているような錯覚を抱いてしまう。
しかし、外資系投資銀行のトップのほとんどが日本人で、当たり前のように億単位の年収を稼ぎ出している。彼らは、なぜ成功者となりえたのか。そして、その成功は、真実の「勝利」と言えるのか。「最強外資」と呼ばれるGS社長の持田昌典を中心に、彼らのビジネス人生を辿りながら、外資で戦う日本人たちの虚像と実像に迫りたい。
■ ■
昭和二十九年、持田昌典は、千代田区神田和泉町で羊毛卸し業の「メリノ」を経営する父・武雄、母・清子の長男として生まれた。子供時代から裕福に育ち、今では「お受験御三家」と言われる西麻布の若葉会幼稚園から、慶應の幼稚舎(小学校)に進学する。
持田が中学生になる頃には、父親が一代で築いたメリノは、子供用ニット製品の専門メーカーで業界トップとなり、年商数十億円を誇る企業に成長した。渋谷区松涛の高級住宅地に六階建ての自社ビル兼住居を構え、父親は運転手付きのBMWに乗り、軽井沢に別荘を持つようになった。休日には、近くに住んでいる女優の山本富士子夫妻とともにゴルフに出かけるなど、典型的な「上流階級」の仲間入りをした。
武雄は、誰よりも早く出社して社内を掃除し、毎朝、写経をしていた。ロマンスグレーの髪も一糸乱れることがなく、紳士の装いを崩さなかった。森ビルの頭山秀徳常務は、伊勢丹社員時代に見た武雄をこう表現する。
「細身のロンドン調といった感じのカシミアのダブルで、ポケットチーフが入るようなコートを着ていたのを覚えてます。本物の英国の紳士といった方で、単に高いものを着ているのではなく、戦前の方の本格的なおしゃれで、今の人とはレベルが違う、身に付いたおしゃれでした」
一方、母親の清子は、持田を厳しく躾けていた。幼少時代からの親友、横山健次郎はこう語る。
「私たちは家族ぐるみの付き合いをしていました。お母さんは非常に厳しい方です。子供の頃、『勉強しなさい』ということで、もうテレビは見せないと言って、テレビに袋をかぶせて紐で縛っちゃったぐらいです。お父さんはゆったりした方で、怒鳴ったりしない。持田の性格は、お母さん譲りだと思いますね」
持田が高校一年の時、母・清子が急逝する。そして、母親の死は、メリノの経営に影を落とす結果になる。実は、会社経営を仕切っていたのは武雄ではなく、母の清子だったからだ。昭和三十年代から、メリノに羊毛の納品をしていた元商社マンの渡辺正一氏が、当時をこう語る。
「会社を切り盛りしていたのは奥さんでした。神田和泉町の頃から、奥さんが番頭さんを使って指示を出していた。ところが、その番頭さんが、ニッター(縫製工場)から無断で借金をしたのでクビにした。次の番頭さんが育つ前に、奥さんが亡くなってしまった。武雄さんは、人格的には素晴らしく、百貨店の仕入れの方からも信頼をされてましたが、残念ながら、あまり危機意識がなかった」
これにオイルショックや海外での工場投資などの負担が重なり、商品の在庫が増える一方、借り入れ金が十億円を超え、第一勧銀、日商岩井からの出向者を受け入れ、経営の建て直しをしていた。ところが、この頃、武雄は、銀座の高級クラブ「ラモール」の元マダムで、「マキシム・ド・パリ」をプロデュースした女性実業家の花田美奈子と再婚し、悠然と田園調布に住んでいたのだ。
そして、慶応大学経済学部に進学した持田は、ラグビー部の花形選手として活躍しながら、金持ちの慶応ボーイらしく、愛車のフェアレディZに乗り、お手伝いさんを雇って一人で松涛の自宅を独占する優雅な毎日を送り、卒業後、第一勧銀に就職する。
「お父さんの会社のメインバンクが第一勧銀だった関係と、ラグビー部の枠の両方で就職できたという感じだった。当時は家を継ぐ予定だったので、よくある『修業にしばらく預かってください』というものだったと思います」(前出・横山)
■ ■
ところが、入行四年目の昭和五十六年六月、メリノの借金返済のため、松涛の自宅ビルが人手に渡ることになった。しかも、自宅の売却をすすめたのが、第一勧銀だったという。
「すでに、軽井沢の別荘、厚木の倉庫を売却した。金利の減免はしてもらいましたが、倒産の危機というほどではありませんでした。銀行側の強い意向があったのと、最後は、武雄社長の〝取引先に迷惑をかけたくない〟との思いで、松涛の自宅を売却することに決めたのです。売却が決まった途端、昌典さんは、荷物をまとめて掃除も手伝わずに家を出て行かれました。自分が勤めている銀行が、自分の家を売り払い、父親の会社を廃業に追い込んだ事実に、耐えられなかったんでしょう」(メリノ元社員)
この頃、日比谷支店に勤務していた持田は、第一勧銀のラグビーの中心選手でもあったが、練習を早めに切り上げて英会話学校に通うようになる。仲間とゴルフに行っても、社内で英会話のテープを聞いていた。そして、弱かったラグビー部を社会人リーグの一部直前まで強化する一方、一年で7人程度しか合格しない、難関の社費留学試験も突破する。
「当時、行内では『持田の親父の会社は銀行に焦げ付きを発生させた』と陰口を叩かれていました。それだけに、彼には見返してやろうという気持ちが強かったでしょう。ラグビー部を創設した藤居寛常務(当時)=現帝国ホテル会長=からも評価されて、行内でも幹部候補生と目されるようになりました」(一勧の元同僚)
持田が、ペンシルベニア大ウォートン校への留学に旅立つ日、日比谷支店の上司や同僚が、成田空港まで見送りに行った。
「頑張ってこい」
「はい、頑張ります」
こんな会話を交わして、持田はMBA留学のため米国に向かった。しかし、持田は一勧に戻らなかった。留学先でGSへの転職を決めたのだ。社費留学の幹部候補生が外資に流出したことで、一勧には「寝返った」という反応が満ちた。わけても、持田を信頼し、結束していたラグビー部関係者からは、「持田は裏切り者だ」という怨嗟の声が挙がった。
メリノは一勧によって廃業に追い込まれたのか。それとも、一勧に巨額の焦げ付きを発生させたのか。今、真実を検証することは難しい。しかし、一勧の一部の人間が、持田を「裏切り者」と信じ、一方の持田は、一勧に自宅と家業を奪われたことに、怒りに似た感情を抱いたのだけは間違いないだろう・・・。
こうして、バブル絶頂期に、後に日本を席巻することになる一人のバンカーが、都銀から外資へと、戦いの場を移していった。
初出:「ハゲタカ外資の虚像と実像(前編)」『週刊新潮』2005年6月30日号
おまけ.....
ソニー再び大赤字......植物園なんかで社員を苦しめているからね
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140206-00000090-jij-bus_all
ソニー、再び赤字転落=14年3月期、純損失1100億円―TV分社化、5千人削減
時事通信 2月6日(木)15時32分配信
ソニーは6日、2014年3月期連結決算(米国会計基準)で純損益が1100億円の赤字になる見通しだと発表した。従来予想は300億円の黒字だったが、不振のパソコン事業の譲渡やテレビ事業の分社化などに伴う損失計上が響く。12年3月期以来、2年ぶりの赤字転落。ソニーは13年3月期に純損益の4年連続赤字を脱したばかりだった。
売上高は従来予想通りの7兆7000億円だが、営業利益(従来予想1700億円)は前期比65.2%減の800億円に下方修正した。
営業赤字が長期に続くテレビ事業は、7月をめどに分社化し、完全子会社として運営。収益構造を改善し、15年3月期の黒字化を目指す。
構造改革費用は、パソコンやテレビを中心に200億円上積みし、グループ全体で約700億円を見込んだ。パソコンとテレビの事業再編などに伴い、15年3月末までに国内1500人、海外3500人の計5000人を削減する計画。
関連記事:ソニーの植物園
http://6707.teacup.com/gamenotatsujinn/bbs/index/detail/comm_id/1666
追い出し部屋?
http://6707.teacup.com/gamenotatsujinn/bbs/index/detail/comm_id/1920
持田がGSへ転職した八十年代、日本のマーケットでの外資系投資銀行は、取るに足らない存在だった。
唯一、頭角を現しつつあったのは、山一證券からソロモン・ブラザーズ・アジア証券に転じていたトレーダーの明神茂(55)だけで、M&Aや引き受けなど、いわゆる投資銀行部門(IBD)は赤字を垂れ流す「お荷物部署」だった。また、外資系金融機関で、実力バンカーと呼ぶに相応しい日本人は、平成四年にシティバンクの在日代表に就任する八城政基の登場まで待たねばならず、当時は、米国からの「天下り外人」によってトップの座を牛耳られていた。
この頃、GSの投資銀行部門の主な仕事は、米国の不動産や企業を日本の投資家に売るため、金融機関や生保などに頭を下げて営業活動するというものだった。営業を担当していたのが、GSの東京支店を数名で支え続けた川島健資(51)=現メリルリンチ日本証券副社長と江原伸好(53)=ユニゾン・キャピタル社長の二人。持田は、コーポレートファイナンス、日本の証券会社で言うところの「引き受け」が仕事だった。
実は、当時のGSは火種を抱えていた。
「東京のGSに『日本人の顔が必要だ』と、ニューヨークが判断して、川島、江原のいずれかをパートナー(共同経営者)にしようと動き出したのです。結果的に、日本の金融機関に顔が売れていた江原さんがパートナーになるのですが、〝年次〟では川島さんが古かった。もっとも、次回は川島さんがパートナーに就任すると思われていました」(当時を知るGS関係者)
こうした微妙なパワーバランスを内在するGSに、一人の若者が出現して、「抗争」が、さらに複雑化する。ソロモン・ブラザーズで明神と働いていた二十六歳の松本大は、GSに移籍するや、デリバティブなどを駆使した債券のトレーディングで、巨額の収益を稼ぎ始めたのだ。
「強烈な〝異文化〟の流入に恐れたのは、IBDでした。これまで十年以上かけてIBDが稼いだ収益を、債券部が数年で超えてしまう勢いだった。次第に、債券部の採用人数や発言力が増していき、IBDは肩身が狭くなっていった」(前出・GS関係者)
M&Aのアドバイザリーなどでフィー(手数料)を稼ぐIBDと、自らマーケットに金を注ぎ込んでアービトラージ(利鞘稼ぎ)で儲ける債券部とは、まったく思想が異なるビジネスである。こうした「対立」は、どこの投資銀行でも共通して生じていた。
■ ■
そんな時、GSの債券部の社員十数人が、ニューヨークから来日していた債券部のヘッドで、パートナー(共同経営者)のジョン・コーザイン(現ニュージャージー州上院議員)が宿泊するホテルオークラの部屋に押しかけ、直談判するというクーデター紛いの「事件」が発生した。
「債券部が、収益の大部分を稼いでいるのに、評価がIBDより低い」
「持田が、債券部との共同事業を自分の功績のようにニューヨークに報告しているのではないか」
なぜ、持田は「疑惑」の目で見られたのか。これについて、GSのIBD出身者はこう解説する。
「持田さんが担当していたコーポレートファイナンスでは、ニューヨークとの間での情報交換やドキュメントのやりとりが不可欠だった。そのため、ニューヨークが朝になる深夜まで会社に残って電話やファックスをしなければならない。それで誤解されたのではないか・・・」
しかし、債券部の危惧は、平成四年に驚くべき形で的中する。パートナー就任が確実視されていた川島が外され、持田が入社九年目で二人目の日本人パートナーとなったのだ。持田は、伊勢丹と提携して「バーニーズニューヨーク」を招致するなど、実績をあげていた。しかし、日本国内での信用構築に十五年以上も取り組んできた川島を差し置いたパートナー就任には、IBDからも「不審」の声が挙がった。
「社内の騒然とした空気を感じ取ったIBDのヘッドのロバート・カプランが、順番にIBDの社員を回って、〝今回のパートナーシップ選考について意見のある人はちゃんと聞きたい〟と言って、一人づつ個別に話をしたほど、気を使わざるを得ない事態でした。持田さんがパートナーになり、川島さんがなれなかったことは、それほど微妙な問題だったのです」(同)
日本でのGS立ち上げの最大の功労者である川島は、その後、パートナーに選ばれることなく、メリルリンチ証券へ転職した。
■ ■
パートナーになった持田は、白金台の家賃約八十万円の高級マンションに引っ越した。広さは五十坪ほどで、ダイニング、リビングがあり、ハーフサイズのバスケットコートや、卓球台やビリヤードなどの施設があった。父が築いた松涛の豪邸には及ばないが、バブル崩壊で疲弊する都銀の銀行員が羨む住居を手に入れたことになる。
しかし、持田がようやくパートナーに相応しい仕事を手掛けるのは、六年後の平成十年、二兆千二百五十五億円という史上最高額のNTTドコモの新規公開である。この時、日本の金融界は、北海道拓殖銀行、山一證券の破綻、野村證券の総会屋事件、日本長期信用銀行の破綻など、未曾有の危機に直面していた。
持田が率いるGSが、日本の危機に尻目に儲けていた時、一人の邦銀バンカーが危機を脱しようと奔走していた。第一勧業銀行の企画部副部長、後藤高志である。いわゆる一勧の「四人組」の一人として、総会屋事件で副頭取や元会長が相次いで逮捕される中、若手改革派の一人として、経営陣の総退陣などを主張した男である。
昨年十月、六本木ヒルズ四六階に陣取る持田は、部下に「西武の堤(義明・コクド前会長)に渡りをつけろ!」と指令を出した。有価証券報告書の虚偽記載で揺れる西武鉄道に目をつけたのは、「相手の危機に乗じて儲ける」という持田の常套手段だろう。しかし、銀行管理下に入った西武鉄道のトップに座ったのは、みずほコーポレート銀行副頭取の後藤だった。
「後藤社長と持田社長との〝溝〟は、総会屋事件の時に、持田の手法を目の当たりにしたことだけではありません。後藤社長は、東大ラグビー部出身で、一勧ラグビー部では先輩・後輩の間柄です。〝裏切り者〟の持田社長と、ビジネスをするとは考えられません」(前出・メガバンク幹部)
持田は、一勧ラグビー部のOB会には一度も顔を出したことがない。いまだ両者の間には、「一勧を裏切った男」「父の会社と自宅を奪った銀行」という、まったく異なった〝事実〟が平行して存在し続けている。
しかし、外資系投資銀行を舞台にして、旧態依然とした会社組織に反旗を翻した男たちが、「死闘」を繰り広げてきた例は、これに止まらない・・・。
(文中敬称略)
初出:「ハゲタカ外資の虚像と実像(前編)」『週刊新潮』2005年6月30日号
その3
平成八年十一月。
ゴールドマン・サックス(GS)の日本人パートナー、江原伸好(53)=現ユニゾン・キャピタル社長=が会社を後にした。江原は、川島健資(51)=現メリルリンチ日本証券副社長=とともに黎明期のGSを支え、金融機関向けのカバレッジ(営業)を担当し、FIG(FINANCIAL INSTITUTION GROUP)のヘッドとして、十六年の長きにわたって「GSの顔」を務めてきた。
日比谷高校を中退して渡米。シカゴ大学でMBAを取得後、米系の金融機関で働いてきた江原は、長身でスマートな風貌と相まって、ウォールストリートの匂いがする外資系バンカーと呼ぶに相応しい人物だった。電電公社(現NTT)の政府保証債の米国での発行など、数々の実績をあげた江原は、邦銀の企画部や国際部では「GSで最も華のある信頼できるバンカー」と語り継がれている。
しかし、この〝信頼できるバンカー〟江原の退社は、GSが、「古き良き」投資銀行の伝統を脱ぎ捨て、狙った獲物を絶対に逃さない「最強外資」へと、その姿を変貌させることを暗示していた・・・。
江原退任の翌年、北海道拓殖銀行、山一證券が相次いで崩壊したのを契機に、「外資」による本格的な日本買いが始まる。彼らが橋頭堡としたのは、「不良債権ビジネス」である。その先兵となったは、不良債権が金儲けになることを知悉していた外国人バンカーたちだった。
■ ■
「なんだこのチンピラみたいな外人バンカーは?」
平成九年三月、東京三菱銀行が米国の穀物商社最大手のカーギルの投資子会社に不良債権の「バルク売り」をしたことを皮切りに、邦銀から吐き出される不良債権の外資による買い漁りが本格化した。
来日当時、日本人から「チンピラ外人」などと見下されていたのは、まだ三十代前半のソニー・カルシ、フレッド・シュミットの二人だった。二人は、モルガン・スタンレー(MS)の不動産投資銀行部に派遣された「外人部隊」だったが、当時の肩書きは単なるアソシエイト。つまり、投資銀行の中では下から二番目の地位である。
「MSは、ワスプ=WASP、アングロサクソン系プロテスタントの白人=が支配する貴族的な社風の会社です。カルシはインド系アメリカ人で、シュミットは日本人とのハーフ。二人とも非常に頭がキレる男でしたが、保守本流である投資銀行部門(IBD)はワスプが牛耳っていたので出世できない。彼らが大金を掴むためには、不動産ビジネスのような歴史の浅い仕事を手掛けなければならなかった」(MSの元社員)
カルシ、シュミットを含め、日本人スタッフら約二十人でスタートした不動産部隊は、恵比寿ガーデンプレイスのIBDと同じフロアに同居した。ところが「貴族階級」のIBDから嫌われてしまう。
「不動産部隊は〝カウボーイカルチャー〟で、昼間から大声を出して騒いだり、他人の机から勝手にCDを出して聴いたりするような連中ばかりだった。それで、六階に追い払われてしまうのですが、そこは〝シェル貸し〟という内装も何も無いタコ部屋同然でした。この部屋だけは、ウッドパネルで飾られ、美人秘書がいる外資系投資銀行とはかけ離れた、雑居ビルのような雰囲気でした」(前出・元MS社員)
タコ部屋でビジネスをスタートしたカルシとシュミットの二人は、当然、チンピラなどではなかった。カルシは、MSの不動産投資ファンド「MSREF(メズレフ)」を通じ、大京からの不良債権の買い取りを指揮した。シュミットは、世界最大の調査機関「クロール」の元エージェントという肩書きが示す通り、英語と日本語を自在に駆使し、不動産管理会社「KGI」の社長として、「どんな相手でも口説き落とせる男」とまでいわれた交渉力で、買い取った不動産の債権者や不法占拠者を整理した。
MSの不良債権部隊の戦略は徹底していた。日本の金融機関が不良債権ビジネスを手掛けられなかったのは、処理の過程で「裏社会」の人間との接触を余儀なくされたのも一因だ。そこでMSは、「ローカルパートナー」という肩書きで、債務者の追跡調査や「闇の勢力」との交渉を請け負う会社を雇い、汚れ仕事を外注してしまう。
余談だが、当時、筆者がMSのローカルパートナーである銀座の「D社」を取材をしていたところ、現役の朝日新聞の記者を使って、「お前、何をコソコソ嗅ぎ回ってるんだ!」と脅されたことがある。カルシやシュミットは、こうした企業を懐に抱き込むのを厭わないほど、不良債権ビジネスに賭けていた。
■ ■
平成九年春、GSのマネージング・ディレクターとして来日したダニエル・H・クリーブスは、不動産買収ビジネスを手掛ける日本人スタッフのリクルートをしていた。クリーブスは、日本経済新聞をスラスラと読むほど日本語が堪能で、GSが送り込んだ「日本買い」のヘッドとして、打って付けの男だった。
「もうすぐ長銀が潰れる。さらに生命保険会社も何社か倒産するだろう。我々は、すでに根回しをしてある。GSは東京中の不動産を買うつもりだ!」
面接に訪れた日本人を前にして、クリーブスが流暢な日本語で豪語すると、あまりの大言壮語に相手が呆気に取られることも少なくなかった。しかし、クリーブスの言葉は、半分は真実となった。日比谷の「やまと生命ビル」を買収したのは、クリーブスの部隊で、長銀も経営破綻した。
もっとも、肝心の「東京中の不動産を買う」という夢は、カルシが率いるMSの不動産部隊に阻まれた。平成十三年に千代田生命の破綻で売り出された広尾の「恵比寿プライムスクェア」の入札でMSに敗れてからは、GSが都心の不動産を勝ち取る例は目立たなくなってきた。一方のMSは、「ウェスティンホテル東京」を五百一億円、「品川三菱ビル」を千四百億円で買うなど、いまだに買収攻勢は衰えていない。
「MSは、買い取った商業ビルの証券化(CMBS)の総額が約四千億円になろうとしています。二位のみずほグループでもMSの三分の一以下で、GSは十位にすら入ってない。今、銀座で豪遊できるCMBSの営業マンは、MSの人間だけだというくらいマーケットを牛耳っています」(メガバンクの不動産ファイナンス担当者)
現在、MSのカルシ、シュミットの二人はマネージング・ディレクターに出世した。米系投資銀行で保守本流に入れず、必死で実績を築くことで「チンピラ」から成り上がった二人は、多くの日本人バンカーからも賞賛されている。
「カルシは、今は成功の証としてポルシェを買い、都心の高級マンションに住み、MSのアジア・オセアニアを掌握する不動産部門のトップに就任している。日本の銀行から不良債権を買い叩いて儲けたが、誰からも恨まれないナイスガイだった」(外資系投資ファンドの日本人幹部)
一方のクリーブスは、GSが六本木ヒルズへ入居する際、森ビルとの間で家賃の値下げ交渉を成功させたのを最後に退社した。クリーブスを知るGSの元社員はこう語る。
「クリーブスは冷徹なバンカーだった。日本語は堪能だったが、打ち解けて付き合っていた日本人は少なかったと思う・・・」
まったく同じ時期に巨大投資銀行の「外人ヘッド」として不良債権ビジネスを手掛けたカルシとクリーブスだが、その後の人生は違うものになりそうだ。
初出:「ハゲタカ外資の虚像と実像」(中編)『週刊新潮』2005年7月7日号
不良債権部隊が派手な買収で利鞘を稼ぎ出していた頃、持田昌典=現ゴールドマン・サックス証券社長=は、GS東京支店長に就任していた。もっとも「支店長」とは名ばかりの肩書きで、NTTドコモの新規公開というGSの歴史に残る偉業を果たしたにも関わらず、持田の上にはマーク・シュワルツという「天下り外人」が社長として君臨していた。
持田が、さらに「白人の上」を狙うには、MSのカルシやシュミットと同様、実績を作る以外にない。IBDの実績は、「M&Aリーグテーブル」の順位によって決まる。「リーグテーブル」とは、アドバイザーとなった投資銀行や証券会社のランキングで、M&Aの取引金額の多い順に民間の調査会社が集計したものである。
「投資銀行が得るM&Aのアドバイザリーのフィー(手数料)は〝レーマン方式〟によって算出されます。例えば、取引額が三億円以下なら八%、三億円から五億円なら六%という具合に取引額に応じて成功報酬が増減する仕組みで、巨額のM&Aであればあるほど、投資銀行の懐に入る金額が増えることになります」(M&Aコンサルタント会社幹部)
持田が率いるIBDが、巨額M&Aのターゲットとして選んだのは、「銀行合併」のアドバイザーを請け負うことだった。そして、一勧、富士、興銀の三行が「みずほフィナンシャルグループ」へ経営統合する際のアドバイザーとなり、平成十一年のリーグテーブルで、GSは「日本企業が関わるアドバイザリーランキング」の取引額ベースでトップに躍り出た。
しかし、江原を失っていたGSが、なぜ、みずほのアドバイザーに簡単に就任することが出来るのか。実は、この順位に異を唱えるM&Aのプロは多い。
「みずほの三行統合は、合併比率も1対1対1と最初から決まっており、頭取同士で基本合意書も締結されていた。そもそも、興銀と一勧の合併比率が同じはずがない。デューディリジェンス(資産査定)もやらず、それらしいオピニオン・レター(第三者の意見書)を出しただけ。みずほ側も外資がリーグテーブル争いをしているのを知っていたので、ダンピングした結果、本来、もらえるはずのフィーは支払われず、受け取った成功報酬は一千万円程度になったと聞いてます」(投資銀行幹部)
リーグテーブルという〝名目上の〟実績作りのため、敢えて利益を度外視してダンピングまでした〝成果〟だという指摘である。持田が不毛なリーグテーブル争いを演じている中、「外資」を語る上で最も重大な事件が起きた。国有化されていた長銀が、米系投資ファンドのリップルウッドに売却されたのだ。
■ ■
長銀の売却では、「瑕疵担保特約問題」と新生銀行が上場した際に、キャピタルゲインに課税できないという二つの問題が指摘されている。この問題では、リップルウッドと新生銀行の八城基政社長に対して、「ハゲタカ外資に国民の税金を奪われた」と、批判の矛先が向けられた。
「当時の〝外資批判〟はあまりにも的外れです。リップルウッドは、長銀売却後の二次ロスを応分に負担する〝ロスシェアリング〟を主張したにも関わらず、なぜか金融再生委員会が、〝瑕疵担保〟という不利な条件を提示した。責任を問われるべきは、金融再生委員会と政府、そして政府側のアドバイザーを担当したGSです」(外資系投資銀行幹部)
「瑕疵担保」という条件を考え出したのは、再生委の一人だという。これに対してGSは「その条件は不利だ」と、的確なアドハイスをしたのか。そして、「このままのスキームでは税金が取れない」と、指摘したのだろうか。
金融再生委員会の数百枚に及ぶ議事録を見ると、GSの発言はすべて黒く塗りつぶされている。その理由は「守秘契約」だという。しかし、この当時、GSは、巨額ディールが欲しいだけで、安価でアドバイスをしていたと言われている。黒塗りの議事録の下に隠されているのは、「止むを得ない事情」か、それとも「手抜き」の証拠だろうか---。
リップルウッドによる長銀買収が決まった平成十一年、ニューヨークのGSも百三十年の歴史の中で、最大の激震が走っていた。一月、CEOのジョン・コーザインが「会長」に祭り上げられ、ハンク・ポールソンが単独CEOにとなった。五月には、長年続いたパートナーシップを解消して株式を公開。これによって「古き良きGS」は、名実ともに「普通の営利企業」になった。
そして、コーザインが経営の再前線から引くことは、日本のGSにも波風を起こす結果となった。
「当時のGSの日本人の大半は、コーザインが採用したのです。債券部のヘッド時代のコーザインは、毎日のように日本に電話をしてました。来日すれば、深夜まで部下を引き連れて飲み歩くような男で、尊敬され、慕われていました。一方、コーザインに代わってCEOになったポールソンは、IBD出身で、最も親しい日本人パートナーが持田さんだったのです」(当時を知るGS元社員)
■ ■
GSを退社した江原は、家族とともにカリフォルニア南部のサンディエゴで休暇をしていた。しかし、北拓、山一の倒産のニュースを聞いて帰国する。江原は、リップルウッドが日本に上陸するよりも早く、企業再生ファンドの「ユニゾン・キャピタル」を設立し、金融界へ復活を遂げる。ユニゾンは、アスキーや東ハトなど数社を買収し、日系の投資ファンドでは中核的な存在となった。しかし、あるGS元社員は、こんな危惧を口にする。
「今の日本の『乱暴すぎるマーケット』では、他の外資系ファンドと戦って勝ち残っていくには、江原さんは紳士すぎるような気がします・・・」
この言葉にある「乱暴なマーケット」を作ったのとは、江原自身が初代日本人パートナーを務めたゴールドマン・サックスに他ならない。
「かつて江原さんが、十数年かけて築いたNTTや金融機関との信頼関係も、ここ数年のGSの手法が一因で冷え込んでいると聞きます。顧客の利益を蔑ろにして自分たちの利益を最優先するようなアドバイスをして平然としていられる。弱った企業からは徹底的に買い叩き、知識の無い者に不利な契約を押し付けて、〝それがビジネスの勝者だ〟という主張が認められつつある」(日系の大手証券会社幹部)
江原がGSのパートナーだった頃、投資銀行のバンカーは飽くまでも〝黒子〟で、主役は企業の経営者や従業員だった。顧客の投資やファイナンスを手伝っても、投資銀行が前面に出ることはなく、その必要も無かった。ところが今や、こうしたお題目は壁にかかってしまった。ライブドアのニッポン放送買収で、株式市場を混乱に陥れたリーマン・ブラザーズを『したたかな外資』と持ち上げる風潮すらある。
江原に、なぜGSを辞めたのか、そして今のGSについて、どう考えるか聞こうとしたが、「もう九年も前のことですから、何もお話しすることはありません」と答えるだけだった。
平成十三年、CEOのポールソンの後ろ盾を得た持田は、「ゴールドマン・サックス・ジャパン・リミテッド」の社長に就任する。そして、日本でフィービジネスが儲からないことを悟ったのか、債券部や不良債権ビジネスで成功を収めたアービトラージ(利鞘稼ぎ)ビジネスに乗り出す。GSは、投資銀行でありながら、一方で「企業」そのものを売買する巨大投資ファンドへと変貌しようとしていた。
GSが、アドバイザーとプリンシパル・インベストメント(自己勘定投資)という二つのビジネスを両輪にして走り出した時、持田昌典自身も、〝凄み〟すら感じられるバンカーへと変貌を遂げていく。
圧倒的な強さを見せつけ始めた「持田GS」からは、かつてのパートナーたちが、一人ずつ消えていった。そして、十年以上も勤めたマネージング・ディレクタークラスの社員も次々と退社している。
「目が覚めている間は仕事のことだけを考えろ」「日曜日は休日じゃない。接待ゴルフの日だ」「勝つために必要なことをやれ。それ以外のことをやる必要は無い」「俺の部下は俺の言う通りに動けばいい」
GSは確実に、「持田独裁」へ向けて歩き出そうしていた。
平成十三年九月、ゴールドマン・サックス証券(GS)の持田昌典(50)は、港区白金の聖心女子学院に近い一等地に転居した。六百平米の土地に築いた三階建て総床面積八百五十平方㍍の大豪邸は、「土地だけでも約五億円は下らない」と言われる。ガレージには、新車価格千四百万円のイタリアの高級スポーツカー「マセラティ・グランスポーツ」が停まっている。
持田は、父の会社が廃業に追い込まれて家を失ってから、二十年の歳月を費やし、自らの手で「上流階級」の生活を取り戻すことに成功していた。
この時点で、「持田は百億円近い資産を築いた」(GS関係者)と言われている。GSの株式公開で、パートナー(共同経営者)として数十億円の配分を受け取り、NTTドモコ株の新規公開などのメガディール(巨大案件)を手掛け、巨額のボーナスを得ていたはずである。すでに「金儲け」のために働く必要はなかった。実際、GSの元パートナーの多くが会社を後にしていた。そして、「第一勧銀に廃業に追い込まれた」と言われる父親の武雄も他界していた。
もし持田が、このまま退社していれば、彼の名前は「外資系投資銀行の元バンカー」の一人として忘れ去られたかも知れない。しかし、GSの在日代表に就いた持田は、会社を辞めなかった。その理由を、ある外資系投資銀行の幹部は、こう推測する。
「持田さんを社長に押し上げたのは、六年前の銀行合併の際のアドバイザー獲得の功績です。しかし、あの争いは、まったく不毛なゲームで、M&Aの取引額を争う『リーグテーブル』でトップに立つため、採算度外視でアドバイスを引き受けていたのです」(外資系投資銀行幹部)
この争いで、二年連続でリーグテーブルの首位となった持田が率いるGSは、逆にライバルのバンカーから揶揄されていた。
「外資の足元を見て露骨なフィー(手数料)のダンピングをしたのは、みずほです。持田さんは、内心忸怩たる思いが残っているでしょうが、ダンピングを受け入れたのも事実です。口の悪いバンカーは、『GSのリーグテーブルトップは〝偽りの勝利〟だ』とさえ言っているほどです」(外資系投資銀行幹部)
しかも、みずほフィナンシャルグループの中には、持田と「因縁」の深い旧第一勧銀も含まれていた。このまま辞めれば、再び「邦銀に敗北した」ことになりかねない。こうして持田は、GSを「最強外資」に育て上げ、その「独裁者」として君臨し続ける道を選んだ・・・。
■ ■
しかし、持田がトップに立つと、「持田支配」を逃れるようにして、GSを去る有力バンカーが相次いだ。KDDIの合併を担当した河野哲也はJPモルガンの社長になり、新卒から二十年近くも在籍してマネージング・ディレクター(MD)にまで上り詰めていた数名の幹部社員もGSを後にした。
中でも、M&A部門のヘッドだった服部暢達(47)の退社は、GSの若手バンカーたちを動揺させた。
「投資銀行は『M&Aの仕掛け人』と言われますが、日本では企業のトップの話し合いで合併が決まるケースがほとんどです。既に決まったディール(合併案件)を、営業活動でアドバイザリーを獲得しているのが投資銀行の実態です。持田さんは、ゴルフや飲食の接待を欠かさず、企業トップと密接な関係を築いてディールを取ってくるタイプです。ところが服部さんは、戦略的なM&Aの提案でディールを取ることを目指していた。若手には、服部さんの姿こそ、理想的なインベストメントバンカーに見えたのです」(GS元社員)
持田と服部の間には、こうした「バンカー哲学」の決定的な違いがあった。持田は、仕事が終わると、親友の横山健次郎が経営する焼き鳥屋に部下を連れて訪れ、酒を飲み交わすことを好んだ。しかし、こうした酒席に服部が顔を出すことは皆無に等しかった。
GSのIBDのトップ同士が、微妙な緊張関係を保つ中で生じたのが、「NTTドコモ海外投資の巨額損失」だった。
ドコモは、平成十一年以降、海外の通信会社六社に約三兆円を投資したものの、わずか数年で二兆円もの減損処理を余儀なくされた。この投資のうち、米国のAT&Tワイヤレスと台湾のKGテレコムのアドバイザーとなったのがGSだった。
「長年、ドコモを担当していたのが服部さんでした。ところがここ数年は、持田さん自らがドコモの立川(敬二)社長=当時=に直接電話をかけてトップセールスをしていた。ドコモは、AT&Tワイヤレスに出資したものの、わずか十六%の株数だっため取締役会での拒否権を行使できなかった。結局、全米二位のシンギュラー・ワイヤレスにAT&Tワイヤレスを横取りされてしまった」(GS元社員)
GSのファイナンシャル・アドハイスは適切だったのか。NTTドコモの中村維夫社長はこう語る。
「投資はドコモの取締役会の決議をへて実行されたもので、失敗の責任は我々にある。今はGSとの間で具体的に進めてる案件は無いです。(持田社長のバンカーとしての評価は)ノーコメントですね」
服部は、退社までの数年間、月曜日の朝八時半から行われる定例の「全体会議」に姿を見せなかった。全体会議には、GSのIBD全員が出席し、各案件の進捗状況が報告される。そして、他社にディールを獲られると、持田から「何をやってるんだ!」と容赦の無い叱責の声が上がる。全体会議は、「持田イズム」をIBD全体に浸透させる〝ミサ〟であり、軍隊の朝会のようなものだ。
GSは「通信分野」の強さを最大の武器にしていた。服部や河野の退社は、GSの屋台骨を支えた「通信」の時代が終焉し、持田の手によって新たな時代の模索が始まったことを物語っていた・・・。
GSからMDクラスの退社が相次ぐ中、持田がターゲットにしたのが、「最後のバンカー」と言われる三井住友銀行頭取の西川善文(66)だった。
当時、三井住友は、「融三案件」という平和相互銀行やイトマン事件に絡んだ巨額の不良債権の処理に追われていた。さらに、銀行内部には、西川の独走を抑えようとする「旧三井」系の行員が蠢動し始めていた。こうした危機を見透かしたように、GSは千五百億円の増資の見返りに、年率四・五%の高額配当と、GSの欧米の顧客へ最大約二千五百五十億円の信用保証を手にした。世に言う「不平等増資」である。
この一回目の増資は、平成十四年夏、GSのIBDを中心に設置されたチーム「プロジェクト・サマータイム」が策定した。しかし、一回目の増資は、西川が、自ら弱みを曝け出した結果に過ぎない。「持田イズム」によって組織されたGSのIBDが圧倒的な強さを発揮するのは、二回目の増資である。
持田は、破格の好条件で提携を結んだ西川を信用し切っていた。横山が経営する西麻布のフランス料理店「P」で西川を接待し、「今まで、私とゴルフをしてくれる上場企業の経営者は、消費者金融のトップぐらいでしたが、西川さんは付き合ってくれる」と、喜んでいたという。
ところが、一回目の増資の払い込みが完了しない平成十五年二月初旬、GSに、「三井住友が、JPモルガンを通じて三千億円超の増資を計画している」という情報が飛び込んできた。
「旧三井系の人間が中心になって、JPモルガンに増資計画のマンデート(業務委託)を与えていたようです。ところが、JPが機関投資家に内々で相談したため、既に増資を公表していたGSに情報が漏れた。第一報を聞いた持田さんは明らかに動揺してました。〝西川に諮られた〟と思ったんでしょう」(GS関係者)
三千億円もの増資が実行されれば、GSの持ち株比率は稀釈化する。持田の「クビ」が飛びかねない事態である。持田は自らヘッドになって、約十名の「ミッション・インポッシブル3」という名のプロジェクトチームを即座に立ち上げた。
そして、GSのCEOのヘンリー・ポールソンが、衛星回線のビデオカンファレンス(テレビ会議)を通じて、「このままでは一回目の払い込みは難しい」と言って、西川を吊るし上げる一幕もあったという。
GSは、二週間という短期間で世界中の投資家から三千五百億円を掻き集め、三井住友の二回目の増資を奪い取った。この時、みずほフィナルンシャルグループは「一兆円増資」の一部をメリルリンチ証券に依頼していた。ところが、GSが市場を席巻したため資金が集まらず、ディールをキャンセルせざるを得なくなったのだ。
「これを聞いたみずほの首脳は、メリルの担当者に灰皿を投げつけて激怒したそうです。『竹中プラン』を受けて、みずほの行員が全国で頭を下げて一兆円を集めている最中、〝やっぱり駄目でした〟で済むほど投資銀行のビジネスは甘くないのです」(先の外資系投資銀行幹部)
GSは、JPモルガンとメリルを蹴散らし、名実ともに「最強外資」であることを証明した。この時こそ、敗北を続けていた邦銀に、ディールを通じて初めて「勝利」した瞬間だった。
■ ■
「最強外資」となったGSは、六本木ヒルズに移転した。IBDのトップである持田は会社からの迎車で、債券部トップのトーマス・モンタグは自宅から150キロの巨体をスクーターに乗せて通勤している。
「モンタグは稼ぐ人間には金を使い、稼がない人間には使わせない。ある種の恐怖政治を敷いてますが、マーケットを見る能力、人を使う能力は突出している。二人とも本部の『経営委員会』に入っているので、ニューヨークへも意見を言える。日本人の持田さんがトップに立ち、本部の方針に振り回され無いこともGSの強さの一つでしょう」(前出の外資系投資銀行幹部)
しかし、持田の地位が高まり、GSが「強さ」を発揮する一方で、「信用」が二の次になる振る舞いが目立ち始める。その代表的な例が「日本テレコム」案件である。
昨年、GSは、自らが保有する日本テレコムの株式をソフトバンクに売却する際、ソフトバンク側のアドバイザーとなった。つまり、売り手が買い手側にアドバイスするという、「利益相反」と批判されても仕方がない暴挙に公然と打って出たのだ。
「GSは二兆円を超える投資ファンドを保有している。こうしたプリンシパル・インベストメント(自己勘定投資)は、米国のGSが始めたことですが、米国では、ファンドへの投資を通じてコンフリクト(利益相反)を起こすようなアドバイザーには就かない。下手をすれば株主から訴えられるからです。その意味で、日本のGSは病的にグリーディー(強欲)です」(同)
GSは、「顧客第一主義」と口で言いながら、実際は日本市場や一般株主を「舐めている」ように見える。
「現在のGSのIBDは、カバレッジ(営業)バンカーが十人ほどで、その下にアドバイザリーグループが八十人ほどいます。カバレッジバンカーは、コーポレートファイナンスを卒業したシニアが就任する例が多い。その結果、〝持田イズム〟を理解したバンカーがピラミッドの頂点にいるので、仕事となると一糸乱れぬ軍隊的な強さを発揮する。ところが、持田さんの指令が最優先されるので、お客さんからは、〝どこを見て商売してるんだ?〟と思われることも多いのです」(外資系投資銀行幹部)
メリルリンチの網屋信介、ドイツ証券の結城公平、元モルガン・スタンレーの吉沢正道など、外資系投資銀行には「信頼できる日本人バンカー」がいる。しかしGSは、勝負にこだり続ける強靭な持田の顔しか見えてこない。
GSは、経営再建中の準大手ゼネコン「フジタ」へ410億円を出資した。さらに「西武鉄道」の買収へ照準を定めている。
しかし、こうした積極的な買収戦略は、まだ日本の市場で受け入れられていない。GSが一から立て直したゴルフ場ですら、「買い漁り」と言われてしまうほどだ。それは、日本テレコムなどのディールを通じて露見した「日本市場や株主を見下した」態度が原因ではないだろうか。
■ ■
持田の父・武雄は、家業の「メリノ」を廃業する際、下請け業者や納品先の百貨店に、一切の焦げ付きを発生させなかった。西武百貨店で「メリノ」の仕入れを担当していた萩本泰博が回想する。
「武雄社長の〝綺麗な廃業〟は、社内で話題になったほどです。その後、メリノの元社員が会社を作った時、西武の社員が一緒に工場まで行き、〝この方は信用できます〟と太鼓判を押したほどです。それほど武雄社長は尊敬され、信頼されていました」
持田の生き方は、父親とは対照的だ。アメリカナイズされた合理主義者でも、頭がいいだけのトレーダーでもない。むしろ、企業統治の手法も営業スタイルも極めて古典的な「日本流」である。
持田は、西川を接待した西麻布のフランス料理店で、深夜までカリフォルニアワインを飲みむことが多い。昼間、まりなじを決して部下を叱責している持田は、この店ではどこにでもいる50代のサラリーマンのようになる。チェーンスモーカーの持田は、セブンスターを次々に灰にしながら、
「俺が人から悪く言われてるのは分かってる。どうせお前も嫌いなんだろ」
と部下に嘯き、笑っているという。しかし、持田の口からは、言い訳も他人の悪口も出てこない。キレイ事を言って自分を正当化しようともしない。ただ、「勝つ」ことだけを目的に働き続けている。〝最も成功した日本人インベストメントバンカー〟と言われる持田は、実は、〝最も古いタイプの日本的経営者〟の生き残りなのかも知れない。
そして「独裁者」となった持田が退任するまで、GSが日本市場での信頼を得られなければ、「金儲けが上手いだけの尊敬されない外資」という評価に終わってしまうだろう。
(文中敬称略)
初出:「ハゲタカ外資の虚像と実像」(後編)『週刊新潮』2005年7月14日号