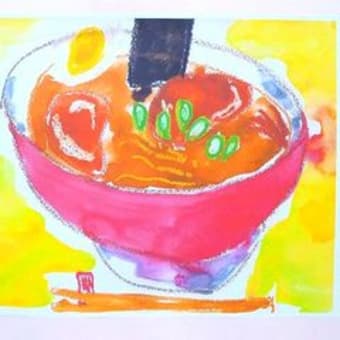76.楽しく宿題!(4)
「知的障害児者、発達障害児者 個性と可能性を伸ばす!」
造形リトミック教育研究所
*楽しいからのパートナー
*新しく知るからのパートナー
*ちょっと簡単からのパートナー
 おはようございます。
おはようございます。宿題を楽しくこなすのにはどうしたらよいでしょうか。具体的な課題を想定して、気楽に考えていきましょう。
今日は、「算数:文章題」
「文章題は苦手」と言うお子さんはたくさんいます。「得意」と言う方が珍しいくらいです。「見るだけでイヤ!」となる前に、楽しく取り組みましょう。
10以下の数なら足し算や引き算ができるお子さんでも、2~3語の文の読解が難しい場合は、「文章題は苦手」でも当然です。そんな段階で、文章題の宿題が出たらどうしたらよいでしょうか?課題をどのようにアレンジしたらよいでしょうか?
決して、叱らりたくない!。また、「○○までに提出する」という先生との約束は守らせたい!そのためには、こんな工夫をしてみましょう。
1)問題を読むことを課題としましょう。あとは、教えてあげながら、書き込ませましょう。
2)問題の内容に対して親御さんが質問をし、その答えを導くことを課題としましょう。言ってみれば「読解」の学習です。「この問題には、だれが出てくるの?」「だれのお話?」「何を買ったの」「何は、いくらだったの?」「問題は、何をきいているの?」・・・というふうに。
あとは、教えてあげながら、書き込ませましょう。
3)式の立て方は、教えてあげましょう。具体物や数カードを操作しながら説明できれば理想的です。しかし、全問をていねいに説明すると、子どもはかえって付いてこられなくなることがあります。混乱するのです。1問だけ、せいぜい3問くらいでいいのです。式を言ってあげながら、書くように促し、書いて、
見て、読んで、確認しましょう。
4)完璧に理解させよう、教えよう、わからせようとしないことです。やってみせる、それでいいのです。ストレスを与えなければ、子どもは聞いています。苦手意識を持つことも少なくなります。
幼いときに数を数え始めた頃を思い起こしてみましょう。私達も、はじめから数概念が形成されていたわけではありません。一緒に声を出して見よう見まねで、くり返しくり返し数えているうちに、数概念が形成されてきたのです。
5)「お母さんと楽しく勉強した」「宿題、もうできちゃった」という気持ちを大切にしましょう。お母さんもストレスをためないことです。
造形リトミック教育研究所
>>ホームページ http://www.zoukei-rythmique.jp/
>>お問い合せメール info@zoukei-rythmique.jp