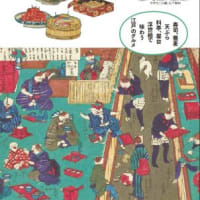昨日(2015/04/18)は、せっかく上野に来たので、
東京藝術大学大学美術館にも行っていました。
行ったのは、新年度に入ってまもなくから、
開催されている『ダブル・インパクト』。
なんか引かれたんですよねぇ。
何が“ダブル”かというと、ボストン美術館と
東京藝術大学のコレクションを合わせるということで、
近代の日本と西洋の相互影響関係を示してみようとする
ものと言うことらしいです。
通常であれば、会場間もない時間帯に行くところなのですが、
上記の通り、この日は夜に『大英博物館展ナイト』に参加予定。
と言うことで、昼も過ぎて、まもなく夕方になりそうな時間帯に到着。
テーマ的に、混むことはないだろうと思っていましたが、予想通り。
でも、なんか、観光旅行のバッジを付けた年配の人達が
多数見受けられたので、日帰り観光とかのコースに
なっているんですかね?
展覧会の後世の通り、黒船来航の頃から展示は始まります。
作者不詳の《ペルリ浦賀上陸図(19世紀後半江戸時代、
ボストン美術館蔵)》には、船の大きさなどの
スペックが記されているんですよね。
これにはビックリ。
その後の戦を想定して、索敵でもしていたんでしょうかね?
河鍋暁斎の《地獄太夫と一休(1870-1880年代、ボストン美術館蔵)》ですが、
地獄太夫って、いろいろあるんですね。
誰の作品だったか忘れてしまっているんですが(苦笑)、
他の地獄太夫作品も見たことがあります。
着物の柄が、中々オドロオドロしい・・・。
柴田是真の《野菜涅槃図蒔絵盆(1888年、ボストン美術館蔵)》。
先日、サントリー美術館で伊藤若冲の《果蔬涅槃図》を見たんですが、
野菜をブッダの涅槃に見立てて描くって、ポピュラーなの?
同じような見立てずに驚きました。
でも、若冲の方が、コミカルで好きかな。
ポスターとかで目にして気になっていた
小林永濯の《菅原道真天拝山祈祷図(1860-1880年代・明治時代、
ボストン美術館蔵)》
ですが、完全に劇画ですね。
それが100年も前に描かれているのには驚きです。
久米桂一郎の《夏の夕(鎌倉)(1894年、東京藝術大学蔵)》は、
モネの《積みわら(1890-1891年、シカゴ美術館蔵)》じゃないのか?
構図とか、テーマとかが激似と思いました。
時代的に、モネに久米桂一郎が触発されたというのは、
有り得る話ですね。
いやぁ、結構勉強になりました。
日本と西洋の交流で、良くも悪くも、
より文化的な発展が進んでいたことが、良くわかりました。
空いていたことも、良かったかな(苦笑)
| 名称 | ボストン美術館×東京藝術大学 ダブル・インパクト 明治ニッポンの美 http://double-impact.exhn.jp/ |
|---|---|
| 会期 | 2015年4月4日(土)~5月17日(日) |
| 会場 | 東京藝術大学大学美術館 本館 展示室1、2、3 |
| 当日観覧料 | 一般1500円、高校生・大学生1000円、中学生以下無料 |
| 開館時間 | 10:00~17:00(入館は閉館の30分前まで) |
| 休館日 | 月曜日(4月6日、5月4日は開館) |
| 巡回展 | 2015年6月6日(土)~2015年8月30日(日) 名古屋ボストン美術館 |