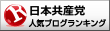政府は、菅首相が18日に建設アスベスト訴訟原告団と面会すると発表した。
国とメーカーの賠償責任認定 権限不行使「違法」―建設石綿訴訟判決・最高裁
建設現場でアスベスト(石綿)を吸い込み健康被害を受けたとして、元労働者と遺族計約400人が国と建材メーカーに損害賠償を求めた4件の集団訴訟(横浜、東京、京都、大阪)の上告審判決が17日、最高裁であった。第1小法廷の深山卓也裁判長は、国と一部メーカーの賠償責任を認めた上で、国が規制権限を行使しなかった「違法期間」を1975~2004年と認定した。個人事業主の「一人親方」に対する国の責任も認めた。5人の裁判官全員一致の意見。
建設アスベスト原告団、最高裁勝訴 2021.5.17
小池書記局長記者会見




神奈川


TBS


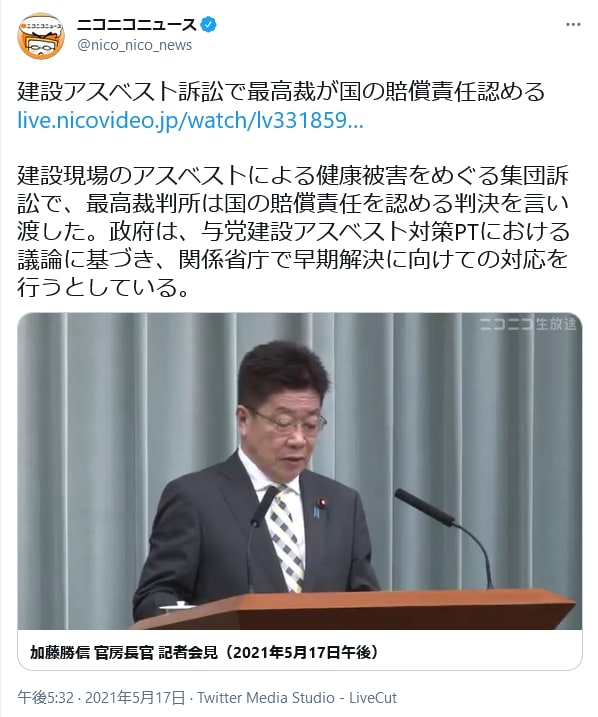
加藤官房長官
命あるうち「全員救済を」 元左官、夫と長男失った妻―判決に切望・建設石綿訴訟
建設石綿訴訟をめぐる初の統一判断。建設現場での石綿被害者は国の認定だけで約1万人に上る。判決を受け、与党のプロジェクトチームは救済策を決定、原告団も同意した。一律解決に向けた動きが加速しそうだ。
小法廷は、72年には石綿の発がん性が明らかになったと指摘。石綿に関する規制が強化された75年10月には、国は建材の粉じんを吸うと肺がんなどを発症する危険があることや、防じんマスク着用の必要性を建材などに表示するよう指導監督すべきだったとした。石綿使用が原則禁止される直前の04年9月まで違法状態が続いたと認定した。
労働安全衛生法の直接の保護対象ではない一人親方も、建設現場で石綿の危険性を掲示するなどして保護されるべきだったとし、国の責任を認めた。屋外労働者については、屋内と比べると粉じん濃度が低く、危険性を認識できなかったとして、国とメーカー双方の責任を否定した。
原告側は、労働者が多数の現場で複数の建材を使うことなどから、原因となった建材の特定が難しいとし、建材ごとに市場シェアの高いメーカーの責任を問うた。小法廷は「シェアが高く、現場の数が多いほど、建材が被害者に到達した蓋然(がいぜん)性は高くなる」として、原告側の立証手法は合理性があると述べ、一部メーカーの責任を認めた。
同小法廷は判決に先立つ決定で、国とメーカーの責任を部分的に確定させてきたが、理由は示していなかった。 時事ドットコム
徳島新聞2021.5.18
徳島建設労働組合のアスベストの取り組み