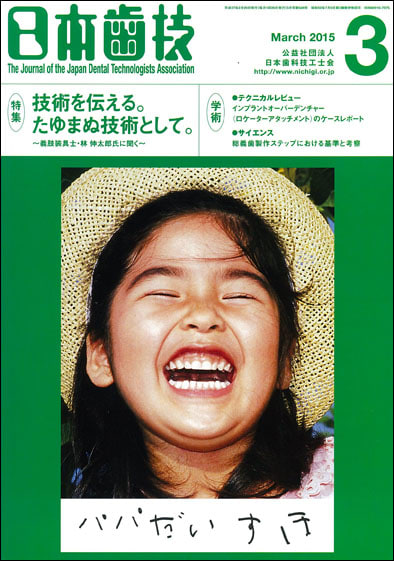
『日本歯技』2015年3月号
書評『歯科五法コンメンタール-歯科関連法律の逐条解説-』

評者 日本歯科技工士会副会長 時見高志
本書は、歯科医療と歯科界を取り巻く環境が急速な変化に対応するため、歯科医学および歯科医療を社会科学的見地から考察する専門化が集まる「社会歯科学研究会」が編集し発刊したものである。
同会は、急速に変化する医療界を取り巻く環境に対応するため、社会歯科学を専門とする大学等の研究機関や歯科医師会等の医療現場の従事者と行政関係者が集まり2007年(平成19年)に設立され、月に2度程度の研究会と年に一度の研修会及び総会を開催し、全国から幅広い分野の研究領域の関係者が集まり、情報の収集と社会科学による問題提起と解決に向けた討議や研究等を重ねている。
当面の課題として、歯科医療提供体制のあり方や歯科医療従事者への教育、医療安全及び感染予防システム、歯科保健医療や保険外併用療養等を含めた医療経済、各種関係法令との関連等、多岐にわたる分野について社会科学を通じた研究を行っている。
さて、本書は“歯科五法”、即ち「歯科医師法」、「歯科衛生士法」、「歯科技工士法」、「医療法」、「歯科口腔保健の推進に関する法律」のそれぞれについて、制定の経緯と法律の文言を、法令の各条文に沿ってわりやすく解説したものである。
私たち歯科技工士が日常の業務を行う上で、専門家である医療従事者として当然知っておかなければいけない「歯科技工士法」は、1955年(昭和30年)、第22回特別国会に於いて、政府提案による「歯科技工法」(法律168号)が制定され、今年は法制定60週年の節目を迎える。
法制定の後、その条文は社会環境の変化とともに必要な改正を重ねられた。1982年(昭和57年)に、それまでの都道府県知事免許から厚生大臣(当時)免許に移行し、1994年(平成6年)には、「歯科技工士法」に名称変更されるとともに、文部大臣(当時)の指定する歯科技工士学校の卒業者についても歯科技工士試験を受験出来ることとなり、大学化への道が拓けた。2009年(平成21年)には、国家資格であることを明確にするため、「歯科技工士試験」から「歯科技工士国家試験」となった。
そして、昨年(平成26年)1月24日に開かれた第186回通常国会において、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」(医療介護総合確保推進法)が、内閣提出法案として国会に提案され、改正歯科技工士法の施行は2015年(平成27年)4月1日となり、平成27年度の歯科技工士国家試験、即ち2016年(平成28年)春に実施される試験からとなる。今後、歯科技工士法改正に伴い、歯科技工士施行令と歯科技工士法施行規則も改正されることとなる。
法律の文言は読みにくいことが多く、兎角苦手とする傾向があるが、本書はそれを解りやすい文言で補い、また、専門家として“当然”知っておかなければならない「歯科技工士法」や、関連する法律等についても学ぶことが出来る“おすすめ”の教本である。
編著:社会歯科学研究所
発行:ヒョーロン・パブリッシャーズ
定価:3500円(税別)


















