
扉を開けると、世界はモノクロに覆われていた。
――天気予報では晴れと言っていたが、どうやら外れたようだ。しかし雨が降っていないのは不幸中の幸いかもしれない。少し肌寒さを感じ、何か羽織るものを取りに部屋に戻る。何を着るか少し悩んだ末、くすんだラベンダー色のカーディガンに袖を通した。
扉の鍵をかけながら頭の中で忘れ物がないか最終確認を行い、愛車に乗り込む。去年買った軽自動車で、そのくせオープンカーという中々面白い車だ。車にこだわりはないが見た目が可愛くて買い、今ではとても気に入っていた。
エンジンをかけ、カーナビで目的地である隣県の温泉旅館を検索する。今日は日帰り入浴のみだが、いつか泊まってみたいとずっと考えていた憧れの宿だ。曇り空は残念だが、それさえどうでもよくなるほど気持ちは弾んでいた。ハンドルを握る。愛車は滑らかに動き出した。
心地よい振動に身を任せながら、前方への注意もそこそこに、思考は別の世界へ飛び込んでいった。先週食べた洋梨のタルトのこと、一昨日読んだ恋愛小説のこと。想像は徐々に今に近づき、そして昨日の出来事へと移っていった。
視界がよりいっそうモノクロに染まる。
仕事でそれなりなミスをした、やや煩わしい記憶。珍しく上司にお小言をもらって、ややへこんでいた。いや、ミスしたことも、お小言を言われたこともへこみはしたが、一番へこんだのはそれを見た同僚の一言だったかもしれない。
「美咲ってさ、めちゃめちゃ楽観的…ていうか能天気だよねー。悩み事とかあんまりなさそう。」
彼女は悪気なくそう言った。だけど、なんか落ち込んだ。なぜ能天気と感じたのかはよくわからないが、「もしかしたら怒られているときにヘラヘラしてたかな」とか、「このくらいのミスならいいやって態度だったかな」とか、色々と考えてしまう。
しばらくもやもやしているうちに、気が付けば鉛色の空は所々に青色を覗かせていた。窓の外に目をやり、なんとなく少しの間を挟んでルーフを開け、太陽の光を車内いっぱいに取り込む。なんだが、もやもや悩んでいたのが馬鹿らしくなった。こういう所が「能天気」と言われる所以なのかもしれない。じゃあもう、能天気でもいいや。今日私は憧れの温泉に行くのだ。能天気だろうが何だろうが、温泉の前では些細な問題だ。さっきまでの落ち込みは嘘のように、気持ちが晴れやかになった。
しかし、そんな能天気な自分だけど、たまに「死」を考えるときがある。何も本気で死のうと思うわけではないが、「もし今自分が死んだら、周りの人はどんな反応をするだろう。」と考えて、なんとなく死にたくなる。理由なんてない。ただ、私が死んだら…お母さんとお父さんは泣いてくれるかもしれない、友達はどうだろう、泣く子と意地でも泣かず笑顔で見送ってくれる子にわかれそうだな、あ、でも朝陽は絶対泣きもしないし笑いもしないだろうな、心の中では一番悲しんでくれそうだけどな…。想像して、その場面を見てみたくなる。だけど、実際に死んだところでその場面は見れないし、まだまだ死にたくはないので実際に行動に移したことはまだない。
大学の頃、この話を友人にしたことがある。彼女は、
「あー、うん。あるある。たまに考えるときあるよ。なんとなくね。」
と言っていた。自分だけじゃないんだ、と少し安心したのを覚えている。もしかしたら話を合わせてくれただけかもしれないけれど、その考えを否定されなかったことが嬉しかった。
そうこうしているうちに、温泉宿のある街に着いた。建物はどれも古く、寂れたシャッター街という印象だ。そういえば、人が住まなくなると家は一気に老朽化すると聞いたことがある。きっと、街もそうなのだろう。通りを歩く人は見当たらなかった。
ナビによるとここからもう少し走るらしい。山の中にある宿なので、当然といえば当然だ。静かな街路を進む。
しばらくすると、道路の奥にひとつの建物が目に入った。他の建物と比べてやけに綺麗で、手入れが行き届いている。一体何だろうか。近づくと「家族葬」の文字が像を結ぶ。なるほど、葬儀場か。なんだってこの建物だけ小綺麗にされているのかと少し疑問に思ったが、考えても意味がないのでやめた。
道なりに進む。
すると、またやけに綺麗な建物が見えてきた。まさかと思い目を凝らすと、やはり葬儀場だった。こんなに近くに葬儀場があるものだろうか、ほぼコンビニくらいの間隔だ。なんとなく異質だが、そんなこともあるだろうと葬儀場の横を通り過ぎ、カーブに差し掛かった。目線を前方へと戻し、道の奥を見据える。そこに見えた建物は、またもや葬儀場だった。ここまでくると不気味だ。
結局、宿に着くまでに見かけた葬儀場の数は優に20を超えていた。
宿は、市街地からやや離れた山中にあった。近くを川が流れているらしく、川のせせらぎが聞こえる。昔ながらといった感じの風情ある造りの受付には、妙齢の女性が無表情で立っていた。
「あの、すみません。日帰りで温泉を利用したいんですけど。」
声をかけた瞬間女性は途端に笑顔になり、
「ああ、ようこそいらっしゃいました。若い方は珍しいものですから。」
少し驚いてしまいました、ふふふ。そう笑って温泉施設の説明を始めた。声はとても落ち着いており、聞いているとなんとなく安心感がある。無表情のときは大人びていた印象だったが、こうしてみると年齢相応で、むしろ少し幼さがみえる。
「――以上ですが、なにかご質問はありますか?」
いえ、と答えようとして、先程の葬儀場が頭を過ぎった。質問があれば是非、とにこにこ笑う彼女の顔を見ていると、どんな質問でも答えてくれそうだ。
「あの、全然温泉とは関係ないんですけど…。」
「ああ、はい。なんでしょうか?」
彼女の長いまつげの奥の瞳が、こちらをまっすぐに見据えている。
「ここに来るまでの間に、葬儀場がやたらたくさんあって…。どれも綺麗だったし。何か少し気になってしまって。」
「やっぱり。それかなぁと思いました。」
笑顔のまま、彼女は答えた。
「単純に、人がたくさん亡くなるんです。ここらへんは。」
あっけらかんとしている。
「たくさん…?えっと、それは何でですか?」
「さあ…。」
笑顔が消えた。
「ただ、自損事故とかが多いですよ。あとは、自殺とか。亡くなった人は喋りませんから、理由はわかりませんが。」
上目遣いでこちらを見る。
「お姉さんは、‘’もし今自分が死んだら皆どんな反応するかな‘’って考えたこと、あります?」
「え…」
「私は、たまに考えることがあります。それで死ぬなんて、馬鹿らしいことですけどね。」
ふっと彼女の口の端が優しく上がる。
「でも、そういう些細なことなのかもしれませんね。」
そう言って目を伏せた。
私は、温泉には入らずそのまま帰ることにした。急にこの街が不気味に思えて、すぐに帰らなくてはいけない気がした。
愛車のエンジンをかけ、ルーフは閉じたままアクセルにのせた足を傾ける。いつもは心地よい振動が、何だか気持ち悪かった。
しかし、街を抜けると徐々に「もったいないことをしたな」という気持ちが強くなってきた。再び宿に戻ろうかと考えたが、もうかなりの距離を戻ってきてしまったのでまた引き返すのも憚られる。
まあ、いいだろう。次は宿泊で訪れて、嫌というほど温泉に浸かればいい。今日はもう寄り道しながら帰ることにしよう。
あ、近くに牧場があるなぁ。久しぶりにアイスクリームでも食べようか。ああでもあっちの渓谷を見に行くのもいいかも。あーあ、朝陽と来られたらもっと楽しかったのに…。あ、そうだ、朝陽に何かお土産を買って帰ろう。喜びそうなの何かあるかなぁ。
何だか楽しくなってきた。ハンドルを握る手から少しだけ力を抜き、ルーフを開けると、『交通事故注意』の看板が目に入った。世界はモノクロに覆われている。
…もしこのまま帰らなかったら朝陽は心配するだろうか。優しい朝陽のことだから、「やっぱり自分も行けばよかった」って思うんだろうか…。途中で交通事故にでもあって、病院に運ばれたりしたら…朝陽は怒るかな、お母さんは泣いちゃうかも。お父さんはどうかなぁ…意外と朝陽と一緒になって怒ったりす















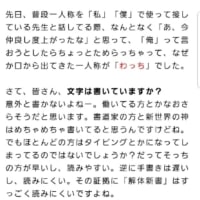




ですが今回だけは単純に「死人には喋ることができない」という意味で読んでくださいませ。お願いね。