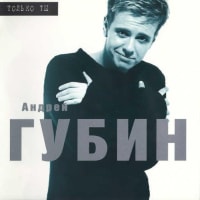ロシアと近隣諸国の音楽を中心とした芸能情報を紹介するコーナー「ユーラシア音楽芸能情報」を発信中!(^_^)v
ユーラシア圏でのLGBTアーティスト事情 (1)
ロシア芸能界の中で両性愛者であることをカミングアウト(※)しているアーティストはただひとり、ボリス・モイセーエフである。1954年生まれの58歳。歌手でありダンサーであり振付師であり・・・・多芸多才ぶりでロシア連邦芸術功労賞を受賞し今も尚走り続ける彼だが、生まれた時から壮絶な人生である。
ベラルーシの獄中で生まれ、父親を知らず、政治犯で投獄されていた実母の元で育ったボリス。ミンスク市の舞踊学校でクラシックバレエを学んだ。その後、ウクライナのハルキウ市に移り、オペラやバレエの経験を積み重ね、10代後半で演出家になった。70年代に歌謡界の大御所アッラ・プガチョワの劇場で活躍した。
1993年に英国のスーパースター、フレディ・マーキュリーを悼み創作した戯曲「ショーは続く-フレディ・マーキュリーの記憶(Шоу продолжается — памяти Фредди Меркьюри)」を上演。また90年代から歌手業にも進出し、こちらでも歌手モイセーエフとしての地位を築いた。

▲フレディ・マーキュリー追悼戯曲「ショーは続く-フレディ・マーキュリーの記憶」
クラシックバレエの影響があるためか、彼の外見や芸風は無骨な男ではなく、端正なメイクが施されたどことなくフェミニンな雰囲気がある。90年代半ばに創作する戯曲についてこうコメントした。「悲劇と愛を歌うんだ。僕はいつも男と女、男と男の間に生まれる人間の感情の深さを見せている。乱高下する、これが愛なんだ。僕はステージの上で感情のストーリーを演じているんだ。」
こうコメントしてから、彼のキャリアに暗雲がかかり始めたようだ。芸術と性的嗜好をごちゃまぜに考える短絡的な露マスメディアはこれを面白可笑しく取り上げ、彼のキャリアと周囲に致命的な影響を与えた。1997年と1999年には当時新鋭アーティスト、ニコライ・トゥルーバチとのデュエットソング「水色の月(Голубая луна)」、「くるみ割り人形(Щелкунчик)」を世に出した。彼らが所属していた芸能プロダクションの入れ知恵から創作されたいずれも愛をテーマにした名作であるが、ガルボーイ(Голубой)とはロシアで「ゲイ」を意味する隠語である。このため、特に前者の歌は巷で「ゲイのための聖歌」と見なされ、ニコライまでもゲイと見なされてしまったのだ。

▲ボリスのコンサートポスターに貼られた白い小紙。
「チケットを買って、ホモセクシャリストたちの
増殖を促進させてください。」と書いてある。
2002年あたりから、ロシア全土に渡る大規模な抗議運動が勃発した。
ボリスはあらゆる宗教を敬愛しているのにも拘らず、同性愛を認めないロシア正教団体を始めとする各種宗教団体やその信者らから「宗教的感情への侮辱と同性愛の喧伝」と、猛烈な反対を受けた。
そして、40都市以上のコンサートがキャンセルされた。コンサートを敢行した会場の前には、大勢の抗議団体がつめかけ抗議運用やコンサートの監視活動を行なった。

▲抗議の様子(左)。同性愛が氾濫して町が滅んだという旧約聖書の
「ソドムとゴモラの戒め」から。「死ぬべき男色(ソドミア)。罪だ!
ロシア正教の国に変態のいるべきところはない。」と書いてある。

▲抗議の様子(右)。「ゲイのボリス、牢獄でドブネズミを楽しませな!
刑法第282条「人間の品格を破壊するに等しい、憎悪または反目分子
の扇動に関する法」を、第121条「AIDSウイルス伝染に関する法」
に変更しよう)」と書いてある。
また意外なことに、味方をしてくれてもいいはずの同性愛者からも大きな不満を受けてしまった。というのは、2006年5月にモスクワで行なわれたゲイパレードに不支持だったからである。「私達は耐えることで目的を達したい。(ゲイパレードのような)あからさまな行動は、大多数の人々を怒らせるだけだ。ロシアみたいな国だからこそ、注意を払わなければならない。」「同性愛者が自身の性的嗜好を見せびらかすようなことをするのは、正しいとは思わない。」と表明したのだ。このため、彼が築き上げる同性愛のイメージは同性愛者間で、「老道化師が繰り広げる、膨大な金目当てのショー」と、ひどく否定的に捉えるようになったのだ。
このようなアーティスト生命を揺るがす災難に見舞われ、ボリスは統一ロシアの党員に保護を求めた(実はボリス自身も統一ロシア党員)。2010年には米国女性と結婚しており、現在は比較的落ち着いているようである。しかし何か彼の話題が出ると、マスメディアも視聴者も色眼鏡で見るという姿勢は変わっていない。
※自身の出生や病気、性的嗜好などを公に告白すること。最近ではカミングアウトとは性的嗜好のことをよく指す。
ボリス・モイセーエフ公式サイト http://bmoiseev.com/
▼ボリスの戯曲「不身持の子供(Дитя порока)」[1994年]
▼ボリス・モイセーエフ&ニコライ・トゥルーバチ「水色の月(Голубая луна)」[1997年]
▼ボリス・モイセーエフ「僕は君を失えない(Я не могу тебя терять)」 [2010年]



ロシア芸能界の中で両性愛者であることをカミングアウト(※)しているアーティストはただひとり、ボリス・モイセーエフである。1954年生まれの58歳。歌手でありダンサーであり振付師であり・・・・多芸多才ぶりでロシア連邦芸術功労賞を受賞し今も尚走り続ける彼だが、生まれた時から壮絶な人生である。
ベラルーシの獄中で生まれ、父親を知らず、政治犯で投獄されていた実母の元で育ったボリス。ミンスク市の舞踊学校でクラシックバレエを学んだ。その後、ウクライナのハルキウ市に移り、オペラやバレエの経験を積み重ね、10代後半で演出家になった。70年代に歌謡界の大御所アッラ・プガチョワの劇場で活躍した。
1993年に英国のスーパースター、フレディ・マーキュリーを悼み創作した戯曲「ショーは続く-フレディ・マーキュリーの記憶(Шоу продолжается — памяти Фредди Меркьюри)」を上演。また90年代から歌手業にも進出し、こちらでも歌手モイセーエフとしての地位を築いた。

▲フレディ・マーキュリー追悼戯曲「ショーは続く-フレディ・マーキュリーの記憶」
クラシックバレエの影響があるためか、彼の外見や芸風は無骨な男ではなく、端正なメイクが施されたどことなくフェミニンな雰囲気がある。90年代半ばに創作する戯曲についてこうコメントした。「悲劇と愛を歌うんだ。僕はいつも男と女、男と男の間に生まれる人間の感情の深さを見せている。乱高下する、これが愛なんだ。僕はステージの上で感情のストーリーを演じているんだ。」
こうコメントしてから、彼のキャリアに暗雲がかかり始めたようだ。芸術と性的嗜好をごちゃまぜに考える短絡的な露マスメディアはこれを面白可笑しく取り上げ、彼のキャリアと周囲に致命的な影響を与えた。1997年と1999年には当時新鋭アーティスト、ニコライ・トゥルーバチとのデュエットソング「水色の月(Голубая луна)」、「くるみ割り人形(Щелкунчик)」を世に出した。彼らが所属していた芸能プロダクションの入れ知恵から創作されたいずれも愛をテーマにした名作であるが、ガルボーイ(Голубой)とはロシアで「ゲイ」を意味する隠語である。このため、特に前者の歌は巷で「ゲイのための聖歌」と見なされ、ニコライまでもゲイと見なされてしまったのだ。

▲ボリスのコンサートポスターに貼られた白い小紙。
「チケットを買って、ホモセクシャリストたちの
増殖を促進させてください。」と書いてある。
2002年あたりから、ロシア全土に渡る大規模な抗議運動が勃発した。
ボリスはあらゆる宗教を敬愛しているのにも拘らず、同性愛を認めないロシア正教団体を始めとする各種宗教団体やその信者らから「宗教的感情への侮辱と同性愛の喧伝」と、猛烈な反対を受けた。
そして、40都市以上のコンサートがキャンセルされた。コンサートを敢行した会場の前には、大勢の抗議団体がつめかけ抗議運用やコンサートの監視活動を行なった。

▲抗議の様子(左)。同性愛が氾濫して町が滅んだという旧約聖書の
「ソドムとゴモラの戒め」から。「死ぬべき男色(ソドミア)。罪だ!
ロシア正教の国に変態のいるべきところはない。」と書いてある。

▲抗議の様子(右)。「ゲイのボリス、牢獄でドブネズミを楽しませな!
刑法第282条「人間の品格を破壊するに等しい、憎悪または反目分子
の扇動に関する法」を、第121条「AIDSウイルス伝染に関する法」
に変更しよう)」と書いてある。
また意外なことに、味方をしてくれてもいいはずの同性愛者からも大きな不満を受けてしまった。というのは、2006年5月にモスクワで行なわれたゲイパレードに不支持だったからである。「私達は耐えることで目的を達したい。(ゲイパレードのような)あからさまな行動は、大多数の人々を怒らせるだけだ。ロシアみたいな国だからこそ、注意を払わなければならない。」「同性愛者が自身の性的嗜好を見せびらかすようなことをするのは、正しいとは思わない。」と表明したのだ。このため、彼が築き上げる同性愛のイメージは同性愛者間で、「老道化師が繰り広げる、膨大な金目当てのショー」と、ひどく否定的に捉えるようになったのだ。
このようなアーティスト生命を揺るがす災難に見舞われ、ボリスは統一ロシアの党員に保護を求めた(実はボリス自身も統一ロシア党員)。2010年には米国女性と結婚しており、現在は比較的落ち着いているようである。しかし何か彼の話題が出ると、マスメディアも視聴者も色眼鏡で見るという姿勢は変わっていない。
※自身の出生や病気、性的嗜好などを公に告白すること。最近ではカミングアウトとは性的嗜好のことをよく指す。
ボリス・モイセーエフ公式サイト http://bmoiseev.com/
▼ボリスの戯曲「不身持の子供(Дитя порока)」[1994年]
▼ボリス・モイセーエフ&ニコライ・トゥルーバチ「水色の月(Голубая луна)」[1997年]
▼ボリス・モイセーエフ「僕は君を失えない(Я не могу тебя терять)」 [2010年]