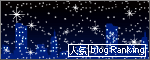先日、お茶のお稽古(5回目)をしました。
テーマ『長月のもてなし』
二十四節気 『白露』
9/7~23頃
この時期になると大気が冷えて
朝の光に白く露が輝きます。
昔の人は「白露」と表現しました。
* 二十四節気とは、
旧暦(太陰太陽暦)において最も日が短くなる冬至を基準とし
1年を24の季節に分けたものです。
お稽古に行くと初めに
お茶?お白湯?が出されます。
今回のお茶は『菊🌼 の節句』に因んだお茶です。
わあ〜〜!! 菊の花びらが浮かんでるぅ〜〜💛

9月9日
重陽(ちょうよう)の節句
別名 ”菊の節句"
菊には魔力、霊力があると言われ
縁起の良いお花とされています。
今日はお干菓子を先にいただきます。


奈良・樫舎謹製
左:うさぎ(和三盆糖)
ピンクのうさぎが月を見上げていますね。
右:名月 満月に見立て。
ほんのり密の甘さに
裏面に白ごまがつけてあり、香り高いお菓子です。
こちらは薄茶(抹茶の中でもカジュアルタイプ)


「粉引く」という白い器です。
今回は4人の生徒さんの器が違っていました。
(すみません、写真撮ってないです。)
2度目の主菓子
『着せ綿』
重陽の節句前日、
菊の花に真綿をかぶせて菊の香りと夜露をしみ込ませ、
その綿で身体を拭いて長寿を願いました。
この慣習を「着せ綿」と言います。


割ってみると
こし餡が入っていました。
子供の時から甘いの苦手なマンマは
和菓子、半分でいいかも?
とか
早くお茶が来ないかな〜。
と
邪念がよぎります💦
美味しいんですけど、
お茶の方が好きです💕

待ちに待ったお茶選びです!!
今日のお茶は
苦味と甘味のバランスが取れた
『白』
を選びました!!

レッスン内2度目のお茶は
自分でお抹茶を立てていただきます。

いつもはここで写真を撮るのを忘れ
茶筅でカシャカシャ始めますが
5回目でちょっと余裕が出てきました。
お湯を入れていただき
これから
カシャカシャ始めますよ〜。

はい!!
すぐできます💕

美味しくって
心が落ち着きます✨✨

茶論の今月の設えです。
お軸ですが、地味〜な感じでした😅
『月』
線描きせず、月を浮かぶように見せています。
立体的ってことかしらん。
ワビサビがわかっていないマンマですので
気にしないでくださいませ。
想像力を働かせてくださいってことですね。


中島 来章
(寛政8年〈1796年〉 - 明治4年7月15日〈1871年8月30日〉)は、
幕末から明治時代にかけて活躍した円山派の絵師。
すごく長いお軸で、
私のiPhone 11 Pro はこれがやっとでした💦
下切れちゃった。

今月のお花です。
山代菊
秋明菊
りんどう
なでしこ
女郎花
(上2つは秋の七草)
あざみ

花入れは
魚の籠です。
( 利休は魚を入れるものを見立てました。)
この花入れは時代も作者もわかりません。

脇
錫縁香合 (すずぶちこうごう)
蒔絵
漆で絵を描いて金銀を付着させます。
錫は匂いも毒もないので
食器に使われました。


菊と桐のお香入れですね。
こんな時、蓋を開けて中が見たくなっちゃう
マンマです💕

5回目のレッスンも
楽しく受ける事ができました。
きちんと覚えていませんが
そろそろ初級コースが終わります。
これで大丈夫でしょうか?
お茶会の前に
勉強しなきゃ💖✨
 また遊びにいらしてね
また遊びにいらしてね
 ランキングに参加しております。
ランキングに参加しております。

ついでにこちらも
♡Copyright 2021 Felice*mamma♡