明日いよいよ試験本番という事で朝から追い込みで過去問復習です
また頭痛がひどくなってきたので、薬を飲んでがんばっていきます
「技術および理論」
1回目自己採点:28点
2回目自己採点:76点
3回目自己採点:
10、10、8、10、6、10,10、8,10,10 → 合計 92点
「法規」
1回目自己採点:52点
2回目自己採点:84点
3回目自己採点:
16、16、16、20、20 → 合計 88点
「技術および理論」
問1
4,3,1,3?、5,
→4,3,1,3,5
(2) p161 内線回路の参考図
試験引き込み回路→呼出信号制御回路→X通話電源供給回路→W過電圧保護回路
(3) p164 夜間閉塞機能とは
選択A:夜間閉塞を開始すると、電気通信事業者の交換機からの呼は、一般の電話機に着信する場合と
同様の接続シーケンスにyおり、夜間受付用電話機に着信する
選択B:夜間閉塞機能を利用するためには、夜間閉塞制御用として着信専用回線を各代表群別に設置し、
電気通信事業者の交換機に対してL1→「L2」線に地気を送出する必要がある
(4) p216 端末アダプタの機能
選択A:パケットモード端末側のLAPBと、Dチャンネル側のLAPDとの間で、プロトコルの変換を行う
選択B:非ISDN端末からのユーザデータ速度を64キロビット秒、または16キロビットに速度変換する
問2
4,2,4(他の通信方式確認)、2,3,
→4,2,4,2,3
(2) p263 SIPに関する説明、SIPサーバの構成要素のうち、登録を受け付けたUACの位置情報を管理するのはロケーションサーバ
※間違い選択 プロキシサーバは端末の代わりにSIPのメッセージを受信し転送する機能を持つ
(3) 参考ページなし?PLCはパワーラインコミュニケーションの略、屋内の電気配線を通信路として利用する方式
選択1:Wi-Fi(ワイファイ)とは、無線LANに関する登録商標である[1]。Wi-Fi Alliance(アメリカ合衆国に本拠を置く業界団体)によって、国際標準規格であるIEEE 802.11規格を使用したデバイス間の相互接続が認められたことを示す名称。
選択2:人口希薄地帯や、高速通信(光・メタル)回線の敷設やDSL等の利用が困難な地域で固定無線アクセスの代替、いわゆるラストワンマイルの接続手段として期待されている。近年は、高速移動体通信用の規格も策定されている。WiMAXは当初、中長距離エリアをカバーする無線通信を目的としておりWiMAXアクセス網は「Wireless MAN」(MAN:Metropolitan Area Network)と定義される。
選択3:Bluetooth Low Energy (Bluetooth LE, BLE) とは、無線PAN技術である Bluetooth の一部で、バージョン 4.0 から追加になった低消費電力の通信モード。Bluetooth は Bluetooth Basic Rate/Enhanced Data Rate (BR/EDR) と Bluetooth Low Energy (LE) から構成される[1]。
選択5:ZigBee(じぐびー)とは、センサーネットワークを主目的とする近距離無線通信規格の一つ。この通信規格は、転送可能距離が短く転送速度も非常に低速である代わりに、安価で消費電力が少ないという特徴を持つ。従って、電池駆動可能な超小型機器への実装に向いている。基礎部分の(電気的な)仕様はIEEE 802.15.4として規格化されている。論理層以上の機器間の通信プロトコルについては「ZigBeeアライアンス(ZigBee Alliance)」が仕様の策定を行っている。
問3
1、2,1,1,5,
→1,2,4、1、5
(1) p215 ISDNの構成
選択A:R点はアナログ端末などの非ISDN端末を接続するために規定されており、TAを介して網に接続される
選択B:S点はTA、NT2間に相当する、T点はNT1、NT2との間に位置する
(3) p234 レイヤ2における情報制御 上位レイヤからの情報は非確認形情報転送手順により UIフレームを用いて転送される
※間違い選択 Fビットとは 同期、保守、エラー検出用のビット(p227)
(5) p227~228 ISDNインターフェースレイヤ1、24個のFビットを活用して、
フレーム同期、CRCビット誤り検出、リモートアラーム表示などに利用している
問4
5,1,3,1,3,
→5,1,3,1,3
(2) p278 光アクセスネットワーク構成 AはADSの説明、BはPONの説明
(3) p280 にはSCM方式に関する説明はなし?
参考URL:https://masassiah.web.fc2.com/contents/17cte/note_ss213.html
(4) p260 PMTUDとは IPパケットの送信元からあて先までの経路上にあるバスにおいて、
IPパケットが分割されずに転送できるMTUを自動的に検出する機能のこと
(5) p274 IP-VPN→レイヤ3、広域イーサネット→レイヤ2、
MPLS網を構成するラベルスイッチルータは、MPLSラベルを参照してMPLSフレームを高速中継する
問5
1,4,4(計算)、5,4,
→2,3,4,5,4
(1) p289 呼損率、アーランB式が成立する条件
選択A:入回線数が有限→「無限」、出回線数が無限→「有限」のモデルにランダム呼が加わる
選択B:入回線に生起する呼の回線保留時間は互いに独立で、いずれも指数分布に従いかつ損失呼は消滅する
問6
5,1(他に認証方式確認),2,4,3
→5,1,2,4,3
(1) 参考ページなし? OP25Bとは ISPがあらかじめ用意しているメールサーバ以外からのメールをISPの外に転送しない仕組み
(2) 認証方式
選択1:シングルサインオンに関する説明 利用者が認証を一度行う事により、個々のシステムログイン操作が不要となる
選択2:アドレススキャン
ターゲットとなるネットワーク内に順番に「pingパケット」を送って応答が返ってくる機器のIPアドレスを調査する手法です。
選択3:ワンタイムパスワード
選択4:RADIUS(ラディウス、ラディアス、Remote Authentication Dial In User Service)は、ネットワーク資源の利用の可否の判断(認証)と、利用の事実の記録(アカウンティング)を、ネットワーク上のサーバコンピュータに一元化することを目的とした、IP上のプロトコルである。
選択5:CHAP は Point-to-Point Protocol (PPP) が、リモートクライアントの正当性を確認するための認証方法として使用される。CHAP は3ウェイ・ハンドシェイクによって、定期的にクライアントの正当性を確認する。これは、最初のデータ通信リンクを確立するときに行われ、その後はいつでも行われる可能性がある。この確認は、共有秘密(英語版) (例えばクライアントユーザのパスワード) に基づいている。
(3) p305 ※選択Aは間違いで、選択Bはあっている
選択A:S/MINEとは 第三者の認証機関により保証されたパスワード→「電子証明書」を用いる電子メールの暗号化方式である
選択B:PGPとは 送信者側がメッセージを共通鍵で暗号化し、さらに送信相手の公開鍵を用いて暗号化するハイブリッド方式
(4) p311~312 IDSの分類→NIDSの機能について 不正アクセスを検知する、
HIDSはファイル削除などのログ監視
※NIDSの機能で正しい:侵入を検知するための方法として、通常行われている通信とは考えにくい通信を検知する
アノまリバース検知といわれる機能などが用いられている
(5) p316 ※選択3が間違い
情報のラベルづけに関する適切な一連の手順は、認証機関→「組織」が採用した情報分類体系に従って策定し実施しないといけない
問7
3,2,4,1,1
→3,2,4、1、1
(5) 参考ページ?
選択A:サービスクラスの設定作業では、発信規制の設定などが行われる
選択B:コールピックアップグループは代理応答用、コールパークグループは保留応答用として設定するグループである
問8
2,3,1、3、2,
→4,3,1,3,2
(1) p338 ポイントツーポイント配線の動作距離 1000m程度(TTC標準)
(3) p339 ポイントツーマルチポイント構成について
選択A:延長受動バス配線構成では、バス配線の途中に信号の増幅や再生などを行う能動素子を取り付ける事が許容されてない
選択B:短距離受動バス配線構成では、1対のインタフェース線における配線極性は
全TE間で同一とする必要はなく → 「全TE間で同一とする必要あり」
(4) 反射減衰量については参考ページなし?
選択1:LAN配線のフィールドテストについては参考ページ見当たらず
選択2:参考ページ見当たらず
選択3:反射減衰量は、入力信号の送信レベルを基準として、反射した信号レベルを測定する事により求められる
選択4:参考ページ見当たらず
選択5:参考ページ見当たらず
(5) p361 ビルディング内の光配線システムの規定
選択A:床スラブ上の配線としては
「アンダーカーペット方式」「フリーアクセス方式」フロアダクト方式→「簡易床二重床方式」のいずれか採用
選択B:床スラブないの配線方式のうち、電線管方式は、配線取り出し口は固定され、他の方式と比較して、配線収納能力が小さい
問9
4,5,3,4?、5,
→4,5,3,4,5
(2) p 332 電話・情報設備の配線図用記号の中に「複合アウトレット」の記号は含まれていない
選択1:情報アウトレット
選択2:端子盤
選択3:電話用アウトレット
選択4:??? ボタン電話主装置に似ている
(3) p372 水平チャンネル長公式を用いて、固定水平ケーブルの最大長を求める
クロスコネクトTO→H=107ーFXの式で求める
(5) p358 MTコネクタ テープ心線相互の接続に用いられる (多芯) 単芯の場合はSCコネクタを使う
コネクタの種類 FCコネクタはねじこみ式なので注意
https://www.fiberlabs.co.jp/tech-explan/about-optical-connector/
問10
2,1,3,2,4,
→2,1,3,2,4
(1) p365 カットバック法による測定の定義 入射条件を変更せずに末端から放射される光パワーと入射点近くで
切断した光ファイバーから放射される光パワー測定し、計算式を用いて光ファイバの損失を求める方法
(4) p393 ヒストグラムに関する説明
データの存在する範囲をいくつかの区間にわけ、各区間を底辺とし、その区間に属するデータの出現度数に比例した
長方形を並べたものを指している
「法規」
問1
2,3,4,3、3
→2,3,4,3,5
(4) p410~411 重要通信の確保 8条、施工規則55条
水道、ガスなどの国民の日常生活に必要不可欠な役務の提供その他「生活基盤を維持」するため緊急を要する事項を
内容とする通信であって、これらの通信を行う者相互間において行わなれるものがある
(5) p415 端末設備の接続の技術基準 52条
電気通信回線設備を損傷し、またはその「機能に障害」を与えないようにする事
※「接続に制限」は間違いの選択 2回目に復習した時も同じ間違いをしていたので注意
問2
1,2,5,3,2,
→1,2,5,1,2
(4) p456~457 有線電気通信設備の届け出 3条
選択A:総務大臣は、有線電気通信設備を設置したものに対し、その設備が有線電気通信法の規定に基づく政令で
定める技術基準に適合しないため他人の設置する有線電気通信設備に妨害を与え、または人体に危害を及ぼし
もしくは物件に損傷を与えると認めるときは、その妨害、危害、または損傷の防止または除去のため
必要な限度において、その設備の使用の停止または改造、修理その他の措置を命ずる事ができる
選択B:有線電気通信設備を設置しようとするものは、有線電気通信の方式の別、設備の工事の体制→「設備の設置の場所」
設備の概要を記載した書類を添えて、設置の工事の開始の日の2週間前まで
(工事を要しないときは、設置の日から2週間以内)に、その旨を総務大臣に届けでなければならない
問3
5,3,4,3,1,
→5,2,4,3,1
(1) p430 用語の定義 2条
選択1:アナログ電話用設備 音声信号→アナログ信号を入出力とするもの
選択2:移動電話用設備 電波を使用するもの(無線がどうこうという定義ではない)
選択3:総合デジタル通信用設備 伝送速度が128ビット→64ビットとなっている
選択4:直流回路 プラグジャック式→ 2線式の接続
選択5:デジタルデータ伝送用設備 (これだけが正解)
電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、デジタル方式により、もっぱら符号または影像の
伝送交換を目的とする電気通信役務の用に供するものをいう
(2) p436 配線設備など 8条
選択A:電線と大地間の絶縁抵抗は、直流200ボルト以上の電圧で0.4→「1メガオーム」以上である事
選択B:配線設備等と強電流電線との関係については、有線電気通信設備令の規定に適合するものである事
※絶縁抵抗が0、2メガオーム以上となるのは電源回路と筐体の間の場合
(3) p436 過大音響衝撃の発生防止 7条
選択1:利用者の接続する端末設備は、事業用電気通信設備との責任の分界を明確にするため、事業用電気通信設備との間に
分界点を有しなければならない
選択2:分界点における接続の方式は、端末設備を電気通信回線ごとに事業用電気通信設備から
容易に切り離せるものでなければならない
選択3:端末設備の機器は、その電源回路と筐体およびその電源回路と事業用電気通信設備との間において
使用電圧が300ボルト以下の場合にあっては0.2メガオーム以上であり、300ボルトを超え750ボルト以下
の直流および300ボルトを超え600ボルト以下の交流の場合にあっては、0.4メガオーム以上の絶縁抵抗
選択4:通話機能を有する端末設備は、通話中に受話器から過大な誘導雑音→「音響衝撃」が発生することを防止する
機能をそなえなければならない
選択5:端末設備の機器の金属製の台および筐体は、接地抵抗が100オーム以下となるように接地しなければならない
ただし、安全な場所に危険のないように設置する場合にあってはこの限りでない
(5) p436~437 端末設備内において、電波を使用する端末設備 9条
選択A:使用する電波の周波数が空き状態であるかどうかの確認
選択B:使用される無線設備は、一の筐体に収められており、かつ容易に開く事ができないものとする
(気密性については特に関係がない)
問4
5,2,1,3,2,
→5,2,1,3,2
(1) p440~441 アナログ電話 選択信号の条件 12条
選択1:高群周波数は、1200ヘルツから1700ヘルツまでの範囲内における特定の4つの周波数で規定
選択2:信号周波数偏差は、信号周波数のプラスマイナス1.5パーセント以内でなければならない
選択3:数字または数字以外を表すダイヤル番号として規定されている総数は、16種類である
選択4:周期とは、信号送り出し時間とミニマムポーズの和をいう
選択5:信号送り出し時間は120→50ミリ秒以上でなければならない ※この選択が正解
(2) p440~441 直流回路の電気的条件 13条
選択1:選択信号送り出し時における直流回路の静電容量は、3マイクロファラド以下でなければならない
選択2:直流抵抗値 50オーム以上~500→300オーム以下である事
ただし、直流回路の直流抵抗値と電気通信事業者の交換設備からアナログ端末までの線路の抵抗が
50オーム以上~1500→1700オーム以下である場合はこの限りでない
選択3:直流回路を開いている時のアナログ電話端末の直流回路の直流抵抗値は、1メガオーム以上でなければならない
選択4:直流回路を開いているときのアナログ電話端末の直流回路と大地の間の絶縁抵抗は、
直流200ボルト以上の1の電圧で測定した値で1メガオーム以上でなければならない
選択5:アナログ電話端末は、電気通信回線に対して直流の電圧を加えるものであってはならない
(4) p443 IP電話端末 基本的機能32条の2、電気的条件32条の7
選択A:発信または応答を行う場合にあっては、呼の設定を行うためのメッセージまたは当該メッセージに対応する
ためのメッセージを送りだしするものであること。
選択B:インターネットプロトコル電話端末は、電気通信回線に対して直流の電圧を加えるものであってはならない。
ただし、総務大臣が別に告示する条件において直流重工が認められる場合にあっては、この限りでない
問5
5、4,2,3,1
→5,4,2,3,1
(1) p459 有線電気通信設備令、用語の定義1条
選択1:線路とは、送信の場所と受信の場所との間に設置されている電線およびこれに係るちゅうけいき
その他の機器(これらを支持し、または保蔵するための工作物を含む)
選択2:絶縁電線とは、絶縁物のみで被覆されている電線をいう
選択3:支持物とは、電柱、支線、つり線その他電線または強電流電線を支持するための工作物をいう
選択4:音声周波とは、周波数が200ヘルツを超え、3500ヘルツ以下の電磁波をいう
選択5:高周波とは周波数が3500ヘルツを超える電磁波 ※上限設定はない、問題では1ギガヘルツ以下となっている
(2) p466 強電流電線に重工される通信回線13条
条件1:重工される部分とその他の部分が 「安全に分離し、かつ開閉できる事」
条件2:重工される部分に異常電圧が生じた場合において、その他の部分を保護するため総務省令で定める保安装置を設置
(3) p464 架空電線の高さ 8条
架空電線が横断歩道の上にあるときは、その路面から「3」メートル以上でなければならない
※注意、道路上にあるときは路面から「5」メートル以上でなければならない
(4) p470 不正アクセス禁止法、用語の定義 2条
選択A:アクセス管理者とは、電気通信回線に接続している電子計算機の利用につき、当該特定電子計算機の動作を管理するもの
選択B:電気通信回線を介して接続されたほかの特定電子計算機が有するアクセス制御機能により、その特定利用を制限
されている特定電子計算機に電気通信回線を通じてその制限を免れることができる情報または指令を入力して
当該特定電子計算機を作動させ、その制限されている特定利用をしうる状態にさせる行為は不正アクセス行為に該当
(5) p474 認証業務の定義 2条
認証業務とは、「自らが行う」電子署名についてその業務を利用するものその他の者の求めに応じ、
当該利用者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項が当該利用者に係るものである事を
証明する業務をいう
また頭痛がひどくなってきたので、薬を飲んでがんばっていきます
「技術および理論」
1回目自己採点:28点
2回目自己採点:76点
3回目自己採点:
10、10、8、10、6、10,10、8,10,10 → 合計 92点
「法規」
1回目自己採点:52点
2回目自己採点:84点
3回目自己採点:
16、16、16、20、20 → 合計 88点
「技術および理論」
問1
4,3,1,3?、5,
→4,3,1,3,5
(2) p161 内線回路の参考図
試験引き込み回路→呼出信号制御回路→X通話電源供給回路→W過電圧保護回路
(3) p164 夜間閉塞機能とは
選択A:夜間閉塞を開始すると、電気通信事業者の交換機からの呼は、一般の電話機に着信する場合と
同様の接続シーケンスにyおり、夜間受付用電話機に着信する
選択B:夜間閉塞機能を利用するためには、夜間閉塞制御用として着信専用回線を各代表群別に設置し、
電気通信事業者の交換機に対してL1→「L2」線に地気を送出する必要がある
(4) p216 端末アダプタの機能
選択A:パケットモード端末側のLAPBと、Dチャンネル側のLAPDとの間で、プロトコルの変換を行う
選択B:非ISDN端末からのユーザデータ速度を64キロビット秒、または16キロビットに速度変換する
問2
4,2,4(他の通信方式確認)、2,3,
→4,2,4,2,3
(2) p263 SIPに関する説明、SIPサーバの構成要素のうち、登録を受け付けたUACの位置情報を管理するのはロケーションサーバ
※間違い選択 プロキシサーバは端末の代わりにSIPのメッセージを受信し転送する機能を持つ
(3) 参考ページなし?PLCはパワーラインコミュニケーションの略、屋内の電気配線を通信路として利用する方式
選択1:Wi-Fi(ワイファイ)とは、無線LANに関する登録商標である[1]。Wi-Fi Alliance(アメリカ合衆国に本拠を置く業界団体)によって、国際標準規格であるIEEE 802.11規格を使用したデバイス間の相互接続が認められたことを示す名称。
選択2:人口希薄地帯や、高速通信(光・メタル)回線の敷設やDSL等の利用が困難な地域で固定無線アクセスの代替、いわゆるラストワンマイルの接続手段として期待されている。近年は、高速移動体通信用の規格も策定されている。WiMAXは当初、中長距離エリアをカバーする無線通信を目的としておりWiMAXアクセス網は「Wireless MAN」(MAN:Metropolitan Area Network)と定義される。
選択3:Bluetooth Low Energy (Bluetooth LE, BLE) とは、無線PAN技術である Bluetooth の一部で、バージョン 4.0 から追加になった低消費電力の通信モード。Bluetooth は Bluetooth Basic Rate/Enhanced Data Rate (BR/EDR) と Bluetooth Low Energy (LE) から構成される[1]。
選択5:ZigBee(じぐびー)とは、センサーネットワークを主目的とする近距離無線通信規格の一つ。この通信規格は、転送可能距離が短く転送速度も非常に低速である代わりに、安価で消費電力が少ないという特徴を持つ。従って、電池駆動可能な超小型機器への実装に向いている。基礎部分の(電気的な)仕様はIEEE 802.15.4として規格化されている。論理層以上の機器間の通信プロトコルについては「ZigBeeアライアンス(ZigBee Alliance)」が仕様の策定を行っている。
問3
1、2,1,1,5,
→1,2,4、1、5
(1) p215 ISDNの構成
選択A:R点はアナログ端末などの非ISDN端末を接続するために規定されており、TAを介して網に接続される
選択B:S点はTA、NT2間に相当する、T点はNT1、NT2との間に位置する
(3) p234 レイヤ2における情報制御 上位レイヤからの情報は非確認形情報転送手順により UIフレームを用いて転送される
※間違い選択 Fビットとは 同期、保守、エラー検出用のビット(p227)
(5) p227~228 ISDNインターフェースレイヤ1、24個のFビットを活用して、
フレーム同期、CRCビット誤り検出、リモートアラーム表示などに利用している
問4
5,1,3,1,3,
→5,1,3,1,3
(2) p278 光アクセスネットワーク構成 AはADSの説明、BはPONの説明
(3) p280 にはSCM方式に関する説明はなし?
参考URL:https://masassiah.web.fc2.com/contents/17cte/note_ss213.html
(4) p260 PMTUDとは IPパケットの送信元からあて先までの経路上にあるバスにおいて、
IPパケットが分割されずに転送できるMTUを自動的に検出する機能のこと
(5) p274 IP-VPN→レイヤ3、広域イーサネット→レイヤ2、
MPLS網を構成するラベルスイッチルータは、MPLSラベルを参照してMPLSフレームを高速中継する
問5
1,4,4(計算)、5,4,
→2,3,4,5,4
(1) p289 呼損率、アーランB式が成立する条件
選択A:入回線数が有限→「無限」、出回線数が無限→「有限」のモデルにランダム呼が加わる
選択B:入回線に生起する呼の回線保留時間は互いに独立で、いずれも指数分布に従いかつ損失呼は消滅する
問6
5,1(他に認証方式確認),2,4,3
→5,1,2,4,3
(1) 参考ページなし? OP25Bとは ISPがあらかじめ用意しているメールサーバ以外からのメールをISPの外に転送しない仕組み
(2) 認証方式
選択1:シングルサインオンに関する説明 利用者が認証を一度行う事により、個々のシステムログイン操作が不要となる
選択2:アドレススキャン
ターゲットとなるネットワーク内に順番に「pingパケット」を送って応答が返ってくる機器のIPアドレスを調査する手法です。
選択3:ワンタイムパスワード
選択4:RADIUS(ラディウス、ラディアス、Remote Authentication Dial In User Service)は、ネットワーク資源の利用の可否の判断(認証)と、利用の事実の記録(アカウンティング)を、ネットワーク上のサーバコンピュータに一元化することを目的とした、IP上のプロトコルである。
選択5:CHAP は Point-to-Point Protocol (PPP) が、リモートクライアントの正当性を確認するための認証方法として使用される。CHAP は3ウェイ・ハンドシェイクによって、定期的にクライアントの正当性を確認する。これは、最初のデータ通信リンクを確立するときに行われ、その後はいつでも行われる可能性がある。この確認は、共有秘密(英語版) (例えばクライアントユーザのパスワード) に基づいている。
(3) p305 ※選択Aは間違いで、選択Bはあっている
選択A:S/MINEとは 第三者の認証機関により保証されたパスワード→「電子証明書」を用いる電子メールの暗号化方式である
選択B:PGPとは 送信者側がメッセージを共通鍵で暗号化し、さらに送信相手の公開鍵を用いて暗号化するハイブリッド方式
(4) p311~312 IDSの分類→NIDSの機能について 不正アクセスを検知する、
HIDSはファイル削除などのログ監視
※NIDSの機能で正しい:侵入を検知するための方法として、通常行われている通信とは考えにくい通信を検知する
アノまリバース検知といわれる機能などが用いられている
(5) p316 ※選択3が間違い
情報のラベルづけに関する適切な一連の手順は、認証機関→「組織」が採用した情報分類体系に従って策定し実施しないといけない
問7
3,2,4,1,1
→3,2,4、1、1
(5) 参考ページ?
選択A:サービスクラスの設定作業では、発信規制の設定などが行われる
選択B:コールピックアップグループは代理応答用、コールパークグループは保留応答用として設定するグループである
問8
2,3,1、3、2,
→4,3,1,3,2
(1) p338 ポイントツーポイント配線の動作距離 1000m程度(TTC標準)
(3) p339 ポイントツーマルチポイント構成について
選択A:延長受動バス配線構成では、バス配線の途中に信号の増幅や再生などを行う能動素子を取り付ける事が許容されてない
選択B:短距離受動バス配線構成では、1対のインタフェース線における配線極性は
全TE間で同一とする必要はなく → 「全TE間で同一とする必要あり」
(4) 反射減衰量については参考ページなし?
選択1:LAN配線のフィールドテストについては参考ページ見当たらず
選択2:参考ページ見当たらず
選択3:反射減衰量は、入力信号の送信レベルを基準として、反射した信号レベルを測定する事により求められる
選択4:参考ページ見当たらず
選択5:参考ページ見当たらず
(5) p361 ビルディング内の光配線システムの規定
選択A:床スラブ上の配線としては
「アンダーカーペット方式」「フリーアクセス方式」フロアダクト方式→「簡易床二重床方式」のいずれか採用
選択B:床スラブないの配線方式のうち、電線管方式は、配線取り出し口は固定され、他の方式と比較して、配線収納能力が小さい
問9
4,5,3,4?、5,
→4,5,3,4,5
(2) p 332 電話・情報設備の配線図用記号の中に「複合アウトレット」の記号は含まれていない
選択1:情報アウトレット
選択2:端子盤
選択3:電話用アウトレット
選択4:??? ボタン電話主装置に似ている
(3) p372 水平チャンネル長公式を用いて、固定水平ケーブルの最大長を求める
クロスコネクトTO→H=107ーFXの式で求める
(5) p358 MTコネクタ テープ心線相互の接続に用いられる (多芯) 単芯の場合はSCコネクタを使う
コネクタの種類 FCコネクタはねじこみ式なので注意
https://www.fiberlabs.co.jp/tech-explan/about-optical-connector/
問10
2,1,3,2,4,
→2,1,3,2,4
(1) p365 カットバック法による測定の定義 入射条件を変更せずに末端から放射される光パワーと入射点近くで
切断した光ファイバーから放射される光パワー測定し、計算式を用いて光ファイバの損失を求める方法
(4) p393 ヒストグラムに関する説明
データの存在する範囲をいくつかの区間にわけ、各区間を底辺とし、その区間に属するデータの出現度数に比例した
長方形を並べたものを指している
「法規」
問1
2,3,4,3、3
→2,3,4,3,5
(4) p410~411 重要通信の確保 8条、施工規則55条
水道、ガスなどの国民の日常生活に必要不可欠な役務の提供その他「生活基盤を維持」するため緊急を要する事項を
内容とする通信であって、これらの通信を行う者相互間において行わなれるものがある
(5) p415 端末設備の接続の技術基準 52条
電気通信回線設備を損傷し、またはその「機能に障害」を与えないようにする事
※「接続に制限」は間違いの選択 2回目に復習した時も同じ間違いをしていたので注意
問2
1,2,5,3,2,
→1,2,5,1,2
(4) p456~457 有線電気通信設備の届け出 3条
選択A:総務大臣は、有線電気通信設備を設置したものに対し、その設備が有線電気通信法の規定に基づく政令で
定める技術基準に適合しないため他人の設置する有線電気通信設備に妨害を与え、または人体に危害を及ぼし
もしくは物件に損傷を与えると認めるときは、その妨害、危害、または損傷の防止または除去のため
必要な限度において、その設備の使用の停止または改造、修理その他の措置を命ずる事ができる
選択B:有線電気通信設備を設置しようとするものは、有線電気通信の方式の別、設備の工事の体制→「設備の設置の場所」
設備の概要を記載した書類を添えて、設置の工事の開始の日の2週間前まで
(工事を要しないときは、設置の日から2週間以内)に、その旨を総務大臣に届けでなければならない
問3
5,3,4,3,1,
→5,2,4,3,1
(1) p430 用語の定義 2条
選択1:アナログ電話用設備 音声信号→アナログ信号を入出力とするもの
選択2:移動電話用設備 電波を使用するもの(無線がどうこうという定義ではない)
選択3:総合デジタル通信用設備 伝送速度が128ビット→64ビットとなっている
選択4:直流回路 プラグジャック式→ 2線式の接続
選択5:デジタルデータ伝送用設備 (これだけが正解)
電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、デジタル方式により、もっぱら符号または影像の
伝送交換を目的とする電気通信役務の用に供するものをいう
(2) p436 配線設備など 8条
選択A:電線と大地間の絶縁抵抗は、直流200ボルト以上の電圧で0.4→「1メガオーム」以上である事
選択B:配線設備等と強電流電線との関係については、有線電気通信設備令の規定に適合するものである事
※絶縁抵抗が0、2メガオーム以上となるのは電源回路と筐体の間の場合
(3) p436 過大音響衝撃の発生防止 7条
選択1:利用者の接続する端末設備は、事業用電気通信設備との責任の分界を明確にするため、事業用電気通信設備との間に
分界点を有しなければならない
選択2:分界点における接続の方式は、端末設備を電気通信回線ごとに事業用電気通信設備から
容易に切り離せるものでなければならない
選択3:端末設備の機器は、その電源回路と筐体およびその電源回路と事業用電気通信設備との間において
使用電圧が300ボルト以下の場合にあっては0.2メガオーム以上であり、300ボルトを超え750ボルト以下
の直流および300ボルトを超え600ボルト以下の交流の場合にあっては、0.4メガオーム以上の絶縁抵抗
選択4:通話機能を有する端末設備は、通話中に受話器から過大な誘導雑音→「音響衝撃」が発生することを防止する
機能をそなえなければならない
選択5:端末設備の機器の金属製の台および筐体は、接地抵抗が100オーム以下となるように接地しなければならない
ただし、安全な場所に危険のないように設置する場合にあってはこの限りでない
(5) p436~437 端末設備内において、電波を使用する端末設備 9条
選択A:使用する電波の周波数が空き状態であるかどうかの確認
選択B:使用される無線設備は、一の筐体に収められており、かつ容易に開く事ができないものとする
(気密性については特に関係がない)
問4
5,2,1,3,2,
→5,2,1,3,2
(1) p440~441 アナログ電話 選択信号の条件 12条
選択1:高群周波数は、1200ヘルツから1700ヘルツまでの範囲内における特定の4つの周波数で規定
選択2:信号周波数偏差は、信号周波数のプラスマイナス1.5パーセント以内でなければならない
選択3:数字または数字以外を表すダイヤル番号として規定されている総数は、16種類である
選択4:周期とは、信号送り出し時間とミニマムポーズの和をいう
選択5:信号送り出し時間は120→50ミリ秒以上でなければならない ※この選択が正解
(2) p440~441 直流回路の電気的条件 13条
選択1:選択信号送り出し時における直流回路の静電容量は、3マイクロファラド以下でなければならない
選択2:直流抵抗値 50オーム以上~500→300オーム以下である事
ただし、直流回路の直流抵抗値と電気通信事業者の交換設備からアナログ端末までの線路の抵抗が
50オーム以上~1500→1700オーム以下である場合はこの限りでない
選択3:直流回路を開いている時のアナログ電話端末の直流回路の直流抵抗値は、1メガオーム以上でなければならない
選択4:直流回路を開いているときのアナログ電話端末の直流回路と大地の間の絶縁抵抗は、
直流200ボルト以上の1の電圧で測定した値で1メガオーム以上でなければならない
選択5:アナログ電話端末は、電気通信回線に対して直流の電圧を加えるものであってはならない
(4) p443 IP電話端末 基本的機能32条の2、電気的条件32条の7
選択A:発信または応答を行う場合にあっては、呼の設定を行うためのメッセージまたは当該メッセージに対応する
ためのメッセージを送りだしするものであること。
選択B:インターネットプロトコル電話端末は、電気通信回線に対して直流の電圧を加えるものであってはならない。
ただし、総務大臣が別に告示する条件において直流重工が認められる場合にあっては、この限りでない
問5
5、4,2,3,1
→5,4,2,3,1
(1) p459 有線電気通信設備令、用語の定義1条
選択1:線路とは、送信の場所と受信の場所との間に設置されている電線およびこれに係るちゅうけいき
その他の機器(これらを支持し、または保蔵するための工作物を含む)
選択2:絶縁電線とは、絶縁物のみで被覆されている電線をいう
選択3:支持物とは、電柱、支線、つり線その他電線または強電流電線を支持するための工作物をいう
選択4:音声周波とは、周波数が200ヘルツを超え、3500ヘルツ以下の電磁波をいう
選択5:高周波とは周波数が3500ヘルツを超える電磁波 ※上限設定はない、問題では1ギガヘルツ以下となっている
(2) p466 強電流電線に重工される通信回線13条
条件1:重工される部分とその他の部分が 「安全に分離し、かつ開閉できる事」
条件2:重工される部分に異常電圧が生じた場合において、その他の部分を保護するため総務省令で定める保安装置を設置
(3) p464 架空電線の高さ 8条
架空電線が横断歩道の上にあるときは、その路面から「3」メートル以上でなければならない
※注意、道路上にあるときは路面から「5」メートル以上でなければならない
(4) p470 不正アクセス禁止法、用語の定義 2条
選択A:アクセス管理者とは、電気通信回線に接続している電子計算機の利用につき、当該特定電子計算機の動作を管理するもの
選択B:電気通信回線を介して接続されたほかの特定電子計算機が有するアクセス制御機能により、その特定利用を制限
されている特定電子計算機に電気通信回線を通じてその制限を免れることができる情報または指令を入力して
当該特定電子計算機を作動させ、その制限されている特定利用をしうる状態にさせる行為は不正アクセス行為に該当
(5) p474 認証業務の定義 2条
認証業務とは、「自らが行う」電子署名についてその業務を利用するものその他の者の求めに応じ、
当該利用者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項が当該利用者に係るものである事を
証明する業務をいう

















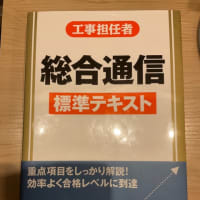


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます