昼飯食べて勉強再開です、少し眠いですが頑張って早く終わらせて
夕飯前に新しい問題を解く作業にかかりたい所です
追記:「法規」の方は内容がかなり頭に入ってきたので、精神的に余裕が出てきました
「技術および理論」をどこまで過去問を頭に入れるかが勝負どころですね
「技術および理論」
1回目自己採点:42点
2回目自己採点:
8、8、4、10、8、10,6、6,6,10 → 合計 76点
「法規」
1回目自己採点:56点
2回目自己採点:
20、16、20、20、20 → 合計 96点
「技術および理論」
問1
4,5,1,3,3,
→4,5,1,2,3
(1) p151 DECT方式、ARIB STD-T101方式
DECT方式を参考にしたARIB STD-T101方式に準拠したデジタルコードレス電話の標準システムは、親機、子機および中継機から
構成されており、同一構内における混信防止のため「識別符号」を自動的に送信または受信する機能を有している
(2) p158 ビハインドPBXに関する記述はなし、内線数を増やせない場合などに、ビハインドPBX方式を用いて、
デジタル式PBXの内線回路にデジタル電話装置の外線を接続して収容する
※令和3年第1回にも類題あり
(3) p159 時分割通話路
選択A:内線回路は、発呼、着信応答、通話中などの内線の状態を検出するために、内線側のA線とB線が
ループ状態にあるかどうかを監視する機能を有する
選択B:内線回路は、内線側に接続されたアナログ電話機からのアナログ音声信号を時分割通話路に
送りだしするためのデコーダ→「コーデック?」の機能を有する
(4) p170 双方公通信方式
選択A:メタリック加入者線を介して受信したバースト信号をピンポン伝送→「時間軸伸張し、連続的なパルス列に変換」
選択B:デジタル回線終端装置は、メタリック加入者線の線路損失、ブリッジタップに起因して
生ずる不要波形による信号ひずみなどを自動補償する等化器の機能を有する
(5) p175 等電位ボンディング
建築物などの雷保護における用語の定義では、内部雷保護システムのうち、雷電流によって離れた導電性部分間に
発生する電位差を低減させるため、その部分間を直接導体によってまたはサージ保護装置によっておこなう接続
問2
4,5,2,2,3,
→4,5,2,1,3,
(4) p313、314 無線LAN
選択A:無線LANのネットワーク構成には、無線端末同士がアクセスポイントを介して通信する
いんふらストラクチャーモードと、アクセスポイントを介さずに無線端末どうしで直接通信を行うアドホックモードがある
選択B;参考書なし?RTS、CTS信号の定義が逆
参考URL https://fielddesign.jp/technology/wlan/ieee802_hidden/
(5) p197 10ギガビットイーサネット
10GBASEーERの場合は、末尾RはLAN仕様、Eがつくばあいは1550mmの波長(WANの場合はEWが末尾)
末尾SRはマルチモードで850mm、末尾LRはマルチモードで1310mmとなっている
問3
3,2?、4,2,2
→1,2、4,5,5
(1) 参考ページなし?
選択A:パケット交換モードにより通信を行う場合、ユーザ情報は、BチャンネルおよびDチャンネルで伝送できる
選択B:間違い箇所?
(2) 参考ページなし?
選択1:?
選択2:1フレームは、Fビットと24個のタイムスロットで構成されている
選択3:?
選択4:?
選択5:?
(3) 参考ページなし?
ISDN基本ユーザ・網インタフェースのレイヤ1において、TEとNT間でINFOといわれる特定ビットパターンの信号を
用いて行われる手順であり、通信の必要が生じた場合にのみインターフェースを活性化し、必要のない場合には
不活性化する手順は「起動・停止」の手順といわれる
(4) p233 TEIの説明
選択1:?
選択2:?
選択3:?
選択4:?
選択5:確認形情報転送手順での情報フレームの転送において、フレームの送受信を制御するときはフロー制御が行われる
(5) 参考ページなし?
図は、ISDN基本ユーザ・網インタフェースの回線交換呼におけるレイヤー3の一般的な呼制御シーケンスを示したものである
ISDN交換網がBチャンネルを着信側TEと接続する動作を始めるのは、「ISDN交換網が着信側TEからCONNを受信」
問4
1,4,1,2,2,
→1,4,1,2,2
(1) p196 1000BASE-Tに関する解説あり、ただし変調方式・符号化技術については解説はなし
4対のより対戦を用いて並列に伝送する「4DーPAM5」といわれる変調方式により伝送に必要な周波数帯域を抑制している
※令和3年第二回でも出題あり
(2) p279あたり
選択1:光アクセスネットワークの設備構成には、電気通信事業者のビルから集合住宅のMDF室などに設定された回線終端装置
までの区間には光ファイバーケーブルを使用し、MDF室などに設置されたVDSL集合装置から各戸への配線に既設の
電話用の配線を利用する形態のものがある
選択2:光アクセスネットワークには、OLTとONUの間に光信号を合・分波する光スプリッタを設置し、
一つのOLTに複数のONUを接続する方式のものがある
選択3:光アクセスネットワークには、波長分割多重伝送技術を使い、上り、下りで異なる波長の光信号を用いて、
1心の光ファイバで上り、下りの信号を同時に送受信する全二重通信を行う方式のものがある
選択4:電気通信事業者のビルから配線された光ファイバの1心を、分岐点において受動素子を用いて分岐し、
個々のユーザにドロップ光ファイバケーブルを用いて配線する構成をとる方式はADS→「PON」とよばれる?
(3) p247 IPV4とIPV6のヘッダ比較
IPV6パケットの優先度の識別などに用いられるフィールドは、「トラヒッククラス」といわれ、IPV4のTOSに相当する
(4) p258 ICMPV6
選択A:ICMPV6を実装しなくてよい→かならず実装する必要あり(間違いの文章)
選択B:ICMPV6の情報メッセージでは、IPV6のアドレス自動構成に関する制御などを行うND(近隣探索)プロトコルで
使われるメッセージなどが定義されている
(5) p275 EOMPLS
選択A:速度の問題、類題あり?
選択B:MPLS網内を転送されたMPLSフレームは、一般に、MPLSドメインの出口にあるラベルエッジルータに到達した後
MPLSラベルの除去などが行われ、オリジナルのイーサネットフレームとしてユーザネットワークの
アクセス回線に転送される
問5
4,5、5(計算)、4,3,
→4,5,3,4,3
(1) p286、288 呼損率
公衆交換電話網において一つの呼の接続が完了するためには、一般に、複数の交換機で出線選択を繰り返す
生起呼がどこかの交換機で出線全話中に遭遇する確率、すなわち結合呼損率は、各交換機における出線選択時の
呼損率が十分小さければ、各交換機の呼損率の「和」にほぼ等しい
(2) p288 呼損率の公式参照
(3) p288 計算問題
(4) p208 レイヤ3スイッチに関する説明
選択1:レイや3スイッチでは、RIPやOSPFといわれるルーティングプロトコルを用いる事ができる
選択2:レイヤ2に対応したレイヤ3スイッチは、受信したフレームの送信元MACアドレスを読み取り、
アドレステーブルに登録されているかどうかを検索し、登録されていない場合はアドレステーブルに登録する
選択3:レイヤ3スイッチには、一般に、受信したフレームをMACアドレスに基づき中継するレイヤ2処理部と
受信したパケットをIPアドレスに基づき中継するレイヤ3処理部がある
選択4:レイヤ3スイッチ→「ルータ」はCPUを用いたソフトウェア処理によりパケットを転送する。これに対し、
ルータ→「レイヤ3スイッチ」はASICを用いたハードウェア処理によりパケットを転送する。このため、
レイヤ3スイッチはルータと比較して転送速度が速い
選択5:レイヤ3スイッチは、VLANとして分割したネットワークを相互に接続することができる
(5) p190 MACアドレス ※両方正しい文章
選択A:MACアドレスは6バイトで構成され、先頭の3バイトはベンダ識別子(OUI)といわれ、IEEEが管理している
残りの3バイトは製品識別子といわれ、各ベンダが独自に重複しないように管理している
選択B:IPアドレスからMACアドレスを求めるためのプロトコルは、ARPとよばれ、
MACアドレスからIPアドレスをもとめるプロトコルはRARPとよばれる ※参考ページなし
問6
3,2,2,4,5,
→3,2,2、4,5
(1) p310 NATとNAPT
選択1:NATやNAPTを用いると、組織内部で使用している発信元IPアドレスを外部に対して隠ぺいできる、セキュリティも高く
選択2:NATやNAPTは、プライベートIPアドレスをグローバルIPアドレスに変換し、または逆の変換も行う
選択3:ファイアウォールの機能はない? ※間違いの文
選択4:NAPTは、複数のプライベートIPアドレスを、一つのグローバルIPアドレスに割り当てることができるため
同時に複数台のパーソナルコンピュータからのインターネット接続が可能である
(2) p304 ハイブリッド暗号化方式
共通鍵で暗号化された暗号文と公開鍵で暗号化された共通鍵を受け取った受信者は、その公開鍵で暗号化された
共通鍵を「受信者の秘密鍵」で複合し、その複合した共通鍵を使用して文章を取り出す
※鍵を暗号、複合するときには公開鍵→秘密鍵と変わる事に注意
(3) p301の補足にプロービングの説明あり ※令和3年第2回にも類題あり
(4) p301 バッファオーバーフロー攻撃
あらかじめ用紙したバッファに対して「入力データのサイズ」がてきせつである事を厳密にチェックしていないOSや
アプリケーションの脆弱性を利用するものであり、サーバが操作不能にされたり特別なプログラムが実行されて管理者権限
を奪われたりするおそれがある
(5) 参考ページなし?
選択A:アンチパスバック:ICカードなどを用い、入室記録後の退室記録がないばあいに再入室を禁止したりする仕組み、
選択B:ゾーニング:セキュリティレベルの違いによっていくつかのセキュリティ区画を設定すること
問7
2,4、2,3、3,
→2,4,4,3,1
(1) p324 星型カッドより
対よりと比較して同一心線数のケーブル「の外形を小さく」することができる
(2) p332 配線用図記号
内線電話機 →1重丸 加入電話機→2重丸
(t) 電話機型インターフォン 子機、 ((t)) 電話機型インターフォン 親機
(pt) についてはインターネットでも解説なし
(3) 施工方法
選択A:p328 アンダーカーペット方式、配線方向を変える処置をするときはフロアクリップとケーブルパスを使用
施工イメージを見るかぎり、立ち上げを行うとき限定?
選択B:簡易二重床配線工事、ブリッジタップを設ける事について ※間違い箇所がよくわからない
(4) p335 ラウンドロビン方式
デジタル式PBXの代表着信方式の設定において、代表グループ内の内線がおおむね均等に利用されるように
内線を選択させたい場合は「ラウンドロビン」方式を選定する
(5) p336 IVR試験、コールパーク試験
選択A:IVR試験では、着信に対して自動音声で応答すること、および自動音声のガイダンスに従い接続先、情報案内どを
選択してプッシュボタンを操作することにより所定の動作が正常に行われる事を確認する
選択B:コールパーク試験ではなく、コールウェイティング試験の定義?
参考URL:http://blog.livedoor.jp/oit_chemical/archives/20238537.html
通話中の内線電話機でフッキング操作の後に特定の番号のダイヤルなどの所定の操作をして通話中の呼を保留し、他の内線電話機から特定番号のダイヤルなど所定の操作をすることにより、保留した呼に応答できる機能。(電話機を変えても電話を切ることなく通話ができる。)
問8
1,4,3,2,3,
→1,2,4,2,3
(1) テスタの機能
ISDNのバス配線の工事確認試験において、DSUから端末機器までのバス配線のT線(TA/TB)の極性を確認するには、
テスタの「直流電圧」測定機能を用いる方法がある
(2) ISDN ポイントツーマルチポイント配線
選択A:間違い箇所?
選択B;短距離受動バス配線構成では、延長受動バス配線構成と異なり、バス配線上の任意の箇所にTEを接続できる
(3) ISDN基本ユーザインタフェース
選択1:?
選択2;?
選択3:?
選択4:バス配線に多対カッド形ケーブルを用いる場合、アナログ電話回線からのインパルス性雑音を考慮し、
基本インターフェース線のT線及びR線は、それぞれアナログ電話回線と同じカッドないに混在収容せず、
同一カッド内収容とする
選択5:?
(4) ビルディング内光配線システム
幹線系光ファイバケーブルの敷設工事では、垂直ラック上でのケーブル固定は「3」メートル以下の間隔で
ケーブルしばりひもなどで固定するとされている
(5) セルラダクト ABともにただしい
選択A:セルラダクトは、建物の床型枠材として用いられる波形デッキプレートの溝の部分をカバープレートで
覆い配線用ダクトとして使用する配線収納方式である
選択B:セルラダクトは一般にフロアダクトと比較して、断面積が大きく収容できる配線数が多い
問9
2,2,3(107ー4ーFX)、3,2,
→3,2,3、3,4
(1) 構内情報配線システム
選択1:ワークエリア内で通信アウトレットの移動の柔軟性が要求されるオープンオフィス環境では、水平配線の
フロア配線盤と通信アウトレットとの間に分岐点を設置するとよい
選択2:分岐点は、受動的な接続器具だけで構成されなければならず、クロスコネクト接続として使ってはならない
選択3:間違い?ワークエリアの数が違う?p369 10→12のワークエリア
選択4:分岐点は、各ワークエリアのグループに少なくとも一つ配置されなければならない
(2) p253 サブネットマスクに応じたホストアドレスの割り当て
(3) p372 水平チャンネル長に関する公式
クロスコネクトTo Eクラス 106ー3ーFXが公式として正解、
Dクラス 107ーFX
(4) p358 FASコネクタ
架空用クロージャ内での心線接続に用いられる光コネクタは、FASコネクタといわれる
(5) 参考ページなし?
平衡配線性能において、挿入損失が4.0デシベル未満となる周波数における近端漏話減衰量の値は、参考とすると規定
問10
2,3,2,3,3,
→2,3,2,3、3
(1) 参考ページなし? 防火区画の処理
防火区画の壁をケーブルが貫通する場合の防火措置において、ケーブル防災設備協議会による代表的な
国土交通大臣認定工法例として、開口部より小さく、ケーブル外形より大きい穴を開けた「耐火仕切り板」で開口部を覆い
アンカーボルトで壁に固定し、隙間を耐熱シール材で埋める工法がある
(2) p365 OTDR法
光ファイバ単一方向の測定であり、光ファイバの異なる箇所から光ファイバの先端まで後方散乱光パワーを測定する方法
(3) 5S活動について
選択A:整理とは 乱れた状態にあるものをかたづけて、秩序を整えること。(問題文は整頓?)
選択B:清潔とは、整理・整頓・清掃が繰り替えされ、汚れのない状態を維持している事をいう。
(4) 工期・建設費曲線
(5) クリティカルパスが15日な事に注意(14日と勘違いする)
「法規」
問1
2,3,1,3,1,
→2,3,1,3,1
(1) p410 重要通信の確保8条
選択1:正しい
選択2:総務大臣に届けでた管理規定にもとづき→総務省令にもとづき
選択3:正しい
選択4:正しい
(2) p414 管理規定 44条
管理規定は電気通信役務の「確実かつ安定的」な提供を確保するために電気通信事業者が遵守すべき事項に関し、
総務省令で定めるところにより、必要な内容を定めたものでなければならない
(3) p419 自営電気通信設備の接続 70条
~その自営電気通信設備を接続することにより、当該電気通信事業者の電気通信回線設備の「提供」が「経営上困難」と
なることについて当該電気通信事業者が総務大臣の認定を受けた時は、その請求をこばむ事ができると規定されている
(4) p410、411 重要通信の確保 8条 ※A,Bともに正しい
選択A:国会議員または地方公共団体の長、もしくはその議会の議員の選挙の執行またはその結果に関し、
緊急を要する事項を内容とする通信であって、選挙管理機関相互間において行われるもは該当する通信である
選択B:治安の維持のため緊急を要する事項を内容とする通信であって、警察機関と海上保安機関との間において
行われるものは該当する通信である
(5) p420 工事担任者資格証
選択A:正しい
選択B:総務大臣は、電気通信事業法の規定により工事担任者資格者証の返納をめいぜられ、その日から
2年→「1年」を経過しないものに対しては、工事担任者資格者証の交付を行わないことができる
問2
3,4,1,4,1?
→3,4,1、4,2
(1) p425 工事担任者資格について
参考URL https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B7%A5%E4%BA%8B%E6%8B%85%E4%BB%BB%E8%80%85
AI第3種の資格について
アナログ伝送路設備に端末設備を接続するための工事(端末設備に収容される電気通信回線の数が1のものに限る。)
及び総合デジタル通信用設備に端末設備を接続するための工事(総合デジタル通信回線の数が基本インタフェースで1のものに限る。)
(2) p426 資格者証の交付 38条 ※A,Bとも間違い文章
選択A:資格者証の交付を受けたものは、端末設備などの接続に関する知識及び技術の「普及→向上」を図るように努める事
選択B:汚して再申請するときに必要なもの→「資格証」「写真1枚」※氏名を証明するものはいらない、住所は重要でない
(3) p428 表示 10条
端末機器に電磁的方法で記録し、当該端末機器の「映像面」に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法
(4) 参考ページ?
電気通信事業者が「その事業の用に供する」設備として設置する場合を除き、本邦ないの場所と本邦外の場所の間に
有線電気通信設備は設置してはならない。ただし、特別の事由がある場合において、総務大臣の許可を受けた時は
この限りではない
(5) 技術基準
選択1:責任の分界が明確である→明確であるために分解点を設置しなければならない
選択2:有線電気通信設備は、他人の設置する有線電気通信設備に妨害を与えないようにすること(正しい)
選択3:p456~458あたりに記載なし(他の通信の一部を制限、または停止)
選択4:識別信号を識別→識別できてはいけない
選択5:p456~458あたりに記載なし(通信の秘密の確保?)
問3
3,2、4、1,3
→3,2,4、1,3
(1) 用語について ※選択3が間違い
選択1:移動電話用設備とは、電話用設備であって、端末設備又は自営電気通信設備との接続において電波を使用するもの
選択2:アナログ電話用設備とは、電話用設備であって、端末設備または自営電気通信設備を接続する点において
アナログ信号を入出力とするものをいう
選択3:直流回路の定義、プラグジャック式→2線式 (p431を参照)
選択4:呼設定用メッセージとは、呼設定メッセージまたは応答メッセージをいう
選択5:制御チャネルとは、移動電話用設備と移動電話端末またはインターネットプロトコル移動電話端末の間に設定され、
主として制御信号の伝送に使用する通信路をいう
(2) 絶縁抵抗
選択A:かける電圧は2.5倍→1.5倍の電圧を連続して10分間加えた時に耐える事
選択B:端末設備の機器の金属製の台および筐体は、接地抵抗が100オーム以下となるように接地しなければならない
ただし、安全な場所に危険のないように設置する場合にあってはこの限りでない
(3) 評価雑音電力
通信回線が受ける妨害であって人間の聴覚率を考慮して定められる「実行的雑音電力」
(4) p435 責任の分界
選択A:利用者の接続する端末設備は、事業用電気通信設備との責任の分界を明確にするため、
事業用電気通信設備との間に分界点を有しなければならない
選択B:分界点における接続の方式は、総務大臣が別に告示する~ →
「電気通信回線ごとに事業用電気通信設備から容易に切り離せる事」
(5) 安全性 ※選択3が間違い
選択1:端末設備は、事業用電気通信設備から漏洩する通信の内容を意図的に識別する機能を有してはならない
選択2:端末設備は、事業用電気通信設備との間で鳴音()を発生することを防止するために総務大臣が別に告示する条件を満たす
選択3:配線設備等の電線相互間および電線と大地間の絶縁抵抗は、直流200V以上の一の電圧で測定した値で
0.2メガオーム→1メガオーム以上でなければならない
選択4:通話機能を有する端末設備は、通話中に受話器から過大な音響衝撃が発生することを防止する機能を備える
選択5:端末設備を構成する一の部分と他の部分相互間において電波を使用する端末設備は、使用する電波の周波数が
空き状態であるかどうかについて、総務大臣が別に告示するところにより判定を行い、空き状態である場合にのみ
通信路を設定するものでなければならない。ただし、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
問4
1,2,3,4,2,
→1,2,3、4,2
(1) p440 押しボタンダイヤの条件
選択A:信号周波数偏差は、信号周波数のプラスマイナス1.5%以内でなければならない
選択B:周期とは、信号送り出し時間とミニマムポーズの和をいい、その値は30→「120」ミリ秒以上
(2) 直流回路を閉じたときの抵抗
例外:直流回路の直流抵抗値と電気通信事業者の交換設備からアナログ電話端末までの線路の直流抵抗値の和が
「50オーム以上1700オーム」以下の場合にあってはこの限りでない。
(3) p442 移動電話端末の基本的機能 ※選択3だけが正しい
選択1:チャネルのブロックでなく、切断する信号を送る
選択2:自動再発信については3回→「2回」以内、最初の発信から2分→「3分」経過したら別の発信とみなす
選択3:発信に際して、応答が確認できないばあい1分以内にチャンネルを切る
選択4:移動電話端末であって、通話の用に供するものは遭難信号→「緊急通報」を受信する機能がないといけない
選択5:漏話減衰量については1700→「1500」ヘルツにおいて70デシベル以上でなければならない
(4) p443~p444 インターネットプロトコル電話端末
選択1:発信または応答を行う場合にあっては、呼の設定を行うためのメッセージまたは当該メッセージに
対応するためのメッセージを送りだしするものである事
選択2:通信を終了する場合にあっては、呼の切断、解放もしくは取り消しを行うためのメッセージまたは
当該メッセージに対応するためのメッセージを送出しするものである事
選択3:2分以内に通信終了メッセージを送る
選択4:IP電話端末は、総務大臣が別に告示する電気的条件および機械的条件→「光学的条件」に適合しないといけない
選択5:インターネットプロトコル電話端末は、電気通信回線に対して直流の電圧を加えるものであってはならない
ただし、総務大臣が別に告示する条件において直流重工が認められる場合にあっては、この限りでない。
(5) p449 アナログ電話と通信する場合 ※選択Bが間違い
選択A:アナログ電話と通信する場合の送り出し電力は、平均レベルでー10デシベル以下→
「ー3デシベル以下」 ※最大レベルの設定も存在しない
選択B:発信または応答を行う場合にあっては、呼設定用メッセージを送出するものであること
ただし、総務大臣が別に告示する場合はこの限りでない
問5
3,2,4,4,2
→3,2,4、4,2
(1) p459 用語の定義 ※選択3が間違い
選択1:高周波とは、周波数が3500ヘルツを超える電磁波をいう
選択2:平衡度とは、通信回線の中性点と大地との間に起電力を加えた場合におけるこれらの間に生ずる電圧と
通信回線の端子間に生ずる電圧との比をデシベルで表したものをいう
選択3:絶対レベルとは、一の有効電力→「無効電力」の1ミリワットに対する比をデシベルで表したもの
選択4:ケーブルとは、光ファイバ並びに光ファイバ以外の絶縁物および保護物で被覆されている電線をいう
選択5:線路とは、送信の場所と受信の場所との間に設置されている電線およびこれに係る中継器
その他の機器(これらを支持し、または保蔵するための工作物を含む)をいう。
(2) p465 架空電線について
選択A:架空強電流電線との水平距離がその架空電線もしくは 架空強電流電線の支持物のうちいずれか
低い→「高い」ものの高さに相当する距離以下となるときは、総務省令で定める所により設置してはならない
選択B:架空電線の支持物には、取扱者が昇降に使用する足場金具などを地表1,8メートル未満の高さに
取付てはならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない
(3) 電線の種類、絶縁電線またはケーブル
(4) p471 不正アクセス
~電子計算機を作動させ、当該アクセス制御機能により制限されている「特定利用」をしうる状態にさせる行為がある
(5) p475 電磁的記録 ※選択2が間違い
選択1:正しい
選択2:※本人にも任意に改変する事ができない記録だったと思われる
選択3:認証業務とは、自らが行う電子署名についてその業務を利用するもの、その他のものの求めに応じ、
当該利用者が電子署名を行ったものである事を確認するために用いられる事項が当該利用者である事を証明する業務
選択4:特定認証業務とは、電子署名のうち、その方式に応じて本人だけが行うことができるものとして
主務省令で定める基準に適合するものについて行われる認証業務をいう
夕飯前に新しい問題を解く作業にかかりたい所です
追記:「法規」の方は内容がかなり頭に入ってきたので、精神的に余裕が出てきました
「技術および理論」をどこまで過去問を頭に入れるかが勝負どころですね
「技術および理論」
1回目自己採点:42点
2回目自己採点:
8、8、4、10、8、10,6、6,6,10 → 合計 76点
「法規」
1回目自己採点:56点
2回目自己採点:
20、16、20、20、20 → 合計 96点
「技術および理論」
問1
4,5,1,3,3,
→4,5,1,2,3
(1) p151 DECT方式、ARIB STD-T101方式
DECT方式を参考にしたARIB STD-T101方式に準拠したデジタルコードレス電話の標準システムは、親機、子機および中継機から
構成されており、同一構内における混信防止のため「識別符号」を自動的に送信または受信する機能を有している
(2) p158 ビハインドPBXに関する記述はなし、内線数を増やせない場合などに、ビハインドPBX方式を用いて、
デジタル式PBXの内線回路にデジタル電話装置の外線を接続して収容する
※令和3年第1回にも類題あり
(3) p159 時分割通話路
選択A:内線回路は、発呼、着信応答、通話中などの内線の状態を検出するために、内線側のA線とB線が
ループ状態にあるかどうかを監視する機能を有する
選択B:内線回路は、内線側に接続されたアナログ電話機からのアナログ音声信号を時分割通話路に
送りだしするためのデコーダ→「コーデック?」の機能を有する
(4) p170 双方公通信方式
選択A:メタリック加入者線を介して受信したバースト信号をピンポン伝送→「時間軸伸張し、連続的なパルス列に変換」
選択B:デジタル回線終端装置は、メタリック加入者線の線路損失、ブリッジタップに起因して
生ずる不要波形による信号ひずみなどを自動補償する等化器の機能を有する
(5) p175 等電位ボンディング
建築物などの雷保護における用語の定義では、内部雷保護システムのうち、雷電流によって離れた導電性部分間に
発生する電位差を低減させるため、その部分間を直接導体によってまたはサージ保護装置によっておこなう接続
問2
4,5,2,2,3,
→4,5,2,1,3,
(4) p313、314 無線LAN
選択A:無線LANのネットワーク構成には、無線端末同士がアクセスポイントを介して通信する
いんふらストラクチャーモードと、アクセスポイントを介さずに無線端末どうしで直接通信を行うアドホックモードがある
選択B;参考書なし?RTS、CTS信号の定義が逆
参考URL https://fielddesign.jp/technology/wlan/ieee802_hidden/
(5) p197 10ギガビットイーサネット
10GBASEーERの場合は、末尾RはLAN仕様、Eがつくばあいは1550mmの波長(WANの場合はEWが末尾)
末尾SRはマルチモードで850mm、末尾LRはマルチモードで1310mmとなっている
問3
3,2?、4,2,2
→1,2、4,5,5
(1) 参考ページなし?
選択A:パケット交換モードにより通信を行う場合、ユーザ情報は、BチャンネルおよびDチャンネルで伝送できる
選択B:間違い箇所?
(2) 参考ページなし?
選択1:?
選択2:1フレームは、Fビットと24個のタイムスロットで構成されている
選択3:?
選択4:?
選択5:?
(3) 参考ページなし?
ISDN基本ユーザ・網インタフェースのレイヤ1において、TEとNT間でINFOといわれる特定ビットパターンの信号を
用いて行われる手順であり、通信の必要が生じた場合にのみインターフェースを活性化し、必要のない場合には
不活性化する手順は「起動・停止」の手順といわれる
(4) p233 TEIの説明
選択1:?
選択2:?
選択3:?
選択4:?
選択5:確認形情報転送手順での情報フレームの転送において、フレームの送受信を制御するときはフロー制御が行われる
(5) 参考ページなし?
図は、ISDN基本ユーザ・網インタフェースの回線交換呼におけるレイヤー3の一般的な呼制御シーケンスを示したものである
ISDN交換網がBチャンネルを着信側TEと接続する動作を始めるのは、「ISDN交換網が着信側TEからCONNを受信」
問4
1,4,1,2,2,
→1,4,1,2,2
(1) p196 1000BASE-Tに関する解説あり、ただし変調方式・符号化技術については解説はなし
4対のより対戦を用いて並列に伝送する「4DーPAM5」といわれる変調方式により伝送に必要な周波数帯域を抑制している
※令和3年第二回でも出題あり
(2) p279あたり
選択1:光アクセスネットワークの設備構成には、電気通信事業者のビルから集合住宅のMDF室などに設定された回線終端装置
までの区間には光ファイバーケーブルを使用し、MDF室などに設置されたVDSL集合装置から各戸への配線に既設の
電話用の配線を利用する形態のものがある
選択2:光アクセスネットワークには、OLTとONUの間に光信号を合・分波する光スプリッタを設置し、
一つのOLTに複数のONUを接続する方式のものがある
選択3:光アクセスネットワークには、波長分割多重伝送技術を使い、上り、下りで異なる波長の光信号を用いて、
1心の光ファイバで上り、下りの信号を同時に送受信する全二重通信を行う方式のものがある
選択4:電気通信事業者のビルから配線された光ファイバの1心を、分岐点において受動素子を用いて分岐し、
個々のユーザにドロップ光ファイバケーブルを用いて配線する構成をとる方式はADS→「PON」とよばれる?
(3) p247 IPV4とIPV6のヘッダ比較
IPV6パケットの優先度の識別などに用いられるフィールドは、「トラヒッククラス」といわれ、IPV4のTOSに相当する
(4) p258 ICMPV6
選択A:ICMPV6を実装しなくてよい→かならず実装する必要あり(間違いの文章)
選択B:ICMPV6の情報メッセージでは、IPV6のアドレス自動構成に関する制御などを行うND(近隣探索)プロトコルで
使われるメッセージなどが定義されている
(5) p275 EOMPLS
選択A:速度の問題、類題あり?
選択B:MPLS網内を転送されたMPLSフレームは、一般に、MPLSドメインの出口にあるラベルエッジルータに到達した後
MPLSラベルの除去などが行われ、オリジナルのイーサネットフレームとしてユーザネットワークの
アクセス回線に転送される
問5
4,5、5(計算)、4,3,
→4,5,3,4,3
(1) p286、288 呼損率
公衆交換電話網において一つの呼の接続が完了するためには、一般に、複数の交換機で出線選択を繰り返す
生起呼がどこかの交換機で出線全話中に遭遇する確率、すなわち結合呼損率は、各交換機における出線選択時の
呼損率が十分小さければ、各交換機の呼損率の「和」にほぼ等しい
(2) p288 呼損率の公式参照
(3) p288 計算問題
(4) p208 レイヤ3スイッチに関する説明
選択1:レイや3スイッチでは、RIPやOSPFといわれるルーティングプロトコルを用いる事ができる
選択2:レイヤ2に対応したレイヤ3スイッチは、受信したフレームの送信元MACアドレスを読み取り、
アドレステーブルに登録されているかどうかを検索し、登録されていない場合はアドレステーブルに登録する
選択3:レイヤ3スイッチには、一般に、受信したフレームをMACアドレスに基づき中継するレイヤ2処理部と
受信したパケットをIPアドレスに基づき中継するレイヤ3処理部がある
選択4:レイヤ3スイッチ→「ルータ」はCPUを用いたソフトウェア処理によりパケットを転送する。これに対し、
ルータ→「レイヤ3スイッチ」はASICを用いたハードウェア処理によりパケットを転送する。このため、
レイヤ3スイッチはルータと比較して転送速度が速い
選択5:レイヤ3スイッチは、VLANとして分割したネットワークを相互に接続することができる
(5) p190 MACアドレス ※両方正しい文章
選択A:MACアドレスは6バイトで構成され、先頭の3バイトはベンダ識別子(OUI)といわれ、IEEEが管理している
残りの3バイトは製品識別子といわれ、各ベンダが独自に重複しないように管理している
選択B:IPアドレスからMACアドレスを求めるためのプロトコルは、ARPとよばれ、
MACアドレスからIPアドレスをもとめるプロトコルはRARPとよばれる ※参考ページなし
問6
3,2,2,4,5,
→3,2,2、4,5
(1) p310 NATとNAPT
選択1:NATやNAPTを用いると、組織内部で使用している発信元IPアドレスを外部に対して隠ぺいできる、セキュリティも高く
選択2:NATやNAPTは、プライベートIPアドレスをグローバルIPアドレスに変換し、または逆の変換も行う
選択3:ファイアウォールの機能はない? ※間違いの文
選択4:NAPTは、複数のプライベートIPアドレスを、一つのグローバルIPアドレスに割り当てることができるため
同時に複数台のパーソナルコンピュータからのインターネット接続が可能である
(2) p304 ハイブリッド暗号化方式
共通鍵で暗号化された暗号文と公開鍵で暗号化された共通鍵を受け取った受信者は、その公開鍵で暗号化された
共通鍵を「受信者の秘密鍵」で複合し、その複合した共通鍵を使用して文章を取り出す
※鍵を暗号、複合するときには公開鍵→秘密鍵と変わる事に注意
(3) p301の補足にプロービングの説明あり ※令和3年第2回にも類題あり
(4) p301 バッファオーバーフロー攻撃
あらかじめ用紙したバッファに対して「入力データのサイズ」がてきせつである事を厳密にチェックしていないOSや
アプリケーションの脆弱性を利用するものであり、サーバが操作不能にされたり特別なプログラムが実行されて管理者権限
を奪われたりするおそれがある
(5) 参考ページなし?
選択A:アンチパスバック:ICカードなどを用い、入室記録後の退室記録がないばあいに再入室を禁止したりする仕組み、
選択B:ゾーニング:セキュリティレベルの違いによっていくつかのセキュリティ区画を設定すること
問7
2,4、2,3、3,
→2,4,4,3,1
(1) p324 星型カッドより
対よりと比較して同一心線数のケーブル「の外形を小さく」することができる
(2) p332 配線用図記号
内線電話機 →1重丸 加入電話機→2重丸
(t) 電話機型インターフォン 子機、 ((t)) 電話機型インターフォン 親機
(pt) についてはインターネットでも解説なし
(3) 施工方法
選択A:p328 アンダーカーペット方式、配線方向を変える処置をするときはフロアクリップとケーブルパスを使用
施工イメージを見るかぎり、立ち上げを行うとき限定?
選択B:簡易二重床配線工事、ブリッジタップを設ける事について ※間違い箇所がよくわからない
(4) p335 ラウンドロビン方式
デジタル式PBXの代表着信方式の設定において、代表グループ内の内線がおおむね均等に利用されるように
内線を選択させたい場合は「ラウンドロビン」方式を選定する
(5) p336 IVR試験、コールパーク試験
選択A:IVR試験では、着信に対して自動音声で応答すること、および自動音声のガイダンスに従い接続先、情報案内どを
選択してプッシュボタンを操作することにより所定の動作が正常に行われる事を確認する
選択B:コールパーク試験ではなく、コールウェイティング試験の定義?
参考URL:http://blog.livedoor.jp/oit_chemical/archives/20238537.html
通話中の内線電話機でフッキング操作の後に特定の番号のダイヤルなどの所定の操作をして通話中の呼を保留し、他の内線電話機から特定番号のダイヤルなど所定の操作をすることにより、保留した呼に応答できる機能。(電話機を変えても電話を切ることなく通話ができる。)
問8
1,4,3,2,3,
→1,2,4,2,3
(1) テスタの機能
ISDNのバス配線の工事確認試験において、DSUから端末機器までのバス配線のT線(TA/TB)の極性を確認するには、
テスタの「直流電圧」測定機能を用いる方法がある
(2) ISDN ポイントツーマルチポイント配線
選択A:間違い箇所?
選択B;短距離受動バス配線構成では、延長受動バス配線構成と異なり、バス配線上の任意の箇所にTEを接続できる
(3) ISDN基本ユーザインタフェース
選択1:?
選択2;?
選択3:?
選択4:バス配線に多対カッド形ケーブルを用いる場合、アナログ電話回線からのインパルス性雑音を考慮し、
基本インターフェース線のT線及びR線は、それぞれアナログ電話回線と同じカッドないに混在収容せず、
同一カッド内収容とする
選択5:?
(4) ビルディング内光配線システム
幹線系光ファイバケーブルの敷設工事では、垂直ラック上でのケーブル固定は「3」メートル以下の間隔で
ケーブルしばりひもなどで固定するとされている
(5) セルラダクト ABともにただしい
選択A:セルラダクトは、建物の床型枠材として用いられる波形デッキプレートの溝の部分をカバープレートで
覆い配線用ダクトとして使用する配線収納方式である
選択B:セルラダクトは一般にフロアダクトと比較して、断面積が大きく収容できる配線数が多い
問9
2,2,3(107ー4ーFX)、3,2,
→3,2,3、3,4
(1) 構内情報配線システム
選択1:ワークエリア内で通信アウトレットの移動の柔軟性が要求されるオープンオフィス環境では、水平配線の
フロア配線盤と通信アウトレットとの間に分岐点を設置するとよい
選択2:分岐点は、受動的な接続器具だけで構成されなければならず、クロスコネクト接続として使ってはならない
選択3:間違い?ワークエリアの数が違う?p369 10→12のワークエリア
選択4:分岐点は、各ワークエリアのグループに少なくとも一つ配置されなければならない
(2) p253 サブネットマスクに応じたホストアドレスの割り当て
(3) p372 水平チャンネル長に関する公式
クロスコネクトTo Eクラス 106ー3ーFXが公式として正解、
Dクラス 107ーFX
(4) p358 FASコネクタ
架空用クロージャ内での心線接続に用いられる光コネクタは、FASコネクタといわれる
(5) 参考ページなし?
平衡配線性能において、挿入損失が4.0デシベル未満となる周波数における近端漏話減衰量の値は、参考とすると規定
問10
2,3,2,3,3,
→2,3,2,3、3
(1) 参考ページなし? 防火区画の処理
防火区画の壁をケーブルが貫通する場合の防火措置において、ケーブル防災設備協議会による代表的な
国土交通大臣認定工法例として、開口部より小さく、ケーブル外形より大きい穴を開けた「耐火仕切り板」で開口部を覆い
アンカーボルトで壁に固定し、隙間を耐熱シール材で埋める工法がある
(2) p365 OTDR法
光ファイバ単一方向の測定であり、光ファイバの異なる箇所から光ファイバの先端まで後方散乱光パワーを測定する方法
(3) 5S活動について
選択A:整理とは 乱れた状態にあるものをかたづけて、秩序を整えること。(問題文は整頓?)
選択B:清潔とは、整理・整頓・清掃が繰り替えされ、汚れのない状態を維持している事をいう。
(4) 工期・建設費曲線
(5) クリティカルパスが15日な事に注意(14日と勘違いする)
「法規」
問1
2,3,1,3,1,
→2,3,1,3,1
(1) p410 重要通信の確保8条
選択1:正しい
選択2:総務大臣に届けでた管理規定にもとづき→総務省令にもとづき
選択3:正しい
選択4:正しい
(2) p414 管理規定 44条
管理規定は電気通信役務の「確実かつ安定的」な提供を確保するために電気通信事業者が遵守すべき事項に関し、
総務省令で定めるところにより、必要な内容を定めたものでなければならない
(3) p419 自営電気通信設備の接続 70条
~その自営電気通信設備を接続することにより、当該電気通信事業者の電気通信回線設備の「提供」が「経営上困難」と
なることについて当該電気通信事業者が総務大臣の認定を受けた時は、その請求をこばむ事ができると規定されている
(4) p410、411 重要通信の確保 8条 ※A,Bともに正しい
選択A:国会議員または地方公共団体の長、もしくはその議会の議員の選挙の執行またはその結果に関し、
緊急を要する事項を内容とする通信であって、選挙管理機関相互間において行われるもは該当する通信である
選択B:治安の維持のため緊急を要する事項を内容とする通信であって、警察機関と海上保安機関との間において
行われるものは該当する通信である
(5) p420 工事担任者資格証
選択A:正しい
選択B:総務大臣は、電気通信事業法の規定により工事担任者資格者証の返納をめいぜられ、その日から
2年→「1年」を経過しないものに対しては、工事担任者資格者証の交付を行わないことができる
問2
3,4,1,4,1?
→3,4,1、4,2
(1) p425 工事担任者資格について
参考URL https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B7%A5%E4%BA%8B%E6%8B%85%E4%BB%BB%E8%80%85
AI第3種の資格について
アナログ伝送路設備に端末設備を接続するための工事(端末設備に収容される電気通信回線の数が1のものに限る。)
及び総合デジタル通信用設備に端末設備を接続するための工事(総合デジタル通信回線の数が基本インタフェースで1のものに限る。)
(2) p426 資格者証の交付 38条 ※A,Bとも間違い文章
選択A:資格者証の交付を受けたものは、端末設備などの接続に関する知識及び技術の「普及→向上」を図るように努める事
選択B:汚して再申請するときに必要なもの→「資格証」「写真1枚」※氏名を証明するものはいらない、住所は重要でない
(3) p428 表示 10条
端末機器に電磁的方法で記録し、当該端末機器の「映像面」に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法
(4) 参考ページ?
電気通信事業者が「その事業の用に供する」設備として設置する場合を除き、本邦ないの場所と本邦外の場所の間に
有線電気通信設備は設置してはならない。ただし、特別の事由がある場合において、総務大臣の許可を受けた時は
この限りではない
(5) 技術基準
選択1:責任の分界が明確である→明確であるために分解点を設置しなければならない
選択2:有線電気通信設備は、他人の設置する有線電気通信設備に妨害を与えないようにすること(正しい)
選択3:p456~458あたりに記載なし(他の通信の一部を制限、または停止)
選択4:識別信号を識別→識別できてはいけない
選択5:p456~458あたりに記載なし(通信の秘密の確保?)
問3
3,2、4、1,3
→3,2,4、1,3
(1) 用語について ※選択3が間違い
選択1:移動電話用設備とは、電話用設備であって、端末設備又は自営電気通信設備との接続において電波を使用するもの
選択2:アナログ電話用設備とは、電話用設備であって、端末設備または自営電気通信設備を接続する点において
アナログ信号を入出力とするものをいう
選択3:直流回路の定義、プラグジャック式→2線式 (p431を参照)
選択4:呼設定用メッセージとは、呼設定メッセージまたは応答メッセージをいう
選択5:制御チャネルとは、移動電話用設備と移動電話端末またはインターネットプロトコル移動電話端末の間に設定され、
主として制御信号の伝送に使用する通信路をいう
(2) 絶縁抵抗
選択A:かける電圧は2.5倍→1.5倍の電圧を連続して10分間加えた時に耐える事
選択B:端末設備の機器の金属製の台および筐体は、接地抵抗が100オーム以下となるように接地しなければならない
ただし、安全な場所に危険のないように設置する場合にあってはこの限りでない
(3) 評価雑音電力
通信回線が受ける妨害であって人間の聴覚率を考慮して定められる「実行的雑音電力」
(4) p435 責任の分界
選択A:利用者の接続する端末設備は、事業用電気通信設備との責任の分界を明確にするため、
事業用電気通信設備との間に分界点を有しなければならない
選択B:分界点における接続の方式は、総務大臣が別に告示する~ →
「電気通信回線ごとに事業用電気通信設備から容易に切り離せる事」
(5) 安全性 ※選択3が間違い
選択1:端末設備は、事業用電気通信設備から漏洩する通信の内容を意図的に識別する機能を有してはならない
選択2:端末設備は、事業用電気通信設備との間で鳴音()を発生することを防止するために総務大臣が別に告示する条件を満たす
選択3:配線設備等の電線相互間および電線と大地間の絶縁抵抗は、直流200V以上の一の電圧で測定した値で
0.2メガオーム→1メガオーム以上でなければならない
選択4:通話機能を有する端末設備は、通話中に受話器から過大な音響衝撃が発生することを防止する機能を備える
選択5:端末設備を構成する一の部分と他の部分相互間において電波を使用する端末設備は、使用する電波の周波数が
空き状態であるかどうかについて、総務大臣が別に告示するところにより判定を行い、空き状態である場合にのみ
通信路を設定するものでなければならない。ただし、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
問4
1,2,3,4,2,
→1,2,3、4,2
(1) p440 押しボタンダイヤの条件
選択A:信号周波数偏差は、信号周波数のプラスマイナス1.5%以内でなければならない
選択B:周期とは、信号送り出し時間とミニマムポーズの和をいい、その値は30→「120」ミリ秒以上
(2) 直流回路を閉じたときの抵抗
例外:直流回路の直流抵抗値と電気通信事業者の交換設備からアナログ電話端末までの線路の直流抵抗値の和が
「50オーム以上1700オーム」以下の場合にあってはこの限りでない。
(3) p442 移動電話端末の基本的機能 ※選択3だけが正しい
選択1:チャネルのブロックでなく、切断する信号を送る
選択2:自動再発信については3回→「2回」以内、最初の発信から2分→「3分」経過したら別の発信とみなす
選択3:発信に際して、応答が確認できないばあい1分以内にチャンネルを切る
選択4:移動電話端末であって、通話の用に供するものは遭難信号→「緊急通報」を受信する機能がないといけない
選択5:漏話減衰量については1700→「1500」ヘルツにおいて70デシベル以上でなければならない
(4) p443~p444 インターネットプロトコル電話端末
選択1:発信または応答を行う場合にあっては、呼の設定を行うためのメッセージまたは当該メッセージに
対応するためのメッセージを送りだしするものである事
選択2:通信を終了する場合にあっては、呼の切断、解放もしくは取り消しを行うためのメッセージまたは
当該メッセージに対応するためのメッセージを送出しするものである事
選択3:2分以内に通信終了メッセージを送る
選択4:IP電話端末は、総務大臣が別に告示する電気的条件および機械的条件→「光学的条件」に適合しないといけない
選択5:インターネットプロトコル電話端末は、電気通信回線に対して直流の電圧を加えるものであってはならない
ただし、総務大臣が別に告示する条件において直流重工が認められる場合にあっては、この限りでない。
(5) p449 アナログ電話と通信する場合 ※選択Bが間違い
選択A:アナログ電話と通信する場合の送り出し電力は、平均レベルでー10デシベル以下→
「ー3デシベル以下」 ※最大レベルの設定も存在しない
選択B:発信または応答を行う場合にあっては、呼設定用メッセージを送出するものであること
ただし、総務大臣が別に告示する場合はこの限りでない
問5
3,2,4,4,2
→3,2,4、4,2
(1) p459 用語の定義 ※選択3が間違い
選択1:高周波とは、周波数が3500ヘルツを超える電磁波をいう
選択2:平衡度とは、通信回線の中性点と大地との間に起電力を加えた場合におけるこれらの間に生ずる電圧と
通信回線の端子間に生ずる電圧との比をデシベルで表したものをいう
選択3:絶対レベルとは、一の有効電力→「無効電力」の1ミリワットに対する比をデシベルで表したもの
選択4:ケーブルとは、光ファイバ並びに光ファイバ以外の絶縁物および保護物で被覆されている電線をいう
選択5:線路とは、送信の場所と受信の場所との間に設置されている電線およびこれに係る中継器
その他の機器(これらを支持し、または保蔵するための工作物を含む)をいう。
(2) p465 架空電線について
選択A:架空強電流電線との水平距離がその架空電線もしくは 架空強電流電線の支持物のうちいずれか
低い→「高い」ものの高さに相当する距離以下となるときは、総務省令で定める所により設置してはならない
選択B:架空電線の支持物には、取扱者が昇降に使用する足場金具などを地表1,8メートル未満の高さに
取付てはならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない
(3) 電線の種類、絶縁電線またはケーブル
(4) p471 不正アクセス
~電子計算機を作動させ、当該アクセス制御機能により制限されている「特定利用」をしうる状態にさせる行為がある
(5) p475 電磁的記録 ※選択2が間違い
選択1:正しい
選択2:※本人にも任意に改変する事ができない記録だったと思われる
選択3:認証業務とは、自らが行う電子署名についてその業務を利用するもの、その他のものの求めに応じ、
当該利用者が電子署名を行ったものである事を確認するために用いられる事項が当該利用者である事を証明する業務
選択4:特定認証業務とは、電子署名のうち、その方式に応じて本人だけが行うことができるものとして
主務省令で定める基準に適合するものについて行われる認証業務をいう

















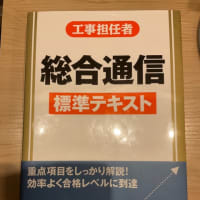


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます