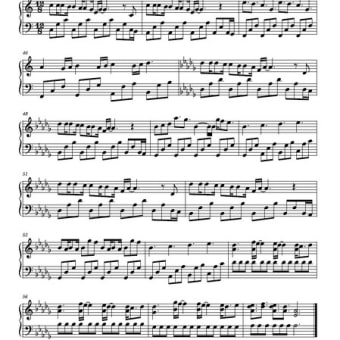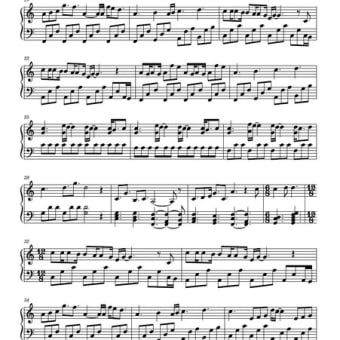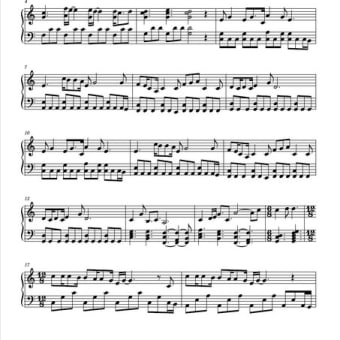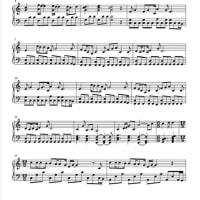その根源を探る方向へと運動する。
そして、そこに現れたのが、「都市」である。
1980年の「家、世の果ての…」から83年の「工場物語」に至る三部作は、
消費社会と都市をモチーフとしており、
これらの作品によって、以後しばらく、如月小春は都市の専門家と
呼ばれるようになる。
再び、Vonegatt を引けば、Mother Night の扉には、
次のような詩が引用されている。
異国の岸辺をさまようことをやめて
足を故郷のほうへ向けたときに
心の燃えあがるのを感じないような男
「これは俺の国、俺の生まれた土地!」
と自分にむかって言ってみないような男
それほど死んでしまった魂の持主がいるだろうか?
もちろん、これはVonegatt一流の反語であるが、
如月小春の問題もまた、その強さはともかく、
これと同質のものであったと思われる。
如月小春が自らの出発点という「家、世の果ての…」、そして
それとほぼ同型の構造を持ち、その、より洗練された形での
パラフレーズであるともいえる「工場物語」は、いずれも
主人公の少女(そして、犬)が次のようなシュプレヒコールをして終わる。
「都市よ、老いたる都市よ!」
この二つの作品には、「《少女と犬》型都市を記述する試み」
という副題がついているが、ここにおいて「少女」が意味することは、
すでに「光の時代」について述べたのと同じだろう。
一方、「犬」は少女の介添えであるが、たぶん、一種の「知恵」、
あるいは「自我」を象徴しているだろう。
いずれの作品においても、「都市」は、その内部の生活者に、
その全貌を見せることのないまま、その生活者を自分の標本として
「生かす」という存在として描かれている。
これは、たとえば、庄司薫の都市論である「ぼくの大好きな青髭」
にも共通する視線である。個々の生活者に見えるのは、自分の身の回りの
辺境の風景であり、そうした風景にとけ込むことによって、
自らを失ってゆく。都市とは、あたかも、生活者の欲求を吸い上げる
ことによって脈動する巨大な生命体である。
生活者はいつのまにか、自分の欲求が、自らのものであるのか、
それとも、都市によって欲求するように仕向けられた結果であるのかを
見失う。もちろん、これは、もともと区別することができない
ものではあるのだが…。
柄谷行人の言葉をかりれば、これは、都市による欲望の
(すなわち、存在の)「転倒」といってよいだろう。
ポルノグラフィや売春の、あるいは、低俗なTV番組の議論
で必ずでてくる、「買う人(見る人)がいるから作るのだ」
「作るから見たく(買いたく)なるのだ」という水掛け論。
どちらも正しく、またどちらも正しくない。
こうした「鶏と卵の命題」にいまだに惑わされてしまうという
ことは、そうした責任所在を明らかにしようという
われわれの線形な因果的認識が、
因果的循環に満ちた有機的な世界を全体として捕らえることが
できないということをよく示しているのだが、それは
わかっていても、この「転倒」に気づいたとき、
世界は突如リアリティの無いふわふわとしたものに変わる。
私とはなんだ? 他者とはなんだ?…
最新の画像もっと見る
最近の「好き」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
人気記事