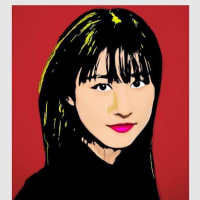辣腕メロディメイカーによる美麗な楽曲群を浴びる、上質なエンターテインメント。
“真っ昼間から いいキモチ。”をキャッチフレーズに、2015年より海外ブラック・ミュージック・アーティストのライヴを中心に行なわれてきた都市型フェス〈SOUL CAMP〉。昨年は9月12日〜17日の期間に〈SOUL CAMP 2018 at ISETAN〉として伊勢丹新宿本館6階で開催されたが、2019年は2017年(その時の記事はこちら→「SOUL CAMP 2017」以来2年ぶりに豊洲PITへカムバック。ボビー・ブラウンとベル・ビヴ・デヴォーによるRBRM(Ronnie,Bobby,Ricky & Mike)とケニー・“ベイビーフェイス”・エドモンズをそれぞれライヴステージのヘッドライナーとする豪華なラインナップで盛り上がる、予定だった。
だが、9月下旬にアル・ビー・シュアがアーティストスケジュールの都合で出演キャンセルとなると(ここまではよくある話だが)、猛烈な勢力の台風19号〈ハビギス〉の影響によりキャリン・ホワイト、レックスン・エフェクトのアキル・ダヴィッドソンが搭乗便の欠航により出演キャンセル、さらにミュージック・ソウルチャイルドとSWVも同様に来日が難しく、立て続けに出演キャンセルが発生。自然による不可抗力な事象とはいえ、当初のコンセプトは大幅にかけ離れたものに(キャンセル払い戻しも行なわれた)。タイムテーブルも急遽変更され、レックスン・エフェクトは時間短縮、当初DJ STAGEでパフォーマンス予定だった数組をLIVE STAGEへ移すなど苦肉の策で対応。両日それぞれ海外勢のライヴアクトは、ほぼRBRMとベイビーフェイスによる単独のような形となってしまった。
個人的には2日目のミュージック・ソウルチャイルドとSWVを目当てにという思惑は外れてしまったのだが、そのように考えていた人は少なくなかったのだろう。SNS上でも同様の声をあちらこちらで目にしたし、泣く泣く払い戻しをしたという報告もあがっていた。当日は小雨にはなっていたが、残念ながら集客は伸びず。それでも熱心なブラック・ミュージック・フリークたちが会場のゲートをくぐると、DJがプレイするエリアへと集い、心地よいグルーヴに身体を反応させている姿が散見された。
自分もほぼベイビーフェイスのみという2日目に当初はそれほど積極的ではなかったが、ベイビーフェイスのビルボードライブでの単独公演の18,000(カジュアル17,000)円と比べると、おそらく同じくらいの演奏時間に他の演者のステージも見られて13,000円ならコストパフォーマンスはいいかもしれないと考えていたところ、運よくチケットをゲットすることが出来、小雨のベイエリアへと足を運んだ次第。ライヴ観賞は東京都世田谷区出身のMC、DJ、トラックメイカーからなるヒップホップ・クルー“KANDYTOWN”の一員のIOとベイビーフェイス。IOはこういう機会でもないとなかなか観ることがないので、結構期待していたのだが、実際に観賞したところ、当初の予想以上の好感を持った。ベイビーフェイスは、貫禄の一言。
◇◇◇
【ケニー・“ベイビーフェイス”・エドモンズ】

稀代のメロディメイカー、そしてエンターテイナー。その言葉に尽きる。年も重ねて“ベイビーフェイス”といった風貌もだんだんと薄れてきてはいるものの、解き放つメロディや煌びやかなサウンドは色褪せない。ステファノ・ランゴーン、オスカル・ロドリゲスのバックヴォーカル陣とベースながらもヴォーカルも執るウォルター・バーンズがバックヴォーカル以上のヴォーカルワークを披露すれば、アンドレ・ロバーソンがサックス、クリフトン・ウィリアムズが鍵盤、マイケル・リポルがギター、レジナルド・ジョンソンがドラムと、それぞれでベイビーフェイス・ワールドを色鮮やかに染め上げていく。
暗転後、白を基調とした衣装のメンバーが登場すると、冒頭からアンドレ・ロバーソンがサックスで“独り舞台”かのごとくソロパートで煽って、ベイビーフェイスのステージインを今かと待ち望んでいるファンたちの心に火を焚きつけるパフォーマンス。そこへ満を持してシルヴァーの煌びやかなジャケットを羽織ったベイビーフェイスが顔を見せると、オーディエンスの歓声が響きわたる。もうそれだけでフロアが一瞬にしてベイビーフェイスの世界に包まれたような、そんな感じすら覚えた。
ベイビーフェイスは自身の楽曲はどちらかというと不遇で、提供曲やプロデュース曲の方が圧倒的ということをよく言われるが、それは提供曲がビッグヒットし過ぎているゆえ、相対的にそう見られてしまうのだろう。マライア・キャリーが参加した「エヴリタイム・アイ・クローズ・マイ・アイズ」や「ウィップ・アピール」は全米6位、「ネヴァー・キーピング・シークレッツ」でも全米15位と、トップ40が一つのビッグヒットの目安となるチャートにおいて充分過ぎる成功を収めているが、異例のロングヒットとなり、グラミーにも輝いたエリック・クラプトンへのプロデュース曲「チェンジ・ザ・ワールド」をはじめ、全米13週1位の「エンド・オブ・ザ・ロード」と14週連続全米1位となった「アイル・メイク・ラヴ・トゥ・ユー」というボーイズ・II・メンによる“バケモノ”級のヒットを手掛けてしまったがゆえのこと。自身のメロディメイカーとしての輝きは、自身の曲だろうが、他への提供・プロデュース作であっても不変だ。
それらが凝縮されたのが中盤から一気に本編ラストまでに連なるベイビーフェイス・ワークス・メドレー。タイトルどおりのスロー・ジャムが展開するミッドナイト・スター「スロー・ジャム」を皮切りに、ベイビーフェイスのメロディメイカー、ヒットメイカーぶりが存分に発露。ザ・ウィスパーズ「ロック・ステディ」やジョニー・ギル「フェアウェザー・フレンド」などでキーボードとドラム以外の5人がベイビーフェイスを中心にステージに並んでステップを踏めば、アフター・7やドゥルー・ヒル曲では滑らかなハーモニーを披露。さらには、“ボビ男!”(80年代後半に日本で巻き起こったダンス/ファッションなどのカルチャーブームを端的に示した言葉)と叫んでからボビー・ブラウン作品を連発し、「エヴリ・リトル・ステップ」ではブラウン顔負け(?)のサイドステップジャンプも飛び出す。ジョニー・ギルの「マイ・マイ・マイ」ではお馴染みのフレーズ“マ、マ、マイ、マ、マ、マイ”を(本家の暑苦しいくらいのエネルギッシュな叫びとは違って)コーラスの熱度を高めてシャウト。メドレーのクライマックスはボーイズ・II・メンのビッグヒット2曲を。「エンド・オブ・ザ・ロード」ではジャケットを脱ぎ捨てたベイビーフェイスがフロアに降りて、後方のバーによじ登ってファンに囲まれながら熱唱する光景も。ベイビーフェイスの衰えない歌唱も良かったが、それをサポートしながらもしっかりとメロウなムードを絶やさなかったバックヴォーカル陣もいい仕事ぶり。ステファノ・ランゴーン(『アメリカン・アイドル』第10シーズンのトップ7)とオスカル・ロドリゲス、さらにはベースのウォルター・バーンズが適度にメインパートを務めるのだが、特にランゴーンがハイトーンを駆使してフロアのヴォルテージを高めているのが印象的だった。個人的にはテヴィン・キャンベル「キャン・ウィ・トーク」からアフター・7「レディ・オア・ノット」の流れなどは、グッと胸に刺さるものに。
アンコールを経て、パーティの幕には自身の曲「ホエン・キャン・アイ・シー・ユー」をアコースティックギターを手にして披露。これも全米4位のヒット曲だ。メドレーのムードとは一転、喧騒の終わりをゆっくりと告げるようなテンダーな音を鳴らしながら、珠玉のグッドメロディの数々をフロアに振らせ、オーディエンスの心に刻み込んでいった。
純粋にヴォーカル・スキルという意味では優れている歌手はいると思うが、それを補って余りあるメロディと良質なヴォーカルワーク、さらにバックヴォーカルやバンドとのコンビネーションなどによって生み出されるエレガントで華やかなステージ。完成度の高さとエンターテインメント性が備わった1時間強は、当初のランナップの少なさによる不安をすっかりと吹き飛ばすほどの満足をもたらしてくれた。
◇◇◇
<SET LIST>
INTRODUCTION
For the Cool in You
Every Time I Close My Eyes
Soon as I Get Home
Never Keeping Secrets
Whip Appeal
Until You Come Back To Me
Time Will Reveal(DeBarge)
Change the World(Eric Clapton)
~BABYFACE WORKS MEDLEY~
Slow Jam(Midnight Star)
Rock Steady(The Whispers)
Fairweather Friend(Johnny Gill)
Can't Stop(After 7)
There U Go(Johnny Gill)
We're Not Making Love No More(Dru Hill)
These Are The Times(Dru Hill)
Two Occasions(The Deele)
Don't Be Cruel(Bobby Brown)
Every Little Step(Bobby Brown)
Rock Wit'cha(Bobby Brown)
Tenderoni(Bobby Brown)
Can We Talk(Tevin Campbell)
Ready or Not(After 7)
My My My(Johnny Gill)
I'll Make Love to You(Boyz II Men)
End of the Road(Boyz II Men)
≪ENCORE≫
When Can I See You
<MEMBER>
Kenny "Babyface" Edmonds(vo,g)
Stefano Langone(back vo)
Oskar Rodriguez(back vo)
Andre Roberson(sax)
Clifton Williams(key)
Michael Ripoll(g, Musical Director)
Walter Barnes(b,vo)
Reginald Johnson(ds)
◇◇◇
【IO(KANDYTOWN)】
当初、2日目のLIVE STAGEのトップバッターとして予定されていたIOは、ベイビーフェイスの直前の時間帯に変更。なんでも〈SOUL CAMP〉史上初となる邦楽ラインナップとなるらしい。6月の1stアルバム『Player's Ballad.』リリース直後にビルボードライブで行なわれたライヴとほぼ同じと思しきメンバーがバンドメンバーとして集結し、ヒップホップからソウルやジャズなど、ディープでアンビエントな色彩のグルーヴを解き放っていた。
想いを言葉に焚きつけるとか挑発するようなフロウを並べないクールな面持ちが通底しているが、そのあたりは一般的なヒップホップ(ラップ)のイメージとしてよく語られる剥き出しの感情と言葉で圧倒するというものはなく、言葉の圧でサウンドを乱さないというか、サウンドとヴォーカルのバランスを楽曲トータルとして考えているような印象。ネオソウルにも近しいメロウな音をバックに、大人の表現力というか、言葉のパワーのみに頼らない演出・アレンジ力に長けているステージを繰り広げていく。終盤の「Pursus」などでも見られたように、客演ラップとメインのエフェクト・ヴォーカル、MALIYAのコーラスといった声と、安藤康平(MELRAW)のサックスほかバンドが生み出す成熟したジャジィなサウンドとが有機的に絡み合い、真夜中を彷徨うような酩酊とセンシュアルなムードを作り上げていった。
ラストは『Player's Ballad.』収録の「Pursus.」から「Player's Section.」でステージアウト。オーディエンスは、次のベイビーフェイス目当てや30、40代以上の客層の占める割合が多く、IOあたりのアーティストに直に触れていないような、おそらく自身のライヴの時とはやや異なるアウェイに近い空気のなかでのパフォーマンスになったとは思うが、フロアに媚びることなく、自身たちの音楽を貫くスタイルは、実に清々しかった。いつか単独で観賞してみたいと思えたアクトだった。
<MEMBER>
IO(KANDYTOWN)(vo)
MALIYA(vo)
hanna(g)
Kan Inoue / 井上幹(WONK)(b)
Hikaru Arata / 荒田洸(WONK)(ds)
Kohei Ando / 安藤康平(MELRAW)(sax,fl)
宮川純(key)
Neetz(KANDYTOWN)(sampler)
◇◇◇